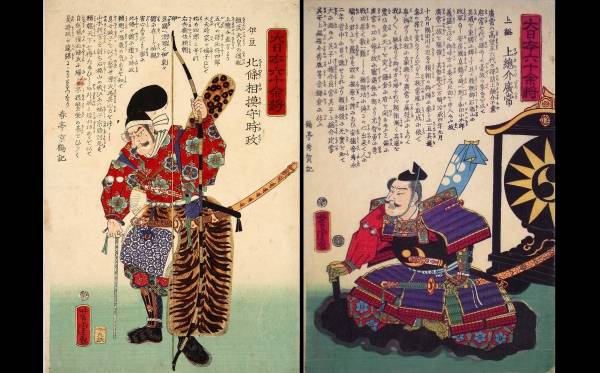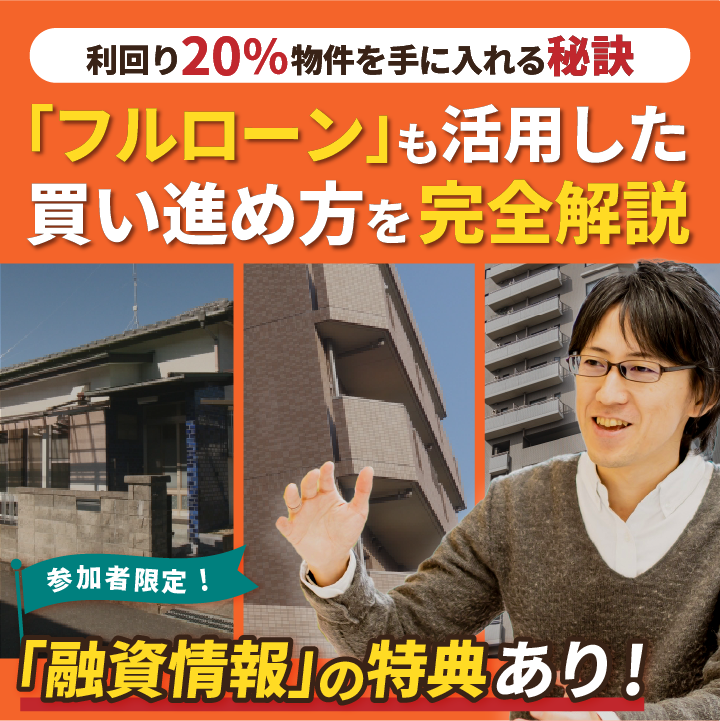2つの伊達家②――宇和島藩「四賢侯の一人」伊達宗城
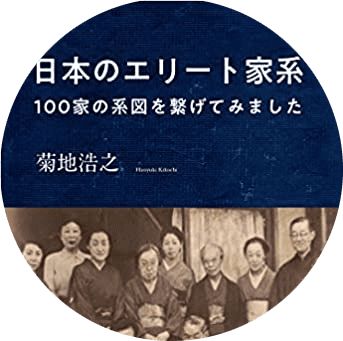
2021/11/26

伊達宗紀/Public domain, via Wikimedia Commons
伊達政宗の「庶長子・秀宗」の活躍で成立した伊予宇和島藩
伊達家というと、多くの方は伊達政宗→仙台というイメージがあるのではないだろうか。しかし、もう1つの伊達家、伊予宇和島の伊達家がある。
大老・井伊直弼とも親戚筋だった宇和島伊達家
井伊直弼が大老に就任して「安政の大獄」で反対勢力を弾圧すると、宗城も一橋派の有力者として引退を余儀なくされた。ただし、宇和島伊達家の藩祖・秀宗が、井伊家の祖・井伊直政の娘婿だったので、親戚筋にあたる直弼としては穏便に事を収めたく、依願引退という形を取った(それゆえ、松平春嶽や山内容堂から裏取引があったのではないかと疑われたという)。
養父の宗紀には引退後に生まれた実子・伊達宗徳(むねえ)がいた。宗城は引退にともない、宗徳に家督を譲った。しかし、井伊直弼が桜田門外の変で斃れると、政治の表舞台に度々復帰した。
文久4(1864)年、松平春嶽の提案で参与会議が開催されると、宗城は松平春嶽、一橋徳川慶喜、会津松平容保、山内容堂、島津久光とともに朝議参与に任ぜられ、そのメンバーとなった。また、慶応3(1867)年12月に王政復古の大号令が発せられると、伊達宗城は明治新政府の議定(ぎじょう)職に任ぜられ、翌慶応4年1月に外国事務総督、2月に外国事務局卿を務めている。明治新政府は薩長に偏った人選でないことを知らしめるために、旧大名を要職に就けようとしたが、そもそもそれに適した人物が少なく、宗城は重宝されたのだ。
幕末・明治の活躍で仙台伊達家と家格が逆転
しかし、宇和島藩10万石は、大藩の薩長土肥に比べて圧倒的に財力が乏しく、幕末には財政危機的な状況に陥り、戊辰戦争に勃発すると「非戦中立」の旗を掲げ、表舞台から退いていく。
宇和島伊達家の家督は本家筋の宗徳が継いでしまったため、宗城の子どもたちは藩主になる機会を奪われた。しかし、幸いにも宗城は名君だったので、大名各家から養子の引き合いが多かった。そのうちの一人、宗城の次男・伊達宗敦は、本家の仙台藩主・伊達慶邦の養子になった。
その仙台藩が戊辰戦争で敗退すると、宗城は仙台伊達家の存続に奔走。明治2(1869)年、宗城は箱館戦争への派兵を拒否した責任を取って議定を免職されたが、親友・松平春嶽の推挙で、民部卿兼大蔵卿として復職している。
明治4(1871)年に宗城は全権大使として清国(現 中華人民共和国)にわたり、李鴻章を相手に日清修好条規の締結にあたるが、西洋並みの特権を得ることができず、政府閣僚から非難され、公職から退いた。
明治17(1884)年に華族令が発せされると、仙台伊達家・宇和島伊達家はともに伯爵に列した。仙台伊達家は旧領が62万5600石だったので侯爵(ナンバーツー)に相当するが、減封後の28万石が伯爵(ナンバースリー)相当だった。
そして、明治24(1891)年に宇和島伊達家は宗城の功により侯爵に陞爵(しょうしゃく。ランクアップ)すると、仙台藩伊達家はこれを不満に抱き、何度か侯爵陞爵を運動したが、叶わなかったという。
【関連記事】『青天を衝け』登場人物の家系
井伊直弼(演:岸谷五朗)
井伊家――家祖登場は平安時代、伝説の多い譜代大名筆頭の名門
渋沢栄一(演:吉沢亮)
渋沢家――さまざまな分野に広がる子孫、財産より人脈を残した家系
一橋(ひとつばし)徳川慶喜(演:草なぎ剛)
一橋徳川家――御三家、御三卿の中で目立つ存在になった理由
松平慶永(演:要潤)
越前松平家――子孫は幸村の首級を挙げ、幕末・維新は政治の中枢、昭和天皇の側近…歴史の転換期のキーマン
阿部正弘(演:大谷亮平)
阿部家――江戸幕府老中を多々輩出した名門のはじまりと維新の生き残り
この記事を書いた人
1963年北海道生まれ。国学院大学経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005-06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、国学院大学博士(経済学)号を取得。著書に『最新版 日本の15大財閥』『三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧 日本の六大企業集団』『徳川家臣団の謎』『織田家臣団の謎』(いずれも角川書店)『図ですぐわかる! 日本100大企業の系譜』(メディアファクトリー新書)など多数。