今年も水害の年 火災保険料には「水害格差」が間もなく導入か 不動産市場への影響は?
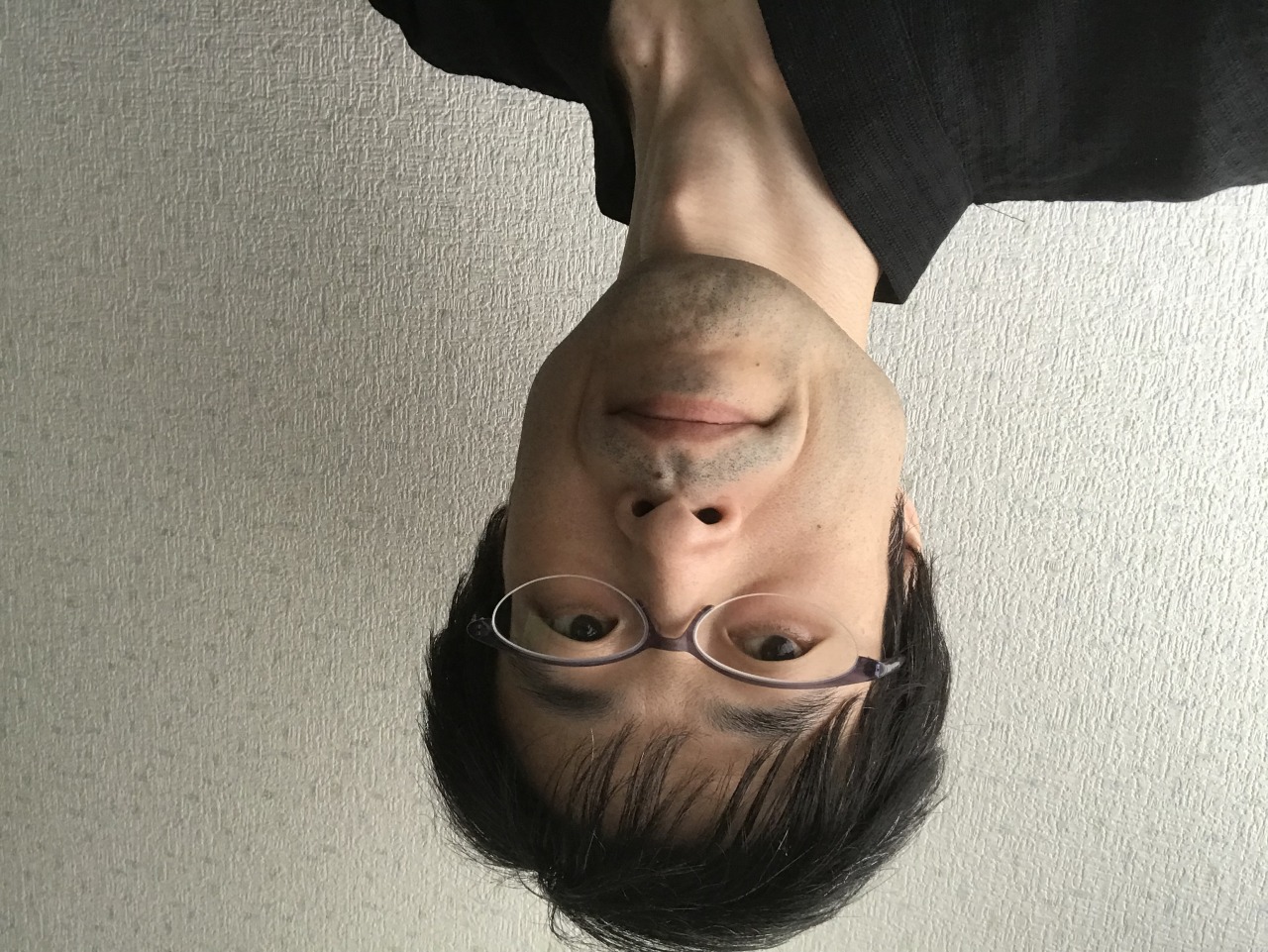
2022/08/26

イメージ/©︎marog・123RF
2022年もやはり水害の年に
まだ8月。台風シーズンは半ばで、秋の長雨の季節を迎えたわけでもない。だが、東北や北陸各地での激しい被害など、今年も日本が「水害の年」を迎えたことは確実だろう。
気象庁の資料によると、ここ10年間(2012~21)に日本に上陸した台風の数は8月以前が20個、9月以降が15個となっている(計35個)。一方、月単体では8月が12個、9月が11個となる(計23個)。このふた月の数字がほぼ拮抗しており、なおかつ全体の約2/3を占めている。
そうした中、春に報じられたこんなニュースを思い出す人も多いだろう。金融庁の有識者懇談会で「個人向け火災保険における水災被害補償分について、現在全国一律となっている料率を見直す方針が示された」というものだ。地域ごとのリスクを反映した細分化、具体的には市区町村単位での“格差”を設ける方向が示されたことになる。
なお、懇談会とはいうが、この会議は実質的に行政が今後の方針について、その最終確認を民間に求めるといった性格のものにみえる。
そのため、報道によれば、損害保険各社はこうした区分にもとづく保険料を2024年度から導入する方向で順次調整に入るとのこと。単純にいうと、河川に近いなど水害リスクの高い土地ではそうでない土地に比べ、今後火災保険料が上がる可能性が高くなる。
火災保険の収支は赤字が常態化
背景をひもとこう。ひとつは保険金の増加だ。上記懇談会に提出された資料によると、近年水災を含む自然災害の補償のため支払われる保険金が増えたことにより、火災保険の収支にあっては赤字が常態化している。
「火災保険の収支状況」
(一般社団法人 日本損害保険協会のとりまとめ・国内損害保険会社合計)
2010年度 (黒字)+1,146億円
2011年度 (赤字)-3,431億円
2012年度 (〃)-2,579億円
2013年度 (〃)-702億円
2014年度 (〃)-839億円
2015年度 (黒字)+145億円
2016年度 (赤字)-252億円
2017年度 (〃)-874億円
2018年度 (〃)-5,225億円
2019年度 (〃)-2,878億円
なお、このうち特に巨額な赤字となっている18年度、さらに翌19年度については、自然災害による支払保険金が連続して1兆円を超える事態となっている。
思い出してみよう。
災害関連死を含め300人以上の死者数を記録した平成最悪の水害・西日本豪雨、関西空港の滑走路が高潮で水没した台風21号……これらは18年。
千葉県を中心に大規模な風害や停電を引き起こした台風15号、北陸新幹線の車両基地を泥水で埋めた台風19号……これらは19年。
あのときの情景がいまも目に浮かぶ人が少なくないだろう。
こうした状況を受け、各損害保険会社が火災保険料を設定するための基準として用いる「参考純率」(損害保険料率算出機構による算出)は、18年(+5.5%)、19年(+4.9%)、21年(+10.9%)と、ほぼ立て続けに引き上げられてきた。すなわち、保険料の値上げにつながる改訂となる。
そのうえで、今回金融庁が主導して固められた方針は、ターゲットを水害(水災)に絞ったうえで、各地域のリスクを見比べ、保険料に反映されるかたちで格差を設けていこう――それを火災保険収支の健全化につなげよう――というものになる。その背景にあるもうひとつの要因が、近年火災保険加入者の中で生じているある傾向だ。
進んでいる「水災補償離れ」
その傾向とは、「水災補償離れ」ともいうべきものだ。金融庁懇談会の提出資料などから数字を拾ってみよう。
「火災保険 水災補償付帯率」(損害保険料率算出機構によるデータ)
2013年度 76.9%
2014年度 75.2%
2015年度 73.4%
2016年度 71.9%
2017年度 70.5%
2018年度 69.1%
2019年度 67.8%
2020年度 66.6%
このとおり、水害が尻上がりで猛威をふるった印象の近年にあって、火災保険における水災補償の付帯率は、実は下がり続けている。「水災は要らない」という人が年々増えているのだ。
その理由のひとつとして、金融庁の懇談会は、この間に人々のナレッジのレベルが上がった旨を挙げている。水害ハザードマップなどさまざまな情報・知見の充実が、現にリスクに晒されている人に対しては注意を促した反面、そうでない人にはある意味での安心をもたらしたといえるだろう。
ハザードマップを見て、「わが家の立地ならば水害は大丈夫」「しかもウチはマンションの上の階なので」などと考えた人が、余計な(?)コストとなる水災補償を外すことは、ごくあたりまえの判断となるわけだ。
ただし、このことは当然ながら水災を補償するために用意されるファンドが目減りすることを意味している。前述の「赤字常態化」と相まって、今後もいつ、さらなる巨大水害に対処することになるかも知れない火災保険にとっては、肝心の資金的土台が削られていく危うい状況が、目下進んでいるということだ。
迫られる微妙な舵取り・匙加減
以上をまとめるとこうなるだろう。
・近年、自然災害が多発、激甚化するなか、社会の重要インフラともいえる火災保険の収支が圧迫されている。そのため保険料率の引き上げが続いている
・上記に対して影響の大きい水災補償においては、リスクの高い地域ではますますリスクが高まりそうな一方、低い地域では逆に水災補償離れが進んでいる
・そこで国や損保業界としては、リスクに応じた保険料率の細分化を水災補償に導入することで、高リスク=高負担、低リスク=低負担のかたちをつくりたい。すなわち格差による公平をつくり出し、火災保険の土台を守りたい
――要は、自動車保険における運転者年齢による保険料格差のごとく、水災補償にも料率区分を設けたい、そのことでいまの危機を乗り切るステップを得たいということだが、では、そもそもなぜこれまで水災補償には料率区分が無かったのだろうか?(同じ火災保険の風災、雪災には地域による区分がすでにある)
その理由として、損害保険料率算出機構の資料などには、過去には細かな地域単位での水災リスクを測るデータが不十分だったことなどが挙げられている。だが、その点については各種ハザードマップの充実など、近年のテクノロジーの後押しも受けた環境変化が、いわゆるブレイクスルーをもたらしたものと見ていいだろう。
とはいえ、今後の舵取りにはかなり微妙なものが迫られそうだ。すなわち、格差による公平は格差による苦境も生み出しやすい。
たとえば、さきほどの水災補償離れを抑制するため、低リスク地域の保険料を下げる傍ら、うっかり高リスク地域の保険料を上げ過ぎると、今度はそちらの契約者が保険加入を維持できなくなる。火災保険の社会インフラとしての機能が危うくなる。
すると、当然ながら保険料の補助云々といった「公助」の話が出てくることになりそうだが、対象は個人の家=私有財産だ。もっと大きな公平が損なわれるおそれもある。
よって今後このテーマは、おそらく地方行政をも巻き込んでの難しい課題を生み出すものとなっていくだろう。
インパクトは2年前の「重説義務化」に勝る?
さて、今回の件の不動産市場への影響だ。
水害と不動産――ということでは、2年前の2020年に「水害ハザードマップにおける物件所在地の説明義務化」というものがあった。いわゆる水害リスクの重説化だ。
これに比べ、今回の火災保険・水災補償での地域格差の導入は、ゆくゆくはインパクトとして勝るものになっていくだろうというのが筆者の予想だ。
なぜなら、われわれは可能性としてのリスクを伝えられるよりも、目の前に生じるコストを伝えられた時の方が、反応が敏感になる傾向が概してつよいからだ。
今後、どんな水害が日本を襲うのかはわからない。だが、それが多くの予想どおり、規模、頻度の面でエスカレートしていくとして、火災保険料にあっては、増えていく被害額に準じ、(今後設定される)料率格差を抱えたまま高額化していくであろう以外に方向性が見当たらない。
そのうえで、保険料コストがほかよりもかかるのならば、その不動産は単純に忌避の対象となる。資産価値の下落だ。そうしたハンディは、カバーする他の要素が少なくなりがちな地方や郊外の物件で、より顕在化しやすいものとなるだろう。
私事を挟もう。実は、筆者もまさにそんな状況を抱える当事者のひとりだ。
近い将来、親が残してくれるであろう土地と実家家屋は、地方の町のさびしい川沿い近くにあって、洪水ハザードマップを見ると周囲は赤く塗られている。河川氾濫時に想定される浸水深度は0.5m以上~3m未満だ。そのうえで、筆者か弟がやがてこれを引き継ぐことになる。そのため、今回の件はまさに他人ごとではない。
すでにマップ上赤く染められたわが実家の土地には、ほどなくまたケチがつくかもしれず(今回テーマの保険料格差)、そこに載っかっている建物は築後四半世紀をゆうに超え、老朽化の度合いをさらに増していく。ついでにこの場所は内水氾濫の可能性があるエリアにも収まっている。要するにさんざんだ。
とはいえ、まったく俯瞰した立場でいえば、筆者はわが実家のごとき災害リスクのある土地からの人口撤退が、わが国の今後とるべき道であるとも思っている。国の総合的な防災力を上げるため、これ以上の「環境整備」はほかにないからだ。
そのためには、そうした土地にあって維持コストが上がり、人々が離れていく方向性には基本賛成となる。
【この著者のほかの記事】
土地を「有利な資産」と考える人は平成初期の1/3に 日本人の「土地離れ」が加速中?
男女共同参画白書が語る「変容」した日本の姿
地価LOOKレポート令和4年(2022)第1四半期分が公表 対象地区20カ所が削減に
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。























