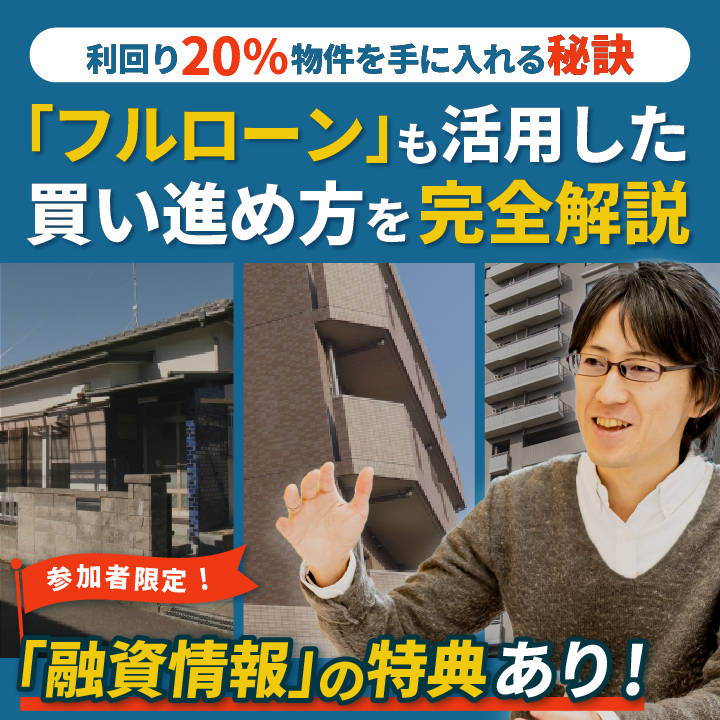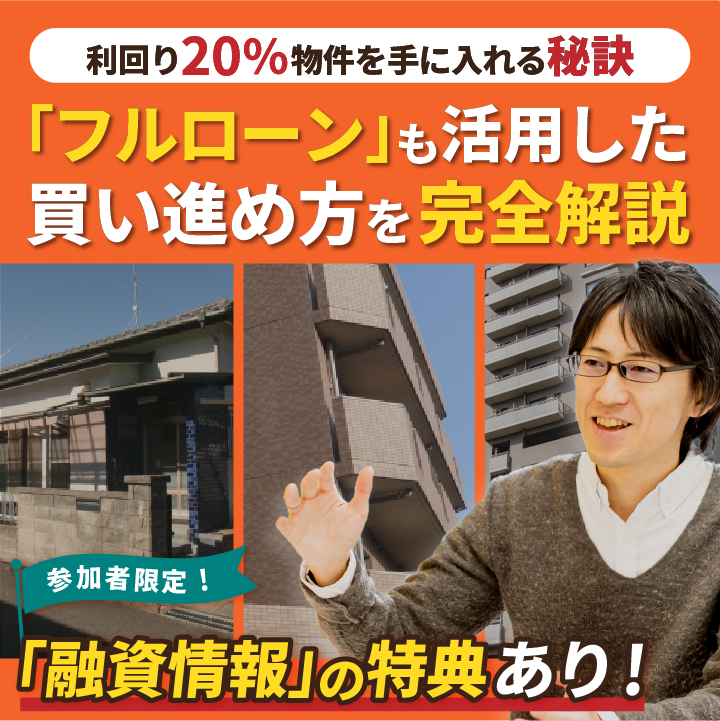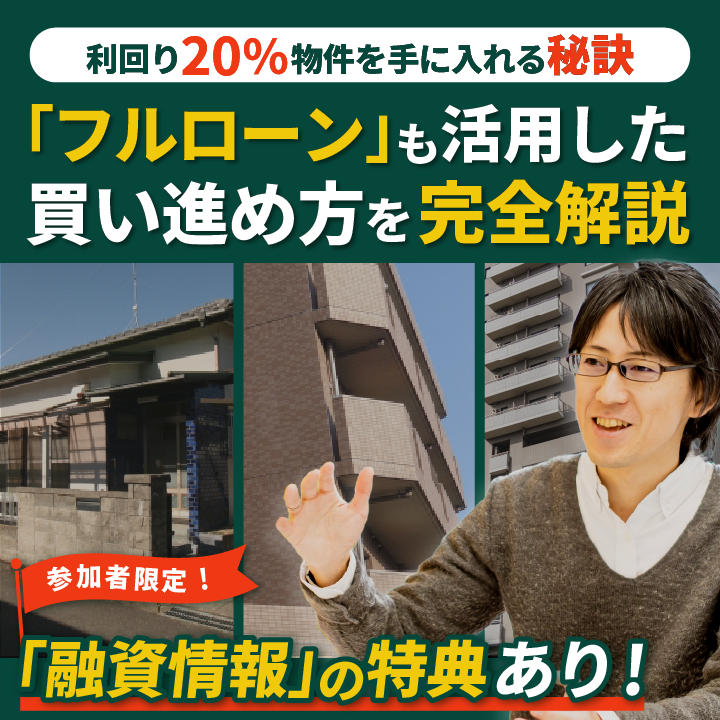小説に学ぶ相続争い『女系家族』⑥――愛人に財産相続の権利はあるのか

2021/12/03

『白い巨塔』や『沈まぬ太陽』など、鋭い社会派小説を数多く世に残した山崎豊子。『女系家族』は、四代続いた大阪・船場の老舗の問屋「矢島商店」で巻き起こる遺産相続のトラブルを題材とした小説です。初版が刊行されたのは、いまから50年以上も前で、これまでに若尾文子主演の映画や米倉涼子主演のテレビドラマなども制作されています。
また、12月4日、5日(いずれも21:00〜)にはテレビ朝日系列にて宮沢りえ、寺島しのぶのW主演で放送されます。
愛人に財産を遺す方法
そこで、いよいよ今回の本題です。親族に愛人の存在を知られることなく、どのようにして財産を遺すのか。方法はいくつか考えらえるので、ひとつずつ紹介していきましょう。
1つ目が、裏金として現金を事前に渡しておく。現金というものは動かしやすく、愛人に遺す場合も最も簡単な方法です。
もちろん、本来は贈与税の支払い義務が課せられますが、たんす預金にでもしておけば、法律の目をかいくぐりやすくなります。
しかし、法律家の私がこんな方法を提案するわけにはいきません。読者の方は、あくまでも“架空の話”へのアドバイスとして受け取ってください。
2つ目が不動産、よくあるのがマンションを購入してあげるという方法です。表向きは愛人名義でローンを組んで、実際にはそのローンをきちんと払ってあげるわけです。ひとつ目の裏金とも似ていますね。
3つ目が給与です。本人が会社を経営するなどしていれば、愛人を社員として給与という形でおカネを渡していきます。親族にもバレにくく、税金もきちんと支払うので法律的にも安全な方法といえるかもしれません。
4つ目が暦年贈与の制度を使うという方法です。暦年贈与は親族だけでなく、誰にでもできます。ただ、年間110万円までで、もらった側、つまり愛人側も贈与税の申告をしなくてはなりません。
5つ目が、愛人と信託契約を結ぶ方法です。この方法は、財産を遺す本人にとっても、愛人にとっても、そして弁護士の私にとってもベストな方法といえそうです。
生きている間に愛人と信託契約を結び、「私が死んだら、この財産は君に託す」といった内容の契約を結ぶのです。
委託者=本人、受益者=本人、受託者=愛人となり、本人が生きている間は、財産は本人のもので、愛人が勝手に手をつけることはできません。
この方法をとっていれば、万が一、愛人と別れた場合などでは、契約を取り消すことができなくもない、というメリットがあります。
※委託者=財産を託す人
※受益者=財産を受け取るなどの利益を受ける人
※受託者=委託者から、財産を管理したり、その契約内容を執行したりすることを託された人
分かりやすいスキームとしては、マンショを購入。これを賃貸にしてその管理を受託者として愛人に任せるというような方法です。
5つ目が生命保険です。
かつては愛人を保険金の受取人にして財産を残す方法は容易でした。しかし、現在は原則、配偶者、2親等以内になっているので、この方法はできなくなっています。
とはいえ、この『女系家族』は昔の話なので、生命保険を使うのも有効な手段だったと言えるでしょう
以上が、愛人への財産の遺し方の一例です。
嘉蔵さんであれば、裏金を渡しておく程度で問題なかったはずです。私としては、嘉蔵さんがなぜ愛人の存在を親族一同に知らしめたのか、本当に理解に苦しむところです。
財産の取り分が変わる非嫡出子の存在
実は、この愛人問題には、もうひとつ話をややこしくすることがありました。それが、文乃さんがお腹に赤ちゃんを宿していることです。
これが嘉蔵さんの子どもであった場合、相続の内容が変わってきます。
嘉蔵さんの子どもは、いまのところ藤代さん、千寿さん、雛子さんの3人です。しかし、文乃さんの子どもが嘉蔵さんの子どもであれば、4人で財産分割しなければなりません。
現代の民法でいえば、遺留分(最低限保障されている相続財産の割合)は、子どもの場合、全財産の2分の1です。つまり、矢島家は3人姉妹ですから、1人分は1/2×1/3で、1/6が遺留分になります。
しかし、これが4人姉弟となると、1/2×1/4、1人分の遺留分は1/8になってしまうというわけです。
ちなみに、『女系家族』の時代の民法は、嫡出子と非嫡出子の遺留分の割合が異なるため、文乃さんの子どもと3人娘が同額の遺留分を受け取るわけではなさそうです。それでも、予定していた取り分が少なくなることを3人娘がおもしろく思うはずがありません。もめごとはさらに大きくなる一方でしょう。
だからこそ、嘉蔵さんは遺言状に愛人の存在を示すべきではなかったと思えます。文乃さん、さらにはお腹の子どもにまで危険が及びかねません。
このため弁護士として、なんとしても遺言状に文乃さんのことは記すべきではないと思う最大の理由です。
昔はお妾さんを囲うのは男の甲斐性などと言われましたが、現代では通用しません。嘉蔵さんの場合は、配偶者の松子さんが他界されているわけですから、財産の分与を明確にしたうえで、再婚してしまったほうが問題を大きくすることはなかったといえるでしょう。
もちろん、それでは小説としては成り立たないかもしれませんが。
いずれにしても、愛人がいらっしゃる方は、財産の遺し方には十分お気をつけください。
【連載】
小説に学ぶ相続争い『女系家族』①――相続争いがはじまる根本的な原因はどこにあるのか
小説に学ぶ相続争い『女系家族』②――財産を次の代に引き継ぐ、相続を考えるタイミング
小説に学ぶ相続争い『女系家族』③――分割しにくい不動産を含めた「共同相続財産」の遺し方
小説に学ぶ相続争い『女系家族』④――相続をひっかきまわす迷惑な人々の介入をどう防ぐか
小説に学ぶ相続争い『女系家族』⑤――遺言執行人は果たして必要な存在なのか?
この記事を書いた人
弁護士
一橋大学法学部卒。1985年に弁護士資格取得。現在は新麹町法律事務所のパートナー弁護士として、家族問題、認知症、相続問題など幅広い分野を担当。2015年12月からNPO終活支援センター千葉の理事として活動を始めるとともに「家族信託」についての案件を多数手がけている。