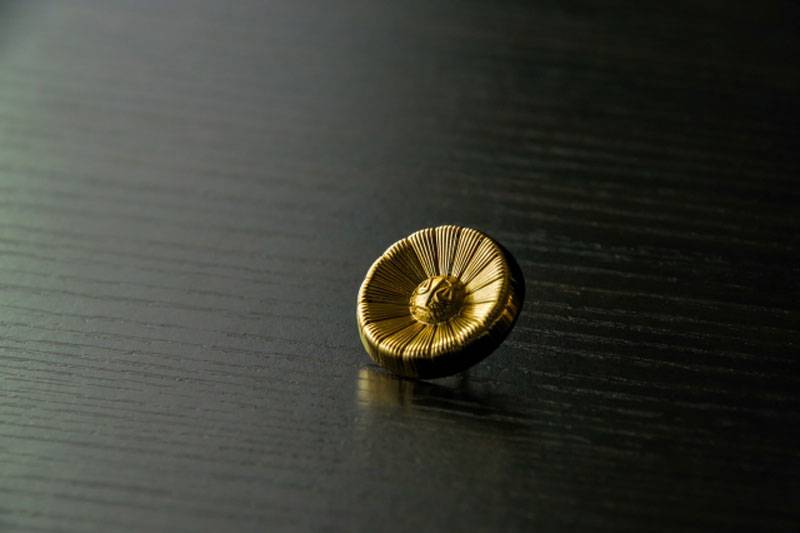いまこそ「相続時精算課税制度」について知っておきたい
2021/12/21

イメージ/©️maposan・123RF
資産家や相続税節税に詳しい税理士の界隈では、今年の12月10日に発表される前までは、
「早ければ2022年には贈与税の改正がある。資産家にとって相続税対策の王道と言われてきた暦年贈与の制度が『廃止される』『相続時に持ちもどされる期間が現行の3年から、欧米諸国並みの10~15年にさかのぼる』」
と、まことしやかに喧伝され、「駆け込み贈与をするなら今年から来年までがチャンス!」などと経済紙や週刊誌などで特集記事が組まれていた。
ところが、ふたを開けてみたら、暦年課税の廃止はなかった。しかし、自民党・公明党から出された「令和4年度税制改正大綱」の一部抜粋をご覧いただくと分かるが、近いうちに「暦年贈与制度の見直し」はあると考えた方がよさそうだ。
【令和4年度税制改正大綱の一部抜粋】
今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
資産家は誰しも「相続で財産を減らしたくない。できれば子孫に財産を引き継ぎ増やしていってほしい」と考えているものだ。
そのような方々にとって何が一番大切なことだろうか? よく資産形成や投資に関して言い古されていることだが、「財産を減らさないで守る」ということに尽きる。
かの有名な投資家であるジョージ・ソロスもこう言っている。
「私の実践的スキルを要約せよ、と求められたなら、ただひとこと『サバイバル』と答えるだろう。まず生き残れ。儲けるのはそれからだ」
と。相続で損をしないで財産をいかに減らさずに守るか?というと、多くの専門家から言い尽くされてきているが、ずばり「もめない」ことと「生前対策」に尽きるのだ。
財産が多くて相続税が高額になるような資産家の家では、生前対策が特に重要とされる。なぜなら亡くなった後では有効な対策はほとんど打てないからだ。このような家庭では当然ながら「遺言」や「生前贈与」などの生前対策がとられることが多い。生前対策のなかでも資産家にとって節税対策として最も有効だとされるのが生前贈与だ。
そのなかでも「贈与を受ける方が年間に110万円までは非課税で申告不要」という「暦年贈与」こそが非常に節税効果の高い方法だったのだが、前記のとおり近い将来見直される可能性が高い。なので、ここではもう一つの贈与の制度、「相続時精算課税制度」について改めて押さえておきたい。
相続時精算課税制度とは、簡単に言えば「生前に贈与された財産と相続で取得した財産を一体化して課税する制度」というものである。
中身をもう少し詳しくいうと、まず「60歳以上の父母か祖父母から20歳以上の子か孫にされる贈与」に限られる。次に「現金や預金、不動産等の財産の種類は問わずに、生きている間に何回でもできるが合計2500万円まで非課税、それを越えた部分には受領する側に20%の贈与税がかかる。ただし、相続時に相続税との差額が精算される」というものだ。
この制度は平成15年1月から施行されたのだが、当時は「失われた10年」と言われたデフレ不況真っ只中で、財産を溜め込んだ引退世代が元気に長生きをするため、財産がなかなか相続によって次世代に移転しないことに業を煮やした政府には「資産を早めに現役世代に移転させ、それを経済活性化につなげたい」という目的があった。
しかしそれから15年以上経つものの、世間の話題に上るほどには利用されていない。なぜならば「相続税の節税には効果がない」と思われているからだ。それもそのはずで、高額な贈与税を回避して生前に多額の贈与ができたものの、生前贈与によって「相続財産が減った」はずなのに、贈与した人が亡くなれば「相続財産に組み戻して」相続税の計算をするわけだから、「贈与しなかったのと同じ」ことに税金の計算上はなるからだ。
あまり人気のない「相続時精算課税制度」ではあるが、実は使い方によってはとても有効な場合がある。それは「贈与時点での財産額で相続税を計算する」ことになっているので、「値上がりする可能性が高い高額財産なら、先に贈与しておくことで、後で払う相続税が減る(=得する)可能性がある」という点だ。
ある土地の近くに鉄道の新しい駅ができる計画が持ち上がったとすると(最近でいうとリニア中央新幹線などが典型例)、その土地は将来かなりの割合で高騰する可能性がある。土地の値段が上がる前に贈与しておくことで、贈与しなかったときの相続財産よりも相続税課税価格が低くなり、結果的に相続税が少なくなる。
また、「儲かっている同族会社の事業承継」で威力が発揮される場合もある。どういうことかといえば、父親が社長で息子が専務の非常に儲かっている中小企業があるとしよう。会社の株式は100%父親が持っているとする。そこで60歳に父親が引退することにして、会社の規定どおり「役員退職金」をそこそこの額でもらって会社を辞める。
儲かってはいても中小企業であれば、高額の退職金を払った瞬間には会社の財務状況は一時的に低下する。そうすると株式の評価額が下がるから、そのときに「相続時精算課税制度」を利用して父親から息子に株式を贈与しておけば、父親が亡くなってから相続で株式を取得するよりも相当に低い価格での株式の承継が実現できる。
持ち株ゼロから100%株式をもつオーナー経営者になった息子は、頑張って会社の業績を向上させれば、収入だけではなく持ち株の価値も向上するので、仕事への意欲も湧いてこようというものだ。相続税の節税だけではなく、会社の業績向上にもつながればまさに一石二鳥だろう。
ただし、相続時精算課税にはデメリットがあるので要注意だ。相続税の基礎控除額の範囲内におさまる遺産しかなければ気にしなくてもいいのだが、相続税がかかる最大の要素が不動産である場合に、「贈与した不動産は相続時に小規模宅地等の特例を受けられない」という点だ。8割も評価額を減らせるのにそれができないのは大きなデメリットになる。
また、不動産を贈与する時に名義変更にかかる登録免許税は、相続に比べて5倍と割高なのだ。不動産の贈与は慎重に検討するべきと言えるだろう。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与を行った後では「暦年課税制度」は二度と使えなくなる。近い将来暦年課税制度が大きく変更される可能税が高いとはいえ、今はまだある「もらう側が1年間に110万円まで非課税」という大きなメリットを簡単に手放すのも難しい。今は金融資産の多い富裕層の相続対策は悩ましいタイミングになったということだろう。
【この著者のほかの記事をみる】
「事故物件ガイドライン」――ガイドラインとは異なる事例の場合
アフターコロナ時代の不動産マーケットを大胆に予測する
実家の不動産相続に大きな影響を与える可能性――「おしどり贈与」
この記事を書いた人
プロブレムソルバー株式会社 代表、1級ファイナンシャルプランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
1961年生まれ、大阪府出身。ラサール高校~慶應義塾大学経済学部卒業。大手コンピュータメーカー、コンサルティング会社を経て、東証2部上場していた大手住宅ローン保証会社「日榮ファイナンス」でバブル崩壊後の不良債権回収ビジネスに6年間従事。不動産競売等を通じて不動産・金融法務に精通。その後、日本の不動産証券化ビジネス黎明期に、外資系大手不動産投資ファンドのアセットマネジメント会社「モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン」にてアセットマネージャーの業務に従事。これらの経験を生かして不動産投資ベンチャーの役員、国内大手不動産賃貸仲介管理会社での法務部長を歴任。不動産投資及び管理に関する法務や紛争解決の最前線で活躍して25年が経過。近年は、社会問題化している「空き家問題」の解決に尽力したい一心で、その主たる原因である「実家の相続問題」に取り組むため、不動産相続専門家としての研鑽を積み、「負動産時代の危ない実家相続」(時事通信出版局)を出版、各方面での反響を呼び、ビジネス誌や週刊誌等に関連記事を多数寄稿。