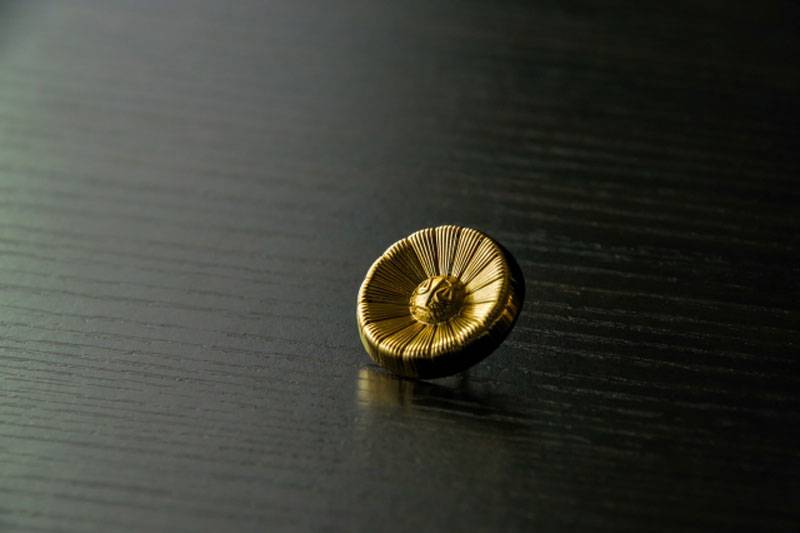相続法改正シリーズ #1 実家の不動産相続に大きな影響を与える可能性――「配偶者居住権」
2021/07/21

法務省/©️tupungato・123RF
約40年ぶりに大改正された相続法(民法の相続関係)
2018年7月6日、国会において可決成立し、同年7月13日に公布された民法の一部(相続法)が改正された法律が、既に19年7月1日から一部施行されている。週刊誌でも、たびたび特集されて話題になった「おしどり贈与」や、「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」に制度が変わったこと、従前は相続人だけに認められていた「寄与分」について、相続人以外の一定の親族にも「特別寄与料」が認められることになった点などだ。そのなかでも最も注目を集めた、20年4月1日から施行された「配偶者居住権」については、実家の不動産を相続する全ての方々に大きな影響を与える可能性があるため、その内容や注意点を押えておきたいところである。
改正相続法の目玉とされた「配偶者居住権」
超高齢社会において「約40年ぶりの相続法改正」とあって、所管する法務省も世間一般に対する大々的な周知活動を行った。法務省の作成した案内パンフレットにも分かりやすい説明がされているので、目玉とされる「配偶者居住権」に関する説明を以下の通り引用したい(以下2点、法務省パンフレットから一部抜粋して引用)。
【配偶者居住権の新設】
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において、配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈などによって、配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
【配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税】
固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者とされており、配偶者居住権が設定されている場合であっても、居住建物の所有者が納税義務者になるものと考えられます。もっとも改正法においては、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対して求償することができると考えられます。
新制度が創設された背景
今回の法律が、改正されるまでの法制審議会への諮問に至る経緯および、法制審議会における審議の経過などの資料によると、「相続法については社会の高齢化が進展し、相続開始時点で相続人(特に配偶者)の年齢が従前より高齢化していることに伴い、配偶者の生活保障の必要性が相対的に高まり、子の生活保障の必要性は相対的に低下しているとの指摘がされていた。また、要介護高齢者の増加による相続と療養看護の在り方の問題や、高齢者の再婚の増加による家族形態の変化が見られ、法定相続分に従った遺産の分配では実質的な公平を図ることができない場合が増えているとの指摘もされていた」とある。
そのあたりの文脈から、「夫に先立たれた妻が高齢化しており、さらに長生きの傾向があるため、その住宅をはじめとした老後の生活を十分に保護する必要がある」と強く考えられたことから、今回の「配偶者居住権」や「おしどり贈与」という制度の創設や相続法改正に至ったと考えられるのだ。
配偶者居住権で解決を図りたい「もめごと」
遺産額が大きくない場合、例えば相続財産が、実家不動産とわずかな預貯金のみである場合で相続人が複数いる場合には、切実な生活上の問題や感情的な問題で相続争いが起こりやすいものだ。現に最高裁判所の司法統計によれば、家庭裁判所に持ち込まれる「相続争い」に関する紛争解決手続きの4分の3は「遺産総額が5000万円以下」という遺産としては多くない、むしろ少額の場合に争いが多いということが分かっている。
典型例としては、離婚した前妻との間に子供がいる男性が亡くなり、その子供と高齢の後妻が相続人になる場合がある。後妻や子供が裕福であれば問題は小さいかもしれないのだが、後妻も子供も裕福でない場合は大きなもめ事に発展するかもしれない。
仮に遺産が、実家不動産(2000万円の相続税評価額とする)と預貯金1000万円の合計3000万円だったとする。子供と後妻は法定相続分としては各1500万円ずつ相続する権利があることになる。預貯金は500万円ずつに分けることは可能なのだが、実家はケーキのように2等分に分けることはできない。離婚した前妻の子供が「後妻の老後の生活のことなどどうなろうと知ったことではない。法定相続分通り遺産の半分である1500万円をもらいたい」と強硬に言えば、後妻は家を売って売却代金を2等分せざるを得なくなるのだ。夫と同居していたのに、後妻は家から出ていかざるを得なくなる。高齢者で一人暮らしの部屋探しは、簡単ではないので困ったことになるのだ。
今回できた「配偶者居住権」を使えば、このような事態に対処できるかもしれないのだ。残された後妻が居住権(相続税評価額を仮に所有権の半分である1000万円とする)を取得したとした場合、義理の息子は実家の所有権(完全な所有権ではなく、配偶者居住権という負担付きのため、2000万円の価値のうち居住権部分の1000万円を引いた残りの価値として1000万円)を相続し、預貯金は500万円ずつに分けることにすれば、法定相続分通りの遺産分割をしても、後妻は住む家を失わずに済むのだ。
配偶者居住権は必ず得られるとは限らない
配偶者居住権は、年老いて連れ合いに先立たれた配偶者(家の所有権を持っているのが夫で、その家に同居してる妻という想定であるが、所有者が妻で残される方が夫という場合も同じく、残された方に配偶者居住権を得る道がある)が住む場所に困ることがないようにとできた制度だが、相続が発生した場合に自動的に保障されているものではない。
ほかの財産の相続と同じように、「遺言が残されていた」場合か、「遺産分割協議で決まった」結果として、残された配偶者が得られるものなのだ。したがって、「遺言に書かれていなかった」場合や「遺産分割協議がまとまらず紛争状態になった」場合には、配偶者居住権の保証はされていない。ではどうなるのか?
イメージ/©️takasuu・123RF
夫に先立たれた妻が、ほかの相続人との折り合いが悪くて遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の審判により、「ほかの所有者(相続人)の被る不利益を考慮してもなお配偶者の生活を維持する必要があると認められたときは、配偶者居住権を取得することができる」とされている。なので、相当な高齢者で引っ越しが困難であるような状況であれば、裁判所に認められる可能性が高いと言えるだろう。
だが、もし残された妻がまだ若くていくらでも引っ越し先を見つけられると判断された場合はどうだろうか? 審判が下りないことも十分に考えられる。そのようなときに、仮に遺言で妻以外の人間に「自宅を相続させる」と書かれていた場合、その自宅を相続した第三者から「あんたは出ていけ」と言われる場合もあるだろう。妻がすぐに出ていかなければならないとすると酷な話である。
今回の相続法改正では、そのような場合もカバーするような制度ができたのだ。これを「配偶者短期居住権」といって配偶者居住権とは区別している。
配偶者短期居住権とは、先に述べた配偶者居住権と違って、被相続人が亡くなってその家に住んでいた配偶者が何も権利がない状態であっても、すぐに追い出されることなく一定期間住む権利が保障されること。所有権を得た第三者から「あなたの配偶者短期居住権の消滅を請求します」と言われてから6カ月間は無償で使用することができる権利なのだ。
そして、被相続人に借金がたくさんみつかって、残された妻が相続放棄した場合にも、後日その家の所有権を取得した者は、配偶者短期居住権の消滅を請求された日から6カ月間は無償で使用することができる権利でもある。
相続税対策に配偶者居住権を使う人は要注意
配偶者居住権制度ができてから、「配偶者居住権を使えば二次相続で節税になる」というような話題が相続を扱う業界で取り沙汰されたことがある。夫が亡くなって2000万円の実家を、妻と長男の2人が相続するケースで考えてみよう。
妻が配偶者居住権を1000万円で相続し、長男が配偶者居住権の負担付き所有権を1000万円で相続したとする。妻が亡くなると長男による二次相続が発生するが、このとき、妻が相続した配偶者居住権は死亡によって消滅するとされ、長男は実家に関しては既に一次相続で得ていた所有権について「配偶者居住権という負担」がなくなるだけで、実家に関する新たな相続は発生しないのである。
このような制度の特徴を考えると、実家の価値が高い場合に「配偶者居住権を使えば二次相続で節税になる」と考える向きが出るのもよく分かる。節税効果がある場合も、あるのは事実なのだが、相続税がかかるような高額な実家を相続する場合に、最も節税効果が高いのは「小規模宅地等の特例」と言われる制度であり、同居配偶者は確実に小規模宅地の特例の適用対象者である一方、相続する子どもが同居していない場合は必ずしも小規模宅地等の特例適用対象者とは限らず、もしかしたら「一次相続+二次相続」の合計でみた場合に、配偶者居住権を利用しない方が相続税が少なくて済む場合もあり得るのだ。
小規模宅地等の特例の適用要件も近年は厳しくなっており、適用可否を精査しつつ、配偶者居住権を利用するかしないかについて、この分野に精通した税理士などの専門家と十分に検討する必要がある。
また配偶者が生存中に介護施設などに入所する必要が出て家を売る場合には、買う人は居住権の負担を排除したいと考えるのが当然である。配偶者居住権は、配偶者(母)の生存中は原則として消滅しないため、売り主となる長男に対して配偶者居住権を放棄してから売ることになる。そのとき、長男に対する「贈与税」が発生すると言われており、注意が必要だ。
【この著者のほかの記事をみる】
サブリースで大家業をやる人に朗報
大家が主役になる時代の幕開け
増え続ける所有者不明土地、法律改正で止められるか
医療・介護問題だけではない――高齢者の財産管理における「2025年問題」
この記事を書いた人
プロブレムソルバー株式会社 代表、1級ファイナンシャルプランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
1961年生まれ、大阪府出身。ラサール高校~慶應義塾大学経済学部卒業。大手コンピュータメーカー、コンサルティング会社を経て、東証2部上場していた大手住宅ローン保証会社「日榮ファイナンス」でバブル崩壊後の不良債権回収ビジネスに6年間従事。不動産競売等を通じて不動産・金融法務に精通。その後、日本の不動産証券化ビジネス黎明期に、外資系大手不動産投資ファンドのアセットマネジメント会社「モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン」にてアセットマネージャーの業務に従事。これらの経験を生かして不動産投資ベンチャーの役員、国内大手不動産賃貸仲介管理会社での法務部長を歴任。不動産投資及び管理に関する法務や紛争解決の最前線で活躍して25年が経過。近年は、社会問題化している「空き家問題」の解決に尽力したい一心で、その主たる原因である「実家の相続問題」に取り組むため、不動産相続専門家としての研鑽を積み、「負動産時代の危ない実家相続」(時事通信出版局)を出版、各方面での反響を呼び、ビジネス誌や週刊誌等に関連記事を多数寄稿。