借主が亡くなった場合、貸主としてどう対処する? ――賃借人の死亡 その2 心理的瑕疵に関するガイドライン

2021/06/18
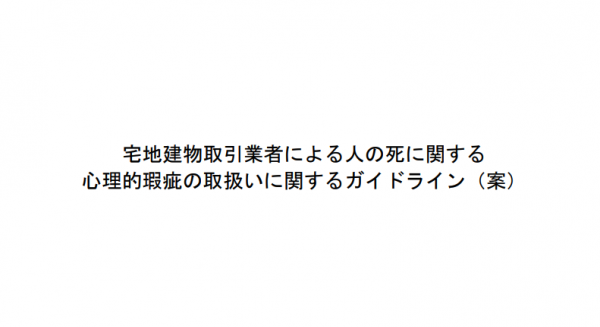
国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課より
先日、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)」(以下単に「ガイドライン」といいます)を発表し、広く国民から意見を募集するパブリック・コメント手続が行われました。
今回のコラムは、このガイドラインについて説明します。なお、このガイドラインは、現時点(2021年6月時点)において国土交通省が出している案に過ぎません。今後変更される可能性もあるので、最新のものを確認するようにしてください。
裁判例の動向
不動産取引におけるいわゆる心理的瑕疵の取り扱いについては、多くの裁判例でも触れられていますので、参考になるものをいくつか紹介します。
① 自殺があった物件に心理的瑕疵を認めた裁判例(横浜地裁 平成元年9月7日)
売買の目的物に瑕疵があるというのは、その物が通常保有する性質を欠いていることをいうのであって、目的物が建物である場合、建物として通常有すべき設備を有しない等の物理的欠陥としての瑕疵のほか、建物は、継続的に生活する場であるから、建物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景等に原因する心理的欠陥も瑕疵と解することができる。
② 信義則上の告知義務を認めた裁判例(大阪高裁 平成26年9月18日)
一般に、建物の賃貸借契約において、当該建物内で1年数カ月前に居住者が自殺したとの事実があることは、当該建物を賃借してそこに居住することを実際上困難ならしめる可能性が高いものである。
貸主は、賃貸借契約を締結するに当たって、建物内で1年数カ月前に居住者が自殺したとの事実があることを知っていたのであるから、信義則上、賃借人に当該事実を告知すべき義務があったというべきである。
このように今までは裁判例を参考にして、宅地建物取引業者(以下「宅建業者」といいます)は、自殺などのいわゆる事故物件に関する告知の要否、告知の内容を個別に判断していました。
しかし、実際の不動産取引の場面においては、心理的瑕疵に該当する事案の存在が疑われる場合において、それが買主や借主に対して告知すべき事案に該当するか否か明確ではなく、告知の要否、告知の内容についての判断が困難なケースが多くあり、宅建業者によっても対応が分かれていました。
例えば、人の死に関する事案の全てを買主・借主に告げているようなケースもあり、心理的瑕疵にかかる対応の負担が過大であると指摘されていたこともありました。
このように対応が分かれている理由は、行政からの統一的な指針が示されていなかった点にあります。
国土交通省はこのような点を踏まえて、不動産において過去に人の死が生じた場合において、そのような不動産を取り扱う宅建業者としてどのような対応をすればよいか、その判断基準を取りまとめました。こうして作成、公表されたものが、このガイドラインです。
ガイドラインの対象
ガイドラインでは、取り引きの対象となる不動産において生じた人の死に関する事案が対象とされています。しかし、人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引、隣接住戸や前面道路での事案、搬送先での死亡事案は、今回のガイドラインの対象外とされています。
さらにガイドラインでは、居住用不動産のみが対象とされ、オフィス等として利用される不動産は対象外となっています。その理由として、居住用不動産の方は人が継続的に生活する場として利用されるものであり、その取り引きの判断に影響を及ぼす度合いが高いと考えられることが挙げられています。
どのような場合に告知すべきか
告知すべき事案として挙げられているのは以下のとおりです。
① 他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合
この場合には、従来の裁判例からも紛争になりやすいものであり、契約締結をするか否かの判断に重要な影響を及ぼすことが大きいため、原則として告知すべきとされています。
② 自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合であって、かつ、いわゆる特殊清掃等が行われた場合
本来、自然死や日常生活での不慮の死(入浴中の死亡や、転落、誤嚥など)は、当然予想されるものであるから、原則として告知する必要はないとされています。しかし、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、室内に臭気・害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行われた場合には、契約締結の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、原則として告知すべきとされています。
告げるべき内容と範囲
賃貸借契約については、事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合にはその旨)について借主に告知すべきとされています。また、特段の事情がない限り、事案の発生から概ね3年間は借主に対して、上記事項を告知すべきとされています。
この3年間という基準は、今回のガイドラインによって新たに示されました。これは実務上、極めて大きな意味を持つと考えられます。ガイドラインが正式に適用された後は、事案の発生から3年を経過した場合には、借主に対して告知をしなくてもよくなることから、「どのくらいの期間告知しなければならないのだろう?」ということに頭を悩ませる必要がなくなり、宅建業者の負担は大きく軽減されることになります。ただし、ガイドラインでは、「特段の事情がない限り」という厄介な文言が入っているので、個別判断が必要となるケースは一部残ってしまうでしょう。
一方、売買契約についても、賃貸借契約と同様、事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合にはその旨)について借主に告知すべきとされていますが、期間についてはガイドライン上何ら制約が設けられていません。つまり、売買契約の場合には、賃貸借契約の場合とは異なり、調査の結果、告知すべき事案であることが判明した場合、宅建業者としては告知し続けなければならないことになります。この点は、賃貸借契約と売買契約との大きな違いといえます。
まとめ
ガイドラインが正式に適用されれば、これまでの実務が大きく変わることになるでしょう。しかしながら、ガイドラインでは、「原則として」や「特段の事情がない限り」といった曖昧な表現を使用している箇所が多数見受けられます。つまり、事案の性質や取り引きの内容によって、告知の要否や内容を個別に判断しなければならないケースも残されているといえます。また、そもそも対象不動産以外で人の死が発生したような場合(例えば隣の部屋で自殺が発生した場合等)はガイドラインの対象から外されており、このようなケースでは事案ごとに個別に告知の要否等を判断しなければなりません。判断に悩まれる場合には、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
なお、冒頭でもお話したように、このガイドラインは、現時点(21年6月時点)において国土交通省が出している案に過ぎません。パブリック・コメント手続を経たうえで、再度正式なガイドラインが公表されることになりますので、今後の動向にも注目していただければと思います。
【関連記事】
借主が亡くなった場合、貸主としてどう対処する? ――賃借人の死亡 その1 相続
契約名義人と異なる第三者に物件を使用されていた…賃貸借契約、虚偽申し込みを防ぐには?
不動産投資 見落としがちな解体、再築費用
この記事を書いた人
弁護士
弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。























