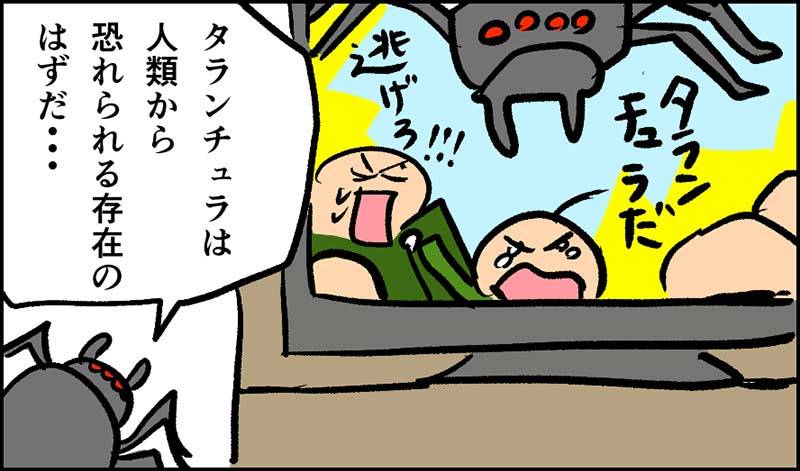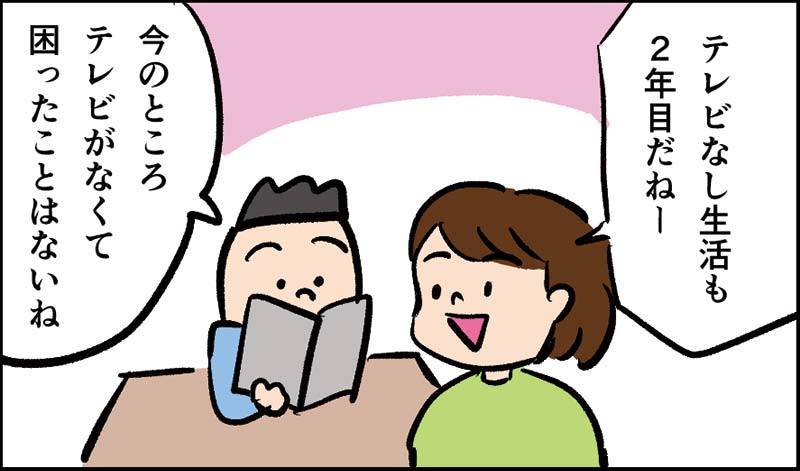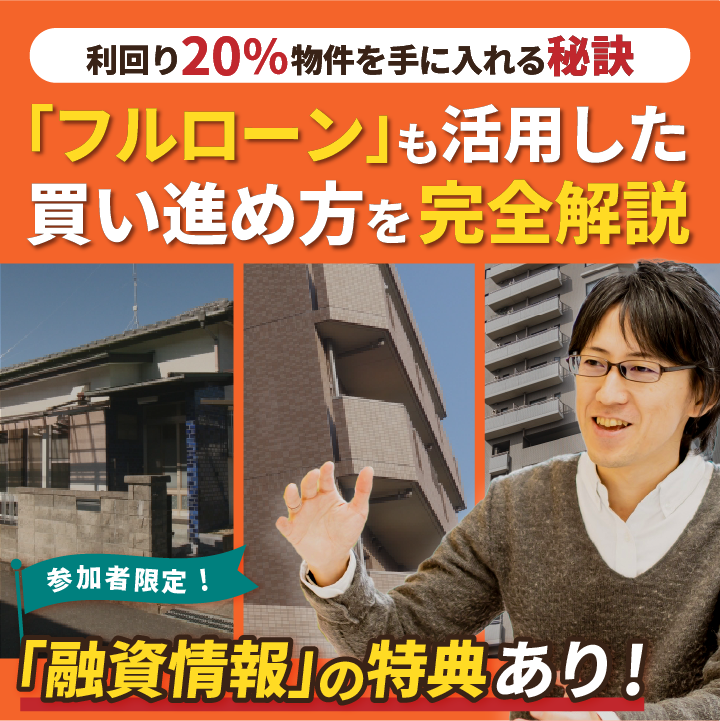離婚しても両親で子育て「共同養育」しているママの声①〜共同養育コンサルタントしばはし 聡子コラム〜

2018/10/05

イメージ/123RF
離婚すると子どもをひとりで育てなくてはと思ってしまいがちですよね。もちろん、子どもに対して暴力するなど危害を加える父親であれば適切な対応が必要ですが、そうではない場合は、子どもにとっては父親であることは変わりません。
とはいえ、離婚するほど関係がこじれた相手と親同士向き合うのも大変なこと。そんななか、共同養育を実践しているママの声をいくつか紹介しますね。
◾️中学校男の子のママ
離婚当初は私自身が面会交流に後ろ向きだったため円滑に進みませんでしたが、現在は父親があいている土日に息子は泊まりに行っています。その間、私は仕事をしたり飲みに行ったり自由な時間を過ごせているので息抜きできています。
公正証書では月1〜4回と決まっていましたが今では月に何回行っているのか数えたこともありません。私が夜予定があるときに合わせてお願いすることもしばしば。断られることもしばしば。子どもの父親と割り切れるようになると案外楽なものです。
受験など子どもの人生に判断が必要なときにはひとりで決めるのは重責すぎるので相談もします。母親はつい甘やかしてしまいがちですが、父親のブレない判断に助けられることもありました。
連絡手段はメールのみで話すことはほぼありませんが不自由ありません。息子もスマホを持ち始め父親と直接連絡が取れるので私が仲介に入るのは日程調整だけです。
結婚生活を振り返ると今の方が明らかに良い関係になっているように感じます。ありがとうも増えました。
ひとりで育てる!と肩に力が入っていた離婚当初は、こんなときがくるなんて思ってなかったですが、今は元夫とのやりとりのストレスもなく、父親・母親・子ども三者がよい関係です。
◾️小学生女の子のママ
元夫とは2年別居ののち離婚しました。離婚時に、娘の養育を共同で行うことを約束しました。別居中から面会交流は続けていました。
元夫は、とても子煩悩な人で、婚姻時から土日は、ほとんど娘と過ごし、娘もパパにべったりでした。とても仲が良い親子で、いつも微笑ましく思っていたので、別居・離婚時にも、元夫への葛藤はありながらも、良い関係を継続してほしいと思いました。
現在はまだ共同養育を約束して数か月と日が浅いこともあり、試行錯誤している状態です。娘が中学受験をするため娘のスケジュールが忙しく、時間がなかなか取れなくなってきているのが悩みです。
娘と元夫の面会交流について、我が家は基本的に、娘の意思に任せています。「月に何回」といった決め方はせず、娘が父親を求めるときに、元夫に時間をとってもらうようにしています。連絡は、娘が自分で元夫に携帯のメッセージを送って調整をしています。泊まりも数回実現しました。
良かったと思うことは、なにより、娘が、親が離婚したことにより娘が失うものを最小限にできたことだと思います。娘は私にもパパの話をよくしますし、家にはパパの写真を飾って嬉しそうにしています。あとは、子育ての負担を分け合えることです。時間的にも精神的にも楽になりました。
実は2年半くらい前に別居が始まった頃、私は元夫に対してとても葛藤の感情が強く、娘と元夫が会うときも、内心はとても苦しかったです。元夫が憎らしかったから。その憎しみも日がたつにつれ徐々に薄れましたが、娘のことだけが心配でした。どんなに大きな喪失感を抱えてこの子は生きていかなければならないのだろうと。
別居から2年近くたった頃、「共同養育」という選択を知りました。離婚しても変わらず娘に父親を与えてやれると、急に心が軽くなりました。そして、元夫に、「共同養育の離婚」を提案した次第です。
幸せそうにパパと過ごした時間の話をしてくれる娘を見ていると本当にこの選択をして良かったと思います。
◾️保育園児男の子のママ
子供が5歳の時に離婚しました。公正証書を作る段階から、面会交流をどうするかということは考えたことがありませんでした。というのも、私たちが、いわゆる夫婦を続けることが困難であったというだけで、離婚は親子関係に何ら影響しないと考えていたからです。
世の中では、子供に会わせる・会わせないが問題になると聞いて驚いています。子供を中心に考えたら、子供にとっての生みの父と母には、代わりはいません。子供は親権者の持ち物ではないので、親の意思で会わせるとか会わせないとか決めるものでもないと思っていました。
父は、夫ではなくなりましたが、きちんと養育費を払ってくれていて、親としての責任を果たしてくれています。であれば、会いたいときに会うことに、私は何の違和感も感じません。
夫婦を続けることはできませんでしたが、夫婦ではなくなることで、感謝しあうこともできるようになり、結婚生活をしていたころより、ずっと良い両親ができていると思います。
無理に家庭を続けようとしていた頃の険悪な空気を思うと、世の中で当たり前とされている家庭像って何だったのだろうとさえ思います。
面会は、特に何回と決めることもなく、予定が合うときで来たいときに、いつでも来てもらっています。父は、普通にインターホンを押して家に来て、子供と遊びに出かけています。子供も、お父さんは遠くにいる、というだけだと思っているようです。
今後それぞれの人生に変化があった場合でも、子供にとっての父であり母であることに、生涯変わりはないと思っています。
いかがでしたでしょうか。最初から行っていた方、乗り越えてきた方、葛藤がある方、ご経験はそれぞれ。離婚は大人の都合。子どもに辛い思いをさせないためにできること、まだまだありそうですね。別居・離婚後の子育てに悩まれている方のご参考になれば幸いです。
この記事を書いた人
一般社団法人りむすび 共同養育コンサルタント
1974年生まれ。慶應義塾大学法学部卒。自身の子連れ離婚経験を生かし当事者支援として「一般社団法人りむすび」を設立。「離婚しても親はふたり」共同養育普及に向けて離婚相談・面会交流支援やコミュニティ運営および講演・執筆活動中。 *りむすび公式サイト:http://www.rimusubi.com/ *別居パパママ相互理解のオンラインサロン「りむすびコミュニティ」 http://www.rimusubi.com/community *著書「離婚の新常識! 別れてもふたりで子育て 知っておきたい共同養育のコツ」️