「時代の証言」本当にあったひどい話 あの頃、賃貸生活は(賃貸業界も)ヤバかった…
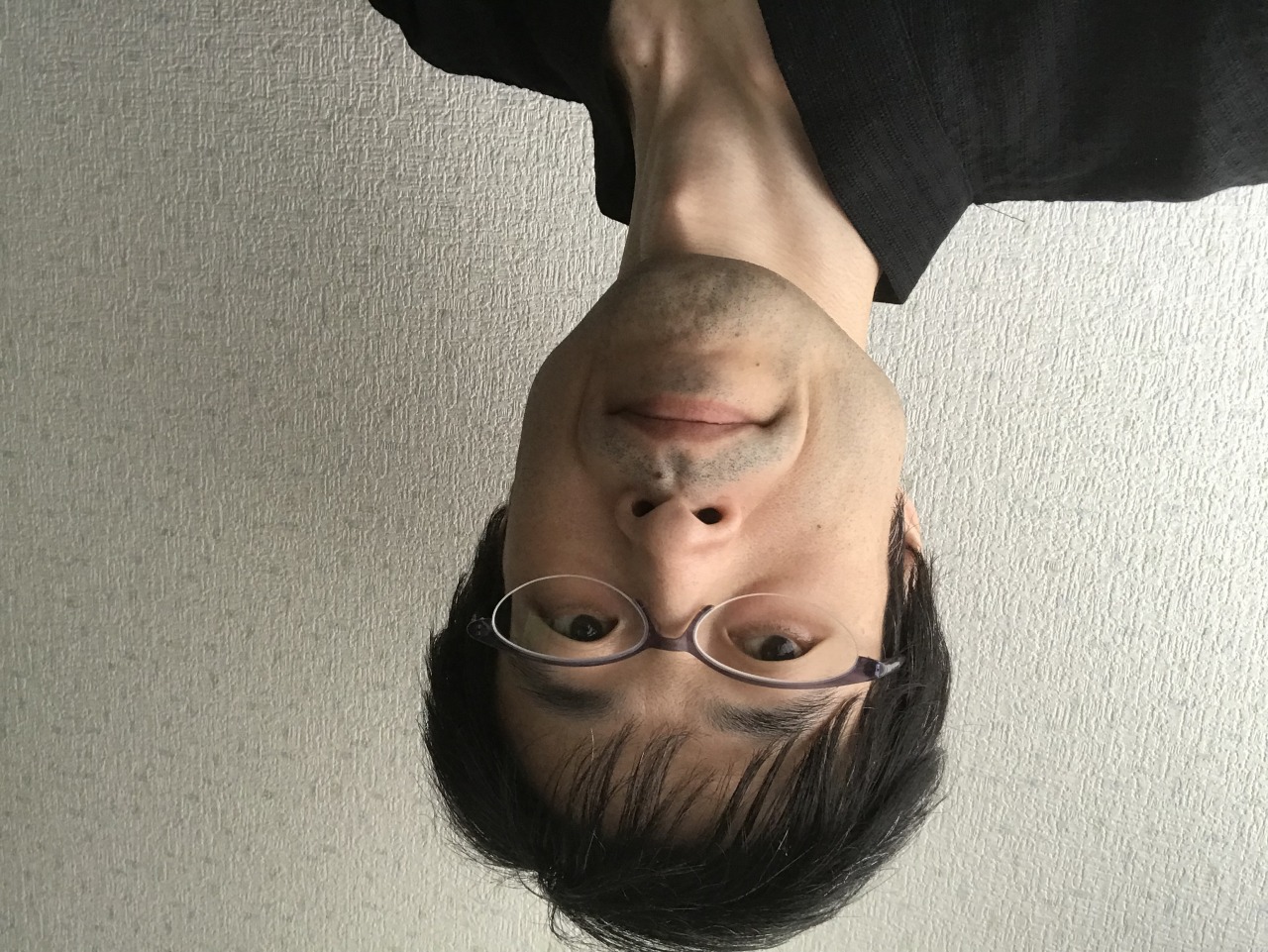
2021/10/29

この話、1ミリも盛っていません/©︎innovatedcaptures・123RF
人は現在を憎み、過去を愛する?
いつの時代も、多くの人は自分が生きている現在を恨むものだ。そして未来を悲観し、過ぎた過去を懐かしく感じる。ときには美しくも想いがちだ。
ところが、ところが!
最近は、古い90年代頃の賃貸住宅の話を若い人に聞いてもらうと、ビックリ驚かれることが多い。なぜなら、ジェントルないまを生きる彼ら・彼女らにとって、それはまるで「修羅の国」的な出来事だからだ。
となると、続く未来はどうやら楽観していい?
時代の証言として記しておきたい。以下はすべて実際にあった本当の話だ。寸分たりとも“盛って”はいない。
客をつかまえて言いたい放題の荒くれ店長

コンプライアンスの厳しいいまの時代であれば懲戒もの/©︎sharpshutter・123RF
バブル末期、90年前後の首都圏賃貸マーケットといえば、礼金2カ月・敷金2カ月も当たり前の貸し手市場だった。とくに築年の浅い単身用物件は需給が逼迫し、どこも満室だった。いきおい、仲介会社の態度もデカくなる。
当時、東京都心のターミナル駅近くの雑居ビルなどに無数に店を構えていた若者向けの賃貸仲介店舗には、“荒くれ店長”や“ヤンキースタッフ”、さらにはそれらを陰でシメる“姐御”などがたまにいて、大人しそうな客をつかまえては大声でいじめていたものだ。
「はあ? フリーター? 貸してくれる大家なんているのかね~」
「ここ、読めねえよ! 名前くらいまともに書けよ」
「あ、〇〇宅建さん? いま、フリーターとかいうのがウチの窓口に来てんだけど、おたくの物件申し込める? ハハハ、ダメだよね? ……ほら、ダメだとよ! まったく時間ばっかり取らせやがって、次どうすんだ!」
繰り返すが本当の話だ。
入居者が「土日は外出」を心掛けたわけ

30年以上前、新聞・教育商材・信仰への勧誘など、とにかくピンポンが多かった/©︎poko42・123RF
90年代およびその前後を通して、「土日は部屋にいたくない」「なるべく外に出る」という賃貸住宅の入居者は多かった。なぜなら、ひきもきらず部屋のインターホンを鳴らされるからだ。
当時、日常的だったさまざまな訪問セールスと勧誘は、単身世帯を中心に、社会の抱える一大ストレスといってもよかっただろう。
なかでももっとも数多く、もっとも警戒されていたのが新聞の勧誘だ。悪質な人材がきわめて多かった。「反社」などの言葉もなかった時代、露骨に自らの所属やその証拠をちらつかせながら(事実もあり偽装もあっただろう)、契約を迫る者も少なからずいた。
強引な一部にあっては、インターホンに応答が無ければテラスに回って窓を叩き、「やっぱりいるじゃないか」と、住人を引っ張り出すなどもした。そうした状況のなかから、ついには殺人事件も発生している。
いまだったら大クレームの“放置プレイ”
「対応が遅い!」「共用部分の照明切れを1週間以上も放っておくなんて何事だ!」……と、そんなことがあれば、いまは管理会社は入居者のみならずオーナーからも厳しく叱られる。
ところが、さきほども記したような貸し手市場の時代、入居者はたびたび「釣った魚にエサはやらない」の立場に放置された。
例えば、私の住んでいたアパートの場合、「廊下の蛍光灯が切れました」と管理会社に電話で告げても、交換まではほぼ3週間以上待たされるのが普通だった。それでも、当時周りの話を聞けば私のところなど比較的甘い方だった。「そもそも一度の電話で済んでいるケースの方が珍しい」と、羨ましがられてしまう有様だった。
なので、地方から転居してくる入居者に物件の鍵を渡す日、店番が自分ひとりであるにも関わらず入り口を閉めてブラブラ買い物、客の引っ越しを半日以上遅らせて悪びれる様子もない管理会社の支店長……と、その程度の話ならば、ごくごく些細な、よくある事例にしか感じられなかったものだ。
心を削る「いかがわしいチラシ」
当時はいかがわしいチラシが郵便受けにどっさり/©︎nobilior・123RF
「帰宅すれば郵便受けには毎日何枚ものチラシ。しかもいかがわしい写真だらけ」……90年代の都市部の単身用賃貸物件ではあたりまえの風景だ。
いかがわしいチラシとは、主に違法なアダルトビデオソフトを宣伝するものをいう。大っぴらには販売できないこれらの商品を宅配する業者が当時は無数に存在し、大量のチラシを撒いて注文を集めていた。
そうした、子どもには拾われたくないタイプのチラシが、空室の郵便受けからあふれ出たり、入居者が床に捨てたりしたところに、管理会社やオーナーの怠慢が重なると(数カ月にわたり掃除に来ないなど)、景色は実に殺伐としたものになる。当時は、あちこちのアパートやマンションで、そんな心を削る風景が展開していた。
一部のオーナーが背負っていた古い時代の影
忘れもしない91年のこと。あるアパートオーナーにこんな悩みを聞かされた。「長く住んでいる入居者をどうにか追い出したい」。理由はその女性入居者が「40歳を過ぎた」から。それ以外に彼女には何の落ち度もない。
しかし、オーナーはこう言うのだ。
「そもそも30過ぎのオバさんが1人で入居してきた時点でオレは嫌な予感がしたんだ。それが案の定、40になっても結婚しないで1人で暮らしているのだから、おそらく今後も独身だろう。いつまでうちのアパートに居座られるのかわかったもんじゃない。部屋で自殺でもされたらたまらないよ」
これを聞き、「一体この人は何を言ってるんだろう?」と、混乱する人がいまは多いだろう。しかし、91年といえばまだ平成3年だ。当時のオーナーといえば、要はつま先から眉毛まで、どっぷりと昭和の文化に浸かって生きてきた人たちだ。
人種や職業、性別、年齢のみならず、国内であっても出身地方によって差別をしたり、謂れのない警戒感をもったりするなど、古い時代の感覚を悪気のないまま持つ人が、いまの数倍、あるいは十数倍規模で存在していた。
そうした差別や偏見に遭った人たちの怒りの声を住宅情報誌のバックオフィスにいながら数年にわたって直接電話で聴かせてもらっていたひとりが、若き日の私だ。
この著者のほかの記事
炎上した「都道府県魅力度ランキング」を覗いたら、魅力ある地域の条件が見えてきた――群馬県には『頭文字D』という宝がある
「道路族」の騒音に現代人が深く悩む理由は、日本人みんなが賢くなったから?
名古屋の復調、ボールパークの町、サーフィン…21年「基準地価」注目すべきトピックス
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。
























