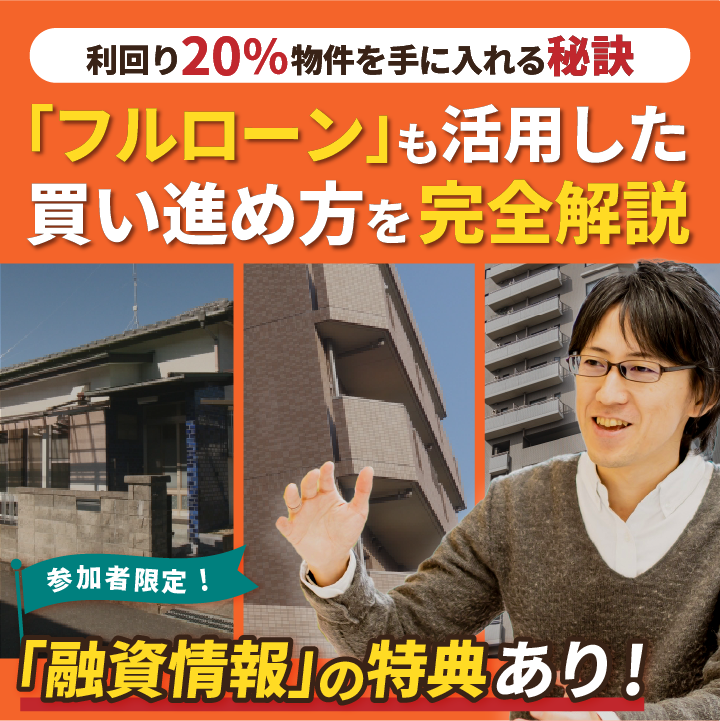コロナ禍1年、我慢の限界に達したホテル業界 近鉄、藤田観光など名門ホテルを売却、新興勢力は撤退、業態見直しへ

2021/03/31

椿山荘/mikimaru・写真AC
近鉄、西武、藤田観光――相次ぐホテル売却、それを狙う外資系ファンド
コロナ禍が1年を超え、鉄道系名門ホテルと京都系の振興ホテルがホテルを手放す危機に立っている。
「都ホテル」などを持つ近鉄グループホールディングス(以下・近鉄HD)は3月、関西地区など8つのホテルを米投資ファンドのブラックストーン・グループに売却すると発表した。
長引くコロナ禍で主力の鉄道収入が落ち込んでいるうえに、訪日客のストップで近鉄系列ホテルの苦境は厳しい。そのため近鉄HDは1兆円を超す有利子負債を抱え「都ホテル京都八条」(京都市)など、国内外で運営する宿泊施設の3割をまとめて数百億円規模で処分を決定したわけである。なお、ブラックストーン・グループの日本におけるホテルの大量取得は初めてという。
民鉄としては営業キロ数が日本一長い近鉄は、これまで京都、奈良、大阪、名古屋、伊勢・志摩など外国人に人気のある観光地を結び、各地のホテルやリゾート施設で収益を上げてきた。
しかし、近鉄だけではないが、本業の鉄道事業は沿線の人口減少や利用者の高齢化に伴い、終電時間の変更や間引き運転をするなどの対応を行い、リストラも余儀なくされている。そこに襲いかかった新型コロナによってさらなる取り組みが求められた。
実際、このコロナ禍で近鉄HDの21年3月期は780億円程度の最終赤字の見込みとなったことで、ホテル処分に踏みきった。おまけに、不振の旅行会社(近畿日本ツーリスト)を抱える子会社のKNT-CTホールディングスは20年末に債務超過に陥っている。
こうした近鉄の鉄道とホテル・観光事業という似通ったビジネスモデルを展開しているのが西武ホールディングス(以下・西武HD)だ。
同社は21年度第3四半期決算説明において、「アセットライトな事業構造へ転換」を掲げた。アセットライトとは「形ある資産を持たない」という意味で、なかでも注目されるのは、このコロナ禍によって西武HDも資産の切り出し、ホテル事業の再編に踏みきるかという点だ。そのためホテル業界や投資ファンドは、西武系の主要なプリンスホテルの処遇がどうなるかを注視している。
また、「ワシントンホテル」の全国展開で知られる藤田観光も、社員の基本給を最大16%カット、家電量販「ノジマ」への社員の出向、希望退職に300人以上が応じたこともあり、その動きが注目されている。
藤田観光の20年12月期の最終損益は過去最大の224億円の赤字に転落した。「創業以来最大の危機」を乗り切るため、関西を代表する結婚式・宴会施設「太閤園」(大阪市)の売却を決めた。藤田はほかにも全国に宴会施設や宿泊施設を保有しているが、なかでも潤沢な買収資金を持つ外資系ファンドからその動向が注目されているのが、結婚式・コンベンション施設を持つホテル「椿山荘」の扱いだ。
我慢の限界に達しつつあるホテル観光業
一方、近鉄HD、西武HD、藤田観光のような大手ではないものの、コロナ以前のインバウンドブームに乗りホテル事業に乗り込んできた新興の不動産デベもその勢いが削がれるどころか、事業の見直しを迫られている。
これらの新興勢力はコロナ前のインバウンドブームを背景に全国のオフィスや賃貸マンション用地をホテルや簡易宿泊施設を誘致する動きを活発に展開してきた。
当然のことながら、こうした動きは東京五輪需要も見込んでいた。しかし、新型コロナによって東京五輪の延期が昨年3月20日決定され、4月7日には1回目の緊急事態宣言が発出。皮肉なことにこの動きに時期を合わせるかのように、これらの新興勢力が進めていたホテルやレジャー施設が続々と完成していったのである。
建物はできたものの、緊急事態による自粛によって、これらの新しい施設には訪れる客もなく開店休業、あるいは開店すらできない状態に陥ってしまった。それから1年、我慢も限界に達しホテル事業撤退どころが、外資系ファンドの傘下に入る、あるいは本業の見直にも迫られている。
そもそもホテルは「稼働資産」の、低収益の事業。しかも人手がかかり、人件費の負担も重くなるため銀行融資の返済も厳しい。このため21年度は中堅のホテル、旅館の経営の正念場になる。
新興勢力の「レアル」「グローバル社」「OYO」の撤退劇
こうしたなかで国内の観光地としても人気もあり、インバウンド需要の最盛期にはオーバーツーリズムがクローズアップされた京都市でさえ、コロナ禍のいまはホテル事業のほころびが目立ってきた。
そんな京都では、ゲストハウスを運営する「レアル」(京都市)も3月25日京都地裁に民事再生法の適用を申請した。コロナ以前のレアルはホテルやゲストハウスを京都市内に75軒ほど展開、上場も目指していた。
また、京都で小規模な高級ホテルを手掛けていた「THEグローバル社」(以下、グローバル社)の動向も注目されている。

一際目立つグローバル社の看板(新宿大ガード)/©︎編集部
ハリウッド女優のミランダ・カーにアルファベットの「g」をかたどった自社のロゴマークを持たせて踊らせるド派手なCMで衆目を引いたグローバル社。同社の本業はマンションや戸建ての販売事業だ。ところが、京都のインバウンド需要の風に乗って東証一部上場も果たしたことから「ホテルベンチャーの風雲児」ともてはやされた。
持株会社のグローバル社の傘下にはマンション事業、戸建て事業、ホテル事業などを事業別に8社の連結子会社を抱えるでグループを形成し、「ウィルローズ」「ウィルレーナ」というブランド名でマンション分譲のほか、京都や東京ではホテル運営、投資用ホテル開発を主軸に展開し、19年6月期は売上高358億円を計上していた。
なかでもコロナ前には、京都市などの小規模な土地を買い上げ、しゃれたホテルに仕立て、買い手を見つけて売却するビジネスで注目された。また、売ったホテルを自らサブリースすることもあり、ホテル関連の業績を伸ばしていた。
このホテルのサブリース事業は企業(オーナー)から「サブリースで丸ごと面倒を見てくれて助かる」といった評価も上々だったようだ。しかし、新型コロナによって状況が一変し、これらホテル事業が大きな負担となり、失速してしまった。
フタを開ければ20年6月期第3四半期のグローバル社の決算短信では、「継続企業の前提に関する注記」を記載せざるを得なくなるほどになっていた。これはホテル事業の損失が響き、17億円余りの四半期損失を計上したためによる。追加融資などによって資金を手当てしたものの、新規に着手したホテルや住宅などの費用の支払い面も苦しく、株価は低迷していた。
こうした苦境のなか、同社では第三者割当増資を実施。不動産開発会社の「アスコット」(本社・東京)がこれを引き受け、グローバル社を子会社化した。このアスコットは中国・平安グループの子会社で、このグローバル社の増資を受けるにあたって、自身も第三者割当増資を実施し、これをSBIホールディングスが引き受けSBIの子会社となった。つまり、現在のグローバル社は平安グループとSBIホールディングスの子会社になったというわけである。
この結果、グルーバル社は、軸足(本社)を京都から東京に移し、ホテル事業を縮小し、過去の住宅事業に戻ることで再建を果たそうとしている。
このほかにもソフトバンクグループが支援し、日本でホテルと不動産賃貸事業を展開するインド系の「OYO(オヨ)」も、苦戦を強いられており、リストラのまっただなかだ。OYOはホテルチェーンに加え、不動産賃貸を日本で展開しているが、どうやら賃貸事業から撤退する模様だ。ピーク時の同社はアパートなど賃貸物件を8000室内外手掛けていたが、最近は数百室まで縮小させている。
苦戦を強いられているOYO/©︎編集部
ホテル業界 事前に手を引いていた航空会社はギリギリセーフ?
さて、新型コロナによって水を差されたホテル事業だが、振り返るとほぼ10年周期でイベントリスク(天変地異・疫病・紛争等など多岐の減収要因)に見舞われてきた。
新型コロナは、すでに変異株が次々と出現しているが、この新型コロナに限らず、今後も新しい感染症が発生することが予想され、感染症リスクのサイクル化が危惧される。これまでホテル業界はリーマンショックなど世界的な景気変動(景気後退)を機に業界再編や物件の売買が繰り返されてきた。
今回の新型コロナでは世界的な超金融緩和政策が実施され、ホテルの事業利益と評価が乖離的になっている。こうした背景もあってホテル業界再編、売買は資産面から注目されている面もある。
よくよく思い返せば05年以降のホテル再編も外資がらみである。
具体的には日本の航空大手2社のJAL、ANAのホテル部門の縮小・撤退劇は、モルガン・スタンレー証券など外資系の投資銀行やファンド、金融機関がホテル売買のスキームを支えた。
その10年後には、かつての航空会社系のホテルは、シンガポールや中国系のファンド・企業に転売された。
国策航空会社だったJALは、10年の経営破たんで過剰債務が軽くなったが、収益源となっていたホテル事業(売却前は国内外40ホテル)は、ホテルオークラ(16拠点)に数十億円で売却され、「小が大を飲む」という形になった。つまり、JALは国の管理下における再建に向け、債務削減の代償として、事実上のホテル事業から撤退を余儀なくされたわけである。
一方、ANAも投資銀行(モルガン・スタンレー証券)の主導でホテルを売却し、この売却益1300億円をもとに、経営資源を本業に投入している。仮にこの新型コロナ前に航空2社がこうしたホテルのリストラを行わないでいれば、さらに赤字幅は膨らみ、経営破綻していたかもしれない。
コロナ以前のホテル業界はインバウンドブームを背景に異業種も含めた事業会社の副業として事業参入も目立っていた。これによって遊休地や資産のの活用としても有効で、もちろんのことながら、有力ホテルは高収益で潤っていた。しかし、それも今は昔。新型コロナによって、ホテル事業は不稼働資産になり下がってしまった。
ホテル事業は単なる不動産資産にとどまらず、ホテルスタッフという人的な資産も含まれるが、稼働できなければそれも宝の持ち腐れでしかない。それゆえ、このコロナ禍、あるいは五輪縮小・中止は、戦後の列島改造計画の破綻、バブル崩壊、リーマンショックも含めて、幾度となく繰り返されてきたホテル業界再編の次の引き金になる可能性となりそうだ。
【この著者のほかの記事】
1964-2020東京五輪へと続く道路開発2――昭和の“遺構”を使った銀座・築地の一体開発とは?
1964-2020東京五輪へと続く道路開発1――幻の地下高速「築地~新富町」ルート
「HARUMI FLAG」住民訴訟に新たな動き 不動産鑑定士たちが指摘する激安価格のカラクリと問題点
この記事を書いた人
都市開発・不動産、再開発等に関係するプロフェッショナルの集まり。主に東京の湾岸エリアについてフィールドワークを重ねているが、全国各地のほか、アジア・欧米の状況についても明るい。