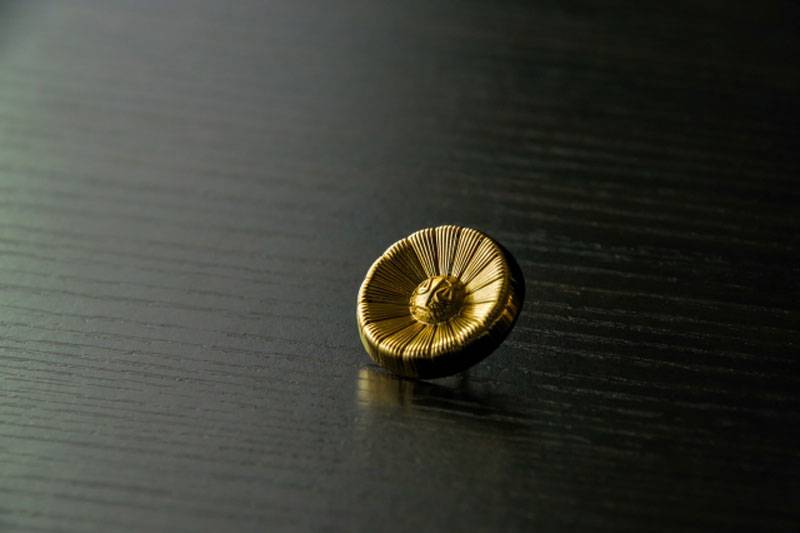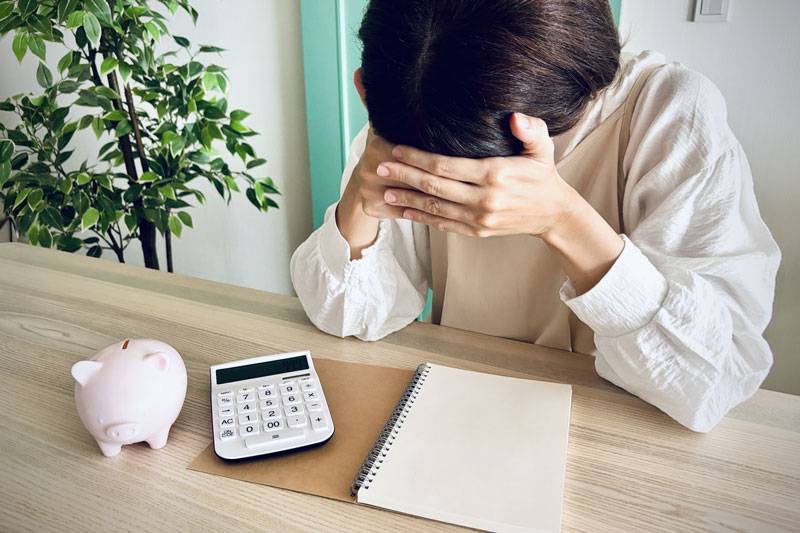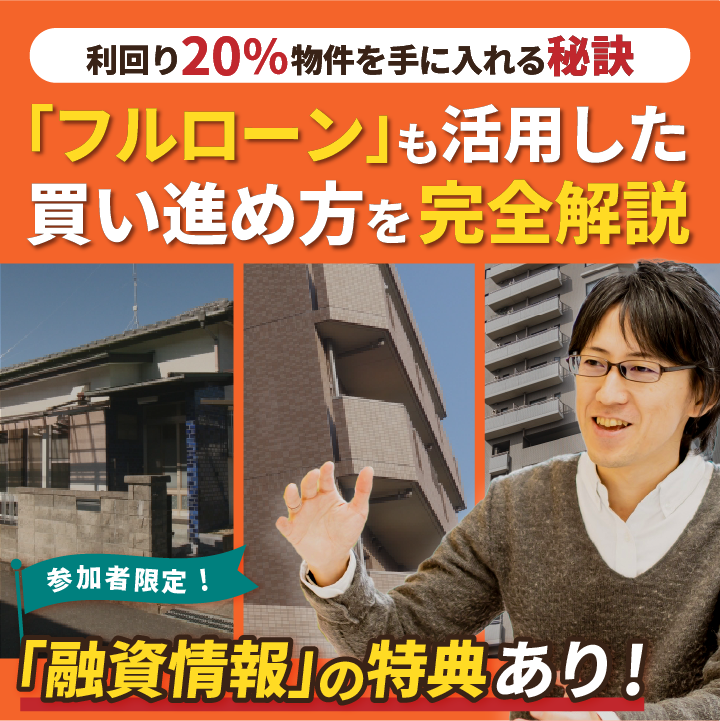ベーシックインカムの実証実験は「宝くじ」で始めては?
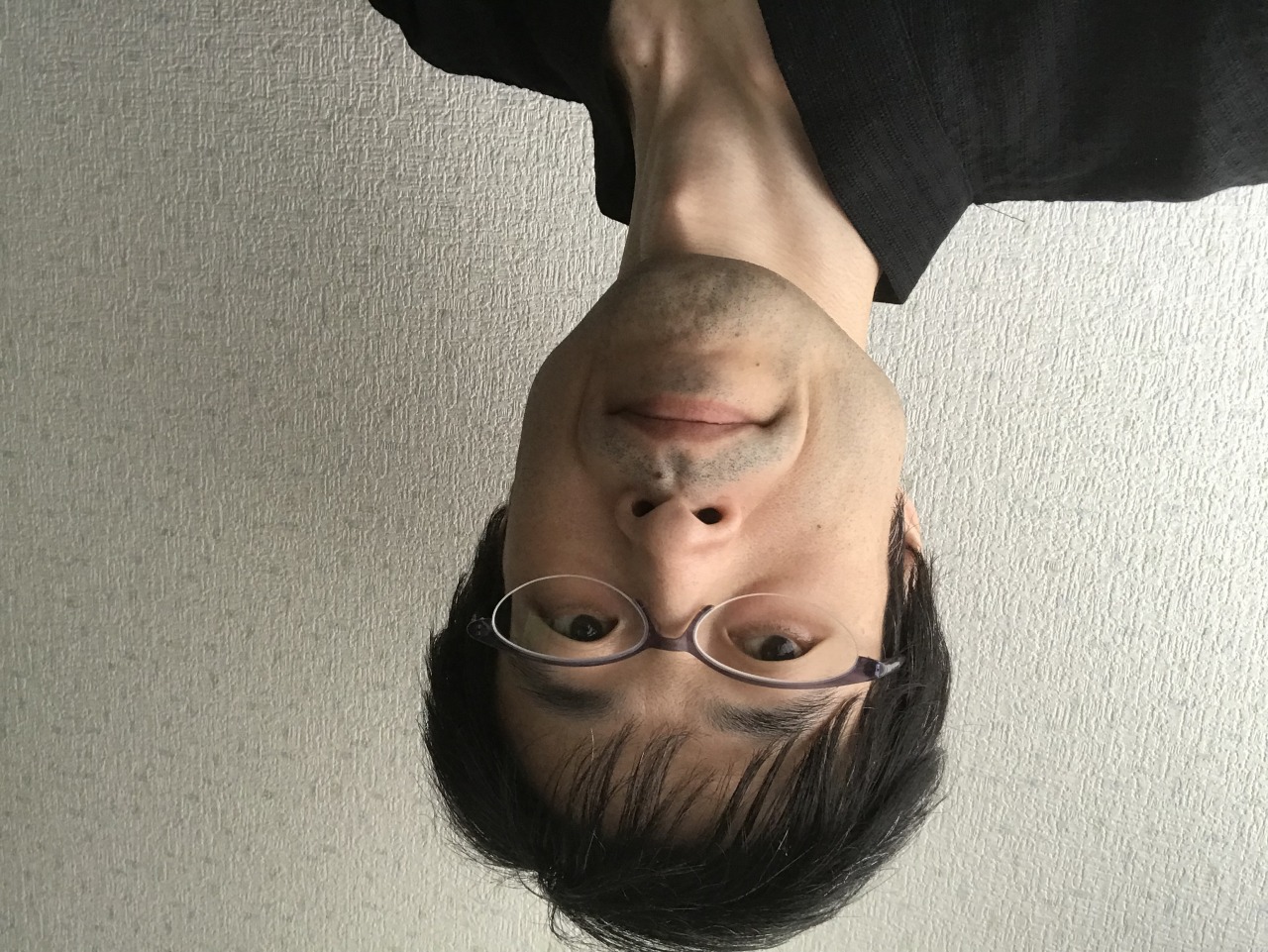
2024/06/27

宝くじの高額当選金をベーシックインカムに
最初に提案から述べたい。ベーシックインカムの実証実験をそろそろ日本でもやってみたらどうだろう。
筆者の推すところはこうだ。宝くじの高額当選金をベーシックインカムにする。
たとえば、昨年末の「年末ジャンボ宝くじ」だ。1等7億円の当たりくじが18本出ている。合計126億円になる。そこで、この金額を「ベーシックインカム賞」に充てることを想定してみる。
まずは、当選者の残り寿命だ。仮に50年とする。この方々に、月8万円のベーシックインカムを生涯給付する。
すると、合計は1人あたり4,800万円となる(8万円×12カ月×50年)。
そのうえで、126億円をこの金額で割ると、262.5という数字が出て来る。265人が当選だ。ベーシックインカムが月10万円だと210人、月12万円でも175人を実験対象にできる。
加えて、上記年末ジャンボでは、前後賞が40本出ている。当選金は1億5,000万円。総額では60億円となる。
これも合わせると、126億円+60億円=186億円となり、ベーシックインカム月8万円・想定残り寿命50年での実験対象者を387人見込める数字となる。
なお、高額当選者の出るジャンボ宝くじの種類は以下のとおり。当選金の規模には大小あるものの、現在、年に5回発売されている。
| くじ名 | 1等 | 前後賞 | 備考 |
| バレンタインジャンボ宝くじ | 2億円 | 5千万円 | 24年の場合 |
| ドリームジャンボ宝くじ | 3億円 | 1億円 | |
| サマージャンボ宝くじ | 5億円 | 1億円 | 23年の場合 |
| ハロウィンジャンボ宝くじ | 3億円 | 1億円 | |
| 年末ジャンボ宝くじ | 7億円 | 1億5千万円 |
このほかにも、億単位の高額当選金が出る宝くじ商品やスポーツくじはいくつか存在する。
よって、それらも動員すると、おそらく年間数百人から千人に近い規模のサンプルを毎年蓄積していくことが可能となる。老若男女問わず、「くじを買った人」という条件以外にスクリーニングのない、属性の広い多様なサンプルだ。
なおかつ、この人たちは、現在の宝くじ当選者がそうであるように、社会的視点からは、単に降って湧いた幸運に恵まれた人と認識される可能性が高い。政策上行われる保護や給付の対象となるのに比べ、不公平感から来る世間の非難や、深刻なやっかみを受けるケースは少ないはずだ。
そのうえで、彼らの人生をその後丁寧にモニタリングしていく。そのことで、ある程度精度高く、ベーシックインカムというパンドラの箱を開いたのちの社会の様子が見えてくることだろう。
もっとも、この方法にも弱点はある。それは、ベーシックインカムの影響と効果を世帯単位では掴みにくいことだ。
だが、その点も、くじの当選のさせ方などの工夫でうまく乗り切っていけるはずだ。端的には、当選者の世帯全員を当選者としてしまうやり方もある。その場合、不測に生じる負担は、後日別のくじの中で調整されることになるだろう。
あとは、給付が多年にわたるため、その間のインフレ、デフレ対応をどう設計に盛り込んでいくかなどが課題となる。
ともあれ、目下、国外から聴こえてくるベーシックインカムについての検証結果といえば、申し訳ないがどれも隔靴掻痒なものといっていい。
対象を失業手当受給者に絞った例であるとか、ある国の一部地域の村での年数を限っての実験であるとか。それでは、条件が狭すぎてパンドラの箱のフタは1秒1ミリほども開いた気がしない。
そのうえで、追加の公費を要さず(投入してもよいが)、未来を継続的に見据えるひとつの方法として、筆者は述べたようなやり方を考える次第だ。
パンドラのフタは、5ミリか1センチくらいは開くことができるだろう。しかも、開き続けることができる。
ブレイクスルーはいつか来る?
筆者は、ベーシックインカムの実現については明確に賛成派となる。
その根底に、あったらいいなの個人的な色気(笑)があることは確かだが、それを除いても、この仕組みには、人類社会の未来という暗がりにおいての光明が確かに感じられる。
なお、ここでの「暗がり」の中心は何かといえば、それは、今後AIと抜き差しならぬかたちで混淆しながら前進することを強いられる、われわれの社会であり、経済であり、人生となる。
なぜなら、筆者が想像するところ、AIと人類が相互に随伴、角逐しながら辿っていく将来の経済社会においては、消費が、ある意味人間の仕事のうちの重要な一種となるからだ。
珍妙な予想だが、農業――工業――第三次産業と、逐次移動してきた人類における人口の重心の行き先は、次には「消費」となる気がしてならない。
人類史は、実はその一面において、生産の苦から少しでも逃れたいがための模索でもあるからだ。われわれは、いまAIにこれを任せたがっている。
よって、人々に消費のための原資を配るベーシックインカムは、経済を回すための燃料供給にほかならない。現下の雇用確保(=賃金確保)に似た意味合いも持つものと言えるだろう。
とはいえ、現状、ベーシックインカムは夢だ。これをまともに実現できるリソースも、条件も、ほとんどの国は持ち合わせていない。われわれ日本の場合も、その財源を考えるだけで、話題はたちまち笑い話に帰してしまう。
しかしながら、経済というのは面白いものだ。テクノロジーの発達と複雑に絡み合いながら、想像もつかない未来をこれまでわれわれの前に実現させてきた。
たとえば、鋳・鍛造技術や印刷技術によって信用貨幣(広義の)が確立し、世の中が信用の概念で動くようになったことのすごさはどうだろう。
その信用が記号化され、通信に乗ることで、金融経済が世界を覆い尽くした事実は?
また、それより小さなところでは、市場経済が生み出した広告モデルによって、さまざまな芸術や創造が万人に開放されることになったり。
いわゆるコンテナ革命が、モノの値段を意味不明なカオスに叩き込んだり。
そうした意味で、筆者は、ベーシックインカムはある程度の段階を経るにせよ、何かのブレイクスルーとともに、案外遠くない未来に実現していく予感がしてならない。
そのときのためのシミュレーションをそろそろ日本でも始めておいたらどうかというのが、以上に示してきた内容だ。
ベーシックインカムとは何か?
順番があとになったが、ベーシックインカムとは何か? についてざっと触れておこう。基本的には、以下のようなかたちのものと考えられている。
ベーシックインカムとは?
国家が、国民一人ひとりに無条件で一定額のお金を支給し続ける制度をいう。給付は0歳から始まり生涯にわたる。もちろん、いまのところは想像上の制度だ。
給付される金額は、生活上必要な最低限を保障(保証でもいい)するものとなる。すなわち、特別な事情がない限り、ベーシックインカムだけで人はどうにか生活を維持できる。そのうえで、ベーシックインカムは課税されない。また、無条件での給付なので、ベーシックインカム以外にどれだけの所得があっても、ベーシックインカムの給付に影響はない。
ベーシックインカムのメリット
ベーシックインカムには、主なものとして、以下のようなメリットがあると考えられている。
- 社会保障にかかるコストの削減
ベーシックインカムが包括し、一元化することで、年金や生活保護、雇用保険など、さまざまな社会保障制度における規模の縮小、廃止が可能となる。誰もが貰えるものであるため、給付対象者を選別するためのコストもかからない。人件費はじめ、行政費用が大きく減らせられる。 - 貧困の減少、自己蔑視の抑制
無条件で収入が確保されるため、たとえば、現状貧困に苦しんでいながらさまざまな理由で生活保護を受けられていないような人も、救済を受けられる。誰もが貰うものであるため、これで生活をつなぐ人が罪悪感をもったり、自己を蔑視したりせずに済む。 - 労働環境の改善、企業の成長
無条件で収入が確保されるため、労働者が意に沿わない労働環境から離脱しやすくなる。と、同時に、いわゆるブラック企業は人員確保がしづらくなる。一方で、通常の企業にあっては、雇用調整がしやすくなることで、成長、変革の機会が増す。 - 人生の選択肢と可能性が広がる
ベーシックインカムが貰える分、働く時間を減らす選択肢が持てることによって、個人がスキルを身につけたり、新しいことにチャレンジしたりする機会を得やすくなる。趣味やボランティア、家族、コミュニティのための時間がつくりやすくなることで、人生充実のチャンスも増す。
ハードルと懸念
ベーシックインカムには、たとえば以下のようなハードルや懸念が指摘されている。
・財源のハードル
ベーシックインカムを実現し続けるには、国の人口に応じた財源が必要となる。ただし、その一部はベーシックインカムが生み出す行政コストの削減によって賄える。とはいえ、それがあったうえでも「生活上必要最低限」の給付を行うのは、高価な天然資源を豊富に蔵するなど、巨額な収入を望める国でなければ難しいと考えられている。また、その場合、収入源が枯渇すれば制度も終了となる。
一方、そうであれば、可能な限りの不完全なベーシックインカムでもよいとする考え方もある。行政コストの削減分および、国の歳入から割くことのできる限度内に収めるかたちで、規模を設定していくというやり方だ。ただし、その場合、給付額は生活上必要最低限―――すなわちベーシックと呼べるものにはならない。
ちなみに、ベーシックインカムの財源について、経済のプロからは、租税以外にも国債や通貨発行益の活用が挙げられたりもする。もちろん、さまざまな経済理論同様、これらには賛否がある。
・勤労意欲の低下、国力の低下、インフレの懸念
働かずとも生活できるだけのベーシックインカムが実現してしまえば、文字どおり働かない人が増え、労働や生産が減り、国力の低下につながるとの声は少なくない。ベーシックインカムを成長の糧にできる人材がある一方、これがない環境であれば本来成長していたはずの人材が、そうでなくなる可能性ももちろんある。なお、この記事の冒頭で提案したような実証実験の狙いは、そこを少しでも見極めていくことにある。
また、ここで起こりうる労働力の減少は、一方でベーシックインカムにより消費が促されることと相まって、基本的にはインフレ要因となることが指摘されている。これに対しては、楽観論と悲観論が濃淡交え存在していて、まさに予断を許さない。
(文/朝倉継道)
【関連記事】
リースバックはピンチを救う。しかし正体は「高負担のローン」かもしれない
野望が年収を上げていく?「労働者の働き方・ニーズに関する調査」のこと
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。