牧野知弘の「どうなる!? おらが日本]#3 バブル崩壊後の不動産と今後
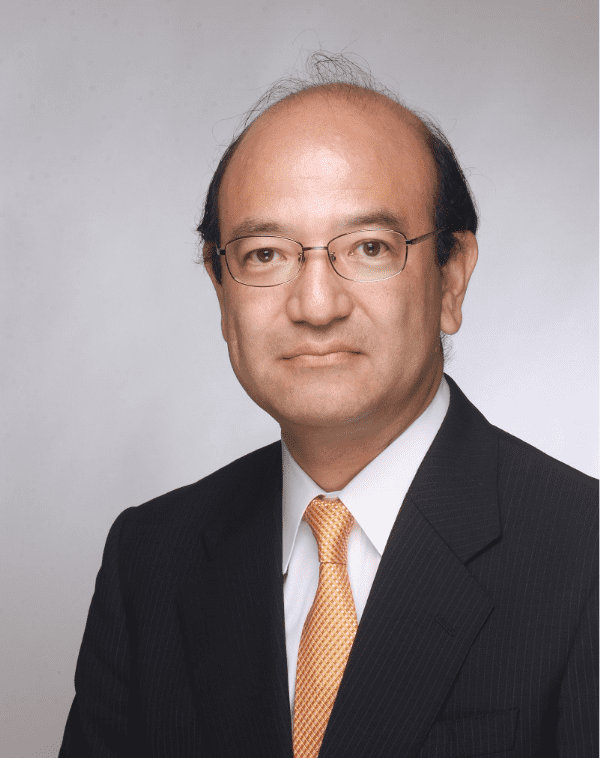
2018/04/20

狂ったようにマネーを供給
平成がスタートする1989年、日本の不動産価格は暴騰していた。プラザ合意を受けての内需拡大の宿題を背負った日本は金融緩和を続け、銀行は狂ったようにマネーを市場に供給し続けた。のちの時代に「過剰流動性」とも論評されたこの政策は、値上がりを続ける土地を担保に多くの企業が銀行から金を借り、不動産投資にのめり込んでいく事態を作り上げた。
地価は湯水のごとくに流れ込むマネーの恩恵を受けて値上がりを続け、土地の売買を繰り返すことで膨大なキャピタルゲイン(売買益)を計上する企業が続出した。この不動産投資にはさしたる理屈はなく、いち早く銀行から資金を調達し、怒涛のマーケットに勢いと度胸をもって参戦する法人のみが、本業ではない投資で勝ち続けるという異常な時代だった。
家の価格が毎月上がっていく
この頃の住宅事情を端的に物語って話題となったのが1991年(平成3年)TBS系列で放映されたトレンディドラマ「それでも家を買いました」だ。主人公は当時トレンディ俳優とも呼ばれた三上博史さんと田中美佐子さんだ。
ドラマでは二人は神戸で社内結婚、当時の常識として美佐子さんは会社を辞めて専業主婦。神戸から横浜に転勤になり社宅に入居するが、社宅の人たちのほぼ全員が、社宅を早く脱出して「家を買いたい」と言う。家は買えば財産になると皆が信じていたからだ。しかも「早く買わないと一生家を持つことはできない」というセリフがドラマでは繰り返し登場する。そこで彼らも横浜市内で住宅探しをスタートさせるのだが、その取得に困難を極めるというストーリーだ。
興味深いのが、当時実際に販売されていた物件が実名で登場し、販売価格と競争率も開示されていることだ。最初に彼らは横浜市泉区緑園で、当時三井不動産と相模鉄道が分譲した駅近のマンションを申し込む。価格は3800万円から4000万円台。彼らの予算では上限だが、そもそも抽選で当選できない。なぜなら競争率は200倍だからだ。
私もこの当時三井不動産に勤務していたが、たしかに人気のあるマンションの競争率が100倍から200倍になるのは珍しいことではなかった。「家の価格は毎月上がっていく」という社宅の住民たちの声を背に、彼らは相模鉄道沿線の大和や海老名などにも手を広げていくが、結局どこも買うことができず、最終的には神奈川県の西端、津久井湖近くの分譲地を購入してドラマは終わる。ドラマのエンディングは横浜の会社まで通勤2時間、早朝に原付バイクに跨った三上さんが最寄り駅まで出勤していく姿を美佐子さんが見送るという場面で終わるのだが、こうした光景自体、この時代ではごくあたりまえの住宅取得物語だったのだ。
平成バブルとも言われたこの現象を叩き潰したのが、日本銀行や政府であった。日銀は公定歩合を上げるだけでなく、不動産融資に関して総量規制を実施、銀行から企業などへの投資マネーの供給を絞り込んだ。政府は地価税を創設、また不動産取引においては国土法を設けて取引の内容や価格を届け出ることを義務付けた。
こうした人為的な地価の引き下げ効果はてきめんだった。1992年(平成4年)ごろから地価は下がり始め、不動産投資にのめり込んでいた多くの企業はマネーの供給源を失い、倒産が続出する。こうした企業は不動産投資を自らのバランスシートで行っていたために、バランスシートは肥大しきっており、金利上昇と不動産価格の急落に耐えられる構造にはなかったのだ。
「ジャパンアズナンバーワン」の綻び
1995年(平成7年)には巨額の農協マネーをバックに不動産融資を続けていた住専(住宅金融専門会社)が破綻、都市銀行の一角だった北海道拓殖銀行も北海道内での不動産融資案件の失敗を引き金に倒産したことは、大手証券の山一証券の倒産とともに大きな話題となった。
地価は政府や日銀の目論見通りに沈静するどころか急落を続け、「ジャパンアズナンバーワン」などと言っていた日本経済全体に暗雲が垂れ込める事態へと発展する。
ところで、この地価の崩落が、不動産業や人々の住宅に対する考え方を大転換させるきっかけを作ったことは、あまり知られていない。実は1995年から1997年(平成9年)の3年間は日本の不動産に大転換をもたらした時期といえるのだ。
日本の地価が大きく下がったことは、それまで不動産に多額の資金を注ぎ込んできた銀行をはじめとする金融機関に大量の不良債権を生み出した。銀行はこの不良債権に苦しみ瀕死の状態にあった。しかし、世の中には屍があればその屍に群がりこれを処理する存在が必ず出現する。
ハゲタカ投資ファンドの登場
外資系の投資ファンドは、日本の不動産を担保とした不良債権に目を付け、これを信じられないほど低廉な価格で買い取るビジネスを展開する。彼らが買う価格はバブル時代の10分の1以下。それでも一刻も早く不良債権を手放したい多くの金融機関が外資系ファンドにこの債権を売り渡した。ファンドはこれらの債権を切り刻んで証券化し、世界中のマーケットに売り飛ばす、不動産自体を再生させて付加価値をつけて売り飛ばす行為にでた。いわゆる「ハゲタカ」はテレビドラマにもなり世間の耳目を集めることとなる。
こうした動きは、不動産と金融の融合と呼ばれる不動産証券化ビジネスの隆盛へと展開していくことになる。
郊外から都心回帰へ
不動産をとりまく日本社会の構造も1995年(平成7年)を境に大きな変化を始めた。それまでずっと増加し続けた日本の人口は、総人口こそ増加基調は保っていたものの、15歳から64歳の生産年齢人口と呼ばれる働き手の人口に関してはこの年をピークに減少に転じる。1ドル80円という超円高を嫌気した東京や大阪の湾岸地帯にあった工場群の多くは、アジアにその生産拠点を移し始めていく。
こうした動きに呼応するかのように1995年には大都市法が改正され、それまで容積率がおおむね200%程度だった工業地域が軒並み600%程度にまで引きあげられ、宅地への転換が後押しされたのである。湾岸部の工場や倉庫の跡地は敷地面積も広く、大手デベロッパーなどがこの土地上に超高層マンション(タワマン)を建設するようになる。土地の価格は大きく下落していたので比較的リーズナブルな価格で土地を取得でき、大量の住戸を低廉な価格で提供できるようになったのだ。これまで郊外へ郊外へとスプロール化していた住宅供給の方向性がこの時期以降大きく転換していくのである。
人々のライフスタイルも一変する。1997年には男女雇用機会均等法の改正が行われた。改正の目玉は、それまで認められてこなかった女性の深夜残業や休日勤務に対する制限が撤廃され、女性も男性と同様に働くことが許されるようになったのだ。
景気の低迷やデフレ経済の進展を背景に、家計も夫一人が支える構造から夫婦共働きがあたりまえとなる。専業主婦世帯と共働き世帯の世帯数が逆転するのも1995年前後のことである。
ダブルインカムとなった共働き世帯は、都心のタワマンに住み、子供を保育所に預けて働く、このスタイルを続けるにはもはや郊外の住宅などには目もくれなくなった。ましてや親が必死の想いで購入した郊外戸建て住宅に同居や相続をして、1時間以上の通勤をするライフスタイルは、家族という枠組みが変化する中で、彼らの選択肢には到底なりえなくなる。こうして都心居住は、マーケット事情、各種政策、そしてライフスタイルの変化を伴って大いに変容していくのだ。
都心回帰の現象は郊外住宅地の不動産価値を減じさせることとなる。かつては憧れの的だった西鎌倉や片瀬山、あるいは逗子といった高級住宅地の価格は大幅に下落、IT長者などと呼ばれる若き成功者たちは便利な都心部の豪華共用施設が整ったタワマンを生活拠点に選ぶこととなる。
不動産証券化の隆盛
平成バブル崩壊後の不動産投資マーケットには大きな変化が訪れた。それまでのバランスシートでリスクの高い不動産に投資することの恐さを思い知らされた不動産業者は、資金を銀行などの間接金融に頼るのではなく、投資家をタニマチに仕立てて、彼らの資金を預かって投資を行うという不動産証券化の手法を開発する。
不動産は証券化という手法を通じてマネーマーケットと結びつき、世界の投資家から個人資金までを招き込んで不動産に投資することによって大きく拡大し始めたのだ。
2001年(平成13年)9月、東京証券取引所に日本ビルファンド投資法人とジャパンリアルエステート投資法人の2社が日本初の不動産投資信託(J-REIT)として上場を果たす。不動産証券化の手法はJ-REITのみならず、様々な形態の投資ファンドが組成され、国内外の投資マネーを日本の不動産マーケットに呼び込む流れを作り出すことに成功する。
日本の不動産マーケットはこれまでは、不動産業を営む大家が自らのファイナンスで投資を行ってきたために、たとえばテナントの賃料等の情報が開示されることはなかった。こうした「情報の非対称性」が不動産を胡散臭い、近づきがたい存在にしてきたが、証券化は幅広く投資家を募るにあたっての、不動産に関する情報開示が求められ、そうした意味で不動産事業の「開国」あるいは「民主化」につながったともいえるかもしれない。
しかしいっぽうで、不動産が金融という魔物と手を結んだことは、魑魅魍魎が跋扈する金融マーケットに不動産の世界が翻弄されることとなる。2008年(平成20年)に生じたリーマンショックは、投資家のお金を集めて運用してきた多くの不動産ファンドが甚大な影響を被ることになる。
不動産はソフトの時代へ
こうした変化の波の中で、現在は2年後に迫った東京五輪を前に、東京をはじめとした大都市のあちこちで開発の槌音が響いている。グローバルマーケットに根差すようになった日本の不動産マーケットは住居などの実需が縮小するいっぽうで、インバウンドマネーなど新たな資金を呼び込むことで新たな成長ステージを築こうとしている。
平成の次の時代は、果たしてマネーだけを頼りにした相変わらぬハード中心の世界で不動産業は成り立っていくのだろうか。それとも自動車産業がガソリンから電気にといったコペルニクス的大転換を迎えようとしているように、不動産もハコの中身を問われる時代がやってくるような気がしている。それはすでにホテルやショッピングモールなどの隆盛に見られる萌芽が、民泊やリゾート、医療や介護施設などをも加えたオペレーショナルアセット(運営を伴う不動産施設)全盛の時代に大きく変化していくことをすでに時代は暗示しはじめているようにも映る。平成という激動期を経て不動産業界にもまた新しい時代が到来するのだ。
この記事を書いた人
株式会社オフィス・牧野、オラガ総研株式会社 代表取締役
1983年東京大学経済学部卒業。第一勧業銀行(現みずほ銀行)、ボストンコンサルティンググループを経て1989年三井不動産入社。数多くの不動産買収、開発、証券化業務を手がけたのち、三井不動産ホテルマネジメントに出向し経営企画、新規開発業務に従事する。2006年日本コマーシャル投資法人執行役員に就任しJ-REIT市場に上場。2009年オフィス・牧野設立、2015年オラガ総研設立、代表取締役に就任。著書に『なぜ、町の不動産屋はつぶれないのか』『空き家問題 ――1000万戸の衝撃』『インバウンドの衝撃』『民泊ビジネス』(いずれも祥伝社新書)、『実家の「空き家問題」をズバリ解決する本』(PHP研究所)、『2040年全ビジネスモデル消滅』(文春新書)、『マイホーム価値革命』(NHK出版新書)『街間格差』(中公新書ラクレ)等がある。テレビ、新聞等メディアに多数出演。





















