牧野知弘の「どうなる!? おらが日本」#23 コロナ禍を契機に変わる家選びの基準
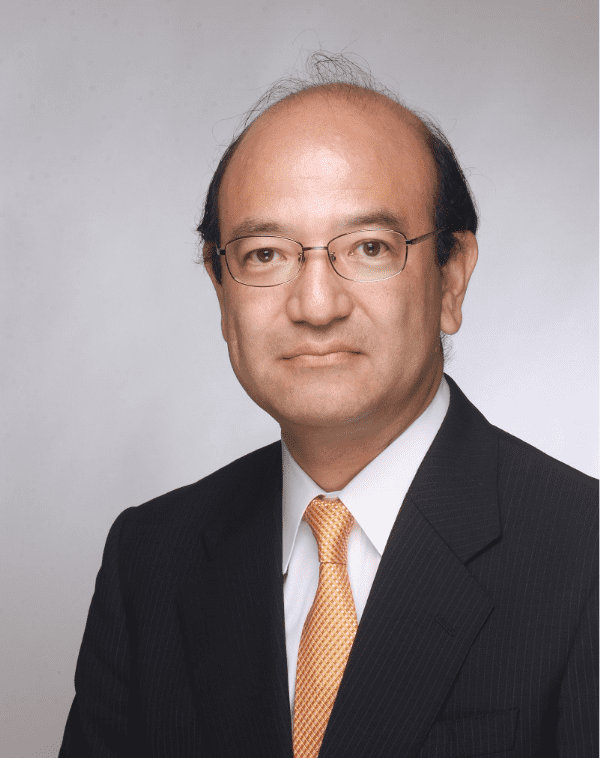
2021/07/28

イメージ/©︎smallcreativeunit・123RF
コロナ禍の収束がなかなか見通せない中、最近は家選びの傾向が変わってきているという。つまり、これまでの都心一辺倒の家選びから、郊外での戸建てやマンションを選ぶ傾向が出てきていることだ。
こうした傾向はコロナ禍によって、会社で働くワーカーが通勤を前提とした働き方から、テレワークを取り入れて、週1回、あるいは月2、3回程度の勤務体系が常識化していることが背景になっている。
現在の東京都心部は、超高層マンションが林立している。特に東京湾岸部、豊洲、晴海、月島、勝どきから芝浦、品川にかけてはタワマン村といってもよいほどの林立ぶりである。これら超高層マンションの多くは、もともと工場や倉庫などがあった場所で、産業構造の変化で、多くの工場が東アジアや東南アジアに移転。その跡地において、大都市法を改正して容積率を2倍から3倍に嵩上げして、建設されたものである。
また最近ではJRの主要駅の駅前を中心に、市街地再開発の手法などを用いて、既存の商店街や老朽化した木造住宅街を再開発。その計画のどれもがお約束のように総戸数数百戸にも及ぶ超高層マンションを建設、分譲している。これも再開発という網掛けを行うことで容積率を上乗せし、超高層マンション建設を誘導している。
「“都心のタワマンは買い”という常識」は未来永劫続くのか?
夫婦共働きが当たり前の時代、会社に通勤するのに便利な都心部のマンションを選ぶのはごく普通の選択肢であったし、タワマンはそうしたワーカーたちの要望を満たすものでもあった。
都心居住への誘いは、都心のマンション価格の高騰をもたらした。続々建設される超高層マンションに人気が集まれば、当然マンション価格も跳ね上がった。折しも、アベノミクスによる超金融緩和策と住宅購入に際しての圧倒的な税制優遇、史上最低レベルに落ち込んだ低金利が後押ししたことは言うまでもない。価格があがれば、さらに国内外からの投資など新たな需要を引きずり込んでマンション価格は上がり続けた。特に2013年から17年頃にタワマンを買った人の多くがかなりの含み益を持っているのは事実であるし、私の知人で、賢く売り抜けた人も少なくない。
ずばり「都心のタワマンは買い」という常識ができあがったのだ。
だが、同じ法則がいつまでも続くほど世の中は甘くはない。コロナ禍がきっかけになって始まった郊外への需要シフトをどう考えるべきなのだろうか。よくこうした傾向について、ネットなどでは、都心のマンションは絶好調、郊外シフトは一時的な現象、コロナが終われば人々は再び都心に戻るから、価格は維持される、あるいはもっと値上がりするといったコメントが並ぶ。本当だろうか。
私からみれば、都心部の所謂ブランド立地と呼ばれる麻布や青山、赤坂、白金といった立地のマンションは、コロナ禍の影響はほとんどない。このマーケットは富裕層と国内外の投資家によって支えられているからだ。都心マンションはぜんぜん問題ないと言っているのは、この一部のエリアでの動きを語っているにすぎない。不動産のプロからみればおそらく常識中の常識だ。
「フーテンの寅さん」のような生活が実現可能に
いっぽうで、会社ファーストの家選びを強いられてきた実需層の動きは、だいぶ多様化してきている。これまでの会社まで1時間以内、できれば40分以内。そのためには駅近、徒歩5分以内といった法則から解放され、居住環境を重視する生活ファーストの家選びにシフトを始めているのだ。
夫婦で在宅ワークをするのには、都心部のマンションでは部屋が狭すぎる。隣戸との音漏れやWi-Fiの容量不足なども気になる。なんといっても都心マンションの価格は夫婦でそれぞれ20年から35年にもわたる長期のローンを組んで返済しなければならない。通勤のウェートが下がれば、何も無理をして都心居住を選択しなくてもよくなるのだ。
首都圏郊外の中古戸建て住宅は都心のマンションに比べれば格安だ。かつての通勤圏で今では都心まで1時間半はかかるところだった、たとえば湘南の茅ケ崎や平塚、大磯、横須賀や三浦ならおおむね2000万円から3000万円も出せば、かなり質のよい物件を手にすることができる。毎日ではなく週1回、月2、3回の通勤なら無理なく暮らせる範囲だ。海を身近にテレワークするにはこれらの街は、絶好の環境といえるだろう。
二拠点居住を選択する人も出てきている。都心のマンションはそのままに、軽井沢など、自分のお気に入りのエリアに家を構え、基本的にはそこに生活しながら、都心に出てきた時だけマンションですごす。毎日通勤する必要がなくなってくれば、自らの拠点をその日のスケジュールやイベント、季節や天候に応じて住み分ける生活も可能となる。
働き方のほとんどがパソコンなどの情報通信端末で働く人、たとえば弁護士や会計士、コンサルタントなどのプロフェッショナル系になると、二拠点居住を超えて、「好きなときに」「好きな場所で」「好きな仕事」をするようになってきている。
昔から夏は北海道、冬は沖縄に住みたいなどと言われてきたが、最近の働き方の変化はこうした「フーテンの寅さん」のような生活が実現可能となっているのだ。
そのような世の中になってくると、さて都心部に高額のローンを背負って、所有しているマンションの資産価値なるものは維持できるのだろうか。当たり前だが、需要がない限り不動産価格を保つことはできない。
物質的な豊かさから「実感できる豊かさ」へ
日本人の寿命は戦後一貫して伸び続けている。今から50年前の1970年における平均余命は男性で69.31歳、女性で74.66歳だった。現在は男性81.41歳、女性87.45歳だ。今マンションを購入している現役世代は、おそらく100歳くらいまで生きることになるだろう。
35年の住宅ローンを組んで、定年退職時まで払い続けた結果得るものは築35年の古ぼけたマンションだ。そして定年は徐々に先延ばしされているとはいえ、退職後にまだ30年程度生きなければならないのが、どうやらこれからの日本人の平均像だ。一生懸命に買ったマンションにずっと住み続ける選択肢もあるが、そのマンション、100歳まで過ごすのに本当に快適なマンションだろうか。何に価値を見出すのかといえば金銭的な価値の値上がりだけというのは悲しすぎる。こうした人生すごろくをクリアしていくのに、「都心で買ったマンションは値上がりするはずだ」という常識には、その先の非常識が顔をのぞかせているようだ。
今、世界はGDP(Gross Domestic Product)からGDW(Gross Domestic Well-being)へ時代の転換期にあると言われている。すべての価値を量的な拡大、物質的な豊かさ、客観的な指標に基づいて評価される常識から、質的向上、実感できる豊かさ、主観的な指標で価値を判断する非常識への転換である。
土地があって、土地面積に容積率を掛け合わせて巨大な建物を建築(量的な拡大)する。その結果としてのタワマンをローンで思い切り背伸びして買う。都心タワマン居住(物質的な豊かさ)という誇りを持って生きる。そこまでしたらマンションは絶対に値上り(客観的指標)してくれなければ困るのだ、という無理筋の常識はこれからの時代には通用せずに非常識に変容していくのかもしれない。
自分たちの生活を第一義(質的向上)に考えて、決して無理をせず、家計的にも優しい(実感できる豊かさ)、住んで楽しい(主観的な指標)、季節や都合によっては複数の家を住みこなす、そんなしなやかな住まい方がやってくる。これを「非常識だ!」と考えるのは自由だが、世の中は常識の先に非常識がある、このことはこれまでの歴史が物語っている。歴史は常に変わるのだ。
牧野知弘の「どうなる!? おらが日本」
大都市でこれから深刻化する賃貸空き家の実態とその活用
コロナ禍と東京五輪開催に翻弄される『HARUMI FLAG』の行方
コロナ終息までホテルは生き残ることができるか
この記事を書いた人
株式会社オフィス・牧野、オラガ総研株式会社 代表取締役
1983年東京大学経済学部卒業。第一勧業銀行(現みずほ銀行)、ボストンコンサルティンググループを経て1989年三井不動産入社。数多くの不動産買収、開発、証券化業務を手がけたのち、三井不動産ホテルマネジメントに出向し経営企画、新規開発業務に従事する。2006年日本コマーシャル投資法人執行役員に就任しJ-REIT市場に上場。2009年オフィス・牧野設立、2015年オラガ総研設立、代表取締役に就任。著書に『なぜ、町の不動産屋はつぶれないのか』『空き家問題 ――1000万戸の衝撃』『インバウンドの衝撃』『民泊ビジネス』(いずれも祥伝社新書)、『実家の「空き家問題」をズバリ解決する本』(PHP研究所)、『2040年全ビジネスモデル消滅』(文春新書)、『マイホーム価値革命』(NHK出版新書)『街間格差』(中公新書ラクレ)等がある。テレビ、新聞等メディアに多数出演。





















