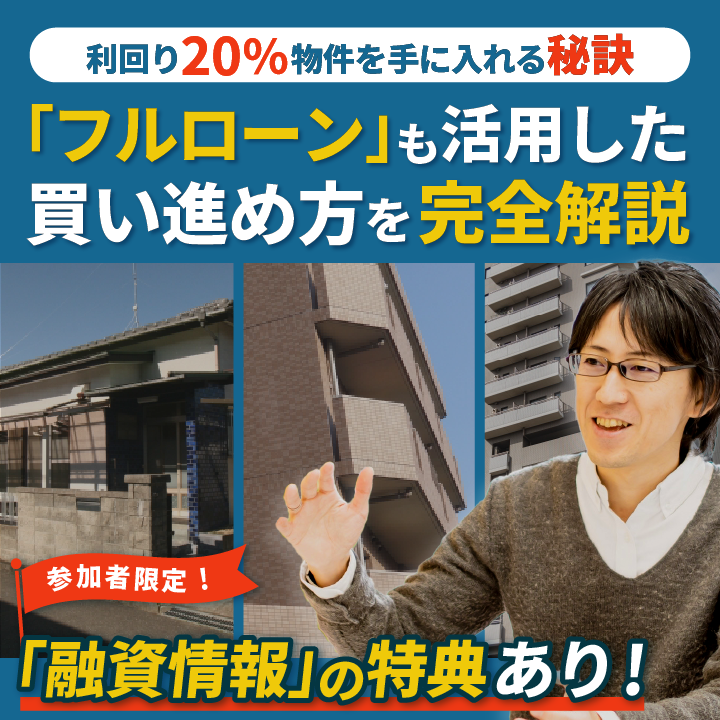なので私はこう言い放った…「メルカリで家は売れない」

2021/05/17

「NIKKEI Real Estate Summit」会場風景/撮影・全日本不動産協会
不動産の賃貸・売買――私たちにとって身近な住まいに関する取引の裏側は、意外にも複雑です。また、市況や資材の騰落、はたまた国の施策や、今後進むであろうデジタル化により、そのとき、そのときで関わり方が変わってくるものです。そこで本連載では、第一住建株式会社代表取締役であり、全日本不動産協会の常務理事でもある南村忠敬氏が、不動産業界・日本国の「明日」を見据えながら、フランスのモラリスト、ミシェル・ド・モンテーニュよろしく、さまざまな問題や解決策を綴っていきます。第1回は~「NIKKEI Real Estate Summit」 登壇記~。
◆◆◆
東京の中心で思いの丈を叫ぶ
新型コロナウイルス感染拡大防止に全世界が右往左往していた。
我が国では、2020年4月に最初の緊急事態宣言が出されたのに続き、2回目の宣言発令により開催が危惧されていたが、宣言発令地域の知事らが前倒しの解除要請を政府に申し入れたため、ハイブリット形式ではあったが、2月19日に東京国際フォーラム(有楽町)で開催された「NIKKEI Real Estate Summit」[(日本経済新聞社主催、東京大学不動産イノベーション研究センター(CREI)協力、野村不動産アーバンネット(現社名・野村不動産ソリューションズ)・三井トラスト不動産 協賛)]、不動産流通のシンポジウムにパネリストとして招かれ、思いの丈を叫んで来た(?)ときのお話。
モデレーターはCREIの機構長で東京大学経済学研究科教授・柳川範之先生。メインテーマは、「不動産流通イノベーション〜不動産情報の集約化と新技術が拓く、不動産業の未来」という、何だか一介の不動産屋には唐突で、いきなりITイノベーションの異端、ジャンヌ・ダルクの心境でステージに設えられた「自分の席」に着いた。

ジャンヌダルクの心境で席に着く/撮影・全日本不動産協会
パネラーには私のほか、大手不動産会社執行役員、プロップテック企業CEO、国交交通省担当者という、こっちの肩身が狭くなるような顔触れである。
一通り自己紹介を兼ねた今日のテーマに沿ったプレゼンテーションで舌の滑りをよくしたあと、柳川先生から、「コロナ禍がデジタリゼーションを促進したことによって不動産流通の分野ではどのような変化が起きるか!?」と問われる。
コロナ禍での特徴的なデジタリゼーションと言えば、テレワーク推奨による非対面の業務へのシフトだろう。コロナ発症以前から、我が業界でも遅ればせながら非対面業務の実証実験は行われてきたが、それに拍車を掛けることとなったのがこの騒動だ。所謂遠隔での業務や作業を必然的に行わなければならない状況が向こうからやってきたというわけ。それを可能にした技術がプロップテックの一つ。巷では「不動産とテクノロジーの融合≒不動産テック」と呼ばれることも多いが、プロップとはプロパティ(Property)のことで、テクノロジーによって不動産投資を呼び込む時代の到来を意味している。
しかしながら、不動産業界と一括りで捉えても、個人免許の事業主や従業員5人以下の零細事業者から、大手と呼ばれる従業員数百名規模の旧財閥系、電鉄系、銀行系事業者など、顔ぶれも多彩で、日本全土、北海道稚内から沖縄与那国島まで約12万社の事業者が営業している。
なかにはAR・VR技術を駆使した物件案内無人化を武器にテックを操る業者も居れば、まだまだ「紙媒体」を得意とし、電話・FAX・マンパワーの営業で頑張っている者も多いのが業界の実情だ。デジタリゼーション・ピラミッドの底部にそれら事業者群を位置付けるなら、彼らだって段階的デジタイゼーションに対応しており、例えばFAXからE-mailへ、新聞広告からインターネット広告へ、というようなレベルから、SNSでの広報戦略、テレビ会議や非対面重要事項説明なんかも導入を急いでいる業者までさまざま。
コロナ禍のデジタリゼーション促進と言われても、必要に迫られればやるし、そうでなければやらない。そんな業界だから、個々の事業者にデジタリゼーションを煽っても大きな波は起こせない。
なので私はこう言い放った。「メルカリで家は売れない!!」って。
東京の中心で思いの丈を叫ぶ 「メルカリで家は売れない!!」/撮影・全日本不動産協会
これ、結構深い意味があるんです。
如何なる産業分野でも、ITイノベーションを巻き起こすためには事業者間における格差の解消が課題となる。DX※社会を目前にしてもなお、旧態依然の業態から抜け出せない事業者は一定数残る。
※DX(デジタルトランスフォーメーション)/「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念のことで、2004年にスウェーデン・ウメオ大学(Umeå University)教授のエリック・ストルターマン氏によって初めて提唱さた。日本では、2018年に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン」を取りまとめ、それを契機に産業界に広まった。
大切なのは小手先のデジタライズではなく煩雑なプロセスを簡素化すること
デジタライズは、デバイスのデジタル化を指すが、それだけではDXには繋がらない。事業者の自己満足で終わる。デジタリゼーションの波が対コロナ対策限定ならば格別、DXの流れはコロナ発症以前から進められていたわけで、単に拍車が掛かったというに過ぎない。
シンポジウムで用意されていたテーマは大きく三つ。最初の課題で大いに盛り上がってしまい、柳川先生は二つ目と三つ目のテーマを上手く混ぜてパネラーに問うた。
禁じ手だ!
「不動産流通を活性化させるために、イノベーションはどう進むのか? 描く未来像は??」と、来たから、プロップテック企業のCEO氏が自社の強みも込めて、不動産事業者向けの技術に囚われない、プレーヤー主導型のエコシステムづくりを進めて行くと語尾を強めた。しかし、私は中小零細不動産業者の代表を買って出た身であるから、技術革新の陰に埋もれるアナログ育ちを置き去りにはできない。そこで、「中小零細もDXは必要! ただし、デバイスのデジタライズを進める前に、アナログ社会が作り上げてきた不動産実務のプロセスを見直すことから始めないとダメ! 要はプロセスのデジタル化が必須条件!」と力を込めて言った。
大手不動産会社なら、資金力や組織力、ネットワークの優位を使ってデバイスのデジタル化にいち早く切り替えが可能だろう。しかし、大手であっても、不動産流通実務においてそのプロセスは零細企業と同じだ。ここは大手だ小手だと言っている場合ではなく、ユーザーニーズ(≒社会的ニーズ)を満たすために、煩雑な不動産流通の仕組みや因習、手続き、税金、法律などを見直し、必要なプロセスをデジタル化していくことが必要だと私は提唱する。そうすることで、小手先のデジタイゼーションに留まることなく、必然的にデジタライズが進み、気が付けばDXが業界全体に定着するのではないか。
国交省担当者からも、「必要な法改正は行う」との発言も飛び出した。
願ったり叶ったり。
〜この国の明日に想いを馳せる不動産屋のエセー〜
不動産「AI価格査定」という宣伝文句の裏側にあるもの
この記事を書いた人
第一住建株式会社 代表取締役社長/宅地建物取引士(公益財団法人不動産流通推進センター認定宅建マイスター)/公益社団法人不動産保証協会理事
大学卒業後、大手不動産会社勤務。営業として年間売上高230億円のトップセールスを記録。1991年第一住建株式会社を設立し代表取締役に就任。1997年から我が国不動産流通システムの根幹を成す指定流通機構(レインズ)のシステム構築や不動産業の高度情報化に関する事業を担当。また、所属協会の国際交流部門の担当として、全米リアルター協会(NAR)や中華民国不動産商業同業公会全国聯合会をはじめ、各国の不動産関連団体との渉外責任者を歴任。国土交通省不動産総合データベース構築検討委員会委員、神戸市空家等対策計画作成協議会委員、神戸市空家活用中古住宅市場活性化プロジェクトメンバー、神戸市すまいまちづくり公社空家空地専門相談員、宅地建物取引士法定講習認定講師、不動産保証協会法定研修会講師の他、民間企業からの不動産情報関連における講演依頼も多数手がけている。2017年兵庫県知事まちづくり功労表彰、2018年国土交通大臣表彰受賞・2020年秋の黄綬褒章受章。