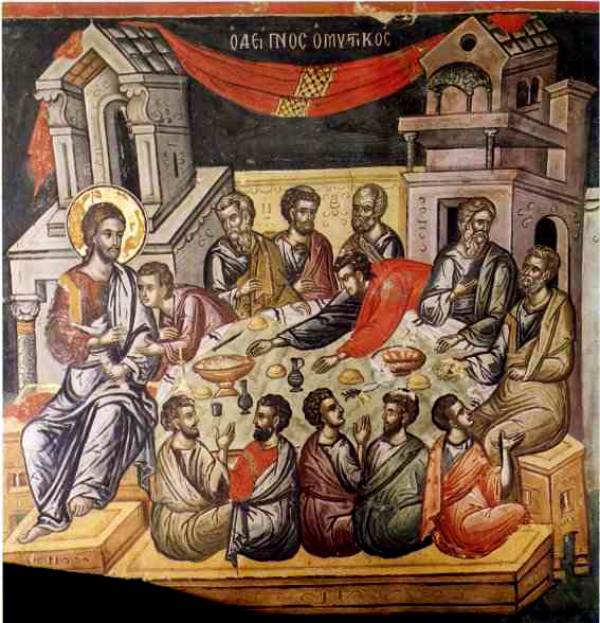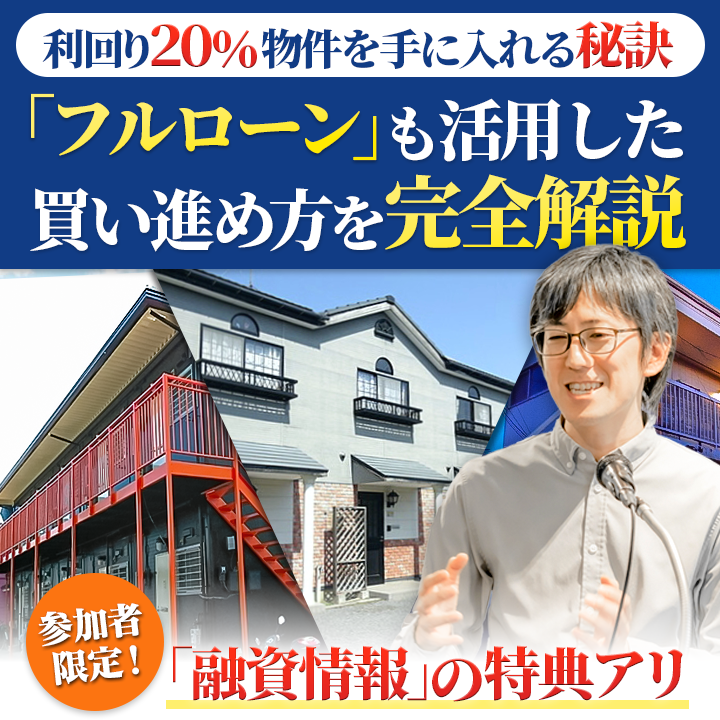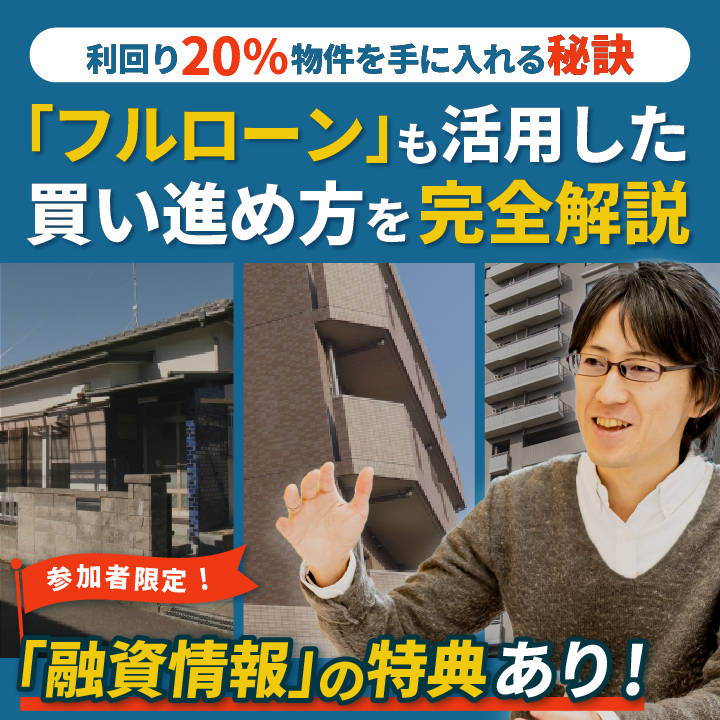インドでの新型コロナ感染爆発とヒンドゥー教の関係

2021/05/13

イメージ/©︎alekstaurus・123RF
信者数世界3位でも世界宗教にならないヒンドゥー教
インドの総面積は日本の8倍、人口は14億人近くあって、そのうちの85%がヒンドゥー教の信者である。ということは、ヒンドゥー教は12億人近い信者がいることになる。この数は、いわゆる世界宗教とされるキリスト教の22億人、イスラム教の18億人に次いで、第3位にランクされる。
ただし、ヒンドゥー教は世界宗教ではない。なぜなら、世界宗教は民族や地域を超えて信仰されている宗教と定義されるからだ。
ヒンドゥー教は、インドネシアのバリ島など、ごく一部に例外はあるものの、信者はほぼインド国内に限られるので、世界宗教ではない。ユダヤ教などと同じように、特定の民族や地域でのみ信仰されている宗教と定義される民族宗教のジャンルに入る。
また、ヒンドゥー教は世界最大の多神教でもある。ちなみに、仏教は世界宗教でしかも多神教のジャンルに入るが、その信者数は約5億人なので、ヒンドゥー教の半分以下しかない。
公認されている言語が21もあるインドの独自性
インドは現在、25州から構成されている。各州は政府と閣僚を擁して独立性が強く、それぞれがミニ国家の様相を示す。その原因の1つに、言葉の問題がある。
連邦公用語はヒンディー語だが、そのほかに憲法で公認されている言語が21もある。かなり多くの人々が使っている言語だけでも15以上あるため、インドの紙幣には17の言語が印刷されている。このような事情から、隣同士の州でも、言葉が通じないことが間々ある。
私自身もこんな経験をした。京都にある国際日本文化研究センターの研究会で、隣同士の州出身のインドの2人の研究者同士が、休憩時間中に流暢な日本語や英語で雑談していたので、理由を尋ねると、自州の言葉では互いに話が通じないから、と答えた。
確かに、インドの自然環境は、南北方向ではヒマラヤ山脈の寒冷地から赤道に近い酷暑地まで、東西方向ではパキスタンに隣接する乾燥地帯からバングラデシュを超えてミャンマーに続く多雨地帯まで、気候が大きく異なる。
インド人同士の一体感とは
民族構成もさまざまだ。
北方から中部にかけては、今から3000年くらい前に中央アジアの西部からやってきたアーリア系の民族が主流を占めている。南の方はそれ以前から居住していたドラヴィダ系の民族が多い。ヒマラヤ山脈にはモンゴロイド系の民族もいる。
この通り、インドはまさに多種多様の地なのだが、それでいて不思議なことに一体感も強烈にある。
例えば、各地方にはいわゆる「お国自慢」があって、自分が住んでいるところほどいいところはないと言いつつ、ほかのところはみな「よくないところだ!」と悪口を言ってはばからない。ところが、そこに私たちのような外国人が口を挟むと、「あなたにそういうことを言われる筋合いはない。インドを馬鹿にするな!」と叱られてしまう。
つまり、インド人が互いの悪口を言うのは許されても、外国人がインドのどの地方であれ、悪口を言ってはならないのである。
ヒンドゥー教の存在が1つの国家としての“絆”
バラバラで、しかも1つ――。この不思議な関係を支えているのは、いったい何か。答えはヒンドゥー教である。
ヒンドゥー教は二層構造をもっている。第1層は、ヒンドゥー教徒全体を統合する層。第2層は、第1層のなかに含まれていて、地方ごとの文化的な伝統として存在する。研究者によっては、前者を「大伝統」、後者を「小伝統」と呼ぶ。イメージとしては、巨大な円蓋が、その下に、無数の小さな円蓋を覆い尽くしている構造である。この構造を理解しないかぎり、インドは理解できない。
やむにやまれない祭礼の開催
どの宗教にも、非日常と日常がある。日本の伝統的な観念では「ハレ(晴)とケ(褻)」だ。
日常=「ケ」をつつがなく全うするためには、ときとして、非日常=「ハレ」が欠かせないというのが、人類が長い歴史を経て獲得した普遍的な知恵といっていい。
そして、非日常=「ハレ」の典型例が祭礼である。祭礼では、日常的な約束事が無視されたり無意味になり、人々はほかには体験できない開放感を満喫する。
もちろん、ヒンドゥー教にも祭礼があまた用意されている。
特に重要なのが、「ホーリー祭(毎年3月ごろ開催されるヒンドゥー教最大の祭礼/春の豊作祈願や悪魔払いなど)」と「ダシュラ祭(毎年9月~10月頃に開催/さまざまなイベントや出し物が行われる)」と「ディワーリー祭(毎年10月~11月の新月に開催されるヒンドゥー教の新年の祝いの祭り/光が暗闇に勝利したことが起源)である。
ホーリー祭で色粉を掛け合うクリシュナと愛人ラーダと牛飼いの娘たち(19世紀の絵画)/via Wikimedia Commons
新型コロナは世界的に初冬~年末年始に広がり、各国でロックダウンをするなど対策が行われた。インドも同様で、この結果、感染の広がりが収まりをみせ始めた時期と「ホーリー祭」の時期が重なってしまった。
なにしろ、前述のとおり、インドは人口が桁違いに多いから、祭礼に参加する人数も桁違いになる。おまけに日常的な約束事が無視されたり無意味になるので、コロナの感染にはマイナスに働くことが明らかだ。しかも、「ホーリー祭」の熱狂は、ほかの二つの祭礼に比べても、はるかに勝るから、事態は深刻きわまりない。
しかし、だからといって、長い伝統をもつ祭礼を中止したり延期したりしたら、信仰心に燃える人々の怒りを駆りたてて、なにが起こるか分からない。前に指摘した通り、「バラバラで、しかも1つ」なインドを維持するには祭礼は欠かせないからだ。為政者にとっては、実に難しい判断だったはずだが、結局、例年と同じように開催された。その結果は、報道されているとおりである。
この記事を書いた人
宗教学者
1953年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院博士課程修了。専門は宗教学(日本・チベット密教)。特に修行における心身変容や図像表現を研究。主著に『お坊さんのための「仏教入門」』『あなたの知らない「仏教」入門』『現代日本語訳 法華経』『現代日本語訳 日蓮の立正安国論』『再興! 日本仏教』『カラーリング・マンダラ』『現代日本語訳空海の秘蔵宝鑰』(いずれも春秋社)、『密教』(講談社)、『マンダラとは何か』(NHK出版)など多数。