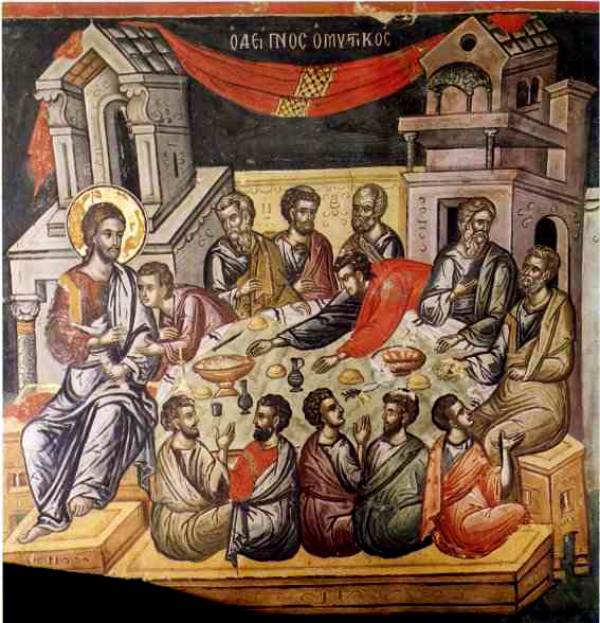4月8日は釈迦生誕日ではない?――まったくわかっていないブッダの個人情報

2021/04/08

イメージ/©shark749・123RF
実は生年も、本名も明確になっていない!?
日本仏教では、4月8日が、仏教の開祖、ゴータマ・ブッダ(釈迦)の誕生日とされてきた。そこで、今回はゴータマ・ブッダの家族にまつわる話をお伝えしたい。
サールナート考古博物館のブッダ像/CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
ゴータマ・ブッダ自身ならびにその近縁者にまつわる情報を、ゴータマ・ブッダが生きた時代からさして離れていない時期に成立し、信憑性があると推測されている文献から拾ってみよう。
最初に申し上げておくが、ゴータマ・ブッダが4月8日に生まれたという伝承は、確証がない。ついでにいえば、2月15日に涅槃に入ったという伝承も、確証がない。さらにいえば、生没年も、いまだ確定していない。あえていうなら、これまで有力とされてきたインド哲学者・仏教学者の中村元氏(1912年~99年)の説である紀元前463年~前383年が否定され、現存する最古の仏教の宗派である南伝系の紀元前624年~前544/543年説が復活しそうな気配がある。
それどころか、呼称からして問題がある。「ブッダ」は、「目覚めた人」とか「賢人」を意味する尊称であり、仏教が登場するずっと以前から使われてきた。つまり、「ブッダ」は歴史上、何人も現れた。興味深いことに、インドの宗教であるジャイナ教最古の文献を紐解くと、一番弟子とされるサーリプッタ(舎利弗)は「サーリプッタ・ブッダ」と記されているのに、なぜか、師のゴータマに関する記載がない。
最大の問題は釈迦の本名である。パーリ語では「ゴータマ・シッダッタ」、サンスクリット(梵語)では「ガウタマ・シッダールタ」とされているが、姓(家名)の「ゴータマ」・「ガウタマ」(最上の牛)についてはともかく、名にあたる「シッダッタ」および「シッダールタ」については、絶対に確実とは言い切れないようなのだ。なお、あえて意味をとると、シッダッタもシッダールタも、「すべてを成就する者」になり、漢訳本では「一切義成就」と書かれている。したがって、全体では「最上の牛家に生まれたすべてを成就する者」という意味になる。
とにかく、インド宗教界の傾向として、個人情報にはほとんど関心が払われなかった。さまざまな文献資料から推測して、超有名人だったことに疑いの余地はないゴータマ・ブッダですら、この程度のことも分かっていない。
神秘性に包まれる聖母の存在
母と父についての情報は、紀元前5世紀末から前3世紀中頃の編纂と推測される南伝系経典の『テーラガーター』の533偈と534偈の記述が初出のようである。それによると、ゴータマ・ブッダが、スッドーダナを父として、マーヤーを母として、この世に生を受けたことがわかる。
スッドーダナは「浄飯王」と漢訳されてきた。事実か否か、あきらかではないが、ゴータマ・ブッダには四人の弟がいて、彼らの名がみな「オーダナ」、つまり「飯」という語を含んでいたと伝えられている。このことから、ゴータマ・ブッダの一族が稲作を農業活動の中核に据えていたと推測されている。
スッドーダナが意味する「きよらかな飯」とは、「白米の飯」を意味していた(中村元『ゴータマ・ブッダ』36~37頁)。米にはいろいろな種類があり、赤米もあれば、黒米も緑米もある。わざわざ「白米の飯」を意味する名を用いていたのは、なぜか。中村元氏は「特に白米を珍重していたから」と述べているが、では、なぜ、白米が珍重されたのか、についての説明はしていない。
母のマーヤーという名が秘める意味については、古来、論議がある。仏伝として最も名高いアシュヴァゴーシャ(馬鳴)の仏典『ブッダチャリタ』には、こう書かれている。
その名をマハーマーヤーと呼ばれていたが、彼女はまさしく比類なき神の神秘力、(人の心を惑わす)幻(マーヤー)のごとくであった。(原実 訳『大乗仏典13ブッダチャリタ』7頁)
この記述に対し、中村元氏はこう述べている。
〈マーヤー〉とは古代インドにおいて「神の不可思議な霊力」を意味した。(後代のインド哲学では〈マーヤー〉とは幻のような世界を仮現する原理を意味するが、この王妃の名にこのような観念をもちこむことは困難である)(中村元『ゴータマ・ブッダ』37頁)
この中村元氏の指摘は、アシュヴァゴーシャの『ブッダチャリタ』の記述から、「比類なき神の神秘力」という部分を肯定し、「(人の心を惑わす)幻(マーヤー)」という部分を否定することになる。
「後代のインド哲学」は、ヒンドゥー教史上、最大の哲学者と称えられるアーディ・シャンカラ(8世紀前半頃)を祖とする「不二一元論(アドヴァイタ)学派」を指している。この学派は、真に実在するのはブラフマンのみであり、この多様性に富む世界は、無明(アヴィッディヤー)が生み出したマーヤー(幻影)にすぎず、まったく実在性を欠いているという「世界幻影論」を展開した(宮本啓一『インドの「一元論哲学」を読む』 ⅲ頁)。
このように、「マーヤー」=「幻」説は、宗教哲学や思想の視点からすると、たしかに魅力的だ。ゴータマ・ブッダを生んだマーヤーは、その深い神秘を秘める名ゆえに、後世に絶大な影響を与えつづけてきたのである。
息子と妻についての謎
最古層の仏典とされる『スッタニパータ』に、ゴータマ・ブッダが実子と伝えられるラーフラに、先輩の僧を軽蔑する傾向が見られたので、それをたしなめた一節がある。
〔師(ブッダ)がいった〕、「ラーフラよ。しばしばともに住むのに慣れて、お前は賢者を軽蔑するのではないか? 諸人のために炬火をかざす人を、汝は尊敬しているか?」
〔ラーフラは答えた〕、「しばしばともに住むのに慣れて賢者を軽蔑するようなことを、わたくしは致しません。諸人のために炬火をかざす人を、わたくしは常に尊敬しています。」(中村元訳『スッタニパータ』71頁)
ここでいう「賢者」や「諸人のために炬火をかざす人」は、前出の一番弟子とされるサーリプッタ(舎利弗)を指している。最高指導者の実子が、最高指導者の筆頭側近と対立する傾向は、時代を問わず、また洋の東西を問わず、ありがちだったのだ。
中村氏によれば、『スッタニパータ』の注釈書『パラマッタ・ジョーティカー』には、若くして出家し、出自・氏姓・家柄・容姿端麗なことなどによって、ラーフラが慢心を起こしたり無駄話をしたりしないように、いさめるためだったと書かれているそうである。
ご存じの方も多いと思うが、ラーフラは「邪魔者」を意味する。自分の息子に「邪魔者」という名を付ける父親というのも、変というか、奇妙というか、普通ではあり得ない。こんな名を付けられた息子の心情は、はたしてどんなものだったのだろうか。
ラーフラを生んだ妻の名は、一般にはヤショーダラー(ヤソーダラー)と伝えられる。ところが、ゴータマ・ブッダの妻の名を記すのは北伝系の仏典に限られ、南伝系の仏典にはかなり後代に成立した文献にも見当たらない。ただ、「ラーフラの母」と書かれているだけなのである。
インドに限らず、古代や中世の段階では、女性にまつわる情報が極端に少ない傾向が否めない。日本を例にあげれば、1000年前の平安中期に活躍した紫式部も清少納言も、いわばあだ名みたいな呼称であり、実名は伝えられていない。ゴータマ・ブッダの妻が生きていたのは、それよりもさらに1500年も前である。したがって、実名が分からないのも、いたし方ないのであろう。
ちなみに、ゴータマ・ブッダは16歳で結婚し、妻は何人もいたという後世の伝承もあるが、古い聖典類には結婚生活にまつわる記述は、ほとんど何も書かれていない。その代わり、ほかの宗教を信仰していたカッサパ三兄弟を、神通力を駆使して、帰服させたというたぐいの話が、延々と語られている。悪魔退治も、繰り返し語られている。要するに、その種の力を行使できなければ、いくら優れた教えを説いたところで、誰も聞く耳をもたなかったということだ。
以上の事実から分かるとおり、初期仏教の段階で、教団を構成していた人々は、わたしたち現代人とはまったく異なる人生観や価値観をもっていたことは、確かである。
この記事を書いた人
宗教学者
1953年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院博士課程修了。専門は宗教学(日本・チベット密教)。特に修行における心身変容や図像表現を研究。主著に『お坊さんのための「仏教入門」』『あなたの知らない「仏教」入門』『現代日本語訳 法華経』『現代日本語訳 日蓮の立正安国論』『再興! 日本仏教』『カラーリング・マンダラ』『現代日本語訳空海の秘蔵宝鑰』(いずれも春秋社)、『密教』(講談社)、『マンダラとは何か』(NHK出版)など多数。