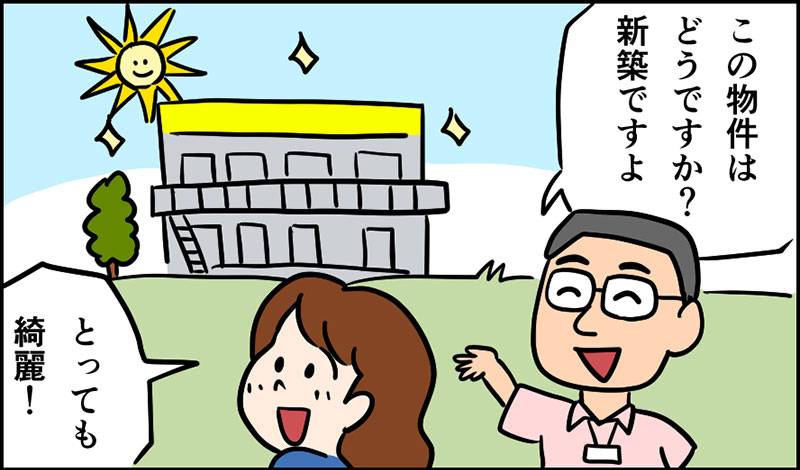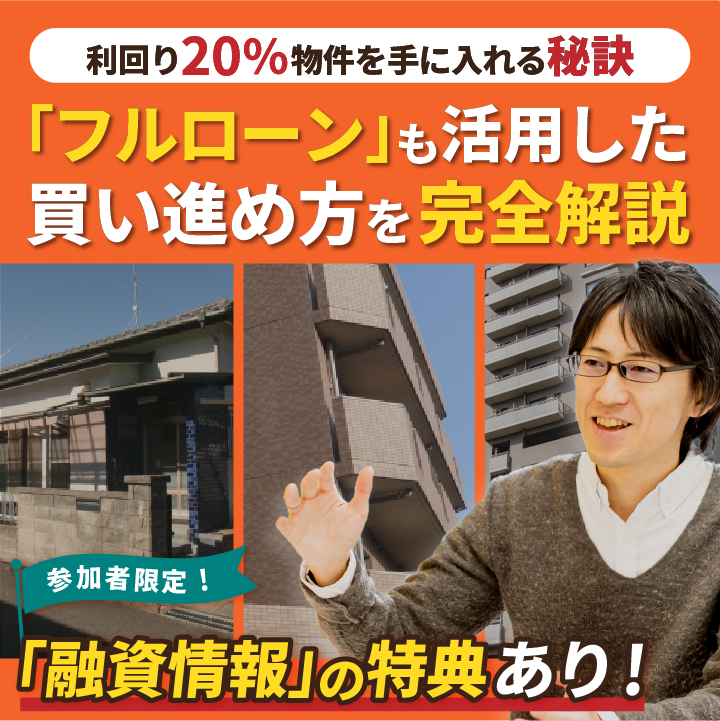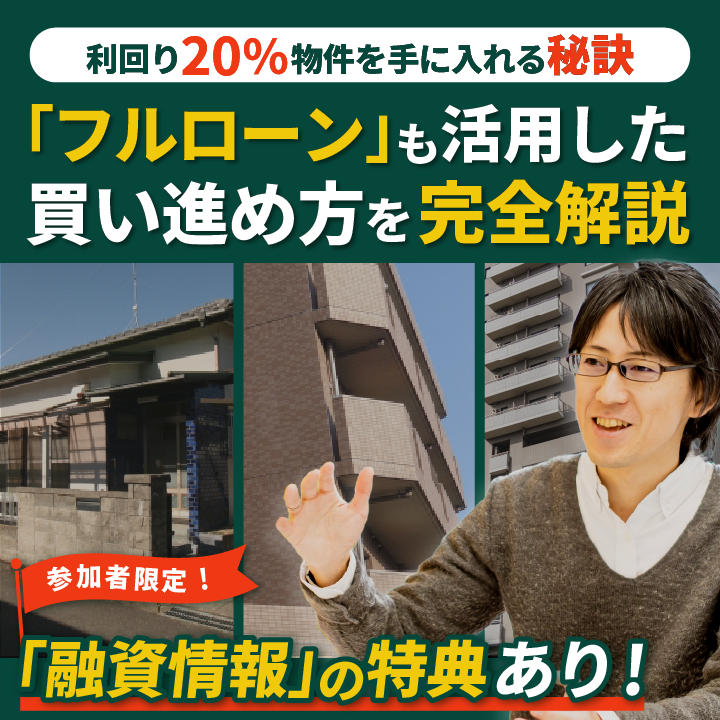賃貸不動産仲介会社があとで「聞いてなかったよ!」と客から叱られる事例
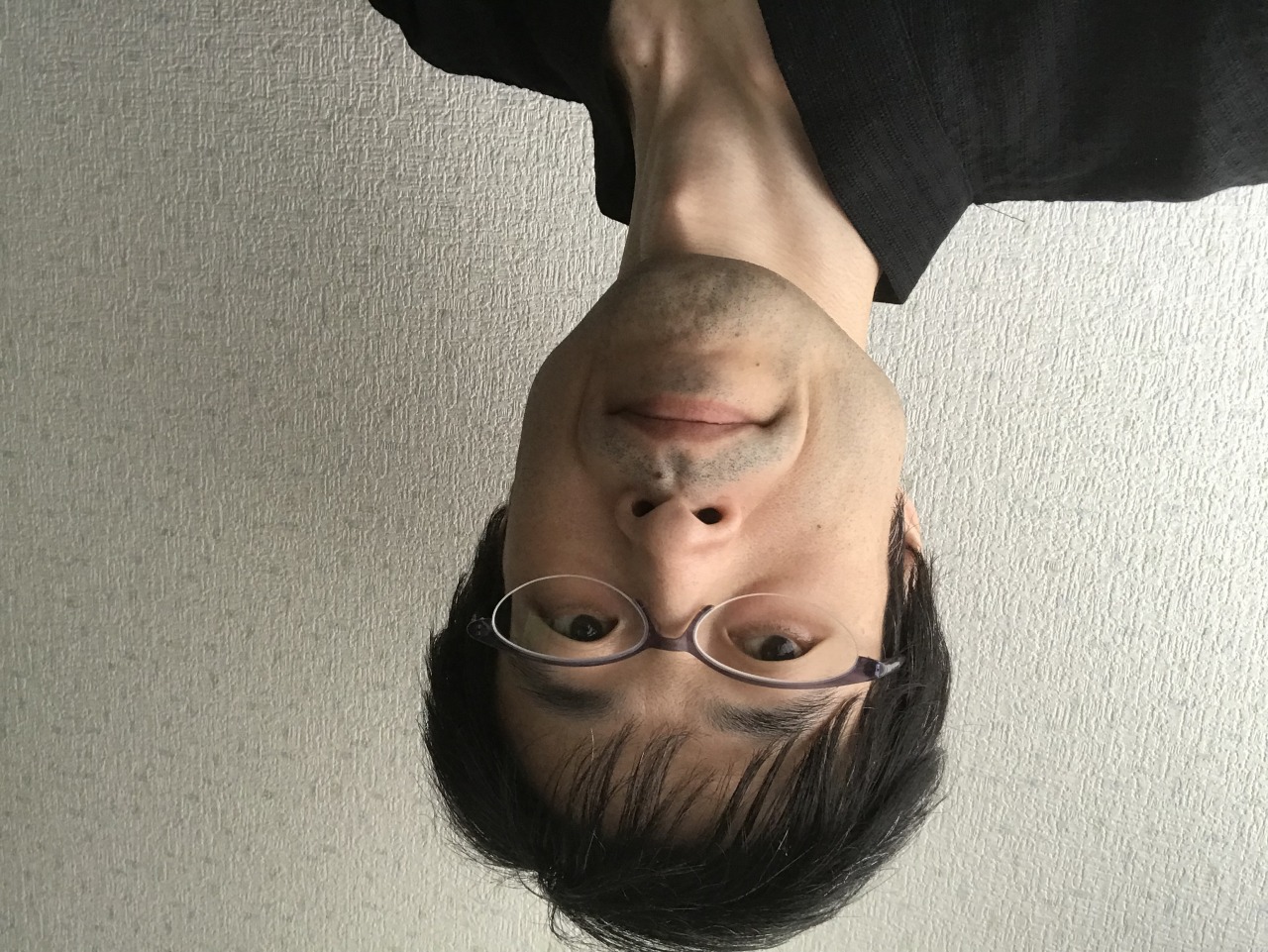
2021/07/22

イメージ/©︎sunabesyou・123RF
誰にでもあり得るトラブル・アクシデント
賃貸住宅への入居を仲介したあと、不動産仲介会社が、入居者となった客に「こんなの聞いてなかった!」と、叱られることがある。あまり話題に出てこない例で、私が経験したもの、周りで見聞きしたもの、いくつかを挙げてみよう。
これから部屋探しをする人にとっては、誰にでもあり得るトラブル・アクシデントとして、参考になるはずだ。
事例1 ガスの保証金1万円ってなんですか?
ある入居者の入居日翌日、「あのお客様、今日は引っ越し作業の続きで忙しいんだろうな」などと思っていたら、突然電話が。
「ちょっと! こんなの聞いてませんよ! さっきガス会社の人が来たんですが、保証金1万円払えって、なんですかこれ!」
ガスの保証金とは、LPガス会社が、ガス料金の未払いが起きたときのために“押さえて”おく預かり金のことだ。開栓時に要求されることが多い。都市ガス物件からLPガス物件に引っ越した人など、これによくびっくりさせられる。「大丈夫、それは預け金ですから。あとで返ってきますので」などと説明しても、「そういう問題じゃないでしょう!」と、財布の中からいきなり現金を抜き取られた気分になった客の怒りは収まらない。気持ちは本当によく分かるのだが……。
事例2 どうして急に家賃が増えてるんだ!
「通帳を見たら、契約した家賃よりも高い金額が口座から引き落とされています。どういうことですか!」
どういうことなのかは、契約に至るまでに何度か伝えている。渡した書面にも明記されている。それでも、忘れられやすいのがコレだ。家賃債務保証会社が入居者の銀行口座から家賃を引き落とす際に上乗せする手数料だ。数百円のことが多いが、年間にすると×12で結構な額になる。しかも、うっかりこの存在を忘れていると、口座残高不足による滞納事故の原因にもなりやすい。注意が必要だ。
事例3 入居日前に部屋の掃除をしたいんですけど……えっ! ダメなの!?
部屋探しの際、誰もが不動産会社の窓口で、「予定の入居日をお書きください」などといわれ、書面に記すことになるだろう。そこで、あくまで予定のつもりで「多分この日になるかな」……程度の日付けを記入する人も多いが、ぼんやりしていると、それがあとあと尾を引いてしまう。
案内された部屋を気に入り、申し込み~契約へと進む過程で、その日付けが賃貸住宅入居者用の総合保険……いわゆる家財・火災保険の補償開始日にされてしまうと、その日より以前は補償対象外となるため、物件への入室を断られることが多い。「引っ越しの前に掃除に行きたい」「先に小さな荷物を運び込みたい」と、いった希望が叶わなくなることがあるので、注意が必要だ。
事例4 鍵交換手数料だけでも懐がイタいのに……
鍵交換は本来賃貸住宅オーナーの負担 イメージ/写真AC
昔よりも格段に「健全」になったはずの賃貸契約に、未だまとわりついている悪習。それは鍵交換手数料の請求だ。原状回復トラブルを起こさないための教科書として、業界に広く普及している国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも、「(鍵交換は)入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当」と明記されているが、なぜかこれをやめない賃貸住宅オーナーや管理会社が多い。そろそろいい加減にしようではないか!
それはそうと、ある入居者曰く、
「今回入居した物件では、部屋の鍵を1本しかもらえなかったので、スペアキーを自費でこしらえましたが、ディンプルキーだとものすごく高いんですね。鍵交換手数料と合わせて軽く2万円超えの出費になりました。ガックリです」
防犯性能が高いことと引き換えに、ディンプルキーにはこんな落とし穴もある。ぜひ心得ておかれたい。
事例5 話がまとまってから人に貸そうよ……駐車・駐輪
「不動産屋さん、今回私が入居したマンションの建物脇のスペースだけど、あなた自転車停めていいって言ってたじゃないですか。でも、実際停めようとしたら、1階のお店の人から、ウチが仕事で使ってる場所だからダメだって言われましたよ。どうなってるの?」
敷地内の駐車ルールや駐輪ルールがいい加減な賃貸物件は意外に多い。ちなみに、私が知る例はすべて事業用の貸室と居住用の貸室が混在している物件で起きている。そこでオーナーに、話が違っているようですがと尋ねると、
「実は、その件で1階のテナントとは言った言わないのトラブルになっている。もちろん、私はあくまでマンション脇のスペースは入居者全員の共用部分のつもりなんだけど、このこと、あなたに伝えておけばよかったね」
思わず「えっー!?」と言ってしまいそうになったが、このようなケースも少なくない。はっきりと入居者用の駐車場・駐輪場として区画されていない怪しい「停め場所」がある物件は要注意だ。しっかりと状況を確かめよう。
事例6 契約書をよく読んでいたのは入居者
最後のこの事例、びっくり焦ったのはオーナーのほうだ。
「どうしよう、ウチの物件ペット不可なのに、入居者さんが勝手に部屋で小鳥を飼っている!」
ところがこの件、契約上問題はなかった。賃貸借契約書を見せてもらうと、犬、猫は飼ってはいけないが、「観賞用の小鳥、魚などであって、明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物は飼ってもよい」となっている。入居者はそこをしっかりと読んだうえで、小鳥を数羽飼っていた。
実は、オーナー側が用意している賃貸借契約書が、国土交通省の標準契約書をひな型にしたうえで、そのなかのペットに関する規定に手を加えずにいた場合、契約内容は自然に上記のかたちとなる。なので、この件では、オーナーがもしも先走って入居者へ苦情を伝えていた場合、入居者からの不満は、当然、契約を取り持った仲介会社に向けられていただろう。つまり、順番的には話がややこしくならずによかったという事例だ。
ちなみに、この物件は賃貸併用住宅。鳥アレルギーを持つオーナーの自宅と入居者の部屋が同じ屋根の下に寄り添うかたちだった。
この著者のほかの記事
理由は偽装免震ゴムか、それとも?――30階建て・築15年のタワーマンションが解体へ
子どもを危ない建物に住まわせるな 「築年月」を気にするべき一番重要な理由
賃貸おとり広告はなぜなくならないのか――2つの「構造」が重なるその仕組み
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。