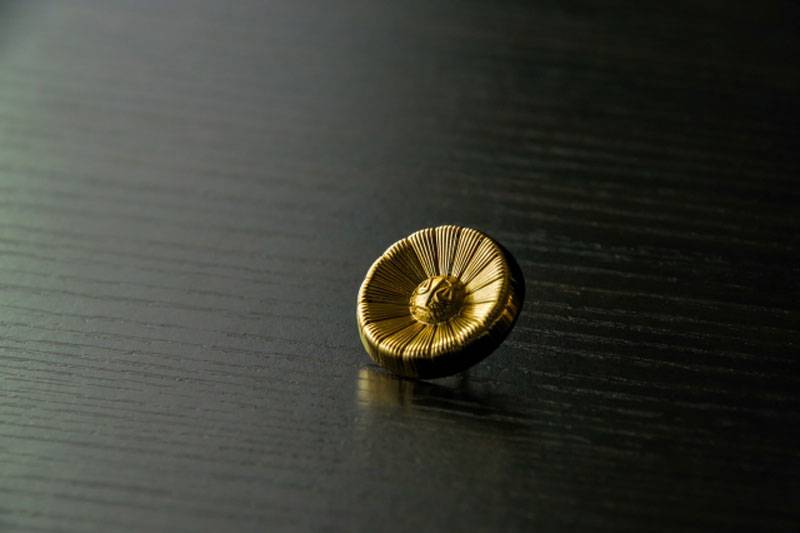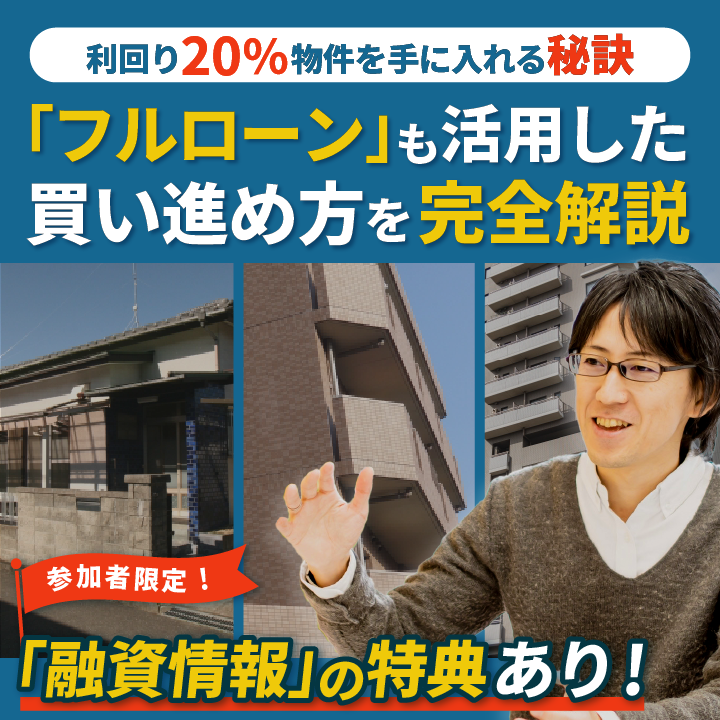親の自宅を子の資金で増改築したら贈与になるのか?

2016/01/31
増築部分も「もとの所有者」が権利を持つ
たとえば、親が所有している建物が、時価500万円と判断されたとしましょう。この家を、子が2500万円の資金を提供し増改築した場合、時価は3000万円となります。しかし、増改築部分ももとの所有者である親が権利を持つことになるため、結果的に2500万円の資金提供は、子から親への贈与とみなされてしまうのです。
また、建物を共有している場合も注意が必要です。共有者のうち一方が全額負担して増改築する場合も、同様の問題が発生する可能性があります。もちろん、共有持分に応じて費用負担をする場合は問題ありません。
一例を出すと、時価1000万円の建物で、親の持分が6(600万円)、子の持分が4(400万円)だとしましょう。この時、親が1000万円をかけて増改築した場合、時価は2000万円となり、持分で考えると親が1200万円、子が800万円の権利を持つことになります。しかし、子は資金を提供していないことから、親から子へ400万円贈与したと判断されてしまうのです。
増改築の対応方法
このように、所有者が違う建物への増改築資金の提供は贈与税の対象となりますので注意が必要です。そこで、どのように対応するのが賢明なのかを考えてみましょう。
まず、親の所有する建物を子に贈与し、その後に増改築をすれば問題が回避できます。確かに、親の所有する建物を子に贈与するという意味では贈与税が課税されるのですが、古い建物の場合、時価は固定資産税評価額をもとに算出されるので増改築にかかる費用が大きいことを考えると負担は少なくなります。
前述の例でいくと、評価額が500万円の建物の贈与税は53万円ですが、増改築資金2500万円の贈与税は945万円となってしまいます。この贈与税には特例などもあることから、一度専門家に相談して一番損をしない方法を探ることをおすすめします。
住宅ローン控除の活用
「あれ? 増改築にも住宅ローン控除が使えるのでは?」と思う人もいるかもしれません。確かに、増改築をローンで行なった場合、住宅ローン控除が適用されることがあります。しかし、その大前提となるのが「自分の所有する家屋への増改築」ということです。
最初の例では、親が所有する建物へ子が資金提供しているので、この条件に当てはまらないことから住宅ローン控除の対象から外れてしまいます。もし、子に所有権を移してから増改築のローンを組んだ場合は、住宅ローン控除が適用される場合があります。
ここで注意しなければいけないのが、所有権をいつ移転するかということです。所有権移転登記と、工事完了後の抵当権設定登記が同じ日になってしまうと、本当に自分の所有する建物への増改築だったのか怪しまれてしまいます。
税務署との無用なトラブルを避けるために、まずは所有権移転登記をすませてしまい、その後増改築に関するローンの契約をすることをおすすめします。今後、高齢化社会が進むにつれ、親の家の増改築は増えてくると予想されていますので、しっかりと対策をしておきましょう。
この記事を書いた人
税理士
CFP、宅地建物取引士 米国アラスカ出身。一般企業勤務を経て簿記知識ゼロから3年で税理士試験合格。著書に「いちばんわかりやすい確定申告の書き方」(ダイヤモンド社)など多数。HP「相続税申告のツチヤ」にはお客様の声50件超掲載。