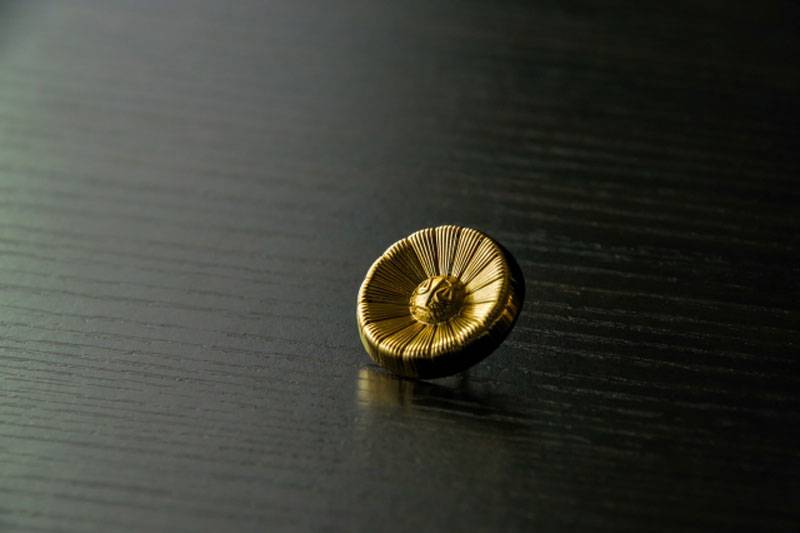相続法改正シリーズ #2 実家の不動産相続に大きな影響を与える可能性――「遺留分侵害額請求権」
2021/08/30

イメージ/©️maposan・123RF
相続争いに深く関係する「相続法改正点」
前回ご紹介した「約40年ぶりに大改正された相続法」について、前回の新たに制度化された「配偶者居住権」に続いて、「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」に制度が変わったことについて本稿でご紹介したい。
前回は、残された配偶者が住む家に困らないようにという配慮に基づいてできた新たな制度であったが、今回は「前からある制度の変更」ではあるが、実家の不動産相続に大いに影響があるし、それに限らず、遺産を相続する相続人全般に関わってくる。そして、相続人間における相続争いに深く関わる点でも、その内容や注意点を押えておきたいところだ。
「遺留分」とは何か?
テレビドラマなどで、大富豪の老人が亡くなって、顧問弁護士が預かっていた遺言書を家族全員の前で読み上げる場面を見たことがある人も多いだろう。
その内容が「全財産を愛人である〇〇に贈与する」などと書かれていて、紛糾する場面があることが多い。民法では、このような理不尽な遺言書が適法に成立する(偽造などではなく正真正銘の遺言書である)場合であっても、残された家族が住む家を失ったり生活に困ったりしないように、一定範囲の法定相続人に保障された遺産をもらう権利を定めている。これが「遺留分」と言われるものだ。
遺留分は相続人ごとに、「直系尊属のみが相続人である場合は遺産の3分の1、そのほかの場合は遺産の2分の1、ただし相続人が複数いる場合は、これらの割合に法定相続割合を乗じた割合」「兄弟姉妹には遺留分はない」と定められている(民法1042条)。
テレビドラマの例のように、有効な遺言があって「愛人に全財産を贈与する」と書かれていても、仮に相続人が正妻と子どもが二人であったなら、正妻には遺産の4分の1を、子どもたち2人にはそれぞれ遺産の8分の1を請求する権利があることになる。これが遺留分という民法上で保障された権利なのだが、権利は必ずしも行使しなくてもよく、「おれは親父の遺産なんかいらないよ」ということもできる。
旧制度ではどんな弊害があったか?
「長男は、先に亡くなった母さんが寝たきりになって亡くなるまで、忙しい仕事の合間を縫って嫁と一緒に介護に努めてくれた。晩年は私も足が不自由になって、外出するたびに車椅子を押してもらったりと苦労をかけた。だから、私が過ごして思い出のいっぱい詰まった自宅は、ぜひとも長男に相続してもらいたい」
このように考えた父親が、「長男に自宅を相続させる。次男には銀行預金全てを相続させる」などと書いてある遺言を残して亡くなったとしよう。自宅不動産の価値は4500万円で、銀行預金が500万円(東京などの大都市では、ウサギ小屋と言われるような小さな戸建てでもこれくらいの価値がある場合が多い。そして、高齢化が進んだ現在の日本では、定年退職した父親が長い老後期間に、退職金そのほかの金融資産を使い減らしており、預貯金が少ない場合も多い)である場合で考えると、次男の法定相続分2500万円の半分である1250万円が遺留分となる。
遺言通り長男が実家を相続すると、次男の遺留分を750万円(1250万円-500万円)侵害していることになるのだ。
次男が旧制度である「遺留分減殺請求権」を行使した場合、実家不動産(4500万円)のうち、750万円部分(所有権の6分の1)を次男が取得することになる。次男が承諾しなければ、長男は実家に住むことはもちろん、売ることも貸すこともできなくなってしまう。せっかく父が長男への想いを込めて残した遺言は、実現しなくなってしまう可能性が出てくるのだ(もちろん、次男が遺留分減殺請求権を行使しなければ遺言は実現する)。
新制度「遺留分侵害額請求権」ではどうなる?
「遺留分侵害額請求権」とは、一言でいえば「遺留分を侵害された金額(上記の例でいえば750万円)を侵害している相続人(上記の例では長男)に金銭債権として請求できるだけの権利」になったのだ。
したがって、長男は遺言によって実家不動産を完全に所有することができる一方で、弟に750万円を支払う義務があることになる。万一、一括で払えない場合は、裁判所の許可を得て分割払いなども可能となった。上記の例では、おそらく自宅を担保にして金融機関から750万円を借りることができるだろうから、相続争いはあっという間に解決できることになる。
旧制度「遺留分減殺請求」の場合だと、次男が既に所有権の一部を取得しているために「共有物」となり、2人の意思が一致しなければ金融機関からの借り入れはできない。次男が「実家を売って売却代金の中から750万円を渡してほしい」と言っても、亡くなった父の遺志を尊重したいとして長男が売却を拒めば、この相続争いは決着しないのだ。最終的には家庭裁判所に持ち込まれることになり、解決まで長期間を要することになる。
旧制度と新制度は言葉のうえでは「減殺請求」と「侵害額請求」と大きな違いがなさそうに聞こえるが、実は相続争いの解決という意味では大きな違いがあるのだ。
遺留分侵害額請求権についての注意事項
① 権利を行使できる期間
遺留分侵害額請求権(旧制度の遺留分減殺請求権も同じ)は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しないとき、または相続開始のときから10年を経過したときに消滅する。(民法1048条)
※少しややこしいが知っておくべきこと
上記の期間内に、事例の「(次男が長男に対して)遺留分侵害額請求権を行使する。750万円を払え」と内容証明郵便などで請求したとする。兄が、金融機関などから借り入れをしてでも払えば円満に解決するが、何らかの事情があって払ってもらえない場合はどうなるだろう? この場合は、「金銭債権の消滅時効」に気を付ける必要が出てくる。
冒頭で述べた通り、「約40年ぶりの相続法改正」があったのだが、それに先立って、同じ民法でも「約120年ぶりの債権法改正」があったのだ。「金を払え」というような金銭債権の請求権は、民法改正前は10年の消滅時効期間だったのだが、2020年4月1日以降に行使した金銭債権ここでは遺留分侵害額請求権)については、消滅時効期間は5年となったのだ(民法166条1項1号)。従って、相続発生から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使した次男は、長男が任意に750万円を支払わない場合は、遺留分侵害額請求権を行使してから更に5年以内に訴訟等の法的手続きを起こさなければならないことに注意が必要だ。
② 新旧制度の適用が異なる相続の発生時期
改正相続法の施行日(2019年7月1日)以降に発生した相続については、新法の遺留分侵害額請求の規定が適用されるのだが、改正相続法施行日以前に発生した相続については旧制度である遺留分減殺請求の規定が適用となることにも注意が必要だ。
【この著者のほかの記事をみる】
サブリースで大家業をやる人に朗報
大家が主役になる時代の幕開け
増え続ける所有者不明土地、法律改正で止められるか
医療・介護問題だけではない――高齢者の財産管理における「2025年問題」
相続法改正シリーズ #1 実家の不動産相続に大きな影響を与える可能性――「配偶者居住権」
この記事を書いた人
プロブレムソルバー株式会社 代表、1級ファイナンシャルプランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
1961年生まれ、大阪府出身。ラサール高校~慶應義塾大学経済学部卒業。大手コンピュータメーカー、コンサルティング会社を経て、東証2部上場していた大手住宅ローン保証会社「日榮ファイナンス」でバブル崩壊後の不良債権回収ビジネスに6年間従事。不動産競売等を通じて不動産・金融法務に精通。その後、日本の不動産証券化ビジネス黎明期に、外資系大手不動産投資ファンドのアセットマネジメント会社「モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン」にてアセットマネージャーの業務に従事。これらの経験を生かして不動産投資ベンチャーの役員、国内大手不動産賃貸仲介管理会社での法務部長を歴任。不動産投資及び管理に関する法務や紛争解決の最前線で活躍して25年が経過。近年は、社会問題化している「空き家問題」の解決に尽力したい一心で、その主たる原因である「実家の相続問題」に取り組むため、不動産相続専門家としての研鑽を積み、「負動産時代の危ない実家相続」(時事通信出版局)を出版、各方面での反響を呼び、ビジネス誌や週刊誌等に関連記事を多数寄稿。