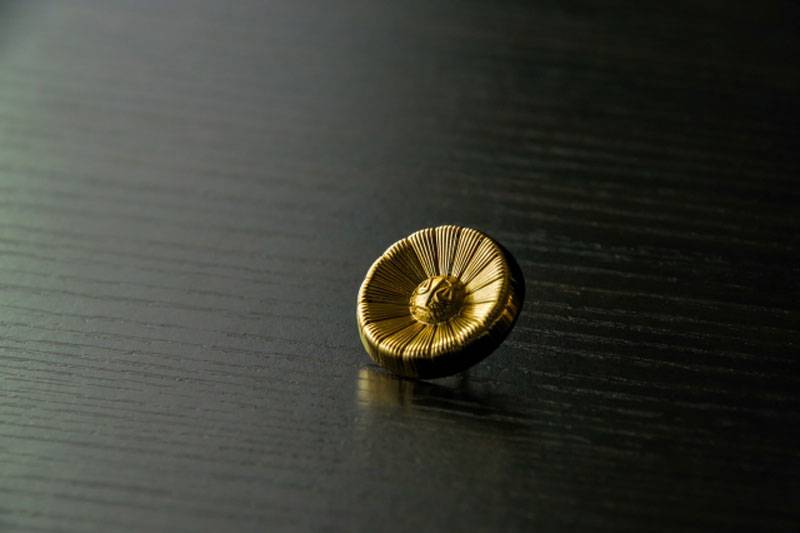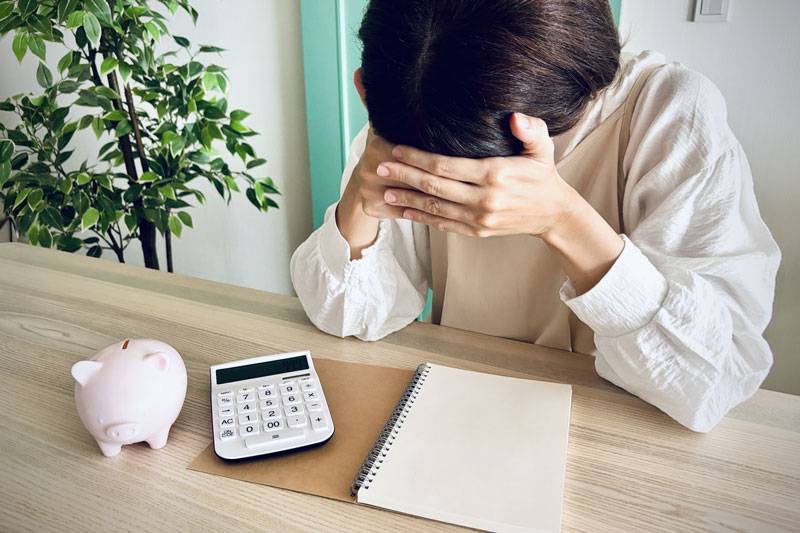増え続けている日本の富裕層・超富裕層。危険な「地方」を生み出すもとに?
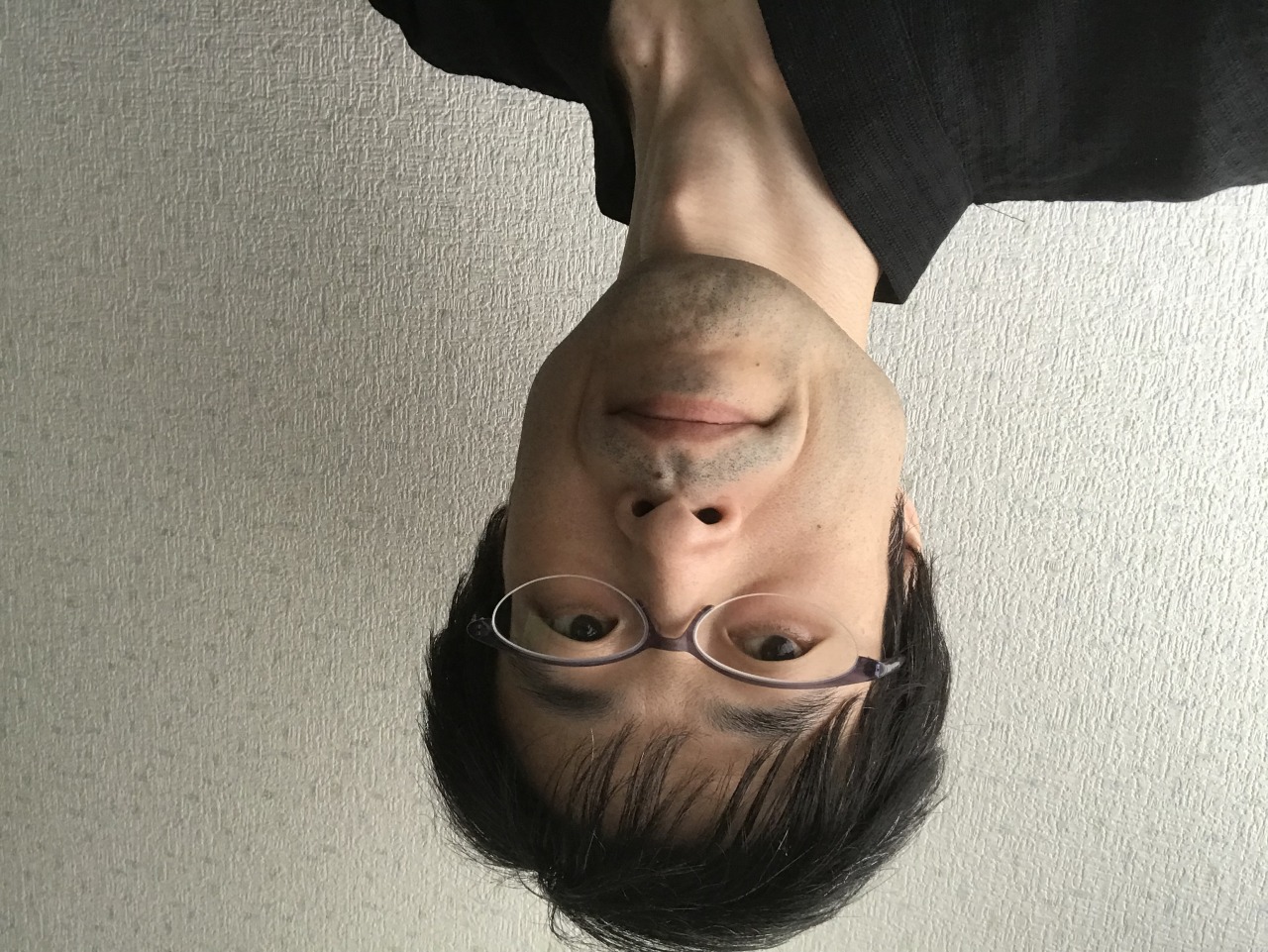
2025/05/17

富裕層、超富裕層、合わせて165万世帯
有名なシンクタンクのひとつ、野村総合研究所(NRI)が「日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯―――」と、題するレポートを少し前に公表している。
このレポートは定例のもので、前回は2023年に21年の分として公表された。今回は「23年の日本における純金融資産保有額別の世帯数と資産規模を各種統計などから推計」と、いうことで、その2年後の状況となる。インパクトある内容のため、前回同様、多くの報道等に採り上げられている。
一部をかいつまんで、数字を挙げてみよう。
「2023年の日本における純金融資産保有額・階層別世帯数と資産規模」
(NRI・2月13日公表のレポートより)
| 世帯の純金融資産保有額 | 年 | 世帯数推計値 | 資産保有額推計値 |
| 5億円以上(超富裕層) | 23年 | 11.8万世帯 | 135兆円 |
| 21年 | 9.0万世帯 | 105兆円 | |
| 05年 | 5.2万世帯 | 46兆円 | |
| 1億円以上5億円未満(富裕層) | 23年 | 153.5万世帯 | 334兆円 |
| 21年 | 139.5万世帯 | 259兆円 | |
| 05年 | 81.3万世帯 | 167兆円 | |
| 5,000万円以上1億円未満(準富裕層) | 23年 | 403.9万世帯 | 333兆円 |
| 21年 | 325.4万世帯 | 258兆円 | |
| 05年 | 280.4万世帯 | 182兆円 | |
| 3,000万円以上5,000万円未満(アッパーマス層) | 23年 | 576.5万世帯 | 282兆円 |
| 21年 | 726.3万世帯 | 332兆円 | |
| 05年 | 701.9万世帯 | 246兆円 | |
| 3,000万円未満(マス層) | 23年 | 4424.7万世帯 | 711兆円 |
| 21年 | 4213.2万世帯 | 678兆円 | |
| 05年 | 3831.5万世帯 | 512兆円 |
ちなみに、05年は本推計開始の年となる。つまり一番古いデータだ。以下、いくつかポイントを挙げていこう。
著しい「お金持ち」の増加
まず、単純にいえるのは、超富裕層と富裕層の世帯数における18年前に比べての著しい増加だ。加えて、超富裕層では前回推計分からの伸びも大きい。
なお、前記各層の内、現実として「富裕な層」といえるのはこれら2つになるだろう。それぞれの世帯数における増加率は以下のとおりとなる。
| 世帯の純金融資産保有額 | 21年から23年の増加率 | 05年から23年の増加率 |
| 5億円以上(超富裕層) | +31.1%(9.0万 → 11.8万世帯) | +126.9%(5.2万 → 11.8万世帯) |
| 1億円以上5億円未満(富裕層) | +10.0%(139.5万 → 153.5万世帯) | +88.8%(81.3万 → 153.5万世帯) |
見てのとおり、これら2つの層の数は18年前に比べ著しい割合で増えており、要は、わが国においては「お金持ち」がとても増えている。なおかつ、「中流の上位」といったところの準富裕層の数も、挙げると以下のとおりとなる。
| 世帯の純金融資産保有額 | 21年から23年の増加率 | 05年から23年の増加率 |
| 5,000万円以上1億円未満(準富裕層) | +24.1%(325.4万 → 403.9万世帯) | +44.0%(280.4万 → 403.9万世帯) |
劃期は株価が上がり始めた2012~13年頃
では、なぜこのようにお金持ちが増えているかというと、その理由を示すデータも当レポートからは明確に見てとれる。こんな具合だ。
| 分類 | 世帯数推計値・推移 | 備考 |
| 超富裕層 | 05年/5.2万世帯 → 11年/5.0万世帯 | 11年の数字は09年の数字とともに歴代最低 |
| 12年はデータなし | ||
| 13年/5.4万世帯 → 23年11.8万世帯 | この間一貫して増加 | |
| 富裕層 | 05年/81.3万世帯 → 11年/76.0万世帯 | 11年の数字は歴代最低 |
| 12年はデータなし | ||
| 13年/95.3万世帯 → 23年153.5万世帯 | この間一貫して増加 | |
このとおり、いずれの層でも13年(あるいはデータのない12年)が劃期となっている。すなわち、「アベノミクス相場」以降こんにちまでの株価上昇が始まった頃となる。
NRIのコメントを抜粋する。
「過去10年近くにわたって富裕層・超富裕層の世帯数および純金融資産総額が伸長している要因は、株式や投資信託などの資産価値の上昇―――(以下略)」
逆をいえば、投資をしっかりと行っている層、あるいは、堅実かつ規模の大きな投資を持続的に行いうる層こそが、これら超富裕層・富裕層であるという、よくいわれる単純な事実が示されていることにもなるわけだ。
不動産は含まれていない
大事なことを添えよう。これは、このレポートに対して付言する人も多い事実となる。
当レポートにおいては、こんな断りがある。
「預貯金、株式、債券、投資信託、一時払い生命保険や年金保険など、世帯として保有する金融資産の合計額から負債を差し引いた『純金融資産保有額』を基に、総世帯を5つの階層に分類し、各々の世帯数と資産保有額を推計」
つまり、ここでの計算には実物資産が含まれていない。要は、不動産が含まれていないことになる。
そこで言えば、いわゆるお金持ちが「土地持ち」でもあることが多いのは、周囲を見渡して多くが感じるところだろう。
よって、当レポートにおける超富裕層などアッパーな世帯が、所有する土地やビル等を金額換算して金融資産に足した場合、これらにひもづく負債を差し引いた上でも、総資産保有額が一気に上がるケースは多分少なくない。
富裕層から超富裕層へ、準富裕層からその上へとランクアップする世帯も、特に地価の上昇が広く見られる現在、かなりの数にのぼるはずだ。
すなわち、日本のお金持ちの数は、NRIが推計するところの165万世帯よりも確実に多い。
都市に貴族が生まれ、地方に盗賊がはびこる?
さて、ここからは、やや不穏当な話をしたい。
いま述べたようなかたちで、金融資産長者であり、不動産長者でもあるといった人は、主に地価の面から、都市部に偏って多いことが当然ながら推測できる。
そのうえで、筆者は、そこに相続が絡むことによって、資産の「濃縮」ともいうべき事象がこれからわが国ではどんどん増えていくと思っている。
分かりやすい実例を示そう。
筆者の知り合いに、お金持ちの家の息子さんがいる。親の資産は、金融資産に土地、建物
を合わせて軽く十数億円に達するだろう。不動産はどれも東京都心部の一等地にある。
なおかつ、知り合い本人もそこそこに裕福だ。親御さんほどではないが、億単位の資産を
すでに持つ。
ところがだ。この人には子どもがいないのだ。独身だ。
ちなみに、年齢はすでに60を超えている。今後もおそらく結婚はしないだろう。
一方、この人には弟さんがいて、こちらは家庭を持っている。子どもが1人いる。知り合
いにとっては甥っ子だ。なお、この弟さんもまたかなりの資産を有している。
つまり、この家で相続が進んでいくと、ご両親が残す十数億円、その息子兄弟の残す数億
からの資産は、やがて、ひとりの子どもの懐になだれ込む。
資産の濃縮だ。
極端には、「国の人口が1人になれば、その国にある資産はすべてその人のもの」などといわれるロジックのものになるが、少子化・人口減少が急速に進むわが国にあっては、こうした「資産の濃縮」が今後過激なペースで増えていく。もちろん、現に増えてもいるだろう。(相続税等による目減りはもちろんあるが)
なお、筆者はさすがに詳しくないが、上記の弟さんの配偶者、すなわち奥さんの家の方も、おそらくは相当の資産をもつご家庭のはずだ。お金持ちの家では、結婚相手をそういった意味で「しっかりと」選ぶ。
実際、そうであれば、甥っ子さんが相続する資産は莫大なものとなる。こうした立場の人、あるいは近い立場の人が、東京を中心に、日本の大都市部にあっては目下続々と生まれていることだろう。すなわち、「貴族」の誕生となる。
貴族―――多額の金融資産と実物資産をもつ都会人のことだ。
よって、少し先の将来、わが国の社会はまるで古代の末から中世初めのような風景を醸し出す可能性が無くはない。都市に貴族が集まって住み、地方に平民が散らばって暮らす平安朝の頃のような社会だ。(不穏当で申し訳ない)
すると、そんな社会にあっては、都会や海外の“貴族”たちが別荘を構えたり、高級な宿に泊まってレジャーに興じたりする場所があちらこちらに生まれるだろう。だが、一方では、かなり危険な箇所も増えるかもしれない。
バイクや改造車に乗った野盗の集団が旅行者を狙い、襲うため、護衛無しにはおいそれと旅行もできない地域といったものが、生じてはほしくないがいくつも生じるといった殺伐とした図を筆者は時折思い浮かべたりもする。
―――以上は、半分SFばなしだ。筆者はこれを周りに言うたび笑われる。
しかしながら、筆者が育った愛するふるさと北海道など、最近は潮が引くような人口減少とともに、人心が無法地帯化してきているかのようなニュースがよく耳に飛び込んでくる。
気を引き締めてはおくべきだろう。未来は実に予測しがたいものだ。
意味が複雑な「マス層」
NRIのレポートに戻りたい。
先ほど、超富裕層、富裕層、そして準富裕層における世帯数の増加について数字を記した。
繰り返すと、超富裕層の05年に比べての23年の増加率は+126.9%、富裕層は+88.8%、準富裕層は+44.0%となっている。
そこで、もうひとつ世帯数が増えている層となるとマス層がある。05年は3831.5万世帯だったが、21年は4213.2万世帯、23年には4424.7万世帯に数字が伸びている。
もっとも、ここでのマス層というのは、他の層とは大きく意味の違う括りのものだ。「世帯の純金融資産保有額が3,000万円未満」ということで、ここには資産ゼロの世帯や、借金を差し引いてマイナスの世帯もすべて含まれている。
すなわち、これを当レポートにおけるほかの括りに合わせて仕分けるならば、ロウワーマス層・準貧困層・貧困層・超貧困層に本来分割されるべきもののはずだ。
よって、とどのつまりは、これら各層の全体か、あるいはいくつかが数を増やしている結果として、マス層全体の増加が表れている。
では、どの層が増えているのか?
さらに掘り下げていきたいところだが、資料の引用等々、話が延々と長くなる。残念だが、本記事にあってはここで擱筆としたい。
「野村総合研究所(NRI)ニュースリリース 日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯、その純金融資産の総額は約469兆円と推計」
(文/朝倉継道)
【関連記事】
中国が5割を超えて最多。外国人による「重要土地」等の取得
「県庁はいらない」―――村上総務相の不適切?発言を考える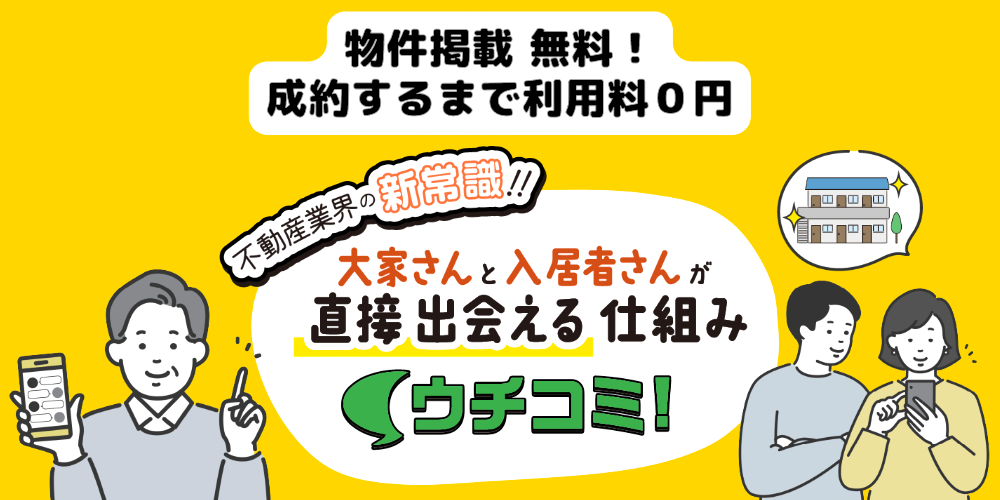
無料で使える空室対策♪ ウチコミ!無料会員登録はこちら
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。