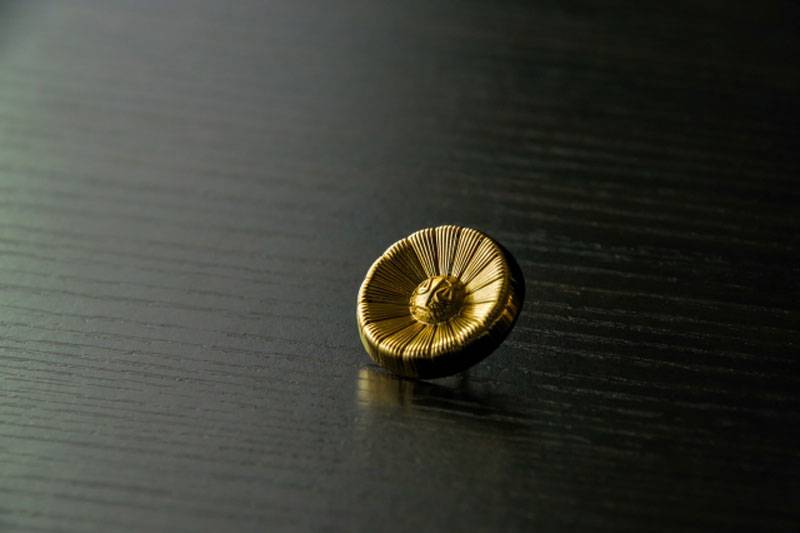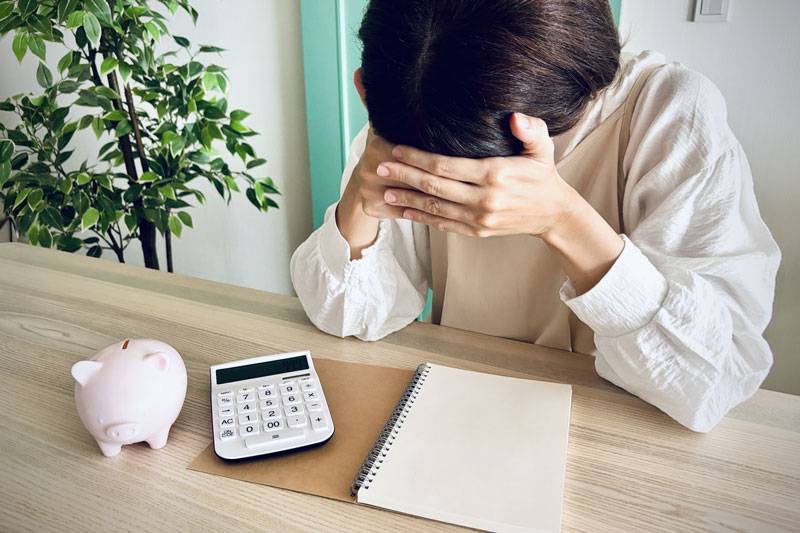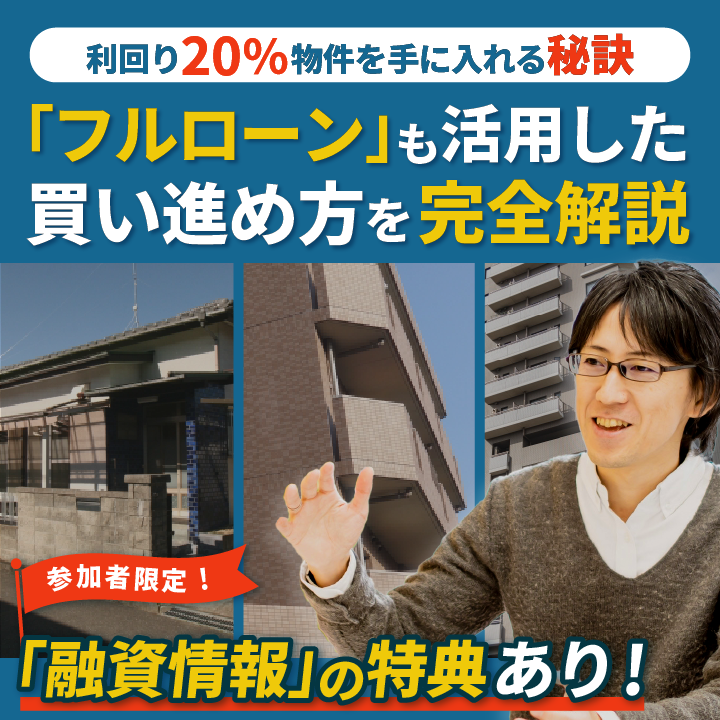「県庁はいらない」―――村上総務相の不適切?発言を考える
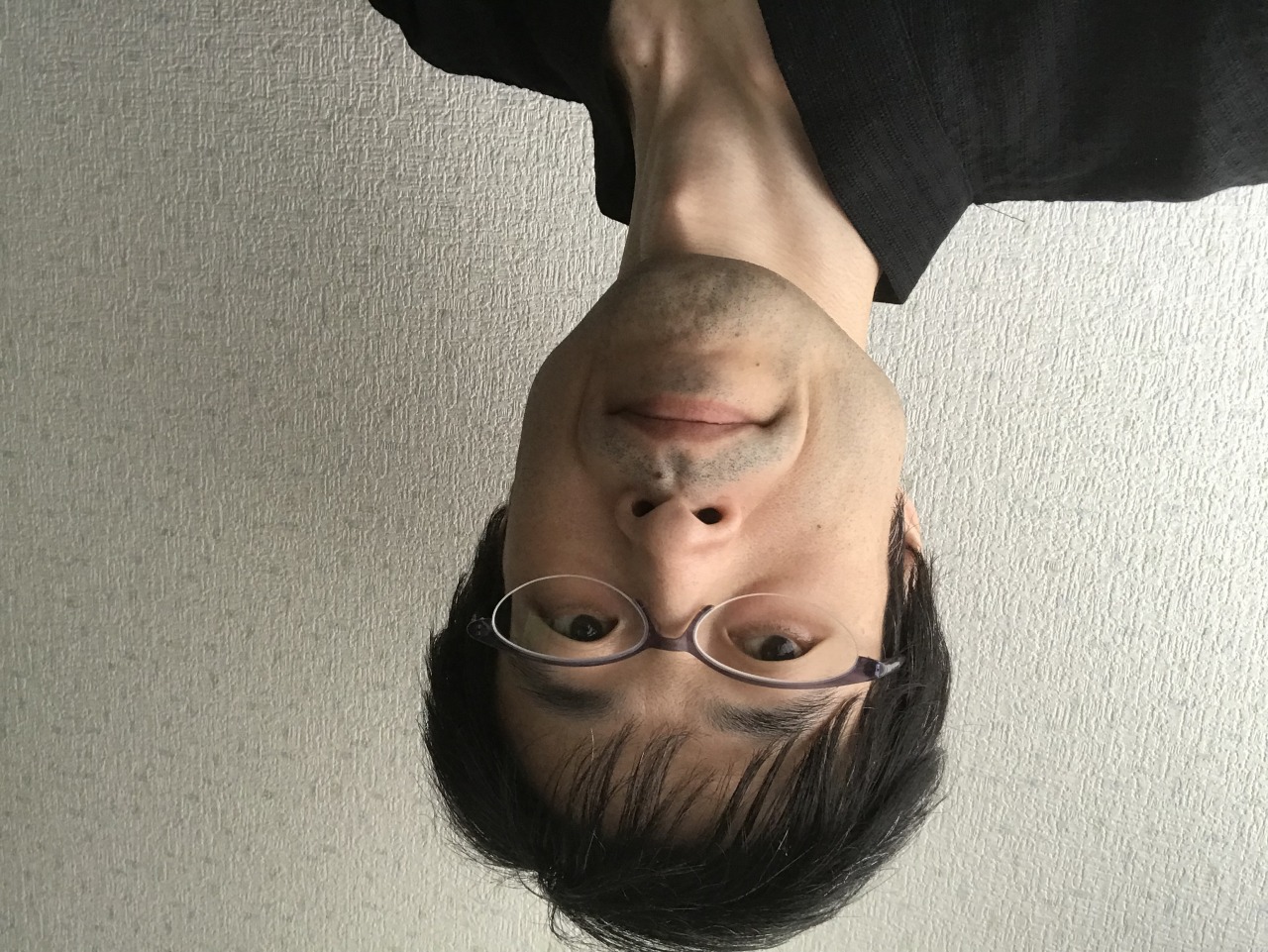
2025/04/26

北九州市くらいの人口が1年で消失
この4月14日、総務省が2024年10月1日現在の日本の人口推計を公表している。
これによると、日本人人口は1億2029万6千人。前年に比べ89万8千人の減少となった。1年の間に北九州市1個程度の人口が消えたことになる。なお、減少幅は13年連続で拡大しているとのことだ。
一方、総人口は1億2380万2千人。前年に比べ55万人減っている。先ほどの89万8千人よりもかなり少ない数字となっているが、この差は外国人が埋めている。社会増減(転入・転出による人口増減)を見ると、日本人は2千人の「減」だが、外国人は34万2千人の「増」と圧倒的だ。
15歳未満人口は1383万人で、前年に比べ34万3千人減少した。総人口に占める割合は11.2%で過去最低となっている。対して、65歳以上人口は3624万3千人。割合は過去最高の29.3%で、ほぼ3割に達している。
都道府県別に、人口の増加を見たのは東京都と埼玉県の2都県のみとなった。他は全て「減」だ。秋田、青森、岩手の北東北3県が、減少率のTOP3を同順番で埋めている。秋田県は65歳以上人口の割合が全国で最も高く、39.5%。すなわち約4割だ。一方、15歳未満人口の割合が最も高いのは沖縄県で、15.8%となっている。
以上、ざっと内容を記したが、各報道ですでに見聞きされている人も多いだろう。
県庁はいらない? 道州制の議論も必要ない?
さて、総務省といえば、現在これを率いる大臣は村上誠一郎という人だ。先般、この人が国会において面白い発言をしている。
要約は誤解のもととなるので、議事録の内容をそのまま掲げたい。
―――村上総務大臣の発言―――
(第217回国会 2月13日 衆議院・総務委員会にて)
「守島委員の御質問にお答えします。
これはあくまで、あくまでですよ、個人的見解として聞いていただきたいんですけれども、まさに私は守島委員と全く同じような考えを持っています。これから人口が、今は一億二、三千万ですけれども、これが今世紀末ぐらいには五、六千万になったときに、今ある国、県、市町村というシステムが本当に構成できるかどうかということは、私は非常に危惧を持っています。
ただ、一応、大臣としての答弁をまず答えさせていただきます。
現在、我が国は急激な人口減少と少子高齢化に直面しており、その中でも住民に必要な行政サービスの提供をしていくために自治体の行財政を持続可能なものにしていくことが重要です。
このために具体的にどのような方策が考えられるか、先ほど局長からも答弁したとおり、現在研究会を立ち上げ、議論を行っています。
その中では、国、都道府県、市町村の役割の在り方を含め検討するように指示をしているところであり、引き続き地方の声を伺いながら必要な検討を行ってまいります。
これが公式見解です。ただ、ここからはあくまで個人的見解でお許しください。
私が今考えていますのは、今言ったように、一億二千万が五、六千万になったら、今のような千七百以上の市町村の構成が難しいと考えています。私は、今、全国を大体三、四十万の市で区切れば、全国で三百から四百の市で済むと思うんです。私は、将来、その市と国が直結して交渉できるシステムが一番いいんじゃないかと。極端なことを言わせてもらいますと、県庁も全部私は要らないし、道州制も意味がないと私自身は考えています。あくまで個人的見解です。よろしくお願いします。」
再び三百諸侯の時代に?
上記は、日本維新の会の守島正氏の質問に答えてのものだ。読んでのとおり、村上氏はこの中で繰り返し「個人的見解」と断りを入れている。
しかしながら、それがゆえ、この発言はわが国が直面する問題の本質のひとつに鋭く触れる結果となっている。
「今ある国、県、市町村というシステムが本当に構成できるかどうかということは、私は非常に危惧を持っています」
筆者も同感だ。(あくまで発言の文脈にのっとった上で)同じ危惧を感じている。
「県庁も全部私は要らないし、道州制も意味がないと私自身は考えています」
こちらも同感だ。行政組織としての県庁も、あるいは道州政府設置の議論も、いずれも必要なくなるのではないかと思っている。(繰り返すが、発言の文脈にのっとった上で)
ちなみに、村上氏が言う「全国で三百から四百の市」について、何かを思わず連想した人も多いのではないか。
江戸時代だ。いわゆる六十余州・三百諸侯の世界となる。
なお、江戸期において、律令以来の六十余州はすでに地域行政の単位ではない。三百諸侯らがそれを担っている。
よって、県庁が消え、300から400の市―――すなわち基礎自治体=コミューンが、国と直結するかたちで地域行政を受け持つという村上氏のイメージは、かなり未来的である一方、実は似たものを日本はかつて経験済みだったりする。
40年後の「諸侯」議会
村上氏発言における各数字を現実の状況にあてはめてみよう。
まずは、30万人~40万人の間(あいだ)を採って35万人、300~400の間を採って350のコミューンが日本に存在する場合を想定する。
35万×350=1億2250万という数字が出てくる。
すると、いうまでもない、これは当記事の冒頭に掲げた数字とほぼ同じだ。
日本の現在の総人口―――約1億2380万人というのは、35万人単位だと350のコミューンにほぼ収まる数字となる。
次に、数字を少し減らしてみよう。
村上発言に示されたうちの少ない方、30万人、300コミューンで考えてみる。
30万×300=9千万となる。
この約9千万人という数字は、現状の予測では、2066年から67年頃のわが国の総人口と一致する。(国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口・令和5年推計)。すなわち約40年後となる。
よって、村上構想(?)がその時代、仮に現実となった場合、わが国では、領域面積がそれぞれ異なる300のコミューンが全国に並立していることになる(都市部にあってはもちろん狭く、地方にあっては広い)。
すると、そこでは当然ながら、民選首長が1人ずつ立てられることになるだろう。
三百諸侯の復活だ。
そのうえで、彼ら諸侯=コミューン長が、地域行政を統べる傍ら、国の議会もかたちづくっていて、「幕政参画」しているなどといった図も、想像するとなかなか面白いものとなる。
すなわち、300議席による「地域代表院」と、全国区選出による「全国院」による新たな二院制だ。何やら話がSFじみてもきたが。
発言は不適切・不用意だったか?
ところで、上記の村上発言には、後日譚もある。
翌日、2月14日のことだ。
衆院予算委員会で、立憲民主党の落合貴之氏が、村上氏へ向けて質問した。議事録をそのまま掲げる。
―――落合貴之議員の発言―――
(第217回国会 2月14日 衆議院・予算委員会にて)
「立憲民主党の落合貴之でございます。
まず冒頭、追加で質問通告をした件につきまして、総務大臣に伺えればと思います。
新聞にも載っていましたが、昨日の総務委員会で、今世紀末に人口が半減するとの推計を踏まえて、現在千七百以上ある自治体は三百から四百の市で済む、極端なことを言うと、県庁は要らないし、道州制も意味がないとの発言がありました。
これは様々な反響を呼んでいまして、不適切、不用意な発言だという意見も多数出ています。
本日、改めまして、総務大臣御自身の昨日の発言につきまして、いかがでしょうか。」
以上のとおりだ。
誰がいつどこで言ったのかは知らないが、落合氏が述べるところによれば、村上発言については「不適切、不用意」との意見が「多数」出たのだそうだ。
かわいそうに―――。
個人的見解、個人的見解と、せっかく何度も念押ししながら話をしたのに、村上大臣にあっては、まことにご愁傷の旨を申し上げるほかない。
しかしながら、筆者は今回の村上発言をぜひ褒めたい。
これこそ大事な提言だ。よいたたき台となる意見であり、とどのつまり前向きだ。個人的見解でむしろ済ましておくべきものではない。
わが国の今後の急速な人口減少にあっては、これはもはやいかなるデータを見ても避けられないことだ。憂いたり、嘆いたり、過去に対策がなかったと悲憤慷慨したりといったタイミングはすでに過ぎ去っている。
間もなく、日本の地方からは、潮が引くように人がいなくなる。
都市部では、増えていく老人が減っていく若者や子どもの呼吸をますます息苦しくさせていく。望まないが、筆者も間もなくそれら鬱陶しい年寄りのひとりとなる。
仲よくやれても、軋轢が生じても、われわれはさまざまな仕事をこれからますます外国人に頼ることになるだろう。2070年における彼らの比率は、予測では総人口の1割を超えている(前出・国立社会保障・人口問題研究所)。いまのパリやロンドンを考えると、東京でも2~3割以上の住人が外国人となる風景が生じる可能性が少なくない。
これらをどういった仕組みで乗り越えていくか、あるいは逆にどう活かすか。
子や孫や、これから生まれる未来の日本人のため、村上発言がその一端を示したような「建設的」課題にこそ、われわれは積極的に議論を重ね合わせていくべきだ。
参考:
「2月13日 第217回国会 衆議院・総務委員会議事録」
「2月14日 同 衆議院・予算委員会議事録」
(文/朝倉継道)
【関連記事】
新内閣の重要課題「地方創生」はなぜ進まないのか?
行きたい人3割半。大阪・関西万博は盛り上がるのか? カギをにぎる2つの追い風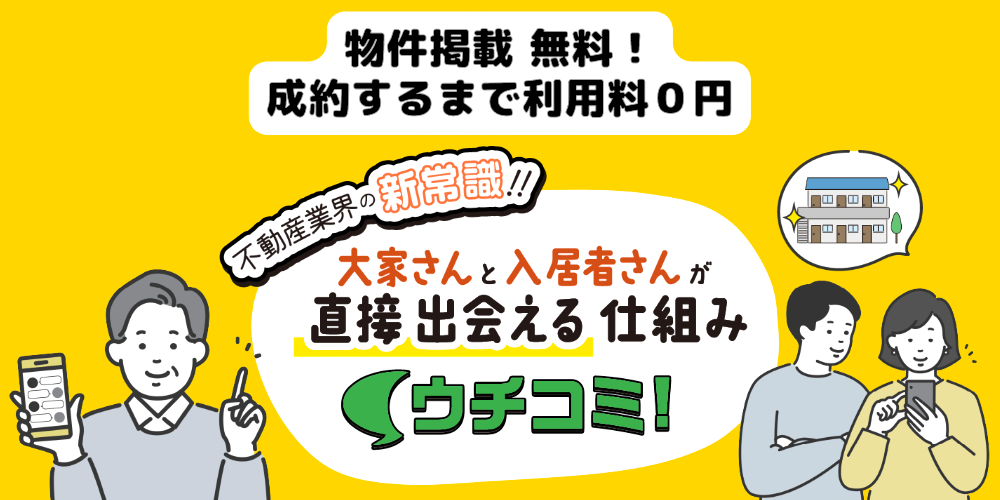
無料で使える空室対策♪ ウチコミ!無料会員登録はこちら
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。