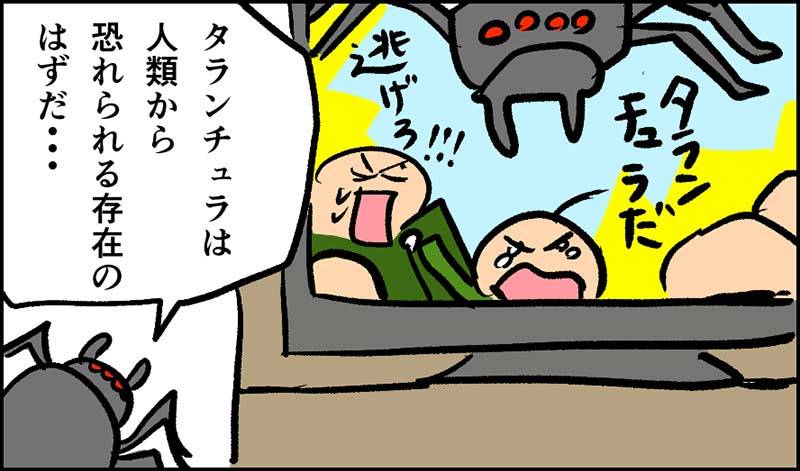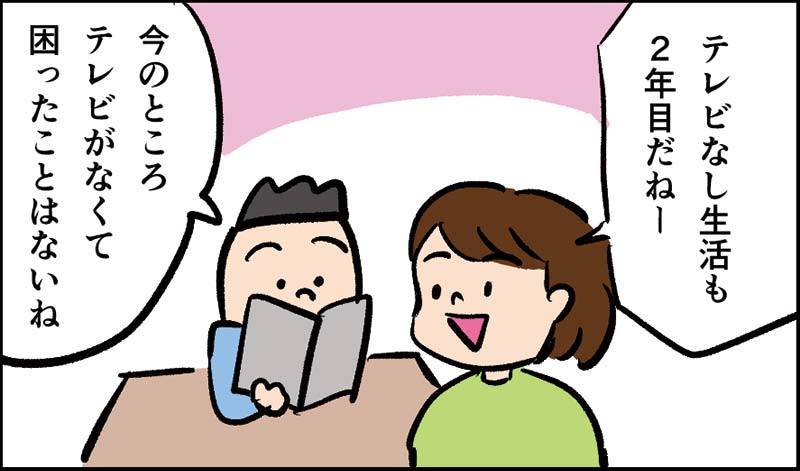新型コロナで帰省自粛、リモート帰省やインターネット墓参りで考える「墓参」の本当の意味

2020/08/08

イメージ/チリーズ・写真AC
そもそも「お墓」とはいったい何か?
新型コロナの感染者が増える中でお盆を迎え、帰省の自粛、オンライン帰省、リモート墓参など議論がされている。日本人にとって、帰省と墓参はセットになった行事になっている。しかし、仏教での墓参は、日本的な墓参とは意味が違っていた。
仏教にかかわる建築物の中で最も重要な存在は「仏塔」で、これは仏教の開祖、ゴータマ・ブッダの遺骨を祀る構築物である。もっとわかりやすくいえば、ブッダのお墓である。そのお墓を取り囲むように、僧院が建設された。
問題はその立地だ。島田明(ニューヨーク州立大学ニューバルツ校准教授)氏などの研究によると、初期仏教の段階において、すなわち紀元前3世紀前後、仏教にとって最重要の施設にほかならない仏塔が、インドの伝統的な発想では「不浄の地」に、おそらくはあえて建設されていた事実が、わかってきた。
もう少し具体的にいうと、南インドのアーンドラプラディッシュ州にあるアマラヴァティー遺跡の考古学的な調査にもとづく研究成果である。
紀元前3世紀前後、アマラバティーは南インドを支配していたアーンドラ王国のサータヴァーハナ王朝の首都だった。そして、南インドの仏教センターとして、北のナーランダー、南のアマラヴァティーといわれるくらい、繁栄していた。その証拠として、紀元前3世紀前後に建立された仏塔の基壇は、直径49.3メートルもあった。古代インドの仏塔としては最も有名なサンチの第一塔が直径36.6メートルだから、アマラバティーの仏塔がいかに大きかったか、よくわかる。
じつはこの仏塔は、王の居住する都城のダーニヤカタカの城壁の外の、しかし城門付近にあった。注目すべきことに、この立地は、たった一例をのぞけば、全インドの仏教施設に共通していた。
インドに現存する仏塔:紀元前3世紀頃にアショーカ王によって建立されたサーンチー/The "Great Stupa" at Sanchi (India) 2003 ©︎Gerald Anfossi
不浄の地に作られた「ブッダの墓」
なぜ、城壁の外の、しかし城門のすぐそばという地が選ばれたのか。
古代インドの精神世界において正統派を自認していたバラモン教からすれば、そこはまさに「不浄の地」だった。にもかかわらず、ブッダのお墓はそこに建設されていた。
バラモン教の考え方では、城壁で囲まれた都城内部こそ、身分制度においても儀礼の遂行においても、正しい秩序が支配する空間だった。逆に、城壁の外はいかなる意味においても正統とはとてもいえない者たちが跋扈する空間だった。言い換えると、バラモン教を拒否する宗教者、バラモン教的な身分制度からはみ出した賤しい者たち、あるいは交易をおこなうためにどことも知れぬ異界から訪れる商人たちが、活動する場だった。
さらに見逃せない事実を、島田氏は指摘している。仏塔があった場所は、埋葬の場と重なっていたのである。その証拠に、アマラバティーの仏塔から北西にわずか100メートルしか離れていない場所に、複層化した埋葬跡地が見つかっている。
このように、僧院や仏塔が埋葬地と重なり合う場所に立地していた事実から考えて、仏教がごく初期の段階から葬儀に深くかかわっていたことは、もはや疑いようがない。仏教は最初から「葬式仏教」だったのである。
なお、葬送を忌避するバラモン教の寺院は、僧院や仏塔がある地域とは正反対の方角にあった。
死者の骨を崇める不気味な宗教だった仏教
仏教は、ヒンドゥー教をはじめ、他の諸宗教からいろいろ批判された。その批判のうちに、「死者の骨を崇める不気味な宗教」というのがあった。インド的な伝統からすると、仏教の遺骨崇拝はそれほど奇異な行為だったらしい。
ただし、崇められる対象はブッダや聖人たちの遺骨に限られ、一般人の遺骨は崇拝の対象にはならなかった。この区別ははっきりしている。したがって、墓参りの対象にされたのはブッダや聖人たちの遺骨が祀られている仏塔もしくは墓所に限られ、一般人のお墓にお参りすることは、原則として、なかった。現に、初期型仏教を継承する南アジアや東南アジアの仏教圏では、人が死ぬと、お墓に埋葬すれば、それですべて終わったとみなされ、そのお墓にお参りすることはまずない。
そもそも、彼らの死生観では、ありとあらゆる生命体は、悟りを開くまで、永遠に輪廻転生を繰り返す。死者の意識体あるいは霊魂は、なにかに生まれ変わっているというものだ。とすれば、墓にあるのは、腐り果てた肉体だけなので、お参りするに値しないと考えられている。
日本と並んで、大乗仏教を継承するチベット仏教圏でも、事情は似たようなものだ。そもそも、お墓は立派な業績を残した聖人の遺骨やミイラを祀る施設と認識されている。
一般人の場合は、鳥葬といって、専門の業者が遺体を小さく切り分け、骨も肉と混ぜて団子状にして、ハゲワシに食わせてしまうので、後には何も残らない。あるいは、火葬した遺灰を粘土に練り込んで、ツァツァと呼ばれる素朴かつ極小の仏塔をつくり、お寺にある大きな仏塔や聖所におさめたりする。いずれにしても、お墓そのものをつくらないので、お参りのしようがない。
墓参りは案外新しい日本の習俗
では、日本の墓参りは、いつ、どのような経緯で始まり、定着したのか――。
それについては、次回、お彼岸の時期に詳しくお話ししていこう。ただ、先に一つだけ申し上げておくと、墓参りが定着したのは、そう古い話ではない。せいぜい江戸時代以降のことに過ぎない。
その理由は簡単だ。江戸初期に幕府の宗教統制政策の一環として、寺檀制(寺請制度)、すなわち菩提寺と檀家という制度が成立するまで、一般人のお墓はほとんどなかったからである。
■関連記事
見直される「お盆」の起源、日本人にとってのお盆の意味
この記事を書いた人
宗教学者
1953年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院博士課程修了。専門は宗教学(日本・チベット密教)。特に修行における心身変容や図像表現を研究。主著に『お坊さんのための「仏教入門」』『あなたの知らない「仏教」入門』『現代日本語訳 法華経』『現代日本語訳 日蓮の立正安国論』『再興! 日本仏教』『カラーリング・マンダラ』『現代日本語訳空海の秘蔵宝鑰』(いずれも春秋社)、『密教』(講談社)、『マンダラとは何か』(NHK出版)など多数。