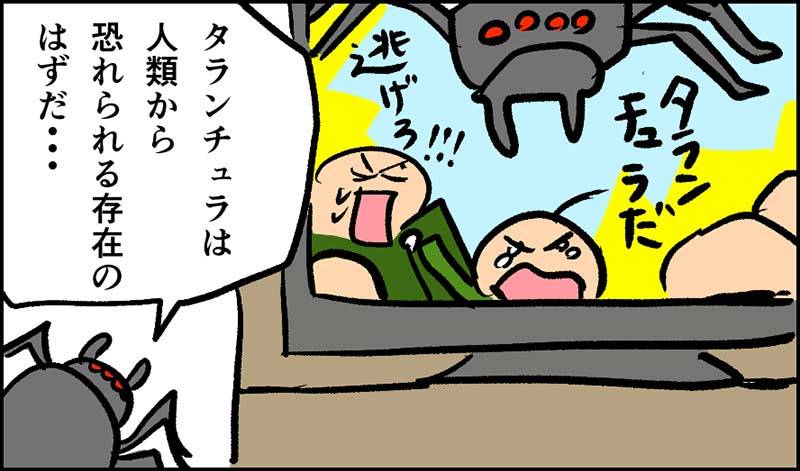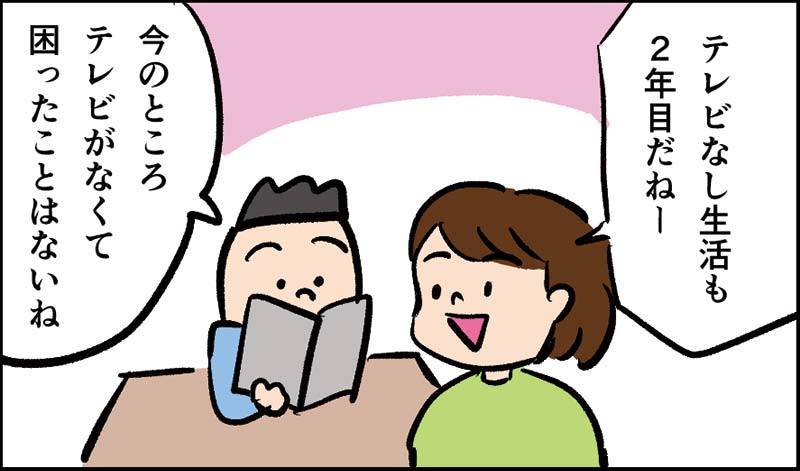第7回 伊豆・福浦――南イタリアの港町のような美しさと江戸自体の息づかい

2018/12/19


どれくらいの人が「福浦」の名を知っているだろうか。ある人に「福浦を知っていますか」とたずねたところ、「知っています」と答えられてびっくりした覚えがある。それは、ご主人がスキューバーダイビング好きで、よく通っていたに過ぎなかったのだが、どうもスキューバーダイビングのメッカとしての知名度は高いようだ。しかし、実際に福浦を訪れ、このような趣味を持つ集団に数多く出合うと、静かな漁村集落とのミスマッチした光景が印象として残る。
珍味の干魚を好物とする人は、福浦という名をよく知っているかもしれない。真鶴半島沖は、とびきりおいしい魚が捕れる。ただ、町中に入り込んでも、真鶴のように飲食店があるわけではない。行き交う人たちは地元住民ばかりで、観光気分で訪れる場所ではない。それでも、時代から長く取り残されながらも、そこに描き込まれる風景は存在感を放つ。
福浦は小さな真鶴の半島を隔てた隣町である。日常的に徒歩で峠越えすることをもはやしなくなった現在、2つの町の距離感は体験的に理解できないほど大きくなっている。忘れがちだが、歩くことは、様々なレベルの空間を自在に身体感覚として認識でき、現在の峠越えもあながち無意味ではないように思う。
真鶴より真鶴らしい町へ
作家の川上弘美は、『真鶴』という地名をタイトルにした小説を書いた。読んでの感想だが、真鶴だけであの痛いほどに視線の奥に内在する空間の深さを表現し得たのかと気になる。真鶴の名を借りて、もう一つ別の世界が潜んでいるように思えた。
福浦の町を訪れようと思い立った直接の理由は、「真鶴より真鶴らしい町」と話していた真鶴町役場の方の一言が気になったからだ。海側から見た真鶴は、家々が入江奥の斜面地にひな壇状に並び、建て込む町並みが一望できる。西日が射し込むころは、家々が日に染まり、南イタリアの港町に迷い込んだ錯角を起こす美しさがある。斜面にできた町の風景が真鶴らしさの一つであるとすれば、福浦はそれをより徹底した斜面地集落を形成した。役場の人は、この風景を見て、福浦が真鶴より真鶴らしく映ったのだろうか。しかしながら、真鶴のようにいっぱいに日を受けた明るさが福浦にはない。地形条件が異なるために、日を浴びる斜面地に家が建てられない。川を挟んだ両側は、風雨とともにまるで日差しを避けるように、家々が密集する。
自然の猛威からさける営みの工夫は、中世の真鶴と類似する環境である。真鶴の原風景は窪地の比較的平坦な土地から出発する。一方の福浦は、はじめから斜面地に成立しており、真鶴らしさの原型の一つが福浦に色濃く残り続けてきたことになる。
真鶴と福浦を結ぶ古道

写真1 真鶴へ抜ける峠越えの道
大正13(1924)年に鉄道の熱海線が引かれた。昭和9(1934)年には熱海・沼津間のトンネルが完成する。その後、東海道本線のルートが変更され、真鶴や福浦の陸の表玄関が真鶴駅となり、駅が真鶴と福浦の人たち双方の出合いの場となる。真鶴駅ができる以前はといえば、半島を横断する険しい坂道を昇り降りしていた。現在ほとんど歩く人もいない道は、夏場になると雑草に隠れて道なき道となる。峠越えはそのような道を歩かなければならない。この道が真鶴と福浦を結ぶ重要な陸の道であり続けてきた。連載の5回目「「伊豆・真鶴」のラビリンス空間①」で、真鶴駅から“背戸道”を辿って突きあたったT字路を右に上がる坂道が福浦に至る古道である(写真1)。
真鶴から、峠を越える道を辿り福浦まで、真鶴半島を横断する道は開発とほとんど無縁であった。静かな道を歩く心細さも加わり、江戸時代に生きた人たちの息づかいがどこからともなく聞こえてくるような錯覚に落ち入る。上り坂であった道は平坦となり、尾根沿いに通された幹線道路を横切った先も思いのほか平坦な道が続く。

写真2 峠越えの道から海と福浦の町並みを望む
真鶴から、峠を越える道を辿り福浦まで、真鶴半島を横断する道は開発とほとんど無縁であった。静かな道を歩く心細さも加わり、江戸時代に生きた人たちの息づかいがどこからともなく聞こえてくるような錯覚に落ち入る。上り坂であった道は平坦となり、尾根沿いに通された幹線道路を横切った先も思いのほか平坦な道が続く。
道が少し下りはじめた感触を足裏に感じた時、覆われた木々のあい間から海が日の光りを反射させ、キラキラと輝く風景が目に飛び込む(写真2)。

写真3 斜面地を上る細い道
開けた場所からは海の広がりと福浦の町並みが確認できる。この先は急な階段が続き、何段も踏み締めて降りることになる(写真3)。眺望はすばらしく、眼下にある福浦の家並みが近づく。
福浦の空間構成

写真4 子之神社の参道
急な階段の途中、南を向いた子之神社の社が眼下に見えてくる。この神社の創建は、鎌倉時代と書いた由緒がある。実際には、さらに古くまで遡る可能性を周辺に漂う空気から感じる。子之神社と隣り合った海側には、天正6(1576)年以前の建立とされる醍醐院の本堂が音無川に向けて建つ(写真4)。

写真5 音無川と両岸に建ち並ぶ家々
参道も唯一流れる川に向く。音無川沿いの斜面地には家々が密集する(写真5)。

写真6 子之神社と海を結ぶ道
子之神社は、醍醐院と同様に、直角に西に折れた立派な参道が音無川に向く。ただもう一つ、子之神社からは、海に向かう細い道も真直ぐ南に延びる(写真6)。現在は、醍醐院の裏を抜けるかたちだが、海との関係の強い福浦であるから、むしろ海に向かう参道の方が古いように思われる。
江戸時代の福浦は、寛永初期の24戸から、200年近くの間に93戸(天保4年)と4倍近くに増加した。戸数の伸びは、特に寛文12(1671)年から寛政4(1792)年の間にかけて集中する。丁度河村瑞賢が東廻り航路を整備した寛文12(1671)年の直ぐ後からであった。ほとんどの家は船乗りで、漁業と廻船が主の寒村にも物流の拡大と江戸の膨大な消費が影響したものと考えられる。それでも、福浦は、真鶴に比べて自然の良港となる入江にめぐまれなかった。そのことから、廻船に関しては沖と内陸を橋渡しする小規模なものに限られた。漁業以外では、わずかな畑地と石切が少しだけ生業を助けた。
かつて小さな入江となっていた、海に流れ出る音無川河口付近は、船溜まりも兼ねた港機能が集中していた。この小さな入江には道が古くから集まった。道幅の狭い、階段状の道が港を起点に斜面を上がりながら集落を形成する。幾つもの坂道が集まる辺りから子之神社の下まで、現在も立派な屋敷が見受けられ、福浦の中心であり続けている場所だとわかる。この仕組みが長い年月を経ても変化することなく残り続ける。それほど変化を許さない地形形状の上に、この港町が成立した。ひっそりと歴史を刻んできた福浦だが、内陸側に潜在する空間のあり様は魅力的である。
この記事を書いた人
岡本哲志都市建築研究所 主宰
岡本哲志都市建築研究所 主宰。都市形成史家。1952年東京都生まれ。博士(工学)。2011年都市住宅学会賞著作賞受賞。法政大学教授、九段観光ビジネス専門学校校長を経て現職。日本各地の土地と水辺空間の調査研究を長年行ってきた。なかでも銀座、丸の内、日本橋など東京の都市形成史の調査研究を行っている。また、NHK『ブラタモリ』に出演、案内人を8回務めた。近著に『銀座を歩く 四百年の歴史体験』(講談社文庫/2017年)、『川と掘割“20の跡”を辿る江戸東京歴史散歩』(PHP新書/2017年)、『江戸→TOKYOなりたちの教科書1、2、3、4』(淡交社/2017年・2018年・2019年)、『地形から読みとく都市デザイン』(学芸出版社/2019年)がある。