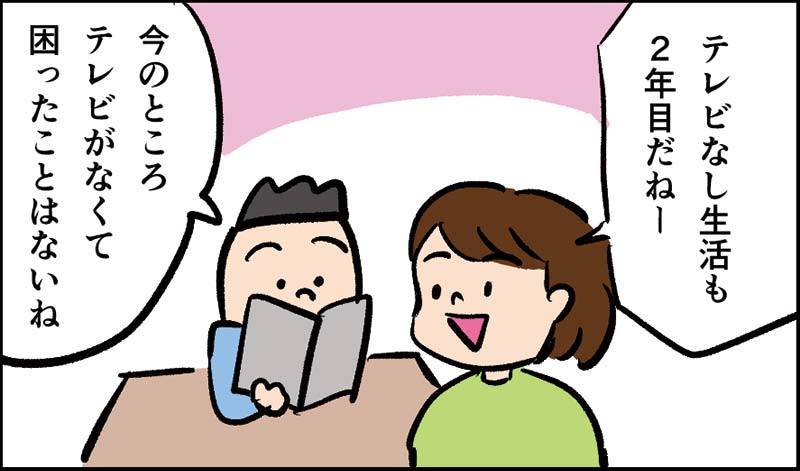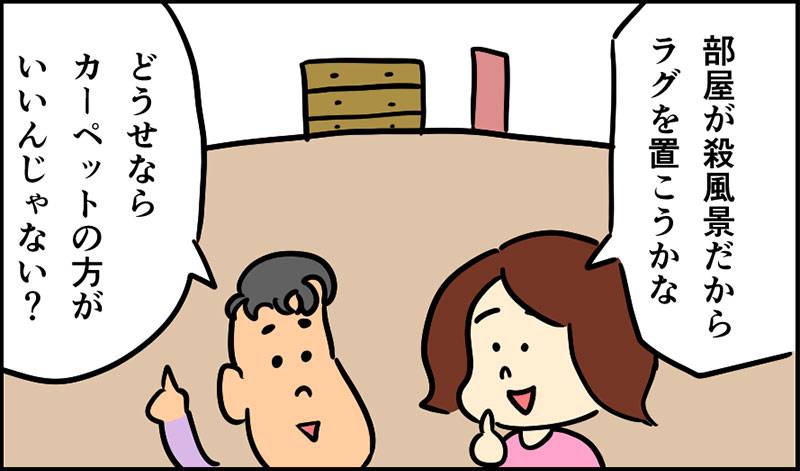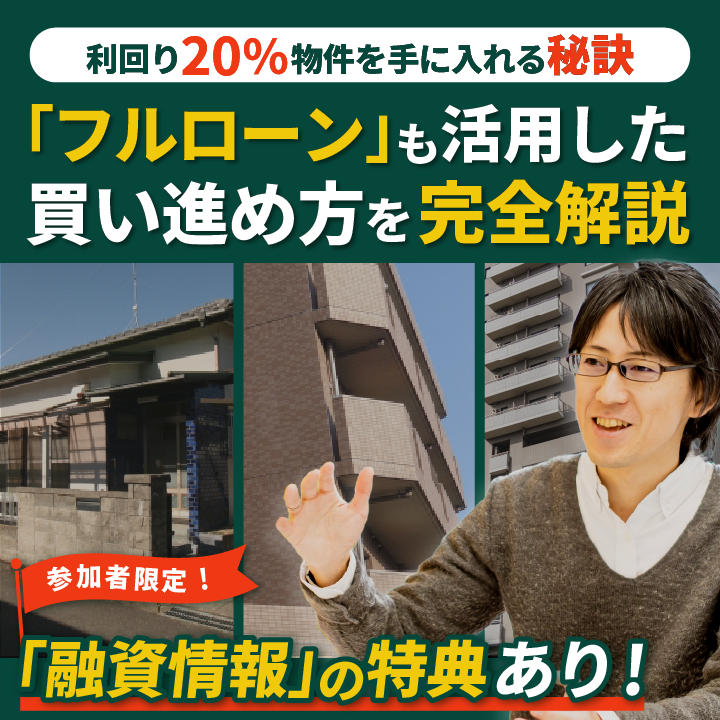「働く母」が8割超に。国民生活基礎調査の結果が公表
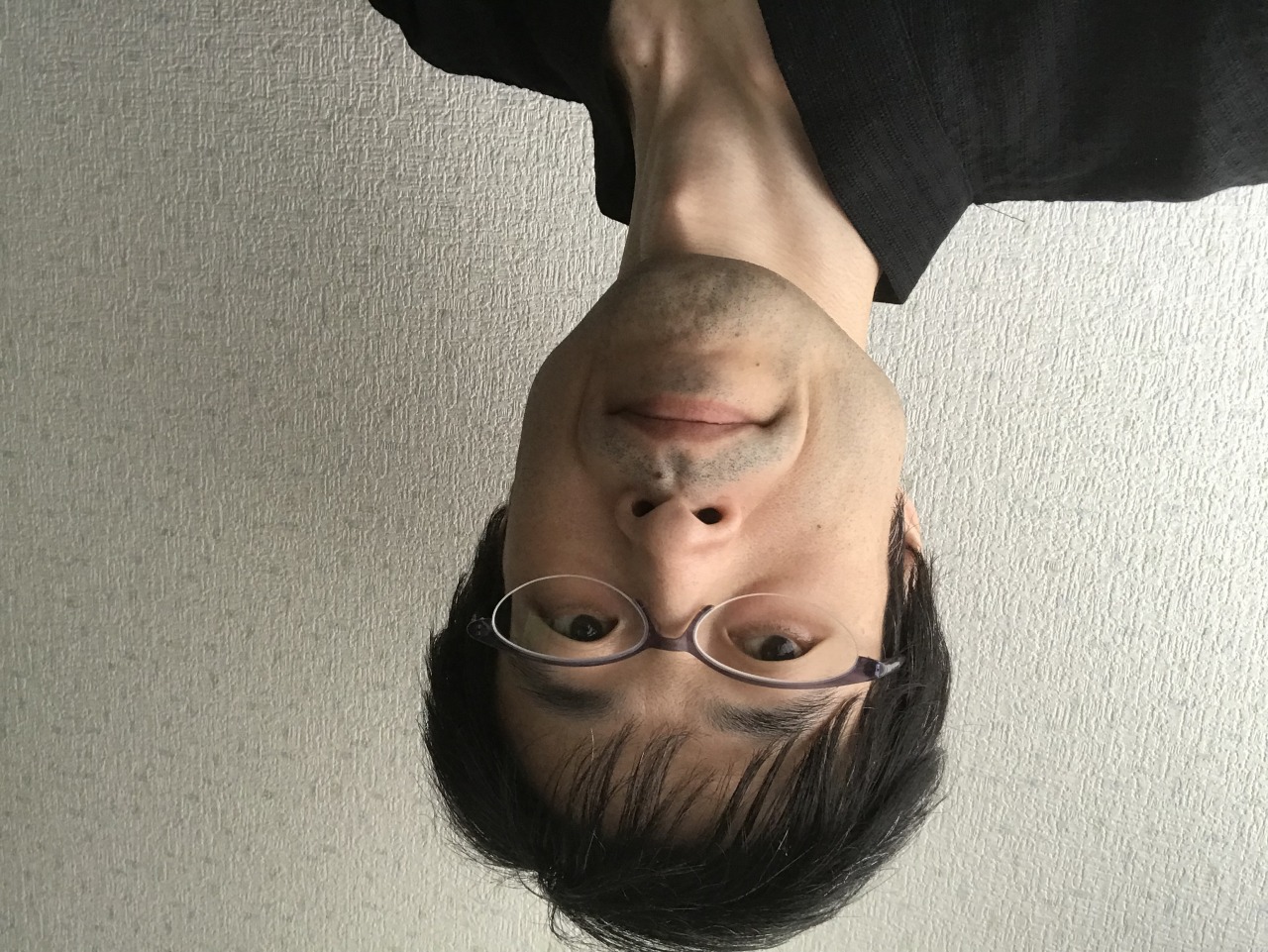
2025/07/16

国民生活基礎調査の結果が公表
この7月4日、厚生労働省から2024(令和6)年「国民生活基礎調査」の結果が公表されている。
「単独世帯は1899万5千世帯で、過去最高(前年は1849万5千世帯)。なおかつ、その割合は全世帯の34.6%で、こちらも過去最高(前年は34.0%)」
「高齢者世帯は1720万7千世帯で、過去最高(前年は1656万世帯)。なおかつ、その割合は全世帯の31.4%で、こちらも過去最高(前年は30.4%)」
「児童のいる世帯は907万4千世帯で、過去最少(前年は983万5千世帯)。なおかつ、その割合は全世帯の16.6%で、こちらも過去最少(前年は18.1%)」
―――とのことだ。
そのほか、いくつか目に付く内容をひもといていこう。
(本調査において高齢者世帯とは、65歳以上の人のみで構成するか、またはこれに18歳未満の人が加わった世帯)
「働く母」が8割超
「児童のいる世帯」における母の仕事の状況をみると、「仕事あり」の割合は 80.9%となっている。8割超えは、比較可能な04年以来初めてのこと。なお「児童」とは、この調査においては18歳未満を指す。
内訳を覗いてみよう。
| 正規の職員・従業員 | 34.1% | 80.9% |
| 非正規の職員・従業員 | 36.7% | |
| その他 | 10.1% | |
| 仕事なし | 19.1% | |
このとおり、「働くお母さん」は、いまはごく普通の存在となった。
ただし、いわゆる「正規」で働く人は、比較可能な04年以降、最高の割合を示しながらも(上記34.1%)、非正規の数字を超えてはいない。
所得は増えても生活は苦しい
「児童のいる世帯」へ、さらにフォーカスしていこう。
以下は、同世帯における、1世帯当たり平均所得金額の年次推移だ。カッコ内に全世帯の平均も添える。
| 年 | 平均所得 | 全世帯平均 |
| 2014年 | 712.9万円 | 541.9万円 |
| 2015年 | 707.6万円 | 545.4万円 |
| 2016年 | 739.8万円 | 560.2万円 |
| 2017年 | 743.6万円 | 551.6万円 |
| 2018年 | 745.9万円 | 552.3万円 |
| 2019年 | 20年の調査が実施されなかったため未詳 | |
| 2020年 | 813.5万円 | 564.3万円 |
| 2021年 | 785.0万円 | 545.7万円 |
| 2022年 | 812.6万円 | 524.2万円 |
| 2023年 | 820.5万円 | 536.0万円 |
このとおり、直近のデータとなる23年の820.5万円という数字は、これを含む過去10年間において最高のものだ。8年前や9年前の数字に比べるとその差は110万円前後。大幅な増加となっている。
ところが、こちらを見てみよう。
児童のいる世帯における「生活が苦しい」を訴える割合だ。「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせた数字となる。
| 調査年 | 割合 |
| 2015年 | 63.5% |
| 2016年 | 62.0% |
| 2017年 | 58.7% |
| 2018年 | 62.1% |
| 2019年 | 60.4% |
| 2020年 | 当年の調査は実施されなかったため未詳 |
| 2021年 | 59.2% |
| 2022年 | 54.7% |
| 2023年 | 65.0%(10年間のうちの最高) |
| 2024年 | 64.3%(10年間のうちの2番目) |
このとおり、所得の大幅な増加とは裏腹に、直近2年間の調査分における「生活が苦しい」―――の割合は、それ以前の数年間に比べてかなり、あるいはやや高い。
これは一見おかしな結果だが、その主な理由は、当然ながら近年の物価高とそれにともなう生活費の増加ということになるだろう。何かと支出がかさむ子どもがいる世帯への影響が、如実に示されているこれらの数字といえそうだ。
所得の平均は500万を超えるも、中央値は400万ちょっと
さきほどチラリと出てきたが、今回の国民生活基礎調査において、全世帯の平均所得金額は536.0万円となっている(23年のデータ)。14年以降では、22年に次いで2番目に低い数字となる。
つまり、「児童のいる世帯」の所得こそ前記したとおり大きく上がっているが、国民全体を均せばまったくそうではない。
そのうえで、この536万円というのはあくまで平均値だ。高額な所得を手にしている人の数値に押し上げられることにより、この数字は、現在多くの人が平均的と感じているであろう値―――実感値よりも、おそらくかなり高いものとなっている。
そのため、全てのデータを並べた上での真ん中の値―――中央値となると、平均値よりも120万円以上低い410万円に下がる。
中央値よりさらに少ない、所得400万円までの人にあっては、
| 100万円未満 | 6.7% |
| 100万円以上200万円未満 | 14.4% |
| 200万円以上300万円未満 | 14.4% |
| 300万円以上400万円未満 | 13.1% |
―――合わせて48.6%にのぼる。
すなわち、こうした状況をもって、われわれの社会は現下の物価高の進行を耐え忍んでいるわけだ。なかなかにしんどいことといえるだろう。
働く母の反省
最後に「働く母」に話を戻し、これに絡んでの話題をひとつ付け加えよう。筆者の思い出話だ。
筆者が昔勤めていた会社は、女性の活躍が早くから世間に知られている会社だった。筆者の在勤中にも、女性が社長になっている(97年)。
そんな会社で、働く母のひとりからこんな話を聞いた。その内容となる。
彼女曰く―――
「私たちのように会社で毎日働く母親は、仕事をこなすため、考え方が段々と論理的になっていく。小さな子どもの感情的な訴えにも、つい理詰めで対応してしまう。正解や結論をすぐに返そうとしがちになる。子どもに対して、気持ちの在りようを尋ねるのではなく、その理由をまず質してしまったりもする」
「それではいけないと気付いた。子どもは親に対して、特に母親に対しては、理屈以前にまずは共感を求めてくる。子どもの気持ちを一旦受け止め、しっかり共感してあげないと、幼い子どもほど、親に対し安心することができない。会話が前に進まなくなっていく」
なるほど、と思った。
- 「痛い」―――「痛かったよね」
- 「出来ない」―――「難しいよね」
- 「嫌い」―――「そうか、これ苦手か~」
筆者も、たしかに幼い頃を振り返ると、母親にはとりわけそんなレスポンスを第一に求めていた気がする。
いまや母親の8割以上を占めることとなった「働く母」の皆さんにとって、以上はもしかすると参考になる話かもしれないと思ったので、添えておいた。
2024年「国民生活基礎調査」については、下記で内容をご確認いただける。
(文/朝倉継道)
【関連記事】
男女共同参画白書が公表。ふるさとは遠きにありて思ふもの?
「税リーグ」と不思議な町おこし
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。