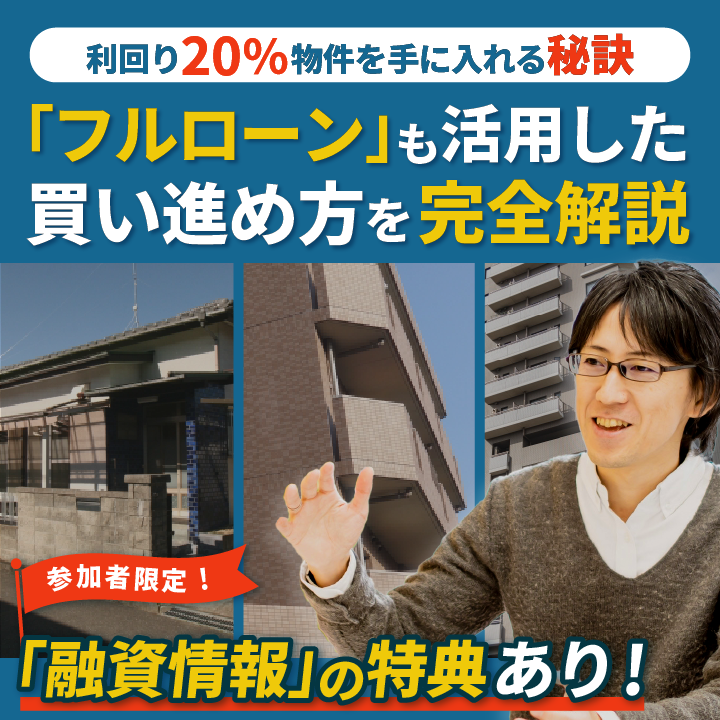住み慣れたこの家でこれからも暮したい――「今の部屋での暮らし、幸せですか?」

2021/12/22

イメージ/©️paylessimages・123RF
一般社団法人日本ホームステージング協会 代表理事の杉之原冨士子さんは、専業主婦から、引っ越しの梱包や開梱、収納、そして内覧のための片付けなど、住まいに関わるさまざまな業務を経験し、日本で唯一ホームステージングを体系的に学べる日本ホームステージング協会を設立した。不動産の売却や賃貸、生活に関わる“ホームステージング”や“片付け”の必要性を、杉之原さんの実体験も交え、さまざまな角度からお届けする。
◆◆◆
衝撃的なタイトル? 『いつ死んでも後悔しないお片づけ』
年末になると、片づけや掃除の本が売れるといわれています。
私は『いつ死んでも後悔しないお片づけ』というタイトルで本を出しています。この年末に23刷の重版が決まりまして、発行部数5万9500部となりました。たくさんの方に読んでいただき本当に嬉しい限りです。
「捨てる」ではなく「安心で安全な部屋」にする
片づける基準は、安心で安全な部屋にすることが第一です。
例えば、
・床上に置いてあるモノにつまずかないように片づける
・脚立を使わないと届かないものは手の届くところに移動する
・食品なら賞味期限を見て、過ぎているものは廃棄する
など、基準を安心・安全に置き換えると、要・不要の分別がしやすくなると思います。
先日セミナーを行ったときに、ある高齢の方から、和ダンスの中の着物がなかなか捨てられない。と質問がありました。
安心・安全の観点から言えば、タンスの中に納まっているのであれば、危険ではありません。そのままにしておいても全く問題はありません。そのときは、「ほかにもっと、片づけなくてはいけない場所があるのではないでしょうか?」というお話をしました。捨てられないものを無理に捨てる必要はないのです。
やり方としては、今使っているものは使う場所に置き、使っていないけれど取って置きたいものは、使っているものとは別にして箱に入れて収納してしまいます。
大事なモノと大事でないモノが一緒に混在していることが混乱の原因ですから、大事なモノだけをまずはそこから取り出すことが必要です。
「お母さん、この中で大事なモノってどれ?」という具合です。するとお母さんは、「これとこれと……」と選ぶようになるはずです。
また、使っているものを手元に置く。
「お母さん、この中でよく使っているモノってどれ?」と同じように聞きます。
自分で選んでもらう。捨てる方に集中するのではなく、必要なものに集中する。という方法をとってみてください。
このようにすることで、感情的な摩擦が軽減されるのではないでしょうか?
感情をぶつけても何もいいことはありません。せっかく、幸せな暮らしができるはずだったのに、親子の関係性が悪くなったのでは本末転倒となってしまいます。
かけがえのない時間を共有できる
実家の片づけをぜひ一緒にやっていただきたい理由があります。
実家にはこれまでの家族の人生の歴史が詰まっています。子どもからすると、生まれたときから親ですので親という顔しか知りません。
当たり前ですが、親も赤ちゃんの頃があるし、学生時代、恋をしていた時代もあるのです。実家の片づけには、そんな知らない親の顔がモノから見えてくることがあります。
若かりし頃デートしている両親の写真や結婚式の写真、自分が生まれて抱っこされている写真。そんな初めて見る親を知ることができる、かけがえのない時間を親子で共有することができるのです。
ぜひ、若い頃の話をたくさん聞いてください。そうすることで、親御さんがさらに愛おしくなるはずです。
【過去の記事】
〜賃貸物件がホームステージングで生まれ変わる②〜
〜賃貸物件がホームステージングで生まれ変わる③〜
ホームステージングの効果は空室改善だけではない
この記事を書いた人
一般社団法人日本ホームステージング協会 代表理事
専業主婦を経て運送会社に就職。事務パートから引越営業職と同時にお客様の荷造り荷解きサービスも担当。2011年に独立し、お片づけ・梱包会社株式会社サマンサネットを設立。多くの現場経験からホームステージングの必要性を感じ2013年日本で唯一ホームステージングを体系的に学べる一般社団法人日本ホームステージング協会を設立。 一般社団法人 日本ホームステージング協会 https://www.homestaging.or.jp/