牧野知弘の「どうなる!? おらが日本]#5 新元号住宅市場~日本の住まい方はこうなる
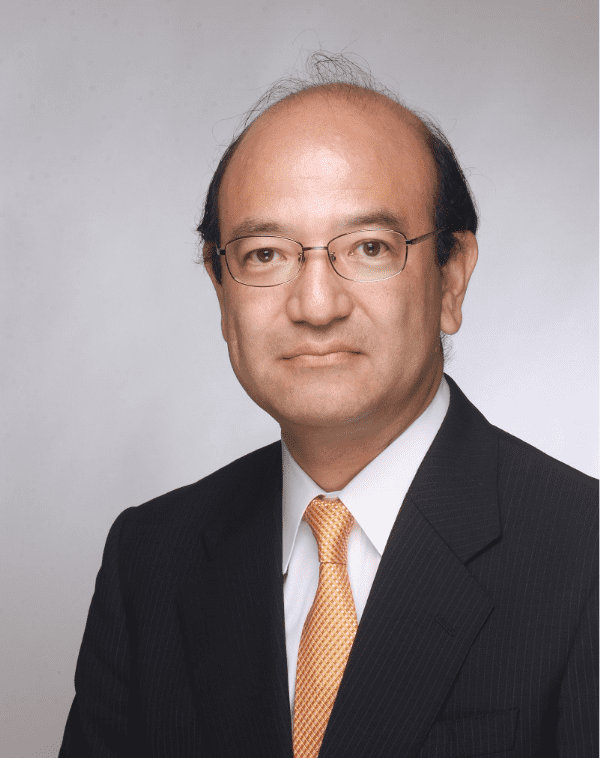
2018/09/01

新元号元年、日本の住宅市場はどう変化するか?
来年5月1日から新元号が制定される。西暦表記が進む中、我々の生活に元号が本当に必要かといった議論はあるが、「昭和世代」「平成世代」といった世代表現や、「平成バブル」といった時代的背景に元号をなぞらえるのは一般的な表現としてよく使われることから元号はある意味便利な表記ともいえる。
さて、新元号が制定される日本の住宅市場はどう変化していくのだろうか。いや、変化せざるを得ないのだろうか、展望する。
カギは消費税率のアップ
来年住宅市場を襲う最大の変化の波は新元号元年10月に迫る消費税率のアップである。安倍内閣はこれまで二度にわたって消費税率のアップを見送ってきた。景気の上昇により税収は民主党政権の時代よりも増加したものの、財政状況の厳しさは相変わらずであり、予算編成にあたって大量の赤字国債を発行せざるを得ない、「火の車」状態にある。ポピュリズムをあからさまに推し進めてきた政権も、さすがに今回の税率アップの「先送り」はできないだろうし、してはならないだろう。
そこで思い出されるのは前回、2014年4月の消費税率アップが実施されたときの状況だ。当時は税率5%から8%への大幅アップだった。今回は8%から10%であるので、引き上げ幅としては前回を下回る。
だが、消費者心理として税率10%というのは相当のインパクトがありそうだ。買物をする際、8%という税率を価格に瞬時に上乗せして税込み価格を算出できる人は少ないが、10%であれば簡単だ。その分、重税感をひしひしと感じることとなるのだ。
住宅の取得にあたっては、土地については消費税がかからないものの、建物については消費税がかかってくる。土地にかからない理由は明快だ。土地は「消費する」ものではないからだ。建物は会計上も減価償却が認められるとおり、摩耗して劣化してやがてはなくなる物、つまり消費財であるから、消費税の対象となる。
デベロッパーの思惑通りにはならない可能性も
ここで注意しなければならないのが住宅のうち、とりわけ建物代の割合が高いのがマンションということだ。一般的にはマンションの販売価格に占める土地対建物の比率は3対7程度だ。これが都心のタワーマンションになるとその比率は2対8から1対9程度まで建物の比率が高まる。建物が大きい(容積率が高い)分だけ建物の割合が大きくなるというのがその仕組みだ。ということは税率のアップが販売価格にストレートに「効いて」くることになる。
前回の税率アップの際は、新築マンション購入の場合、特例で増税前年である2013年9月末までに売買契約を締結すれば、2014年4月の税率アップ時点で、建物が完成、引渡しがされていなくとも、消費税率は旧税率5%を適用するというルールだった。
このため、2013年はマンションの「駆け込み需要」と呼ばれたように、マンション販売は絶好調。モデルルームに大量の客が押し寄せ、ちょっとした社会現象となった。この現象を裏付けるように、2013年のマンション供給戸数は不動産経済研究所の調べによれば5万6478戸と前年を23.8%も上回ることとなった。
今回も同じ考え方に基づけば、2019年4月までに売買契約を締結したものについては旧税率が適用されることになるため、マンションデベロッパー業界では「夢よもう一度」とばかりに供給を増やす動きが顕著になっている。
しかし、どうやら今回については、彼らの思惑通りにはならない可能性が高い。まず、都心居住が進む中、新築マンションは都心部でないとなかなか売れない時代に入ってきている。また都心のマンションも都心居住という「実需」だけで売れているのではなく、相続税などの「節税」ニーズや外国人投資家による「投資」ニーズで販売を補っているのが実態だ。彼らにとっては消費税率よりも相続税の節税効果や、短期間での売却益等が購入動機としては主体となるので消費増税が即、購入に走らせる動機にはつながらない。
また、ここ数年マンションの用地担当者は都心での用地取得に苦戦している。理由は2つ。ホテルの開発ラッシュでマンション適地であっても、ホテル会社との競合に敗れて用地を仕入れられないことがひとつ。そして、建設費の高騰で、土地代を含めたマンション販売価格が実需層である一般の消費者にはすでに手の届かない範囲にまで値上がりしてしまい、都心での商品企画が困難な状況になっていることがふたつめの理由だ。
それでも用地取得のノルマを抱える担当者が向かうのは、土地代が安い郊外ということになる。今後マンション市場では郊外のマンション販売が急増すると言われているのは上記が理由なのだ。
しかし、この作戦はどうだろうか。都心居住に「逆行」してまでも、今の実需層が新築マンションを購入しようと思うだろうか。都心の中古マンションに対する人気は高まるように思うが、郊外の新築マンションに「駆け込み需要」が発生するとは考えにくいものがある。
また前回の「駆け込み需要」は、翌年に大幅な供給減となり、業界では当初、これを需要の先取りによる「反動減」と表現したが、実際にはその後もマンション供給戸数は減り続け、2016年には3万5672戸と4万戸の大台を割り込む状況となっている。
このことからも今回の税率アップがマンション業界の「干天の慈雨」と期待するのはやや楽観的にすぎるのではないだろうか。
また東京五輪開催まであと2年に迫る中、これまで投資用で買われていたマンションの多くが「鞘取り」を目論んで売却する住戸が増加することが見込まれる。これらのマンションの多くが、東京湾岸部のタワマンなど比較的都心部に立地する物件が多いため、中古市場には都心物件も数多く出回ることとなりそうだ。郊外の新築よりも都心部の中古を選択する実需層が多いかもしれない。
大量の相続物件がマーケットを混乱させる
さらには新元号時代には首都圏郊外に住宅を持っていた団塊世代を中心とした高齢世帯の多くで大量の相続の発生が見込まれる。相続した世代にとっては親の残した住宅は通勤にも不便で車なしでは生活ができない「ありがたくない」家がほとんどだ。こうした家が中古住宅として大量に出回ることも住宅市場の混乱要因となるであろう。
マンション業界はこれまではとにかく、供給戸数を増やす「量的拡大」作戦を首尾一貫続けてきた。もともとマンションは利幅の大きなビジネスではないために、ある程度の量を確保することで、経営を維持しなければならなかったからだ。
しかし、今は住宅に対する実需は人口が減少し、年齢構成が高齢化に向かう中で、拡大は期待できない。多くの人々にとって、住宅はすでに所与のものとなっており、新しい住宅を求めるというよりも、親の残した実家や子供たちが出ていった後の自宅を持て余す時代になっている。
ミレニアル世代が「住まい方」を変える
自分たち家族だけが買って住むのでは、家にかかるコストがもったいない。最近ではシェアリングエコノミーという発想が住宅に対する考え方にも芽生え始めている。どうやら新元号の住宅市場では、建設費の際限ない上昇と消費税率アップによって新築住宅を買うというこれまでのステレオタイプ的な住宅に対する考え方に大変革が生じてくる可能性が高いのだ。
今のミレニアル世代以下の人たちは、モノを共同で使用することにあまり抵抗感がないといわれる。
シェアハウスは、学生や若い人たちが職業や国籍、性別などに関係なく、同じ家をシェアして暮らすというものだ。リビングルームや水回りなどは共用し、入居者はそれぞれの部屋を専有し、互いに干渉することなく生活している。
この考え方は欧米人などではごく普通の考え方で、最近話題の民泊などもこの考え方に近いものだ。欧米ではバカンスシーズンなどになると、1ヵ月も2ヵ月も家を空けることになるので、その間、観光客などに自分の家を貸しだす。
「自分たちは使わないのでどうぞシェアしてください」
というものだ。これまでの日本人は自分が留守の間、他人に自宅を使わせることには抵抗を覚える人がほとんどだった。
しかし、シェアハウスなどを使いこなす彼らは、こうしたことにあまり抵抗を感じなくなってきているといわれている。
すでにカーシェアという、一台の車を近隣住民がシェアして利用する仕組みも世の中ではどんどん普及してきている。このカーシェアもはじめのうちは「他人と車を共有するなんてレンタカーじゃないのだから」などといった、おもに親世代からの批判的な意見が多くあったが、今ではすっかり定着している。車一台を所有してメンテナンスすることの無駄を彼らはしなやかに理解し、車をシェアすることに対して「別にいいじゃない」「気にしない」「合理的」と考えるのだ。
彼らはさらに日頃身に着ける衣服までメルカリでシェアして着ることにまったく頓着しない。人が着た服であることに何の違和感も抱かないのである。
こうした考え方に則れば、新元号では、家を夫婦共働きだから、自分たちが使わない昼間は、近所の人たちのお稽古事に使ってもよいですよ、とか一時的に倉庫として貸してもよいですよ、キッチンを充実させて近隣の奥様がたのお料理教室にお使いください、といったシェアリングエコノミーの考え方が広がってくる可能性がある。
オフィスと住宅などが混在するエリアなら、近隣オフィスのための「貸会議室」に開放してもよいかもしれない。近隣のお店の倉庫として余った部屋を活用してもらうことも考えられるだろう。
住宅はもはや自分だけの財産ではない
住宅を自分だけの財産として、何の収益も生み出さずにただ囲い込んでいるのではなく、活用して、自分たちの生活をさらに豊かにするための道具として活用するという発想だ。
このように考えてくると、新元号時代においては「資産性の高さ」という曖昧なセールストークだけで、管理規約でガチガチに利用を制限される新築マンションを買うよりも、中古住宅を買って自分たちの稼ぎの足しにもなるように自由に活用していく「しなやかな」住まい方が求められるようになるのではないかと考える。
皮肉なことに、新元号元年の「消費税率アップ」が、多くの人々の住宅に対する見方、住まい方を変えるきっかけとなるのではないか。住宅市場は大きな転機に直面しているのである。
この記事を書いた人
株式会社オフィス・牧野、オラガ総研株式会社 代表取締役
1983年東京大学経済学部卒業。第一勧業銀行(現みずほ銀行)、ボストンコンサルティンググループを経て1989年三井不動産入社。数多くの不動産買収、開発、証券化業務を手がけたのち、三井不動産ホテルマネジメントに出向し経営企画、新規開発業務に従事する。2006年日本コマーシャル投資法人執行役員に就任しJ-REIT市場に上場。2009年オフィス・牧野設立、2015年オラガ総研設立、代表取締役に就任。著書に『なぜ、町の不動産屋はつぶれないのか』『空き家問題 ――1000万戸の衝撃』『インバウンドの衝撃』『民泊ビジネス』(いずれも祥伝社新書)、『実家の「空き家問題」をズバリ解決する本』(PHP研究所)、『2040年全ビジネスモデル消滅』(文春新書)、『マイホーム価値革命』(NHK出版新書)『街間格差』(中公新書ラクレ)等がある。テレビ、新聞等メディアに多数出演。





















