SNSの荒海を渡るとき、気をつけたい「合接の誤謬」というワナ
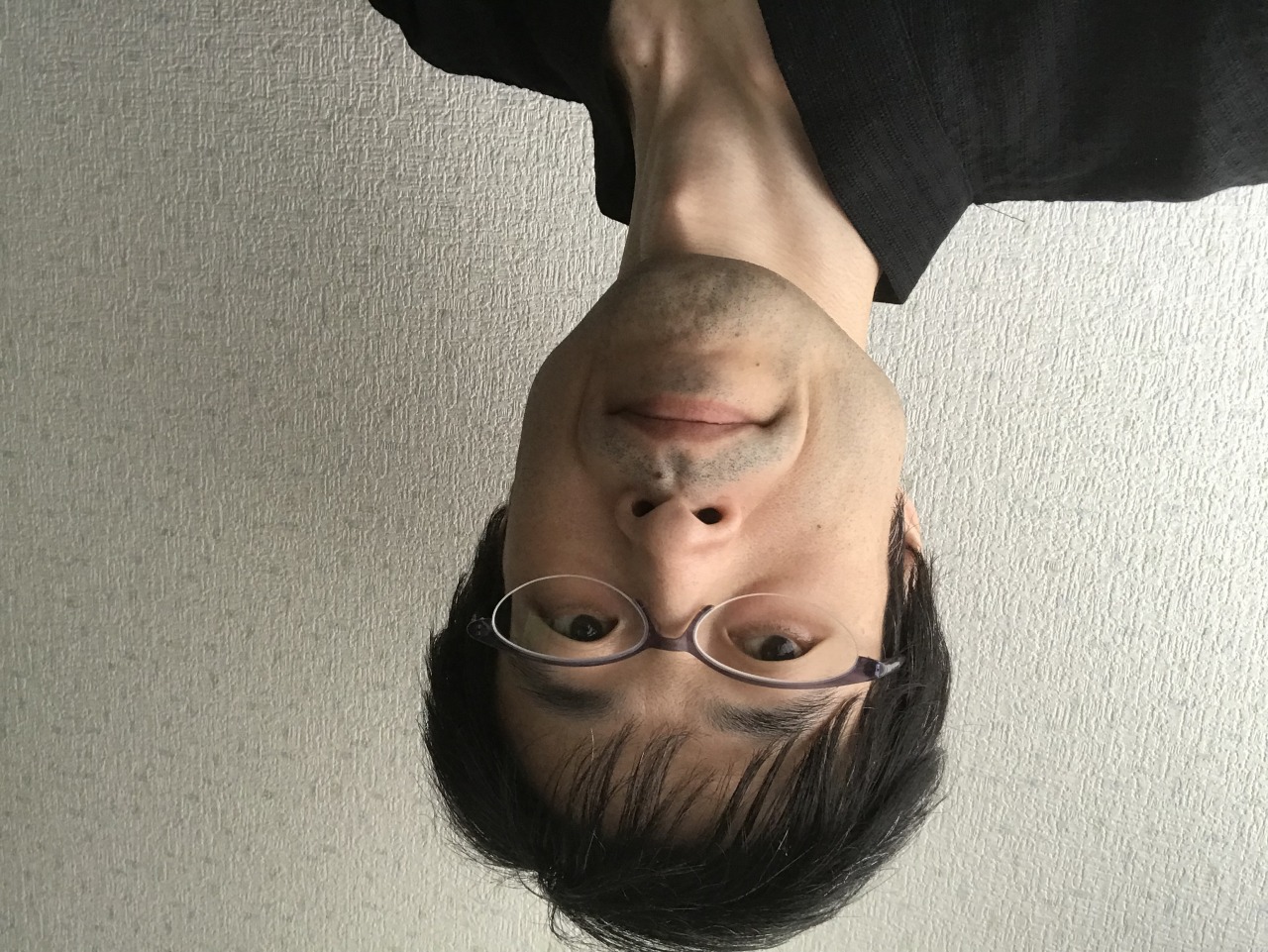
2025/11/08

ある国会議員のミス
筆者も日頃色々と間違えることが多い間抜けな人間のひとりだ。なので、他人のミスをあげつらうことは本意ではない。ただ、いまからこの記事で述べることに絡んで、とても参考となるので、まずは以下を示したい。
先般9月初めに、ある国会議員がSNSに掲げた一文となる。
--------------------------------------------------
(以下原文のまま。一部の改行と空欄のみを削除)【年間の行方不明となった技能実習生数】
2023年(令和5年)に日本で行方不明(失踪)となった技能実習生数は過去最多の9,753人。これは前年の約3倍に増加した数字です。技能実習生全体に対する失踪率は、約1.9%とされ、近年では年間おおよそ1.7~1.9%の範囲で推移しています。どのような形であれ海外から労働力を入れ、日本の労働力不足を解決しようとするのではなく、「積極財政」によって日本人の賃金が上げられる環境づくり、徹底的な設備投資、機械化を促す政策的サポートが急務です。取り組んでまいります。
(参政党参議院議員 塩入清香氏・9月2日付「X」へのポストより引用)
--------------------------------------------------
この一文がおかしなことについては、少し注意しながら読んでいればすぐにわかる。
- 「行方不明(失踪)となった技能実習生の数は前年の約3倍」
- 「技能実習生全体に対する失踪率は、近年では年間およそ1.7~1.9%の範囲で推移」
すなわち、前者であれば、失踪者は前年の約200%増となっている。爆増だ。
ところが、後者では「近年の失踪率は年間およそ1.7~1.9%の範囲で推移」―――ほぼ横ばいの動きということで、話がかなり心もとない。
そのため、この発言に対しては、たちまち指摘や反論が寄せられたが、議員本人が直後に説明したところによれば、数字の出どころは約1年前の新聞紙上(あるいはサイト上)に載せられた記事だったという。
その一部、冒頭部分を抜粋する。
--------------------------------------------------
(朝日新聞 2024年9月28日付記事)「実習生失踪、最多9,753人 ミャンマー急増、資格変更相次ぐ」
昨年1年間に失踪した外国人技能実習生が9,753人にのぼり、過去最多だったことがわかった。ミャンマー人の失踪者数が前年の3倍近くに増加。転籍が認められない実習先からいなくなり、就労先に制限のない在留資格に変更するケースが相次いでいるといい、出入国在留管理庁は運用を厳格化する。(以下略)
--------------------------------------------------
このとおり、23年に失踪した外国人技能実習生の数は、たしかに過去最多であったと報道されている。しかしながら、前年の約3倍に及んだわけではない。
なお、この記事の元となる出入国在留管理庁の資料によれば、前年(22年)の数は9,006人となっている。よって、正しくは約1.08倍となる。1割増にも届かず、「3倍」とはまるでかけはなれた数字といっていい。
そのため、議員は、追ってこのように陳謝している。
「(前略)ミャンマー出身者が前年の3倍に増加、の一文を抜かしておりました。申し訳ございません。」
以下、詳しい数字を掲げておこう。
(出入国在留管理庁 外国人技能実習制度における行政処分等に関する公表情報のうち国籍別の失踪者数・25年11月5日現在の速報値より)
| 年 | 人数 | 内、3月以内に所在確認ができた者を除いた数 |
| 2020年 | 5,885人 | 5,117人 |
| 2021年 | 7,167人 | 5,445人 |
| 2022年 | 9,006人 | 7,740人 |
| 2023年 | 9,753人 | 7,093人 |
| 2024年 | 6,510人 | 4,517人 |
なお、細かいところをつつけば、上記議員は「2023年(令和5年)に日本で行方不明(失踪)となった技能実習生数は過去最多―――」と、最初のポストに記していた。
そのうえで「行方不明」という事象に該当しそうな上記の数字といえば、「3月以内に所在確認ができた者を除いた数」が、おそらくそれとなる。
すると、見てのとおり、23年においては7,093人と記されている。前年の7,740人より647人少ない。つまり、過去最多ではない。
よって、議員の発信内容は、この部分にあてはめてもやはり破綻を来たしている。
(なお、こうした「行方不明」が毎年数千人単位で生じている事実については、もちろんよいことではない)
ちなみに、急に名前が出てきたミャンマー人だ。いま述べたとおり、23年の失踪者「3倍」は、外国人技能実習生全体にかかる数字ではない。数ある国々の人のうち、ミャンマー人のみに関わる数字となっている。抜き出してみよう。
| 年 | 人数 | 内、3月以内に所在確認ができた者を除いた数 |
| 2020年 | 250人 | 149人 |
| 2021年 | 447人 | 108人 |
| 2022年 | 607人 | 35人 |
| 2023年 | 1,765人 | 5人 |
| 2024年 | 1,263人 | 56人 |
このとおり、朝日新聞の記述は正しい。23年の総数はたしかに前年の3倍近くに及んでいる(607人 → 1,765人)。
そのうえで、「3月以内に所在確認ができた者を除いた数」―――行方不明相当は5人だ。こちらは前年の1/7に減っている。
この期に及んでさえも?
以上のとおり、SNS上で少なくない数の人々から指摘を受けた議員の発信だが、これをわれわれがいい気になって揶揄するのはよくない。
なぜなら、筆者含め、われわれ人間の多くは、当該議員と似たような過ちを犯しやすい、脆弱で頼りないアタマを持ちつつ生まれて来てしまっているからだ。
以下、3つの文章を読んでみてほしい。あなたの頭脳はいまどれに強く反応するだろう?
- 外国人技能実習生のうち、2023年の失踪者は9,753人に及んでいる
- 外国人技能実習生のうち、2023年の失踪者は9,753人に及んでおり、これは過去最多の数だ
- 外国人技能実習生のうち、2023年の失踪者は9,753人に及んでおり、これは過去最多の数で、しかも前年の約3倍に増えている
なお、すでに述べたとおり、1と2は事実だ(国の公式発表の上で)。
しかし、3はウソだ。途中までは本当だが、話の最後に間違いが含まれている。
ところが、だ。
何とも不思議なことに、あなたの脳はこの期に及んでさえ、3の文章に「ピクリ」と反応してはいまいか。あるいは、3を読みながら「ムズムズ」していたりはしまいか。
なおかつ、その不可解な反応にあっては、次に以下の文章を読んだとき、重大なミスを呼ぶ引き金になりかねないものに感じられたりはしないだろうか。
(再掲・朝日新聞)
「昨年1年間に失踪した外国人技能実習生が9,753人にのぼり、過去最多だったことがわかった。ミャンマー人の失踪者数が前年の3倍近くに増加。転籍が認められない実習先からいなくなり、就労先に制限のない在留資格に変更するケースが相次いでいるといい、出入国在留管理庁は運用を厳格化する。」
いかがだろう?
ちなみに、今回発信した議員は、文面の主旨からも判るとおり、わが国における外国人労働者の増加に対し、強い懸念を示す立場に立っている。
そのうえで、当該議員にとって、外国人技能実習生における失踪者が過去最多であった旨を報ずる上記記事は、自らの意見を補強するのに都合のよい、いわば「もってこい」の内容を備えたものだったように思われる。
だが、そんな浮き立つ状況でこそ、悪魔はそっと忍び寄って来るものだ。
善良かつ政治活動に熱心な当該議員は、
「失踪者過去最多」「前年の3倍近く」
これら2つの刺激的かつ好都合な文字の間にそっと置かれた「ミャンマー人」という大事な前提をここで手痛く見逃してしまった。
合接の誤謬(あるいは連言錯誤)の罠
ある環境下において、われわれ人間は、発生する確率がおよそ低い事象であっても、これを誤って、発生確率の高い別の事象を超えて過大に見積もってしまうことがある。
以下、ご存じの方も多いだろう。行動経済学の分野においては非常に有名な「リンダ問題」となる。Wikipediaから引用、一部を補足する。
--------------------------------------------------
リンダは31才、独身。率直な性格で、とても聡明な女性である。大学では哲学を専攻した。学生時代には差別や社会正義といった問題に深く関心を持ち、反核デモにも参加した。(リンダの現在について)どちらの可能性がより高いだろうか?
1.リンダは銀行窓口係である。
2.リンダは銀行窓口係で、フェミニスト運動に参加している。
--------------------------------------------------
この問いかけに対しては、多くの人が「2」と答えることが知られている。
だが、それは間違いだ。2の可能性の方が高いわけなどない。
なぜなら、リンダが銀行窓口係であり、かつフェミニスト運動への参加者である可能性は、彼女が銀行窓口係である「まで」の可能性よりは、必ず、低いか同等のものになる。限定された条件の中に、さらに限定された条件が重なっているためだ。
よって、これは、ひとりの人物をこの場に連れて来るとして、この人物が、
- 「男性である可能性」
- 「男性であり、かつプロボクシングの世界チャンピオンでもある可能性」
両方を比べるのと同じことになる。
後者は、決して前者を超えられない。また、後者が現実として途方もなくありえないことは、誰もが悩むことなく、あたりまえに理解できるはずだ。
つまり、何かを括る条件は、それが連言されるほど(重なっていくほど)それら全部に該当する確率は下がっていく。
よって、繰り返すが、リンダが銀行窓口係であり、しかもフェミニスト運動の参加者でもある可能性は、彼女が銀行窓口係であるという広範な可能性を超えられない。絶対に超えることができないわけだ。
ところが、ここで時折奇妙なことが起こる。
あるケースにおいては、われわれは不思議なミスを犯してしまうのだ。
それは、何かを括る条件とは別の余計な(?)情報に、われわれが接してしまう場合だ。上記リンダ問題においては、リンダの過去こそがそれにほかならない。
「哲学を専攻。差別や社会正義といった問題に深い関心。反核デモにも参加」
と、記された彼女の来歴だ。
こうしたいかにも“香ばしい”情報を得ることで、われわれの頭脳は簡単に舵を失ってしまう。
「そういう過去をもつリンダならば、現在はおそらく銀行窓口係でありつつ、フェミニスト運動にも燃えているにちがいない。単なる銀行員であるよりも、その可能性はきっと高いはずだ」
まるでアホのごとく、そう判断してしまうことになるわけだ。
なおかつ、そうした傾向は、たとえばリンダ問題の場合、反対の立場に立つにせよ、賛同するにせよ、自らがフェミニスト運動への関心を持つほどに、強まっていくことが想像されるものとなる。
これを「合接の誤謬」あるいは「連言錯誤」とよぶ。
そのうえで、われわれは、こうした頭脳の難船状態を誰もが日常のものとして経験しているはずだ。それは、たとえばTVのワイドショー番組を観ている時、ネットニュースの文字列を眺めている時、そうした瞬間、瞬間―――。
さらには、これら誤謬や錯誤が、軽微な判断ミスをよぶにとどまらず、生活上、あるいは仕事上の大事な場面で発生することもあるので注意が必要だ。
誤報や冤罪を生んだり、重大な人権侵害、人的被害にそれが繋がったりすることもあるわけだ。
いま一度、振り返ろう。
「外国人技能実習生の失踪が9,753人」
↓
「上記は過去最多」
↓
「かつ、前年の3倍近くに増加」(誤認)
↓
「以上を受け、出入国在留管理庁は制度の運用を厳格化」
見てのとおり、これらの事象は、誤認も含めていわば入れ子の構造になっている。前提に前提が重なっていくため、あとになればなるほど、それが生じる確率はもともと低かったはずのものになる。
しかしながら、これを受け取る側の心理にある種のバイアスがかかっていると、そのことが認識されにくくなる。
次第に狭く、危うくなっていく目の前の山道が、逆に広く快適になっていくように見えたりもするわけだ。
すると、脳が油断する。
誤読や読み飛ばしという悪魔が知らぬうちに潜んでいても、われわれはなかなかそれに気付けない。
議員は次も出馬するのか?
繰り返すが、この記事は件の議員を揶揄するために書いたものではない。
読者に伝えたいことは、われわれ人間の判断や行動は、ともすれば事実や現実をさしおいて、印象によって動かされやすいということだ。
そのうえで、合接の誤謬は、典型的なその原因のひとつといってよい。
今回の議員の失敗は、その外形と輪郭をなぞる限り、一定のバイアスに合接の誤謬が絡んだ結果生じたと思われる事例においてのよい一例となるだろう。
なおかつ、こうしたものが、インターネット・SNS上にはつねに無数に存在する。
また、その発信者に自らがなる可能性もつねにある。
これらを忘れないことは、デジタル空間の荒海を無事に毎日渡りきるため、重要な指針のひとつとなるはずだ。
さて、最後に出題となる。
今回の議員は、いわゆる保守派であり、保守派政党に属していて、ほかにもわが国の核武装に関わる端的な発言で議論を呼ぶなど、話題となるエピソードが多い人だ。
将来、どちらの可能性がより高いだろうか?
- 当該議員は、次の選挙にも出馬する
- 当該議員は、次の選挙にも出馬する。ただし、問題となる発言を今任期中さらに重ねていたため、党内にも味方は少なく、選挙戦は厳しいものとなる。
2にならないよう、陰ながら見守りたい。
(文/朝倉継道)
【関連記事】
SNSが肥大化させる心の闇
「人口100人でみた日本」で10年前と現在を比べる
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。























