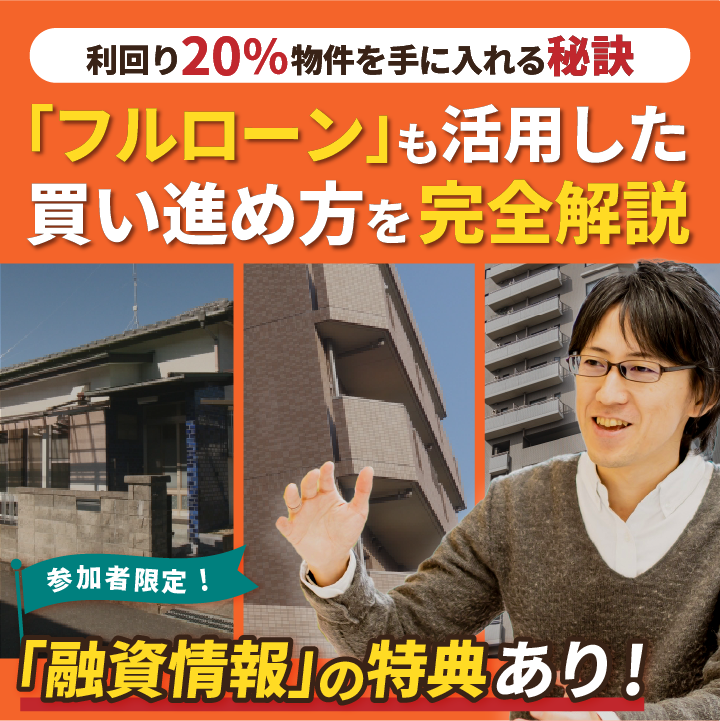人口減少が嫌ならば外国人に来てもらうしかない? 日本人マイナス91万人vs外国人プラス35万人
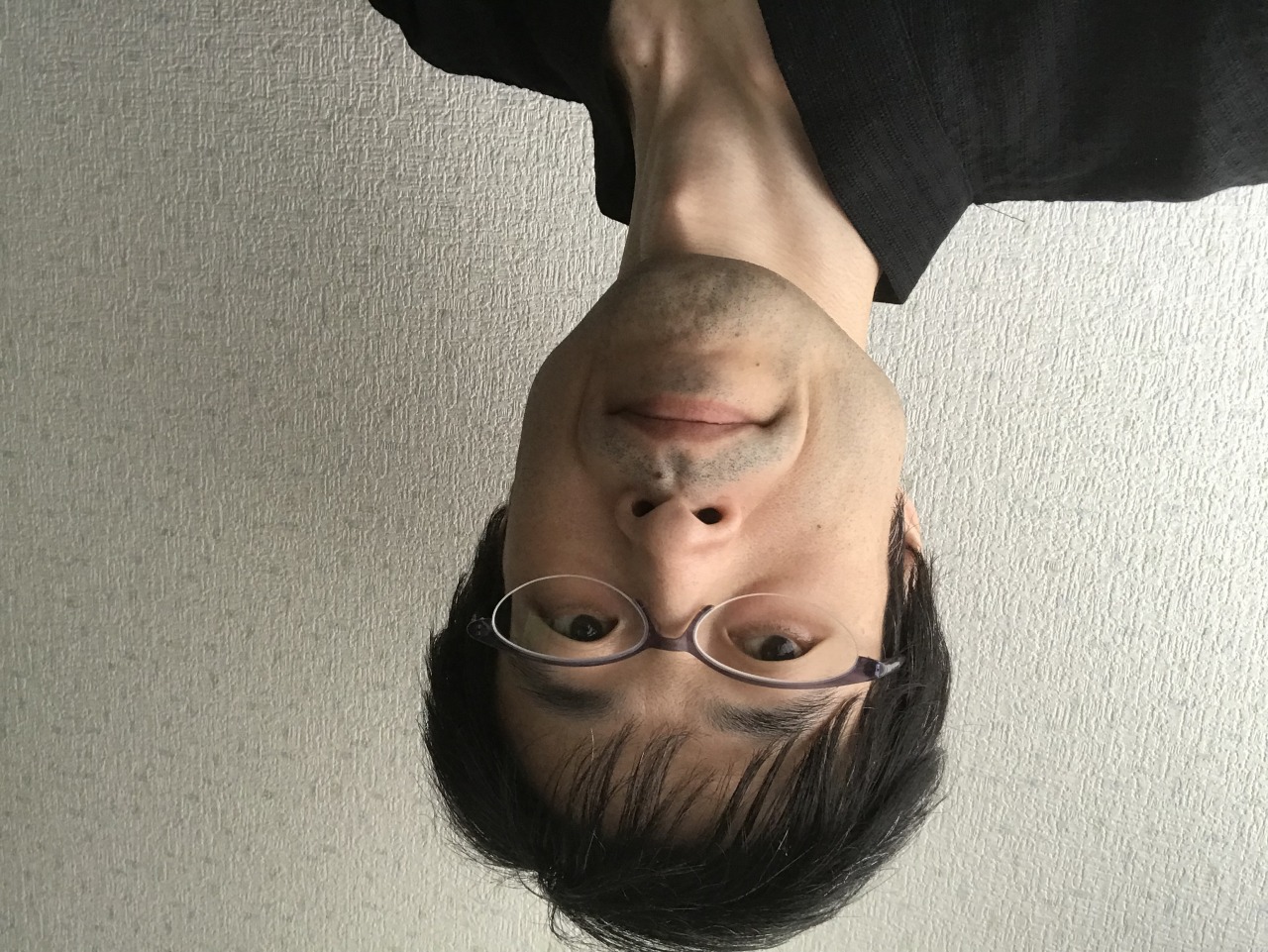
2025/08/18

日本人の減少は政令指定都市1個並み―――約91万人
この8月6日、総務省から「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」の令和7年(2025)1月1日現在分が公表されている。
- 「日本の総人口は1億2433万690人」
- 「前年比はマイナス55万4485人だが、日本人のみであればマイナス幅はさらに広がり90万8574人。対して、外国人はプラス35万4089人」
- 「外国人の増加が日本人の減少を補い、日本の総人口の急速な減少を和らげている」
ヘッドラインを記せばそんなところだが、この記事では、このうち「外国人」について、もう少し深く掘り下げていきたい。
なお、上記資料においては「日本人住民」「外国人住民」と、それぞれ表記されているが、当記事ではこれらを「日本人」「外国人」としておく。
外国人人口は、日本最大の市に迫る約368万人
上記のとおり、約35万人が増加した外国人人口にあっては、総計が367万7463人となっている。日本最大の市である横浜市に迫る数字だ。
総人口(1億2433万690人)に占める割合は2.96%となる。ざっと34人に1人程度が外国人の計算となる。この調査開始以来最多であり、かつ、今回増加分の数も過去最大だ。
都道府県別では、東京都において外国人は最も多く、72万1223人となっている。都全体の人口(1400万2534人)に占める割合は5.15%で、こちらも都道府県別で最高の数字だ。ざっと、都民20人に1人が外国人との計算になる。
そのため、東京都にあっては、今後さらに外国人の割合が増す場合、「都民ファースト」と、近ごろ話題の「日本人ファースト」は、やや矛盾するスローガンとなる可能性がある。もっとも、「外国人は日本人ではない。よって都民には数えない」と、規定する場合、その限りではなくなる。
以下、ここ10年の外国人人口の増加の具合を見てみよう。(日本全体)
| 年 | 住民基本台帳人口 | 対前年増減率 |
| 2016年 | 2,174,469人 | 5.41% |
| 2017年 | 2,323,428人 | 6.85% |
| 2018年 | 2,497,656人 | 7.50% |
| 2019年 | 2,667,199人 | 6.79% |
| 2020年 | 2,866,715人 | 7.48% |
| 2021年 | 2,811,543人 | △1.92%(コロナ禍の影響によるマイナス) |
| 2022年 | 2,704,341人 | △3.81%(コロナ禍の影響によるマイナス) |
| 2023年 | 2,993,839人 | 10.70% |
| 2024年 | 3,323,374人 | 11.01%(増加率過去最大) |
| 2025年 | 3,677,463人 | 10.65%(増加数過去最大 354,089人) |
このとおり、コロナ禍が過ぎて以降、増加率は一段と高まっている。
そのうえで、今後、毎年10%の増加がしばらく続くとしよう。26年には外国人人口は400万人を超え、29年には500万人を超えることになる。2030年には600万人に迫る。
| 年 | 住民基本台帳人口 | 対前年増加率(仮定) |
| 2026年 | 4,045,209人 | 10% |
| 2027年 | 4,449,730人 | 10% |
| 2028年 | 4,894,703人 | 10% |
| 2029年 | 5,384,173人 | 10% |
| 2030年 | 5,922,590人 | 10% |
すると、東京都では、その頃外国人の数は120万人前後に及んでいる可能性がある。(上記592万2590人に対し、現在の東京都の外国人人口における全国比―――19.61%をあてはめた上で類推)
「10人に1人が外国人」の風景も間近となって来るわけだ。
外国人街が都内あちらこちらに広がる中、東京では選挙がある毎に外国人にかかわっての世論の対立が激化していく可能性も少なくない。
20~30代にボリュームが集中している外国人人口
日本人人口に比べての外国人人口の特徴は、年齢階級別の数字によく表れている。
先ほど、日本の総人口に占める外国人の割合は2.96%と記したが、年少人口および生産年齢人口においては以下のとおりとなる。
| 年齢 | 総人口 | 外国人 | 総人口に対する割合 |
| 0~4歳 | 3,925,286人 | 106,658人 | 2.72% |
| 5~9歳 | 4,809,272 人 | 100,095人 | 2.08% |
| 10~14歳 | 5,290,412人 | 92,861人 | 1.76% |
| 年齢 | 総人口 | 外国人 | 総人口に対する割合 |
| 15~19歳 | 5,556,552人 | 139,661人 | 2.51% |
| 20~24歳 | 6,328,583人 | 592,891人 | 9.37% ――数、割合共に2番目 |
| 25~29歳 | 6,542,213人 | 630,045人 | 9.63% ――数、割合共に最大 |
| 30~34歳 | 6,484,433人 | 483,625人 | 7.46% ――数、割合共に3番目 |
| 35~39歳 | 6,946,520人 | 351,310人 | 5.06% ――数、割合共に4番目 |
| 40~44歳 | 7,716,225人 | 274,091人 | 3.55% |
| 45~49歳 | 8,764,380人 | 213,713人 | 2.44% |
| 50~54歳 | 9,881,665人 | 188,273人 | 1.91% |
| 55~59歳 | 8,552,509人 | 159,639人 | 1.87% |
| 60~64歳 | 7,616,180人 | 120,843人 | 1.59% |
このとおり、20代~30代でのボリュームの集中がはっきりと見られる。
そのうえで、こうしたうち、どれだけが将来自らの国へ帰る人か、そうでないかで、わが国の風景はかなり違っていくはずだ。
すなわち、定住、永住、さらには帰化する人の割合が、婚姻も絡めつつ増えるほどに、いまは数も割合も少ない外国人の子ども、あるいは日本国籍をもつ外国系の子ども―――日本国民が増えていくことになる。
日本人という概念自体が多様化、あるいは複雑化する社会が、やがて訪れることにもなるだろう。
人口減少シナリオへ与えるインパクト
今回の総務省の発表による、外国人人口増加数・過去最大の35万4089人という数字は、あるインパクトを国の別の資料にも与えるかたちとなっている。
国立社会保障・人口問題研究所による「日本の将来推計人口(令和5年推計)」だ。
これによると、今後の日本の総人口は「出生中位・死亡中位」という、中庸かつ穏当な条件のもとで、以下のような推移をたどる。
| 年 | 総人口 |
| 2040年 | 1億1283万7千人 |
| 2050年 | 1億468万6千人 |
| 2060年 | 9614万8千人 |
| 2070年 | 8699万6千人 |
しかしながら、これは2040年の外国人入国超過数が163,791人になるとの仮定を基礎にしての推計だ。なお、この数字は、16年から19年までにおいての実績からなる平均値となっている。
つまり、これが変わると予測も当然変わることになる。
そこで、同推計に掲げられている「条件付推計結果」を見てみよう。以下は、40年における外国人入国超過数を先ほどの数字から大幅に増やし、25万人と仮定して導かれたものとなる。
| 年 | 総人口 | 前記の数字にプラス |
| 2040年 | 1億1515万人 | 231.3万人 |
| 2050年 | 1億817万人 | 348.4万人 |
| 2060年 | 1億82万1千人 | 467.3万人 |
| 2070年 | 9286万9千人 | 587.3万人 |
このとおり、外国人人口の増加にあっては、日本の全人口に対するその「効果」が著しい。今から35年を経ても、わが国の人口は1億人を維持できる予測となっている。
しかも、ここでベースとなっている25万人というのは、いうまでもないが、現下における実際のデータ―――総務省公表による外国人人口増加数35万余を大きく下回る控えめな数字となる。
そこで、仮定をもっと大胆に「40年の外国人入国超過数50万人」としてみよう(ありうる数字だ)。すると、2060年の人口は1億1389万8千人。
さらに大胆に「75万人」とすれば、1億2748万2千人。なんと、今よりも増えてしまう。
よって、日本の人口減少を日頃から憂い、悩んでいる向きにあっては、外国人増加のニュースは、形式的にはそれを癒す特効薬といえそうだ。
だが、実際はそうもいかないだろう。
上記のうち、少なくない数の人が、「外国人や、外国系の日本国民ばかりが増えても困る。血統としての純然たる日本人―――大和民族がこの国から減るのは耐えがたい」とも思っているのではないか。
よって、それに対しては、以上の話はむしろ恐怖を及ぼすものとなりそうだ。
紹介した総務省および国立社会保障・人口問題研究所の各資料は、下記にてご確認いただける。
「総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数 令和7年(2025)1月1日現在」
「国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口 令和5年(2023)推計)」
(文/朝倉継道)
【関連記事】
「税リーグ」と不思議な町おこし
地価LOOKレポート2025年第1四半期 「コト消費」するために街へ行く?
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。