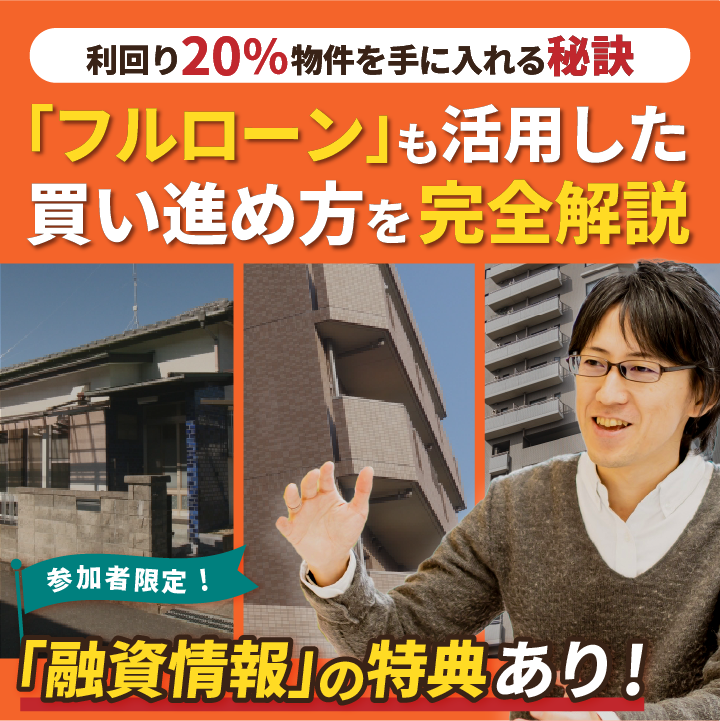男女共同参画白書が公表。ふるさとは遠きにありて思ふもの?
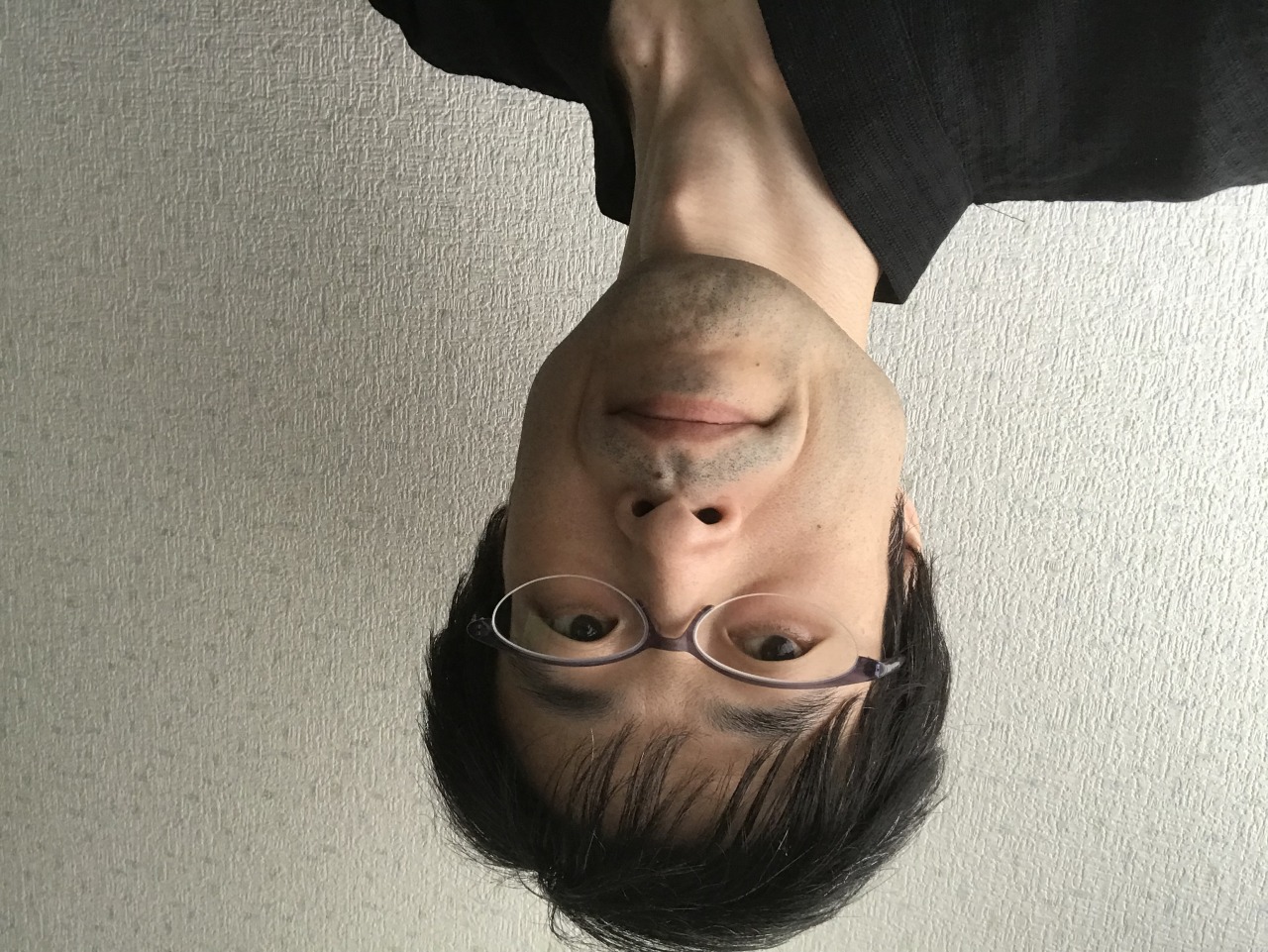
2025/07/09

「男女共同参画白書」令和7年版が公表
6月13日、内閣府男女共同参画局より「男女共同参画白書」の令和7年版が公表されている。
この中で、「男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくり」と、題した特集がまとめられている。
「近年は、若い女性が地方から都市へ転出する傾向が強くなっている。女性や若者の都市への転出によって、地方の活力が低下すると同時に、地域によって男女別人口の不均衡が発生することから、未婚化や少子化の要因の一つともなり、将来的には、都市を含む日本全体の活力の低下につながることも懸念されている」―――とのこと。
当該特集部分より、いくつか目をひく内容をこの記事ではピックアップして紹介したい。
故郷を離れる理由
まずは、こんなアンケート結果からだ。
「東京圏以外の出身で、現在は東京圏に住んでいる男女」のうち、「自分の都合で出身地域を離れた人」に、その理由を尋ねた答えとなる。
なお、質問内容をひらたく記すと―――
「あなたが、自分の都合で、中学校卒業時点に住んでいた地域から転居した(離れた)理由を教えてください。(いくつでも)」
ちなみに、ここでの東京圏とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県のこと。(本記事において以下同じ)
回答しているのは、18~39歳の女性299人、同じく男性293人となる。
そのうえで、女性が答えた「転居の理由」として、パーセンテージが高く(10%以上)、なおかつ、男性との差が大きなもの(5ポイント以上の開きがある)を挙げると、以下の3つとなる。
| 回答 | 女性 | 男性 | 女性/男性 |
| 希望する進学先が少なかったから | 42.1% | 29.7% | 1.42倍 |
| 地元から離れたかったから | 26.8% | 15.0% | 1.79倍 |
| 親や周囲の人の干渉から逃れたかったから | 10.7% | 3.8% | 2.82倍 |
このとおり、「親や周囲の人の干渉―――」における男女差が特に目立つ。
さらに、興味深いことには、男性の場合、以上と同様の条件(パーセンテージ10%以上、かつ女性よりその数字が多い)に該当するものが、通常の選択肢の中には見当たらない。下記が唯一の例となっている。
| 回答 | 女性 | 男性 |
| この中に当てはまる理由はない | 13.4% | 20.5% |
すなわち、「希望する進学先が少なかったから」「地元から離れたかったから」「親や周囲の人の干渉から逃れたかったから」―――これら3つは、地方の女性が故郷を離れ、東京・首都圏に移り住むにおいて、男性に比べ顕著に生じやすい理由であるとはいえそうだ。
加えて、女性においては、「親や周囲の人の干渉」を受けやすいか、あるいはそれをふるさとのコミュニティにおけるストレスと感じるケースが多いことが、以上からは読み取れる。
「女性はこうあるべき」の空気から逃れて都会へ?
以上に挙げた「地方の女性が故郷を離れて東京・首都圏に移り住むにおいて、男性に比べて顕著に生じやすい可能性がある」理由3つのうち、
「地元から離れたかったから」「親や周囲の人の干渉から逃れたかったから」―――これら2つに関連が深そうな下記の質問となる。
「中学校卒業時点であなたが住んでいた地域で、下記のようなことはありましたか?」
下記のようなこと―――例は9つだ。
- 「家事・育児・介護は女性の仕事」
- 「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」
- 「職場でのお茶出しや事務などのサポート業務は女性の仕事」
- 「個人の価値観よりも世間体が大事」
- 「自治会などの重要な役職は男性の仕事」
- 「家を継ぐのは男性がよい」
- 「子供が生まれたら、女性は仕事を控えめにした方がよい」
- 「男性が前に立って、女性は後ろで支えるべき」
- 「正社員は男性、女性は非正規社員」
こうした、性別による「固定的な役割分担意識」が、出身地域に存在したかどうかについて、
「東京圏以外出身で、東京圏に住んでいる女性(18~39歳)」
= 現・東京圏在住女性(391名)
「東京圏以外出身で、東京圏以外に住んでいる女性(同上)」
= 現・東京圏以外に在住の女性(3,367名)
それぞれに尋ねた結果、そうしたものが「あった」(「よくあった」または「時々あった」)と答えた割合が、以下のとおりとなる。
| 性別による固定的な役割分担意識の例 | 現・東京圏在住女性 | 現・東京圏以外に在住の女性 | 両者のポイント差 |
| 家事・育児・介護は女性の仕事 | 42.5% | 30.3% | 12.2ポイント差 |
| 地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事 | 42.2% | 30.7% | 11.5ポイント差 |
| 職場でのお茶出しや事務などのサポート業務は女性の仕事 | 34.5% | 27.1% | 7.4ポイント差 |
| 個人の価値観よりも世間体が大事 | 36.3% | 25.9% | 10.4ポイント差 |
| 自治会などの重要な役職は男性の仕事 | 34.0% | 26.4% | 7.6ポイント差 |
| 家を継ぐのは男性がよい | 38.6% | 27.0% | 11.6ポイント差 |
| 子供が生まれたら、女性は仕事を控えめにした方がよい | 31.5% | 23.0% | 8.5ポイント差 |
| 男性が前に立って、女性は後ろで支えるべき | 29.7% | 21.2% | 8.5ポイント差 |
| 正社員は男性、女性は非正規社員 | 22.0% | 17.5% | 4.5ポイント差 |
このとおり、全ての項目で「現・東京圏在住女性」の数字が「現・東京圏以外に在住の女性」の数字を上回る結果となっている。
また、そのギャップもほとんどで大きい。上記「ポイント差」を見てのとおりだ。
よって、ここから単純にいえること。それは、地方の出身地を離れ、東京・首都圏に移り住んでいる女性にあっては、「性別による固定的な役割分担意識」が故郷に存在したことを認識している割合が明確に高いということだ。
なおかつ、多くの場合、当人はそれらに対し、大なり小なりの忌避感、拒絶感、あるいは失望感を抱いていたであろうことが推し量れる。
ふるさとは遠きにありて思ふもの
この記事で採り上げる最後の質問となる。
「あなたは、中学校卒業時点で住んでいた地域に、どれくらい愛着がありますか?『全く愛着がない』を0点、『とても愛着がある』を10点とした場合に、何点くらいになると思うか教えてください」
このような質問を「東京圏以外出身で、現在東京圏に住んでいる女性(391名)男性(408名)―――いずれも18~39歳」に投げかけた答えが、次のとおりとなる。
| 愛着がある(7~10点) | 中間(4~6点) | 愛着がない(0~3点) | |
| 東京圏以外出身で、現在東京圏に住んでいる女性 | 62.9% | 24.8% | 12.3% |
| 東京圏以外出身で、現在東京圏に住んでいる男性 | 50.0% | 28.9% | 21.1% |
見てのとおり。さきほどまでの質問・回答からわれわれの胸に浮かんだ印象が、ここで少し変わってくる。
故郷を出て東京圏に暮らす女性にあっては、平均して、男性よりもふるさとへの愛着が強い様子がある。
ある詩を引用したい。室生犀星の有名な作品の前半部分だ。
「ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの よしや うらぶれて異土の乞食(かたゐ)となるとても 帰るところにあるまじや」
ふるさとは、自分が遠い地に在ってこそ想い馳せるべきものだ。たとえ落ちぶれても、そこに帰るようなよき場所ではない―――。
男女共同参画白書の令和7年版の特集部分をざっと縦覧して、筆者の心中、真っ先に浮かんだものがこれとなる。
犀星は明治半ば生まれの人。それでも、この句については「わかりみ深い」と、感じる女性がいまどき多いのかもしれない。
男女共同参画白書は下記でご覧いただける。
(文/朝倉継道)
【関連記事】
新内閣の重要課題「地方創生」はなぜ進まないのか?
「県庁はいらない」―――村上総務相の不適切?発言を考える
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。