アパートを包み込んだ死臭 20代半ばの青年はなぜ事故物件から去らなかったか
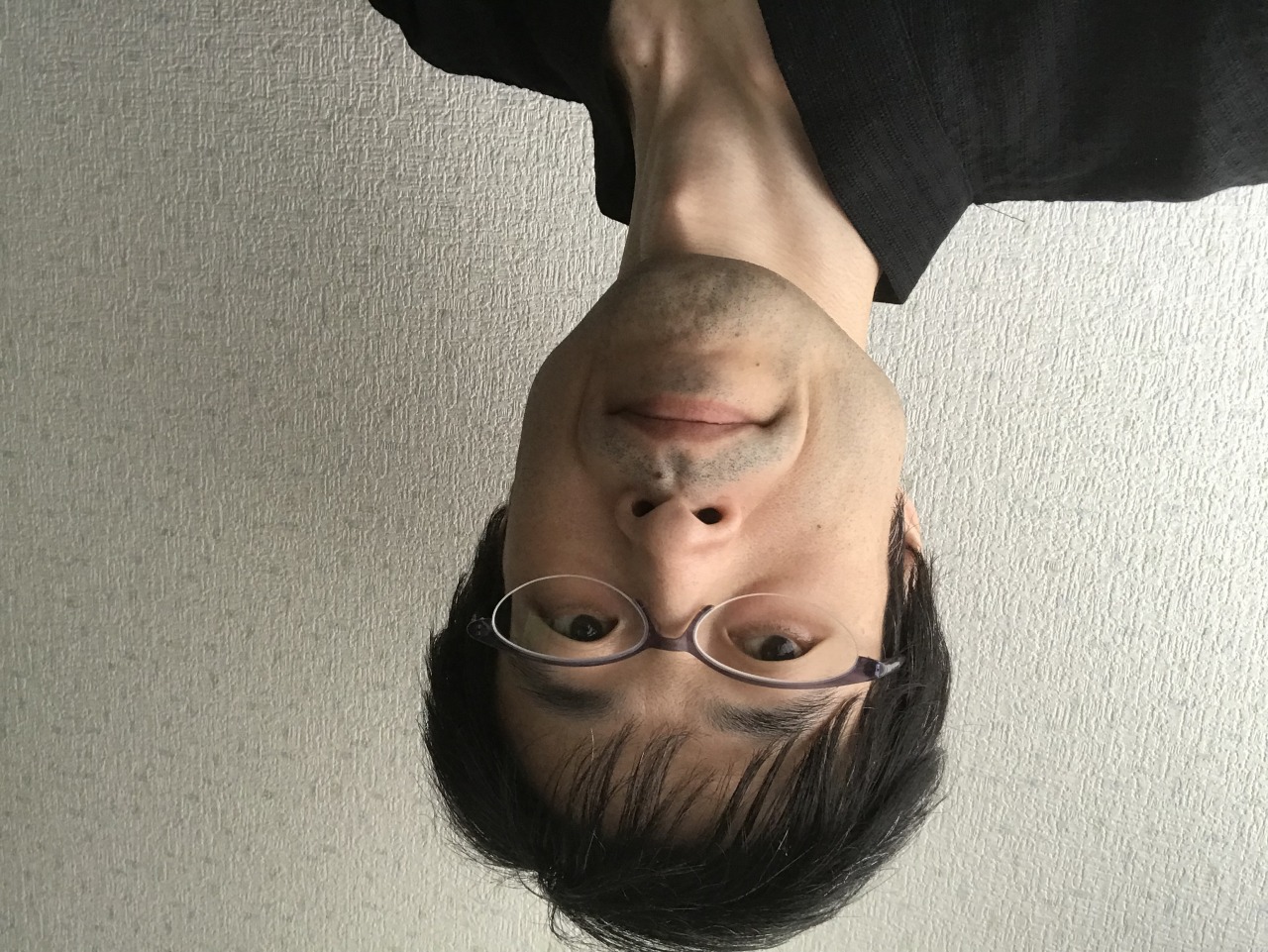
2021/06/25

イメージ/©︎nito500・123RF
進む「賃貸・人の死」への対策
今年に入り、賃貸住宅での人の「死」に関して、国土交通省が2つの有意義なアクションを進めている。
1つは「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定」だ。
「単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃借人の死亡後に契約関係および物件内の家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除および残置物の処理に関する契約条項のモデルを策定」したというものだ。
1月下旬から2月にかけ行われたパブリックコメントの募集を経て、この6月7日に、条項内容が正式に公表されている。
もうひとつは、「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)」の発表となる。こちらは、パブリックコメントの募集がつい先日終わったばかりだ(5月20日~6月18日)。
「過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関するガイドライン」と、いうことで、いわゆる事故物件の告知等に関する現場での判断の基準を国がリードしようというものだ。
今後、策定となれば、賃貸を含む不動産物件流通の円滑化に一定の効果が期待できるものとなるだろう。
筆者は事故物件体験者のひとり
ところで、いま記したとおり、不動産において人の死が発生し、その死因や前後の状況から、物件が周囲から取引などを敬遠される状態に陥っている場合を指して、これを「事故物件」という呼び方が、いま、世の中にほぼ定着している。
こうした物件で、事故の発生を間近に体験したうえで、その後もそこに長期間住み続けたことがある人の声というのは、あまり外に知れることがない。
実は、私はそのひとりだ。90年代、まだ20代半ばの頃に、そんな経験をしている。
現場は、首都圏の某所にある木造2階建てのアパートだ。当時、いわゆる若者向けとされていた、淡い色のサイディングボードが壁を囲む瀟洒な洋風の造りで、部屋はすべて1Kだった。
事故は、私の部屋からは2部屋を間に挟んでの、同じ階の3戸隣りで起きた。小さな建物なので、感覚的にはすぐ目の前だ。
亡くなったのは若い男性だった。当時の私と同じくらいの年齢だったろう。
なお、物件は現在も稼働している。そのためこれ以上の詳細は記さないが、「猛暑の時期、長期の発見遅れ」という、状況としては最悪のものだった。
すぐに半数が退去
ちなみに、この物件には管理会社が介在していた。しかし、入居者に対しては、事故後何も報告はなかった。それが当時のスタンダードであっただろう。
が、私は状況をよく知っていた。なぜなら、現場発見者の一人であり、通報者の一人でもあったからだ。
そのうえで、アパートからは、即座に半数の入居者が逃げ出した。彼らは、先般1~2週間のあいだ建物を包み込み、その後もしばらく残存していた強烈な臭気の理由を近隣の住民から知らされたらしい。
さらに、少しして、残りの入居者も相次いで物件を立ち去った。ただし、彼らの場合、いくつかの状況からみて、同じ屋根の下で起きたことを最後まで知らずにいての、通常の退去だった可能性もある。
結果、私は、事故のことを知る住人としては、ひとりだけそこに残った。
当初は気持ち悪さに怯えながらも、その後、結局5年以上そのアパートに暮らしたのには、理由が2つあった。
弱気を笑われる
ひとつは、事故物件に住むという悩みを一笑に付されたことだった。
当時、東京都内に本社を置く某会社に勤めていたが、所属していたのは若干ややこしい部署で、同僚には、年上の警察官OBが3人もいた。
そのうち、主な業務をともにしていた2人に、「これこれのことが家で起きた。引っ越ししようか悩んでいる」と、話したところ、
「人の死なんていちいち怖がっていて賃貸に暮らせるか」
と、大いに笑われたものだ。すなわち、その頃といえば、事故物件サイトもなければ、入居希望者に対して過去の事実を真面目に告知する不動産会社も、いまより格段に少なかった時代だ。
ある意味で、事故物件との出会いはロシアンルーレットのようなものといってよく、なおかつ、運悪くタマが当たったとしても、本人はまるで知らぬが仏であることも多かった。しかも、彼ら警察OB両人ともに、過去の仕事柄、人の死体に関わることには慣れ切っている。
「毎晩、事故のあった部屋の前を通って帰宅するのが怖い」と、心細げに訴えたが「死んだ人間が、肩をいからせながらお前の部屋に新聞の勧誘をしに来るのか?」――生きている人間の方が100倍怖い、と、彼らはかさねて笑い飛ばしてくれたものだ(ガラの悪い新聞の勧誘は、当時の日常風景だった)。実際、私の気持ちは、これで一気に軽くなった。
亡くなったあいつが詫びている?
もうひとつの理由は、これも不思議な巡り合わせだが、亡くなった若者との間には、実は多少の交流があった。
管理会社にカギの保管位置を教えられ、この物件を私がひとりで内見に訪れた際(当時こうしたケースがよくあった)、たまたま出くわしたのが、この若者だった。私は、彼を早速つかまえ、物件の住み心地を尋ねた。
その際、いろいろと親切に教えてくれた彼の部屋に、入居後、土産を携えて訪れた。その後も、顔を合わせるたび互いに挨拶を交わした。
ちなみに、このアパートは、私にとっては初めての一人暮らしの舞台だった。つまり、亡くなった若者は、心細いそのデビューを支えてくれた最初の友人でもあったのだ。
そのうえで、さきほどの両警察OBに、怖気づいた気持ちをあっさり笑い飛ばされたあと、若者の住んでいた部屋のドアの前にあらためて立ってみた。すると、「住み心地を悪くして申し訳ない」と、彼が何やら詫びている声が、中から聞こえるような気もしてくる。
「友達だったオレまでがここから逃げ出すと、こいつは可哀想か」
と思い、とりあえず引っ越しは当面考えずにおくことを決断したというのが、このときの顛末だ。
個人にとっての「他人の死」とは
以上の体験は、賃貸住宅オーナーや、管理・仲介会社含め、事故物件への事前・事後の対策に関わっている人、さらには、いま賃貸物件を探している人にとって、特段役に立つものではないだろう。
ただ、ひとつ思うのは、他人の死というものは、それが自らの人間関係の中において起きたものであるか否かによって、大小意味が違ってくるということだ。
その点、この事故後、当該アパートにたったひとり残った「私」という住人は、おそらくは、亡くなった若者にとっても、同じ屋根の下に暮らす生前唯一の知り合いだったことだろう。
彼のことを知らぬ隣人は皆その場を去ったが、彼を多少なりとも知る者だけがそこに残ったという事実は、いま、自分ごとながら振り返ってみて興味深い。
他人であり、隣人である者の死に際しての、個人個人が受け取る意味において、このことは、わずかながらなんらかの示唆をもたらす材料であるといってよいのかもしれない。
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。























