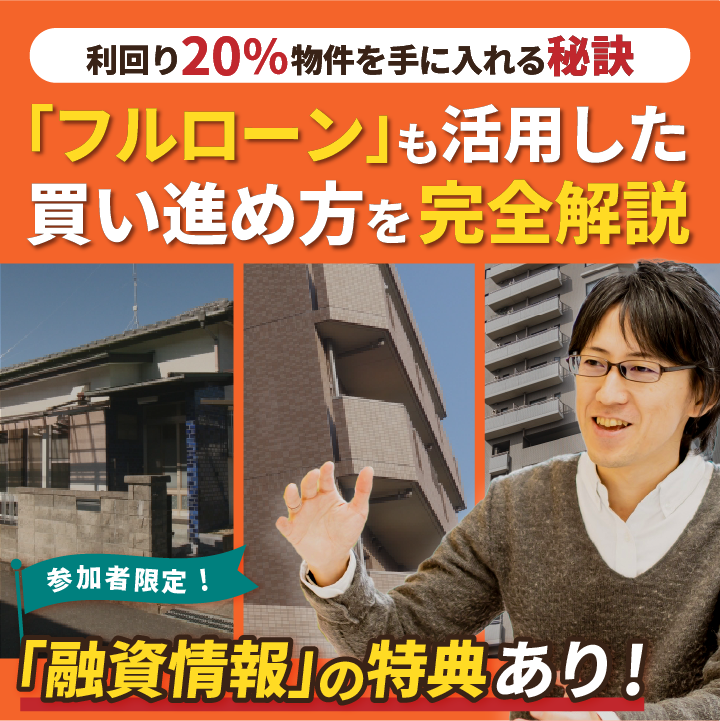新内閣の重要課題「地方創生」はなぜ進まないのか?
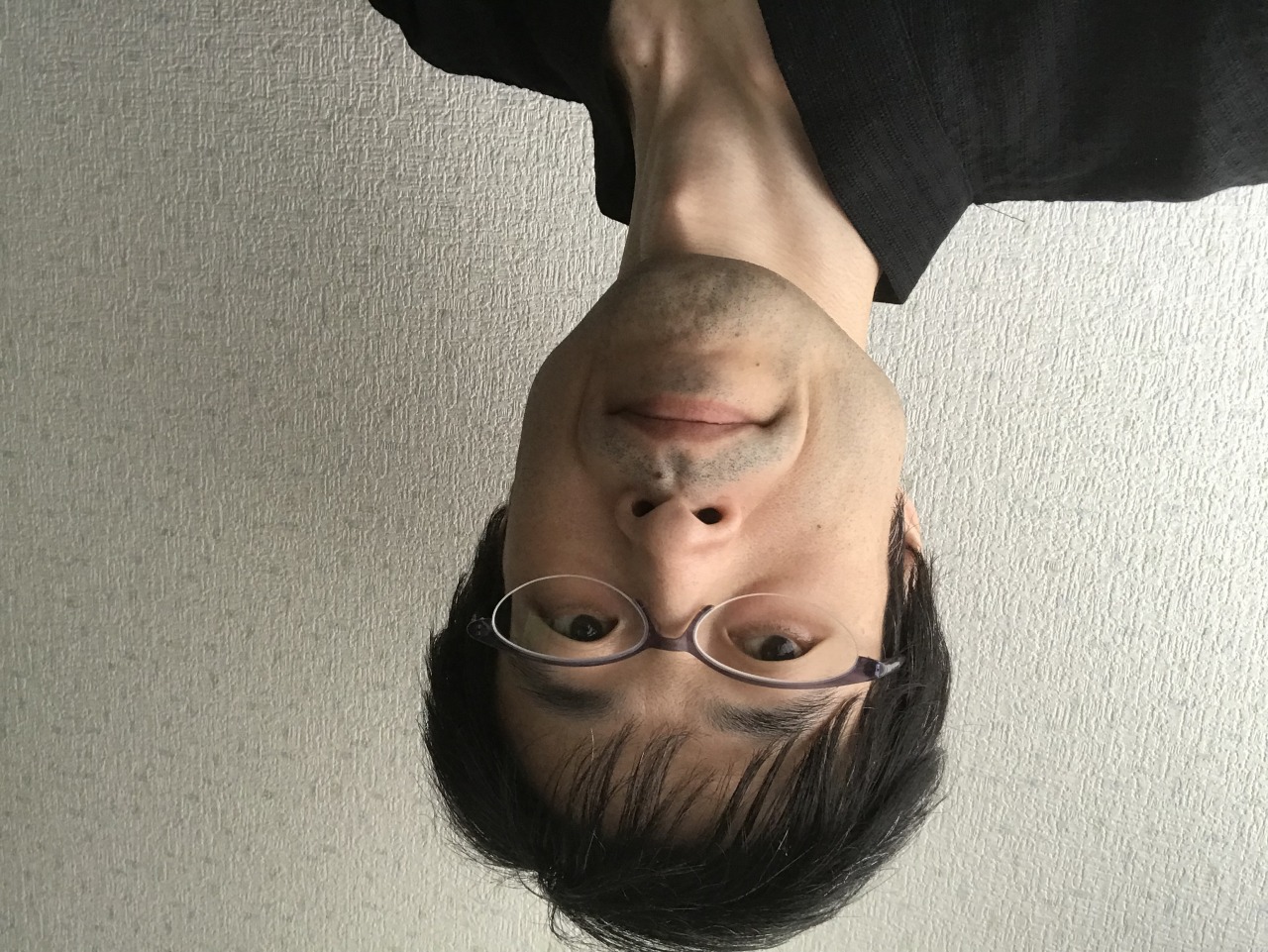
2025/04/07

石破新総理がライフワークとして掲げる「地方創生」。だが、担当大臣が生まれて10年以上、結果は出ず、状況は進展しないままだ。理由は何か? 地方創生は今のかたち、方向性でよいのか。立ち止まって考える。
石破氏は初代地方創生担当大臣
2014年9月のことだ。第2次安倍改造内閣が発足している。その際、地方創生担当大臣と呼ばれるポストが生まれている。就任したのが石破茂氏だ。以降、2年近く同職を務めた。その石破氏だが、昨年10月には内閣総理大臣となり、石破内閣をスタートさせている。年が明けた1月6日の記者会見ではこのように述べている。───「令和の日本列島改造と位置付け、地方創生2.0を強力に推し進める」「新たに創設を目指す防災庁も含め、政府機関の地方移転、国内最適立地を強力に推進する」。
長年にわたりなかなか前に進まないこの課題に対して、官、すなわち国が率先して動くかたちで突破口を見出すとの決意だ。なお、石破氏は地方創生を自らのライフワークと位置付けているそうだ。地方創生が上手くいかなければ「日本の国が終わる」との危機感も抱いているという。
地方創生10年間の結果
述べたとおり、11年前に石破大臣から始まった地方創生への新たな取り組みだが、その後の10年間を総括したレポートが昨年6月に国から公表されている。結論はこうなっている。───「本年(24年)は、地方創生の取り組みが本格的に始まってから10年の節目となる。しかしながら、国全体で見たときに人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには至っておらず、地方が厳しい状況にあることを重く受け止める必要がある」(「地方創生10年の取組と今後の推進方向」より抜粋、要約)。
同レポートの添付資料に興味深いものがあるので挙げてみよう。東京都への道府県別の転入(人口)超過数のランキングだ。1~9位までが以下のとおりとなっている(数字は2014~23年の累計)。
東京都への道府県別の転入(人口)超過数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 73,054人 |
| 2位 | 愛知県 | 60,716人 |
| 3位 | 兵庫県 | 45,885人 |
| 4位 | 福岡県 | 38,047人 |
| 5位 | 北海道 | 35,483人 |
| 6位 | 静岡県 | 30,850人 |
| 7位 | 宮城県 | 27,959人 |
| 8位 | 新潟県 | 25,705人 |
| 9位 | 広島県 | 22,707人 |
これは、すなわちより多くの人口を東京へ送り出している“送付元”のランキングとなる。そして、お気付きだろうか。これらはすべて政令指定都市が所在する道府県だ。大阪市を筆頭として、名古屋市、福岡市、札幌市など、いわば地方の都会を抱える道や府、県となる。これを受け、レポート内ではこんな言及がされている。───「こうした都市において、東京圏への人口流出を抑制する役割(いわゆる人口のダム機能)を担うことが期待される」。
では、現状はどうか。以下は、人口を東京へ流出させずに地方に留め置くダムとしての期待値が特に高いと思われる6都市を擁する6道府県の状況だ。(同資料より)
| <人口が転入超過の3府県> |
|---|
| 大阪府(大阪市を擁する) 関西地方を中心に転入超過 全体としても転入超過だが、東京圏に対しては転出超過 |
| 愛知県(名古屋市を擁する) 中部地方を中心に転入超過 全体としても転入超過だが、東京圏に対しては転出超過 |
| 福岡県(福岡市を擁する) 中国・九州地方を中心に転入超過 全体としても転入超過だが、東京圏に対しては転出超過 |
| <人口が転出超過の3道県> |
| 北海道(札幌市を擁する) 目立つほど転入超過の地方なし 全体として転出超過 東京圏に対しても転出超過 |
| 宮城県(仙台市を擁する) 東北地方を中心に転入超過だが、全体としては転出超過 東京圏に対しても転出超過 |
| 広島県(広島市を擁する) 目立つほど転入超過の地方なし 全体として転出超過 東京圏に対しても転出超過 |
上記において東京圏とは、東京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県
このとおり、6道府県は、人口が全体で転入超過している3府県と、同じく転出超過している3道県に分けられるかたちとなる。このうち、前者(大阪府、愛知県、福岡県)はダム機能を一応果たしているといえるだろう。一方、後者(北海道、宮城県、広島県)は果たせていない。ダムの“水量”は差し引き減っている。そのうえで、転入超過の3府県も、転出超過の3道県も、結局のところすべてが東京圏に対し転出超過となっている。名だたる地方の都会でもブレーキがかけられない、まさに東京一極集中といえる姿がこれだ。
その結果は、たとえば以下の数字に端的に表れている。(住民基本台帳人口移動報告より)
| ◉東京圏の転入超過数 |
|---|
| 2014年(地方創生スタート) 約11万6千人 |
| 2024年(地方創生10年目) 約13万6千人 |
地方創生はなぜ進まないのか?
石破新総理が、これができないと「日本が終わる」とする地方創生。なぜ進展しないのか。その答えは、おそらく多くの日本人が口に出さぬまま胸に留めている。
ひとつは、この課題に対し、われわれの多くは実のところ「総論賛成・各論反対」の立場にあるということだ。たとえば「地方に人を増やし、賑わいを増やそう」と誰かが唱えれば、これに表立って反対する人はまずいない。そこに「国土の均衡ある発展」などと理屈が付けばなおさらのこととなる。
一方で、個々の現実においてはまるで話が違ってくる。子どもが「東京の大学へ行きたい」「東京の大きな会社に就職したい」と言えば、これを押し留めようとする親は極めて少数だろう。ましてや、その理由として「国土の均衡ある発展のためだ」などと親がもしも言い出したとなれば子どもは面食らう。その家や、そうした家族を取り巻く不可解な田舎からの脱出をますます望むことになるはずだ。すなわち、地方創生───そのうち特に地方の人口を増やす方向性を探る議論───は、あえて貶めるならば「絵に描いた餅」となる。公のスローガンと国民個々の行動が実際には相容れない代表的な事柄のひとつといっていい。
では、なぜ人々は地方創生をメンタルで肯定しても、現実としてはそれに沿った行動をしないのか。筆者の答えは「セキュリティ」となる。都会に出ることは、すなわち人生の安全確保につながることになるからだ。
ちなみに、この点について、多くの意見は昔から「都会には夢がある」「希望がある」等の可能性論や、「都会は楽しい」といった欲求論に傾きがちだ。それは表面上正しい。だが、本質はもっと深い場所に存在する。なぜなら、巨大な労働市場が広がる都会においては、生き方の選択肢が地方の何百倍もあふれているのだ。すなわち、都会では街の規模が大きければ大きいほど、あらゆる人的資本に対し需要が見つけ出せる。夢を目指して挫折した若者も、自身の持つ別の適性を探す機会を都会ではふんだんに手にできる。理由は単純だ。労働市場が巨大かつ多様であるからだ。
つまり、これが都会の持つ高度なセキュリティ機能となる。都会では、要は誰もが「つぶしが利く」。こうした都会の“生涯安全性”をわれわれは言語化できなくとも肌で感じているため、子どもがそこを目指すことを否定できない。地方の親たちは、子どもに「夢」ではなく、人生の「安全」という親心を託しつつ、大事な子どもたちを都会に送り出している。
東京は人類史上最大の「成功している都会」

そのうえで、東京だ。日本人が大いに誇っていいこの街のすごさは、世界中の大都市が悩まされる「集積の不利益」を抑え込むことに高いレベルで成功していることだ。
都市には、メリットとデメリットがある。一方は「集積の利益」などと呼ばれ、経済面においてその効果が顕著に表れる。また一方は「集積の不利益」あるいは「集積の不経済」などと呼ばれている。こちらは、環境や治安の悪化、渋滞、過密、混雑といった都市問題、すなわち都会の病として表面化する。ちなみに、OECD(経済協力開発機構)はこの件に関してのレポートで700万人というひとつの基準を過去に示している。人口がこのくらいの規模を超えると、その都市には集積の不利益が発生しやすくなるというものだ。
そこで、東京を見てみよう。現在、東京都の人口は700万人どころか1,400万人を超えている。周囲を併せた都市圏人口となると3,500万人を超え世界一だ。ところが、そんな巨大すぎる街が、かつての公害を乗り越え、スラムを無くし、治安も比較的良好に維持し続けている。精緻な交通網によって、都心部に絶望的な渋滞が発生することもない。
集積とは逆の都市の病であるスプロール化(都市中心部の空洞化)も起こさず、清潔さも保たれ、街としてのいわば奇跡をわれわれの目の当たりにさせている。
そのうえで、東京の残る課題といえば、日常のものとしては通勤の混雑くらいとなる。なお、非日常の懸念としては地震等、災害への備えがあるが、ともあれ、東京の安心・安全面での成績は、人類史上最大の街にしておそらくは人類史上異様なほど高い。そこに、さきほどの巨大労働市場による「生涯安全性」が加わるのだ。
独裁国家よろしく強固な移住制限をかけるなどしない限り、日本語・日本文化という同じプロトコルが通用するこの街に(これはわれわれにとって大きなチャンスだ)地方の日本人が集まるのを抑える術などあるわけがない。
人口が増えることが地方創生か?
そこで提案となる。その前に疑問だ。なぜ、地方創生は地方の人口を中心的指標に掲げてしまうのか。あるいは、なぜそのような雰囲気、流れとなってしまっているのか。
前出のレポートの冒頭近くにはこうある。───「人口減少に歯止めをかけ、東京圏への過度な一極集中を是正するための対策は、我が国全体で戦略的に挑戦すべき課題」。
こんな自己評価も見える。───「地域によっては人口増加や、13年当時の人口推計の値を上回るところもあり、この中には地方創生の取り組みの成果と言えるものが一定数あると評価できる」。
現実から目を背けたい向きにあってはこうしたお花畑で遊ぶのも仕方ないだろう。だが、それでもわが国の人口が今後急減し、激減するのは確実なのだ。
そのうえで、地方創生なるものを進めるにおいて、人口を主たる物差しに置き、それを見ながら一喜一憂していてどうするのだ。45年後には約7,800万人に減るとされる日本人人口(日本の将来推計人口・令和5年推計)と、現在とのその差について、関係者はまさかこれをすべて移民によって埋めていこうと考えているわけでもあるまい。繰り返す。日本の人口は減るのだ。これをモノサシにどれだけしたところで、地方創生は成り立たない。
よって、地方創生は、それをやるのならば人の数ではなく、その土地に暮らす人間ひとりあたりの生産性を基準に臨むべきだ。人がほぼおらず、野生動物の楽園となる地方があちらこちらにあってよいのだ。
これからの日本人はそれを寂しがるべきではない。怖がるべきでもない。そこに住むわずかな観光事業者、治安・防衛関係者、漁業者、エネルギー関連事業者等の数でその地域の総生産を割ったとき、国の平均を超えているのならばそこは豊かな地方なのだ。
自然にあふれた美しい場所であり、それこそが見事に「地方創生」された地方のひとつだ。
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。