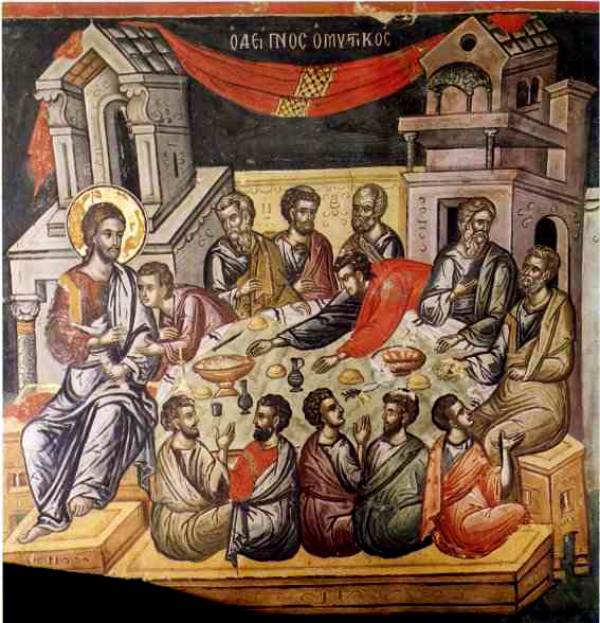「鬼」に性別の違いはあるか?――女鬼(めおに)と鬼女の役割

2020/12/15
前鬼・後鬼を従えた役行者(葛飾北斎『北斎漫画』)/Katsushika Hokusai (葛飾北斎, Japanese, †1849), Public domain, via Wikimedia Commons
【関連記事】『鬼滅の刃』から考える鬼の正体――鬼は実在するのか?
役行者に使えた夫婦の鬼
『鬼滅の刃』では、人が鬼にされてしまうが、昔から日本にはさまざま鬼にまつわる話がある。
修験道の開祖として有名な役行者(えんのぎょうじゃ)には、二人の鬼が仕えていた。前鬼(ぜんき)と後鬼(ごき)である。『役行者本記』などには、前鬼と後鬼について、こう書かれている。
役行者は三九歳のとき、現在の大阪府と奈良県の境にそびえる生駒山に登り、きびしい修行に励んでいた。と、ある日、夫婦の鬼がやって来て、役行者のまえにひざまずき、こう言った。
「私たちは天手力雄(あめのたぢからおのかみ)の子孫であります。この山に住んで、まだ人間の次元まで堕ちていませんので、神通力(超能力)をもっています。役行者さまは、悟りを開いた菩薩であり、生きとし生けるものすべてを救済してくださいます。お願いですから、どうぞ私たちを弟子にしてください。けっして背いたりいたしません。なぜなら、こういうことは、祖先の神がこうしなさいと命令したからです」
ちなみに、天手力雄は、天の岩屋戸に隠れてしまった天照大神を引っ張り出した、怪力無双の神である。
引用文を読むと、前鬼と後鬼は、自分たちはまだ人間の次元まで堕ちていないと述べているから、神と人間の中間的な存在を自認していたようだ。実態は、そんじょそこらの農民とは違うと強く主張する、誇り高き山の民といったところであろうか。
この伝承にあるとおり、この二人は夫婦で、前鬼が夫、後鬼が妻だから、後鬼は女性だったことになる。かれらを表現した絵画や彫像を見ると、なにしろ鬼なので、怖い顔をしているが、それでも両方を比べると、大概の場合、後鬼のほうがやや優しく表現されている。
たとえばヘアスタイルも、夫の前鬼は髪を逆立たせた、いわゆる怒髪が多い。しかし、妻の後鬼の髪は、ウェーブしていたり巻き毛になっていたりするが、逆立ってはいない。良くも悪くも、両眼をギョロつかせた怖い顔のおばさんといったところである。
地獄にいる女鬼の仕事
女性の鬼は、鬼の本場といっていい地獄にも、ちゃんといる。後白河法皇(1127-92)が制作させ、蓮華王院の宝蔵に納められていた「六道絵」にあたると考えられている奈良国立博物館所蔵の「紙本著色地獄草紙(原家本)」(紙本着色 縦26.5cm 横454.7cm)の「函量(かんりょう)地獄」には、三つの目をもつ老婆の鬼がすこぶるリアルに描かれている。
函量地獄とは、生前、計量を不正に行い、暴利を貪った者が堕ちる地獄である。この地獄に堕ちた罪人は、三つ目の老婆の鬼に、つねに監視されながら、熱い鉄の火の炭をほとんど永遠に計らされ続ける、と『起世経』という経典の「地獄品」に説かれている。
同じく「紙本著色地獄草紙(原家本)」の「鉄磑(てつがい)地獄」にも、女性の鬼が描かれている。「鉄磑地獄」とは、生前、他人のものを盗んで、うまく逃げおおせた者が落ちる地獄だ。罪人たちは、鉄製の臼の中に投げ込まれ、粉々に磨りつぶされている。臼の下からは、血があふれでている。こうして粉々に磨りつぶされ、血まみれになった罪人の身体が、やはり三つの目をもつ老婆の鬼に箕に入れられ、地獄を流れる河で洗われている。
面白いのは、鬼たちの表情がみな愉快そうに描かれ、いかにも楽しんで仕事をしているように見えるところだ。その理由は憶測するしかないが、ひょっとしたらこんな絵を描かせた後白河法皇の見識が影響しているのかもしれない。
後白河法皇は政治的には無能もいいところで、とりわけ人事の面では依怙贔屓の権化みたいな人物だったらしいが、芸術の領域ではたいへんな目利きだった。しかも、当時の人としては、案外、醒めた目の持ち主で、誰もが恐れおののく地獄を、超一流の絵師におもしろおかしく描かせて、悦に入っていた可能性も十分に考えられる。
男を惑わす、妙齢の美女鬼
ここまで取り上げてきた女の鬼の場合、後鬼はおばさん、地獄の三つ目の鬼は老婆として、表現されている。もちろん、もっと若い、女の鬼もいる。
地獄は大小さまざまあるが、その中に刀葉林(とうようりん)地獄という地獄がある。読んで字のごとく、葉がすべて剃刀という樹木が聳えている地獄である。
この地獄は、愛欲に溺れた男が堕ちる地獄である。愛欲に溺れるのは男女を問わないはずだが、源信の『往生要集』に説かれる刀葉林地獄は、もっぱら男専用とされている。
この地獄へ墜ちた男が、ふと見ると、樹木が聳えている。さきほど述べたように、葉がすべて剃刀という樹木である。そして、その頂きに妙齢の美女がいて、おいで、おいでをしている。愛欲に駆られた男が樹木をのぼっていくと、その身は剃刀の葉で切り裂かれてしまう。痛い思いをこらえにこらえて、ようやくいただきにのぼり詰めると、美女の姿はない。
見下ろすと、彼女は地面にいて、媚びた目つきで男を見つめながら、「抱いてちょうだい!」と叫んでいる。その姿を見、その声を聞くと、男はもうたまらなくなって、樹木を下りていくが、途中でその身はまたまた剃刀の葉で切り裂かれてしまう。ほうほうのていで下り終えると、美女はいない。見上げると、樹木の頂きにいて、おいで、おいでをしている。そこで男は上へ下へ……、これがほとんど永遠に続くのである。
彼女は妙齢の美女の姿はしていても、地獄にいて、罪人を責め苛んでいるのだから、鬼と呼ぶしかない。もっとも、地獄でなく、私たちが今いる現世でも、この刀葉林地獄の妙齢の美女鬼にそっくりの女性がいないとも限らない。
女の鬼――般若面に込められた意味
般若のお面/写真AC・kakkiko
女鬼という言葉をひっくり返すと、鬼女になる。日本語では、女鬼という表現はあまり使われず、むしろ鬼女という表現がよく使われてきた。
有名な例をあげれば、長野県戸隠の紅葉伝説、三重県鈴鹿山の鈴鹿御前伝説、栃木県安達ヶ原の黒塚伝説などである。
地獄の女鬼が生まれながらの鬼なのに対し、鬼女はもとはといえば、ふつうの人間だった女性が、前世の因縁や現世の怨念ゆえに、鬼になってしまったという話が多い。鬼女は若い女性が鬼になった場合で、年老いた女性が鬼になった場合は鬼婆というようだ。
若い女性の鬼といえば、般若面が思い浮かぶ。女性の怨念が凝りかたまって鬼となってあらわれた姿を表現する能面である。頭には二本の角がはえ、これ以上は大きくならないほど大きく見開かれた両眼はつり上がり、しかも真っ赤に血走っている。口もかっと大きく開かれ、怒声をあげているように見える。
全体として、あまりの怒りのために、引きつったような印象が強い。しかし、その反面で、どこか悲しげでもある。怒りと悲しみが、同時に表現されているともいえる。そのせいか、この面が使われる演目は、『道成寺』、『葵上』、『安達原』など、どれも女性の物狂わしい執念がテーマになっている。
『道成寺』は、恋しい男に逃げられた娘が巨大な蛇に変身し、最後には男を焼き殺してしまう物語。『葵上』は、光源氏の正妻だった葵上を、嫉妬に狂う六条御息所の生霊が取り殺してしまう物語。そして、『安達原』は、絶望と悲嘆のあまり、ついに鬼になってしまった老婆の物語である。
ここで問題になるのは、般若面の「般若」という言葉だ。般若は、古代インドの公式言語だったサンスクリット(梵語)で「智恵」を意味する「ジュニャーナ」という言葉の発音を漢字で写したもの、いわゆる音写であり、俗世間の知恵ではなく、仏の悟りに関する深い認識を指している。
つまり、般若面というのは、語源からすれば、「賢い女」の顔であり、「智恵のある女」の顔を意味しているのである。これは、とても意味深長だ。
般若面という呼称の由来は、歴史的な事実からいうと、安土桃山時代に活躍した能面師の般若坊という名前の達人が創作したので、そう呼ばれるようになったと伝えられる。したがって、般若面が最初から「賢い女」や「智恵のある女」の顔を象徴していたわけではない。
しかし、それにしても、この符合は不気味すぎる。なぜなら、西洋の鬼女に当たる魔女の由来にも、「賢い女」や「智恵のある女」説があるからだ。どうやら洋の東西を問わず、多くの人々のなかに、特に男性に、「賢い女」や「智恵のある女」はひじょうに恐ろしくて、ときとして鬼にもなるという認識があったようだ。もし、そういう認識がなかったならば、般若面がこれほど有名になることはなかったのではないか。そう思わせる何かが、この面にはある。
この記事を書いた人
宗教学者
1953年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院博士課程修了。専門は宗教学(日本・チベット密教)。特に修行における心身変容や図像表現を研究。主著に『お坊さんのための「仏教入門」』『あなたの知らない「仏教」入門』『現代日本語訳 法華経』『現代日本語訳 日蓮の立正安国論』『再興! 日本仏教』『カラーリング・マンダラ』『現代日本語訳空海の秘蔵宝鑰』(いずれも春秋社)、『密教』(講談社)、『マンダラとは何か』(NHK出版)など多数。