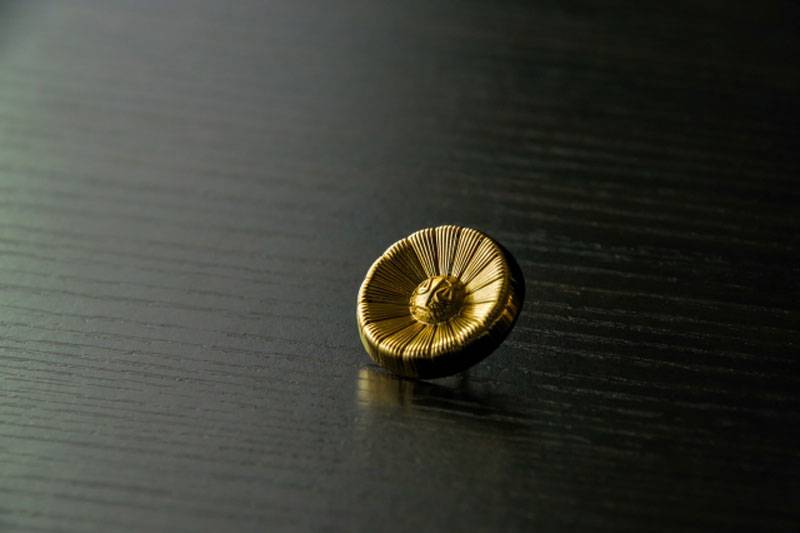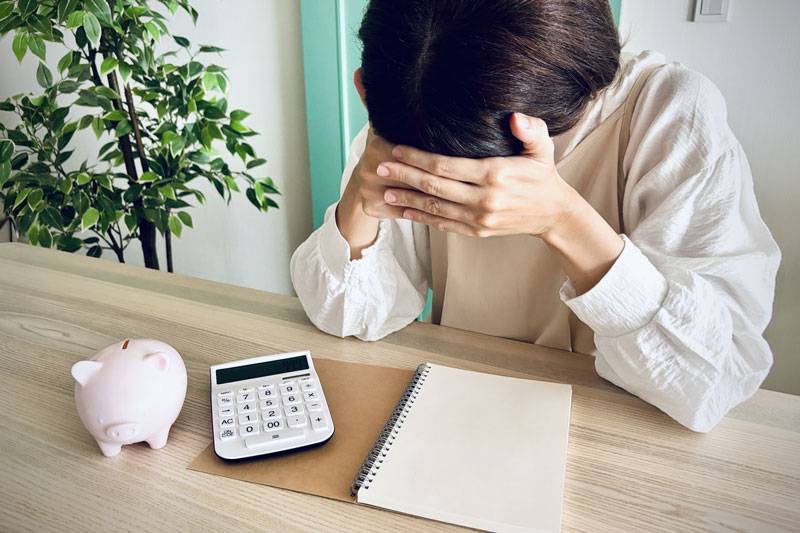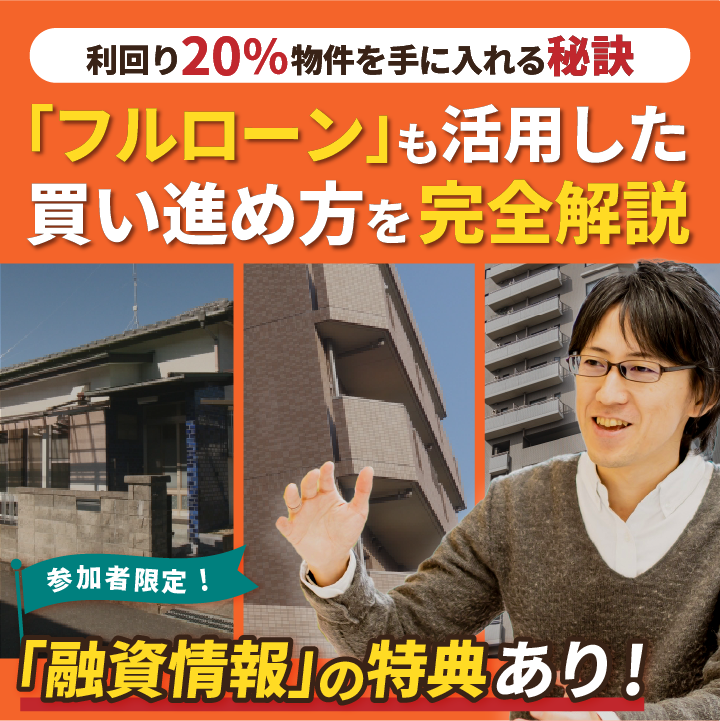それでも外国人は必要? ホームタウン騒動一旦収束のいま、外国人問題を考える
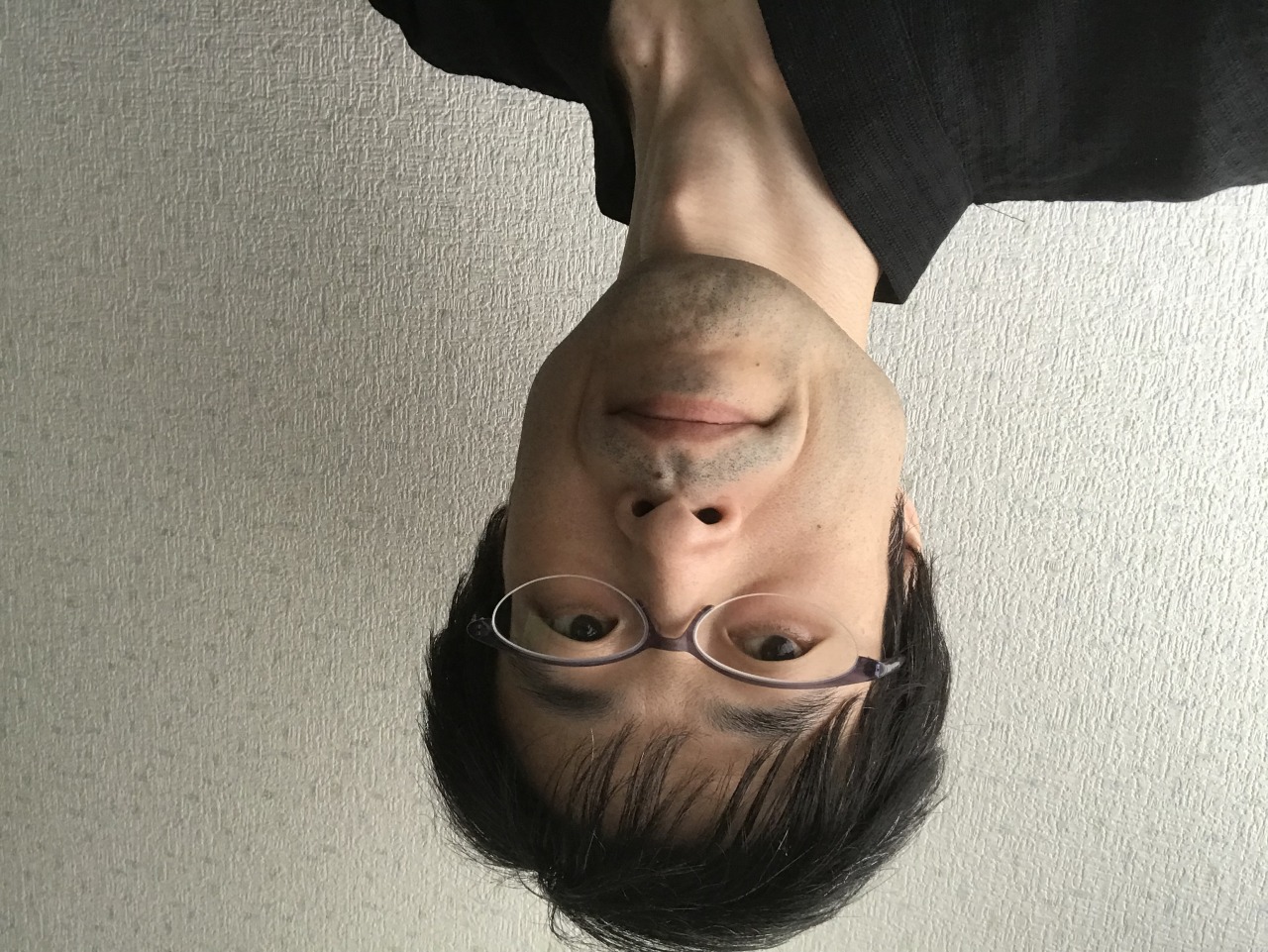
2025/10/10

晩夏の炎上騒ぎ―――ホームタウン騒動
今年の夏の終盤、国内で最も大きく炎上した話題といえば「JICA アフリカ・ホームタウン騒動」ということになるだろうか。
8月20日から22日にかけ、横浜で開催された日本政府等の主催による「第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)」において、JICA(独立行政法人 国際協力機構)が、日本の4つの自治体をアフリカ各国の「ホームタウン」に認定した。
これが、アフリカからの移民受け入れ促進政策の始まりではないかと疑われ、騒ぎになった。SNSでは昼夜にわたって論争が巻き起こり、該当する自治体に抗議電話が殺到する事態となっている。ついには9月25日、この事業の撤回をJICAが会見を開き、表明するに至った。
近年、わが国における在留外国人は加速度的に増え、目下、総人口の約3%、約370万人に及んでいる。この数字が大きいか否かは意見が分かれるところだが、外国人人口は大都市部に集中しがちなため、たとえば東京都では人口の5%を超え、20人に約1人の割合となっている(総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」)。
そうしたなか、国論をおよそ二分すると見られる(昨今の世論調査に鑑み)外国人の受け入れについて、その片側の人々における意見や危機感が一気に噴き出したのが、今回のホームタウン騒動ともいえるだろう。
経済学者の多くは外国人の増加に肯定的
さて、そんな一件が生じたつい前月(7月)のこと。歴史の長いシンクタンクのひとつ、公益社団法人日本経済研究センターが、大変興味深い調査結果を公表している。筆者もこれを大いに熟読させてもらった。紹介したい。
ここでは、経済学者の方々を対象に、在留外国人増加についてのアンケート調査が行われている。回答したのは47名。答えのほとんどに、回答者によるコメントが付されている。いわゆる外国人および外国人労働者問題、移民問題について、印象論や感情論は一旦措き、冷静に考えるためのよい参考となるものだ。
最初に数的結果を示すと、以下のとおりとなっている。全3問のうち、経済学の専門分野に該当する2問の数字を挙げてみたい。
| 強くそう思う | 6% |
| そう思う | 70% |
| どちらともいえない | 15% |
| そう思わない | 2% |
| 全くそう思わない | 0% |
| 無回答 | 6% |
| 強くそう思う | 0% |
| そう思う | 66% |
| どちらともいえない | 28% |
| そう思わない | 0% |
| 全くそう思わない | 0% |
| 無回答 | 6% |
見てのとおり、問1では「そう思う」「強くそう思う」が、合わせるとかなり多くを占めている。問2では「強くそう思う」は0%であるものの「そう思う」の割合は高い。逆に、明確にネガティブな回答(どちらともいえない・無回答を除く)にあっては、問1における「そう思わない」―――2%のみに留まっている。なお、この2%というのは、人数にすると1名だ。
すなわち、経済学のプロはその多くが、わが国に外国人が増えることを「平均的日本人の生活水準の向上」および「わが国財政収支の改善」において、プラスと見ていることになる。
そのうえで、今回、筆者はこれらに付されたコメントの多くに蒙を啓かれた思いでいる。なかでも、とりわけお二方の意見に目をひかれた。一橋大学の森口千晶教授と東京大学大学院の岩本康志教授だ。誤解が生じないよう、以下にそのままを抜粋しよう(筆者による下線だけを付す)。
「在留外国人数の増加は、平均的な日本人の生活水準の向上に寄与する(問1)」
森口教授(回答:そう思う)
「近年の日本における外国人受入れの特徴は、難民が非常に少なく、若年労働者を中心に企業の主導で日本人労働者が不足する産業・職種・地域を中心に受入れが進み、その規模は総労働力の数%に留まっている点にある。実証研究によると外国人と日本人労働者は主に補完的関係にあり、日本人の賃金や失業率に負の影響を与えていない。在留外国人の増加は生産人口を増やし、経済を活性化し、日本人の生活水準を向上させる可能性が高い。」岩本教授(回答:そう思わない)
「在留資格は政策的に決められるので、日本人の生活水準が低下したとすれば、政策の失敗である。外国人を労働力としてしか見ずに社会生活を営む人間であることを無視したため、移民政策を失敗した国が多い。日本の政策もその轍を踏んでいるので、費用を考慮せずに進めばいずれ生活水準の低下につながる。適切な運用でそれを避けることも可能であり、確実にそうなるとまでは言えないが、警鐘の意味で『そう思わない』と回答する。」
まずは前者、森口教授が指摘されている外国人と日本人の労働市場における(現状の)補完的関係性については、ほかにも数名の方が、直接、あるいは非直接的に触れておられる。
だが、このことは、われわれ素人が意外と忘れてしまいやすいものなのかもしれない。
まとめると、
「外国人労働者と日本人労働者は、現状、主には補完関係にある」
よって、今後もそうである以上は、
「日本人の賃金や失業率に悪い影響を与えないだろう」(あるいはそれが期待できる)
と、いうことになると思われるが、ともあれ、これはこの議論を冷静に進めるための大事な立脚点のひとつだろう。
そして、後者となる。岩本教授が指摘しておられるポイントだ。それは、外国人を「労働力」としてのみならず「生活者」として見ることの重要性だ。こちらは、われわれ一般の国民よりも、国や経済を動かす中心にいる人たちこそが主に忘れてしまいやすい点かもしれない。
これを忘れた政策や経営が、今後、外国人がさらに増えていく中で行われたとして、それはわれわれ日本人にとっての不幸をおそらく生むことになる。外国人の扱いをめぐって人々が分断され、憎しみ合う弊害に永く苦しむことになるだろう。
なお、外国人を労働力としてのみ見てしまうことの問題については、早稲田大学の野口晴子教授も、やはりその旨コメントしておられる。
以上、本記事読者にもぜひ一読をおすすめしたい日本経済研究センターの調査結果は、以下でご覧いただける。
「日本経済研究センター・エコノミクスパネル 外国人増加、『日本人の生活水準向上に寄与』が8割」
外国人「増」が生む心配と可能性
わが国における、いわゆる外国人および外国人労働者問題、移民問題について、学者でもなく政治家でもない筆者の中には、現在、2つの見方が混在している。さきほどの経済学者の皆さんよりは大きく劣るかなり素人な見解だが、添えておこう。
ひとつは、外国人、主には外国人労働者が増えることへの懸念だ。
このことは、もしかすると、労働力不足という奇貨(?)がわが国に生み出すはずの前向きな可能性を塞いでしまうのではないかと、筆者はうっすら感じることがある。
端的にそのひとつを挙げれば、テクノロジーだ。
足りない人材の補完を外国人に頼る場合、そうせずにテクノロジーをもってこれを乗り越えていくチャレンジの機会をわれわれはその分だけ失うことになる。または、それを手にするタイミングを先送りすることになるだろう。
つまりは、手っ取り早い解決策を選ぶことで失われるもうひとつの世界線(いわゆる)だ。それが仮に生じるとすれば惜しいことだな―――という、やや漫画チックな憂慮となる。
たとえば、筆者はロボタクに早く乗りたいと思っている。
運転手不足だからといって、外国人にタクシードライバーになってもらうよりも、当面のリスクはあってもロボットタクシーの国内実用化を早く見たい。
なので、筆者に限っては、プログラムにバグの潜んだ未熟なロボタクが近所を走り回り、これに轢かれて人生が終わってしまっても、本望であるため仕方がない。
以上、外国人が増えることへの反対論に立つ筆者の意見。
もう一方は、つまらない本音だ。こちらは外国人歓迎派としての筆者の想いとなる。
多様な人種が行き交う風景が、実は筆者は好きなのだ。コスモポリスにときめきを感じる方の人間だと思っている。
そのうえで、治安に破綻のない、世界にもまれな安全なコスモポリスを日本はもしかしたら生み出せるのではないかという、「甘い」と叱られそうな考えを筆者は以前から持っている。
ただし、その理由は感覚的なものにすぎない。
世界の平均に照らして、日本人と日本文化は、多様をうまく一様に溶かし合わせていく、多種融合的能力にきわめてすぐれた本質を備えているように、筆者は勝手に感じているからだ。
多くの国や文化が、いわゆる人種のサラダボウルまでしかつくれないとしたら、案外わが国は、真のるつぼ―――メルティングポットを創造できる能力を持っているのかも?
そして、それら「一様」のなかには、もちろん、女性の夜道の一人歩きが可能だったり、落とした財布が高確率で戻って来たりといった、われわれの社会が持つすぐれた容儀が残っているとの期待となる。
(文/朝倉継道)
【関連記事】
人口減少が嫌ならば外国人に来てもらうしかない? 日本人マイナス91万人vs外国人プラス35万人
男女共同参画白書が公表。ふるさとは遠きにありて思ふもの?
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。