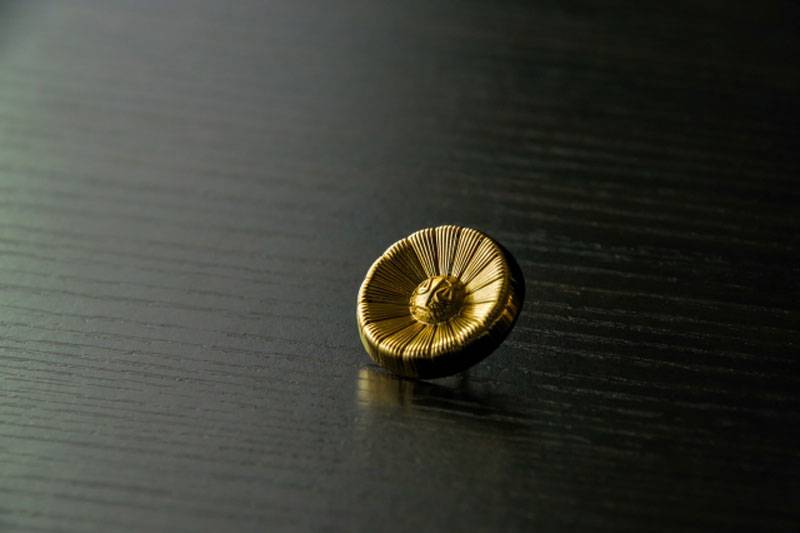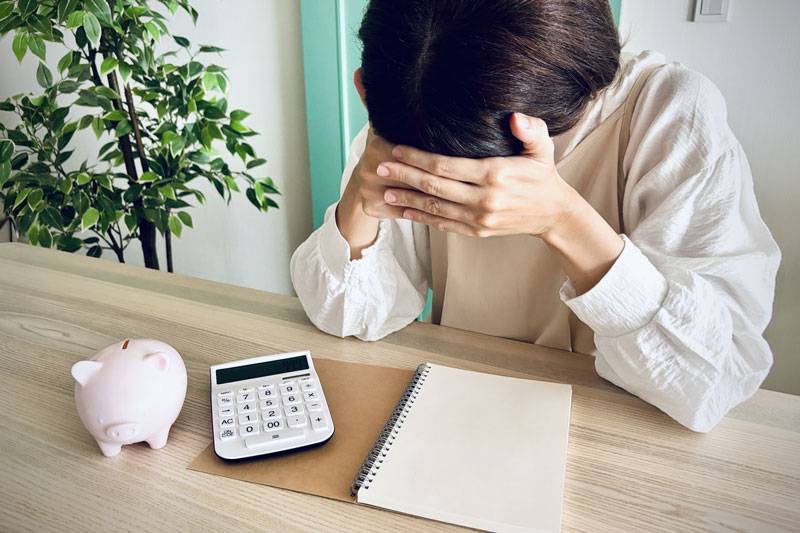無断での多人数居住に関するトラブル

2025/08/06

賃貸借契約において居住人数に関する条項を定めていたにもかかわらず、賃借人が無断で他人を住まわせていたという経験はありませんか。最近は、コスト削減などを理由としてシェアハウスの需要が増えており、同じ部屋で多人数が共同生活をすることも世間に浸透してきております。そこで、今回は無断での多人数居住に関するトラブルと対策についてご説明します。
上限を超えた多人数居住によりさまざまなトラブルが発生!
部屋の居住人数はその構造や居住環境などから定まっており、これを超える人数が部屋に居住した場合にはさまざまなトラブルが生じる恐れがあります。そこで、代表的なトラブルをいくつかご紹介します。
- 建物の設備に対する過剰な負荷
賃貸物件は、入居者数を想定して設計・管理されているため、許容されている人数を超えて居住することで、水道や電気の設備に過剰な負荷がかかったり、排水トラブルや空調設備が故障したりといった問題が発生しやすくなります。また、ゴミの排出量が増加することで、処理が追いつかず悪臭や害虫の発生といった衛生面での問題も生じかねません。 - 近隣トラブル
無断で複数人が居住することにより、生活音が大きくなったり、共有部分を占有したりするなど、ほかの居住者や隣接住民への迷惑行為につながる可能性があります。例えば、夜遅くまでの話し声、複数人による出入りの多さ、駐輪場やゴミ置き場の使用ルール違反などが積み重なることで、近隣住民からの苦情が増え、建物全体の居住環境が悪化してしまいます。こうした状況は、ほかの入居者の退去や空室率の上昇、さらには物件の評判低下にもつながり、賃貸人にとって長期的な損失となります。 - 災害時におけるリスクの増大
火災、地震、台風などの災害発生時、想定よりも多くの人が建物内にいる場合、避難誘導が困難になり、人命に関わる重大な事故につながる可能性があります。例えば、非常口や共用廊下が無断で居住している者の私物で塞がれていた場合、迅速な避難ができなくなり、被害が拡大するおそれがあります。また、消防署や自治体への届け出内容と実態が異なる場合、緊急時の対応にも支障を来たすことがあります。
無断での多人数居住があると賃貸借契約を解除できる可能性あり!
無断での多人数居住が発覚した場合、上記のトラブルを避けるために、賃貸借契約を解除して違反者を退去させたいと考える賃貸人が多いと思います。そこで、無断での多人数居住が発覚した場合に賃貸借契約を解除し違反者を退去させることができるかについてご説明します。
・判例を踏まえた基本的な考え方
最高裁判所は、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用収益させた場合でも、その行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特別の事情があるときは、解除権は発生しないと判断しています(最判昭和28年9月25日)。
したがって、賃貸借契約書に居住人数に関する条項を記載し、これに違反した際は解除できると定めていた場合でも、無断での多人数居住が発覚したからといっていきなり賃貸借契約を解除することはできません。しかし、逆に言えば、無断での多人数居住により賃貸借契約を継続するために必要な信頼関係が破壊されたといえる場合には賃貸借契約の解除が認められるのです。この考え方を信頼関係破壊の法理と呼びます。
・賃貸借契約解除から退去までの具体的な手順
- 賃貸借契約の記載内容を確認
無断での多人数居住が発覚した場合には、まず賃貸借契約書の記載内容を確認します。具体的には、賃貸借契約書に、「居住者は契約者本人のみとする」「同居人を追加する際には賃貸人の承諾が必要となる」など居住人数に関する条項が明記されているかを確認し、契約違反の有無を確認します。 - 証拠収集
実際に多人数が居住している証拠を収集します。証拠の例としては、現地調査、ほかの入居者からの苦情、郵便受けの状況、出入りの頻度の記録などがあります。その後の交渉や訴訟の際に重要となるため、あらかじめ証拠を収集しておいた方がよいでしょう。 - 期限を定めた是正通知と是正がされない場合の賃貸借契約解除
違反が確認された場合でも、いきなり契約を解除するのではなく、まずは賃借人に対し是正を求める必要があります。このとき、適切な期限を設けておくことが重要です。期限を過ぎても状況が改善されず、また賃借人からも合理的な説明や対応がない場合には、信頼関係が破壊されたと判断され解除が認められる可能性が高いといえます。そのため、賃借人に対して内容証明郵便などを用いて通知書を送付し、通知書には「賃貸借契約書に居住人数に関する条項があること」、「賃貸借契約違反が認められたこと」、「期限までに同居人の退去や状況の説明を求め、これに応じなければ本通知書により賃貸借契約を解除すること」などを記載します。 - 退去交渉または明渡訴訟の提起
解除通知書に基づき、賃借人が自主的に退去すれば問題はありませんが、任意退去を拒否する場合には、法的手段をとる必要があります。この場合、裁判所に対して明渡請求訴訟を提起します。判決で明渡しが認められれば、強制執行により明渡しを実現できます。ただし、このプロセスは数か月を要することが多いため、なるべく交渉による任意退去を目指した方がよいでしょう。
無断での多人数居住に関するトラブルを未然に防ぐためには
賃貸人として無断での多人数居住によるトラブルを未然に防ぐためには、契約時の明確なルール設定と充分な管理体制が必要です。
まず、賃貸借契約書には「居住人数に関する条項」、「違反時の契約解除条項」などを明記し、入居者に十分な説明を行うことが基本となります。さらに、入居時に入居者の氏名と身分証明書を確認し、申告内容が正しいかを確認することも効果的です。
また、契約後も定期的な物件の巡回や、管理会社を通じた現地確認を行うことで、不審な出入りや異常な生活状況に早期に気付くことが可能になります。また、防犯カメラの設置やオートロックシステムの導入も、不正な出入りの防止につながります。
それでも、無断での多人数居住に関するトラブルが発生してしまった場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談するべきです。賃貸借契約解除から退去までの手続きや通知書の文面などについて専門的な助言を受けることで、トラブルの長期化や不利な展開を避け、迅速な解決を図ることができます。
【関連記事】
やってはいけない賃貸の「又貸し」―――無断転貸。初心者は特に注意
賃借人が行方不明となっている場合の対応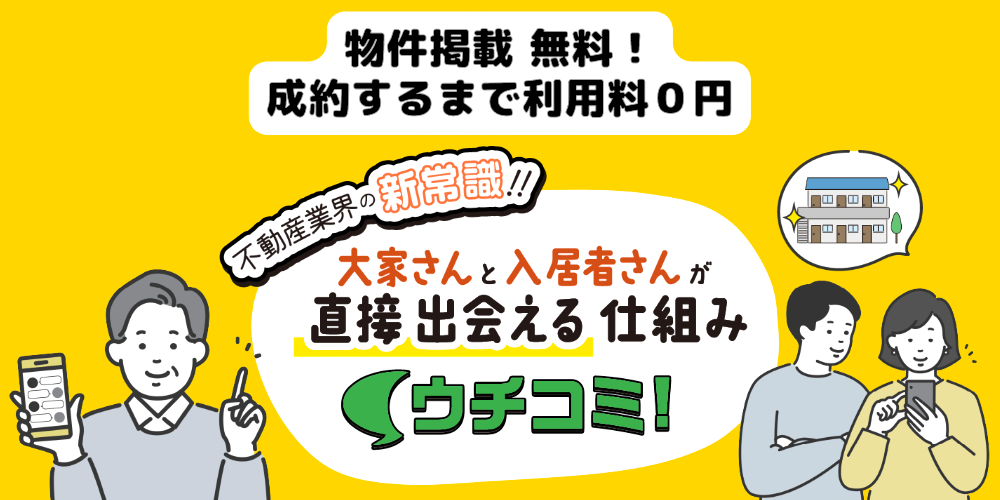
無料で使える空室対策♪ ウチコミ!無料会員登録はこちら
この記事を書いた人
弁護士
弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。