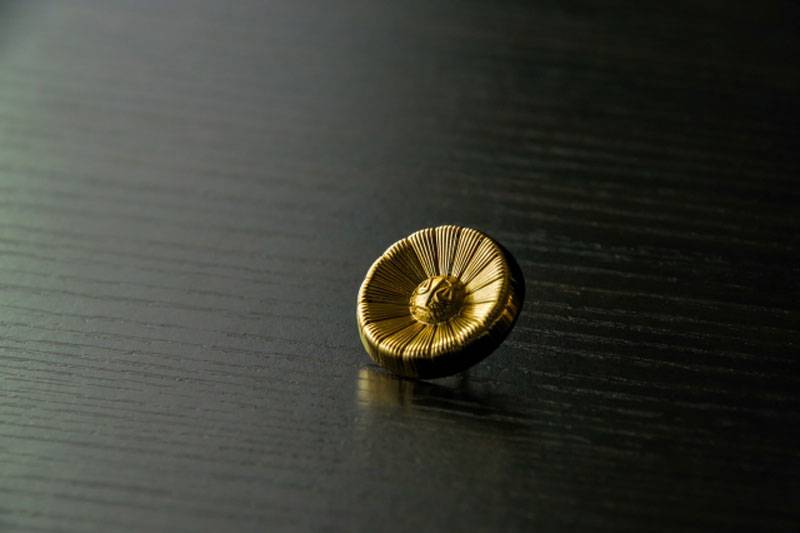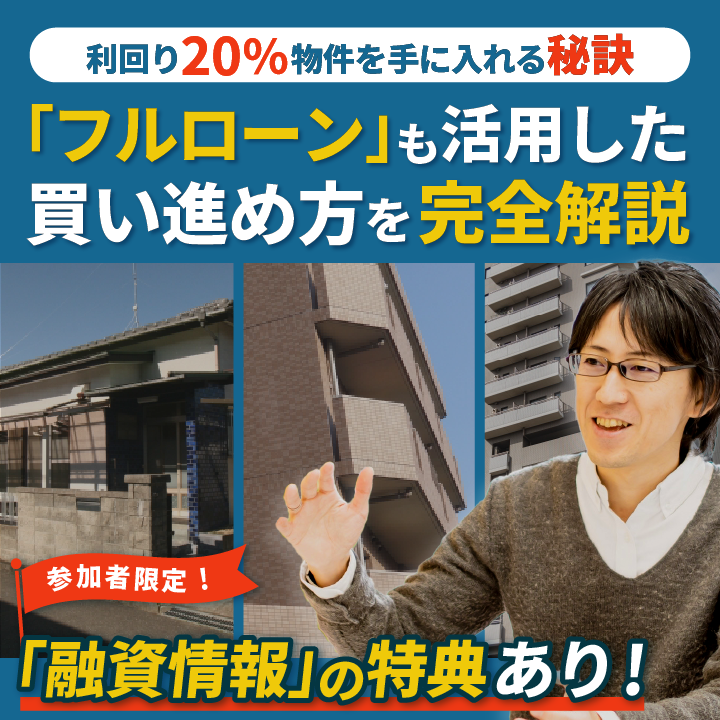住居確保給付金「転居費用の補助」がスタート。4月から制度拡充

2025/04/18

家賃が安い賃貸住宅への転居費用補助がスタート
この4月1日から、住居確保給付金の制度が拡充されている。従来の家賃補助に加え、家賃が安い住宅への「転居費用補助」が始まった。
たとえば、仕事を失うなどして困窮し、苦しんでいる人によく見られる状況としてこんなものがある。
「いまの家賃では生活していけない。もっと安い部屋へ転居したいが、引っ越し費用や、仲介手数料、礼金など初期費用を払う余裕がない」
こうした状態だと、家賃の滞納や、ともすれば夜逃げといったような、当人だけでなく周りにとっても不幸な事態が迫ってくる。これらを避け、家計の立て直しをサポートするため、実情に即した国の新たな対応が始まったかたちとなっている。
以下、この記事では、新制度を利用するための主な要件などを挙げていきたい。
なお、さらに具体的な制度の運用のされ方、利用のしかたについては、住んでいる地域の「生活困窮者自立相談支援機関」に問合せし、確かめることになる。
同機関は、自治体の直営、もしくは社会福祉法人等への委託によって運営されている窓口だ。それぞれにつながる最初の連絡先を検索できるサイトがあるので、のちほどリンクを掲げたい。
「転居費用補助」―――支給の主な対象
主な対象者は、
「収入が大きく減少し、家賃を払えなくなりそうな人や、すでに住まいを失った人で、家計の改善のために、家賃の安い住宅に転居する必要がある人」
となる。例を挙げると、
「病気で離職し、必要な収入を確保できなくなった」「配偶者が亡くなり、世帯の収入が減少した」
―――などだ。
支給の要件
以下に概要を掲げていく。(1~4)
なお、収入要件や資産要件は自治体によって異なる。そのため、結論としては、前記の自立相談支援機関への問合せが必要となる。
そのうえで、参考までに東京都豊島区の例を添えておいた。25年4月1日のウェブサイト更新時においての案内から引用している。
1.期間の要件と申請者の立場に関する要件
この制度による補助の申請を行う月において、それが世帯収入額の減少した月から2年以内であること。加えて、申請者(支給対象者)が、その世帯の生計を主として維持している人であること。
2.収入要件
申請を行う月において、申請者および申請者と同じ世帯に属する人の収入の合計が「基準額+家賃額」より少ないこと。
なお、基準額は自治体によって異なる。同様に、家賃額にも上限の違いがある。各地域の自立相談支援機関に問合せて、確かめることになる。
「参考」東京都豊島区の場合
―――申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入(失業給付、年金なども含む)の合計額が下記以下であること。
| 世帯数 | 条件 |
|---|---|
| 1人世帯 | 基準額8.4万円に、家賃額(53,700円が上限)を合算した額 |
| 2人世帯 | 基準額13万円に、家賃額(64,000円が上限)を合算した額 |
| 3人世帯 | 基準額17.2万円に、家賃額(69,800円が上限)を合算した額 |
| 4人世帯以上 | ※要問合せ |
3.資産要件
資産(預貯金・手持ちのお金など)の合計が基準額の6倍(その額が100万円を超える場合は100万円)以下であること。
こちらも、自治体による基準額の違いによって、それぞれ金額が異なる結果となるので、収入要件同様に確認が必要だ。
「参考」東京都豊島区の場合
―――申請者および申請者と同一の世帯に属する方の預貯金(債権、株なども含む)の合計額が下記の金額以下であること。
| 世帯数 | 預貯金の上限額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 50.4万円 |
| 2人世帯 | 78万円 |
| 3人世帯以上 | 100万円 |
4.転居により家計が改善すると認められること
当制度の利用を希望する人は、まずは自立相談支援機関による家計改善支援を受けることになる。そのため「家計改善支援事業」への申込みを行う。
その中で、「転居によって家計が改善する」と認められれば、転居費用の補助・支給の実施へと進むことになる。
なお、転居先の家賃が現在の家賃より多少高くとも、転居によって家計全体が改善すると認められれば、補助の対象となる場合もある。たとえば、「転居先の方が、現在の住居よりも病院への距離が近く、通院のための交通費が減り、家計全体の支出が削減できる」と、いったケースだ。
支給対象となる費用
転居先への家財の運搬費用、すなわち引っ越し代、さらには転居の際に通常必要となる、いわゆる「初期費用」が支給の対象となる。
具体的には、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、賃貸住宅の入居者が加入を求められる保険料、鍵交換費用など。転居前の住居の原状回復費用、ハウスクリーニング費用もこの初期費用に含まれる。
なお、貸主(大家・オーナー)に預ける「預け金」である敷金や、家賃の一部となる前家賃は対象とならない。
さらに、支給額全体に対し、上限がある。これも自治体によって異なるので、具体的な金額についてはやはり問合せが必要だ。
「参考」東京都豊島区の支給上限額
(豊島区外へ転出する場合、上限額が異なることがある)
| 世帯数 | 支給上限額 |
|---|---|
| 1人世帯 | 161,100円 |
| 2人世帯 | 192,000円 |
| 3人世帯 | 209,400円 |
支給のかたち
自治体から、不動産仲介会社や、補助・支給の対象となるそれぞれの代金・料金を受け取る事業者等の口座へ、直接振り込まれるかたちが原則となる。
転居費用補助を受けたいと思ったら―――動く順番
以下、問合せ・相談から転居、さらに、転居以降までの流れについて概要を記していこう。なお、具体的には、自立相談支援機関の指示にそれぞれ従うことになる。
- まずは問合せ・相談
最初に行うのは自立相談支援機関への問合せだ。各地域の最初の窓口となる連絡先を下記のサイトで調べることができる。
「厚生労働省 住居確保給付金 申請・相談窓口」
こちらでまずは状況を説明し、以降の案内を受けよう。 - 家計改善支援を受ける
自立相談支援機関への問合せ・相談の結果、要件に適うようであれば、前記したとおり「家計改善支援事業」への申し込みを行う。相談員によるサポート・指導のもと、家計の立て直しを目指すプランの作成などを行うことになるだろう。
そのうえで、家計改善のために「転居が必要」と確認されれば、補助が実施されることになる。そのための必要書類等を整え、提出する流れとなるだろう。 - 転居先住居の確保
次に、転居先となる住居を確保する。基本として、自立相談支援機関の指導のもと、指示された家賃の額以内の物件を探すことになる。
また、この際、不動産会社に記入してもらう書類のことなど、必要な手続き等について、支援機関からガイダンスがあるはずだ。
自ら転居先を探すことが難しい場合は、機関側に相談するといいだろう。状況に応じてサポートを得られるはずだ。 - 審査・転居・送金
転居先が決まり、書類も整い、それらの内容が審査の結果適正と判断されれば、いよいよ給付金の支給が開始となる。支給決定通知書が交付される。併せて、家財運搬費用(引っ越し代)の見積書の提出など、付随する手続きについても指示があるはずだ。 - 転居後の書類提出
この制度によって転居費用を受給した人は、転居先への入居日から7日以内に、指示された書類を提出しなければならない。建物賃貸借契約書の写し、住民票の写しなどだ。遅れずに実行しよう。
従来からの「家賃補助」について
以上、従来の家賃補助に加えて、住居確保給付金制度のなかで新しく始まった「転居費用補助」についてお伝えした。
なお、家賃補助の方ももちろん続いている。どういう制度か、簡単にまとめると、
「主たる生計維持者が、離職・廃業後、2年以内」
もしくは、
「個人の責任・都合によらず、給与等の収入を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している」
そのうえで、一定の要件を満たす場合に(求職活動等を行う要件もある)、
「市区町村ごとに定める額を上限に、実際の家賃額が原則3カ月間支給される(延長は2回まで・最大9カ月間)」
と、いった制度だ。
先般「コロナ禍」の時期、利用する人が一気に増えて広く知られるようになったものだが、内容については、わかりやすい厚労省の特設サイトが下記にある。
「厚生労働省 生活支援特設ウェブサイト 住居確保給付金・制度概要」
まずは、上記を閲覧しよう。
次に、各自治体のサイトにある案内等も確認し、ある程度予習をした上で、窓口である自立相談支援機関にアクセスするのがスムースな流れとなるだろう。
(文/賃貸幸せラボラトリー)
【関連記事】
「住みたい街」で横浜はなぜ強い? 住みたい街を礼金率で比べてみる
賃貸デビューする人は必読!「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室