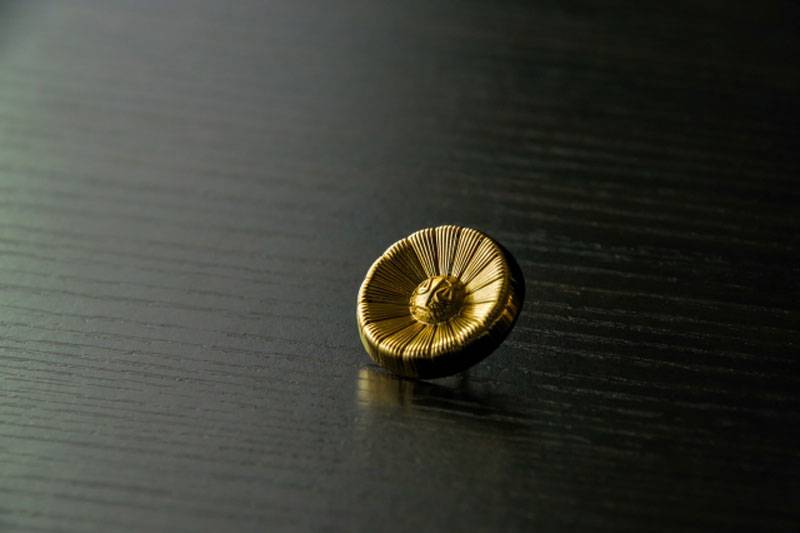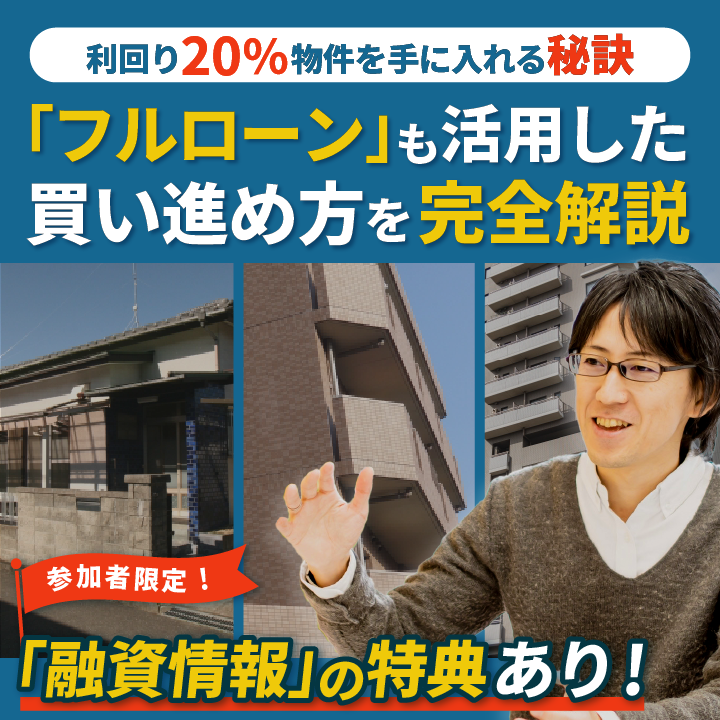賃貸デビューする人は必読!「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

2025/02/10

国交省の肝煎り「ガイドライン」
この春、親元などを離れ、賃貸マンションやアパートで初めての一人暮らしを始める人も多いはずだ。きっかけは、進学だろうか、就職だろうか。あるいは別の理由だろうか。いずれにしても、その前途を心よりお祝いしたい。
さて、そんな「賃貸一人暮らしデビュー」をする人に、必ず目を通してほしい資料がある。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」だ。国土交通省が作成したもので、インターネット上で公開されている。
内容は、ズバリ、原状回復トラブルについての判断基準となる。
「原状回復トラブル」とは何か?
皆さんは、これから賃貸マンションやアパートといった「賃貸住宅」で暮らすことになる。つまり、建物を借りて暮らす。
借り物である以上、持ち主がいるわけだが、それが「大家さん」あるいは「オーナー」と呼ばれる人たちだ。多くが何千万~何億円というお金のかかった、彼らの大事な財産である建物の一部を借りて、皆さんは生活をする。
すると、1年、2年……あるいはもっと長く続くその過程で、建物、すなわち物件が汚れたり、傷ついたりすることももちろんあるだろう。
その中には、うっかり自分でつけてしまった傷や汚れなどのほか、時間が経つにつれ勝手に変色したり、摩耗したりといった、経年による劣化、自然な変化といえるものももちろんあるはずだ。
そこで、こうしたさまざまな理由による損耗や毀損―――併せて「建物価値の減少」について、これを元のかたちに戻す、すなわち「原状回復」させるとすれば、その責任は誰にあるのだろう?
もっと単純に言えば、その傷や汚れは誰が直すのか?
直すのにお金がかかるとして、誰が負担するべきなのか? 建物を借りている入居者か? オーナーか?
「判断するのは、ケースによってはかなり難しそうだ」
容易に想像できることだろう。
そこで、そうした際の判断基準と、基となる考え方を示したものが、この「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」なのだ。
ちなみに、この「ガイドライン」は、国が定めたものとはいえ法律ではない。つまり、強制力をもつ決まりごとではない。
しかしながら、ジャッジメント(判定)が平等で、かつ論理立てもしっかりしているため、昨今はそれに近い扱いがされている。
すなわち、賃貸物件を管理する不動産管理会社や、先ほどのオーナー、あるいは法律に関わる仕事をする人など、関係者みんなが頼りにする「よりどころ」だ。
なので、賃貸住宅に暮らす入居者も、これをぜひ読んでほしい。日々の生活上、心得ておくべき事柄がたくさん網羅されている。
前置きはここまで。
ありがちな原状回復トラブルについて「ガイドライン」がどんな判断・基準を示しているのか、いくつか例を見ていこう。
壁に画鋲を刺してカレンダーを下げた!
判定―――入居者に原状回復の責任はない。
「それって、入居者の故意によるものだから、原状回復の負担は当然じゃないの?」と、反応する人も多いこのケース。だが、ガイドラインは「ポスターやカレンダー等の掲示は、入居者の通常の生活において行われる範疇のもの」としている。よって、そのために壁に画鋲を刺し、穴を開けたくらいならば、入居者に原状回復の責任はないとの判断だ。ただし、釘やネジなどで「下地ボードの張り替えが必要な程度」の穴を開けた場合などは、その限りでない。
冷蔵庫の裏側の壁が「電気ヤケ」で黒ずんだ!
判定―――入居者に原状回復の責任はない。
冷蔵庫の裏側に面した壁や壁紙に生じる、いわゆる「電気ヤケ」による黒ずみについて、ガイドラインはこれを「入居者が通常の住まい方をしていても発生すると考えられる」ものとしている。なおかつ、冷蔵庫は「一般的な生活をしていく上で必需品」との判断も重なり、入居者に原状回復の責任はないとする。
日の差す部屋でフローリングが色落ちした!
判定―――入居者に原状回復の責任はない。
窓から差す太陽の光によって、フローリングの色落ちや畳の変色が生じた場合も、ガイドラインは先ほどの「電気ヤケ」同様、入居者に原状回復の責任はないとしている。「日照は通常の生活で避けられないもの」との判断だ。
タバコのヤニ、臭いが壁紙に染み付いた!
判定―――入居者に原状回復の責任がある。
昭和の昔であれば、喫煙によるヤニの付着やニオイは「通常の住まい方」をした結果の一部と見られることも多かっただろう。だが、現在はダメだ。ガイドラインはこれを「通常の(賃貸物件の)使用による結果とはいえないもの」に別け、入居者に原状回復の責任があると判断している。
幼い子どもが壁に落書きしてしまった!
判定―――入居者に原状回復の責任がある。
ガイドラインは、「落書き等の故意による毀損」について、これを当然ながら「通常の(賃貸物件の)使用による結果とはいえないもの」としている。すなわち、入居者に原状回復の責任がある。たとえ、入居者家族のうちの小さな子どもがやってしまったことでも同様だ。ガイドラインは例外となる人的条件を挙げていない。管理者である親が責任を果たすことになる。
床にこぼした飲み物の跡がシミになって残った!
判定―――入居者に(あるいは「入居者にも」)原状回復の責任がある。
ガイドラインは「飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられる」とするものの、「その後の手入れ不足等で生じたシミの除去は、入居者の負担により実施するのが妥当」ともしている。こぼれたことにすぐ気付かず、長時間拭かないでおいたものがシミになって残ったなど、場合によっては、入居者に原状回復の責任が一部、あるいは全部にわたって生じることになるわけだ。
結露によるカビの発生が繰り返され、壁が腐り、シミになった!
判定―――入居者に(あるいは「入居者にも」)原状回復の責任がある。
結露が起きてしまうこと自体は、建物の構造的な理由によることが多く、入居者の責任とは通常いえない。だが、そうした問題があることをオーナーあるいは管理会社に報告せず(改善の機会を与えず)、自ら水滴を拭き取るなどの処置も怠っていたとなれば、それは入居者の管理が悪いために事態が拡大したものと見るのがガイドラインの判断だ。原状回復の責任が、相当の範囲で入居者に生じることとなる。
3つに区分される判断基準
以上、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」による判断のいくつかをピックアップしてみた。いかがだろうか。
なお、こうした考え方の基礎として、ガイドラインは、賃貸物件に入居者が住むことによって生じる建物価値の減少のかたちを3つに区分している。以下のとおりとなる。
- 「A」―――入居者が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの
先ほどの例だと「電気ヤケ」「日光によるフローリングの色落ち」さらには、意外に感じる人もよくいる「壁に画鋲」がこれにあたっている。このAについては、入居者は原状回復の責任を負わない。よって、かかる費用はオーナーが負担する。 - 「B」―――入居者の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの)
先ほどの例だと「タバコのヤニ、臭い」「落書き」がこれに該当する。入居者は原状回復の責任を負うことになる。すなわち費用を負担する。 - 「A(+B)」―――基本的にはA(入居者に責任なし)だが、その後の手入れ等、入居者の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
先ほどの例のうち「床にこぼした飲み物」「結露」がこれにあたる。これらが発生したこと自体に対し、入居者は責任を負わされるべきではないが、結果に至った過程(必要な処置を怠ったなど)に対して責任を負う。法律用語でいうと「善管注意義務違反」だ。全部にせよ一部にせよ、その費用の負担から入居者が逃れるのは難しくなる。
なお、これら3つをまとめて表現すると、
「入居者の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、入居者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」
となる。すなわち、これに該当するものについては入居者の責任とするのがガイドラインの考え方であり、ほぼ常識に沿った判断ともいえるはずだ。
敷金トラブル=多くは原状回復トラブル
以上のとおり、入居者が責任を負うべき原状回復が結果として生じており、それに対し費用を要することとなった場合、多くのケースで、入居者は、その物件から退去するタイミングで、オーナーに預けてある「敷金」からそれを払うことになる。
あるいは、敷金が契約により預けられていなかったり(敷金0物件)、敷金だけでは金額が足りなかったりする場合は、不足分を補って支払うことになるわけだ。
原状回復トラブルが、「敷金トラブル」「退去時トラブル」などとよく呼ばれるのは、そのためだ。
「ハウスクリーニング特約」との関係
大事な注意喚起を付け加えよう。
近年、賃貸住宅の契約でよく見られるものとして、「ハウスクリーニング特約」がある。
「特約条項 ―――退去時、借主(入居者)は、業者によるハウスクリーニング費用相当額○万○千円を負担する」
などというものだ。こうした条文が契約の中に盛り込まれる。
すると、なかには意味を誤解してしまう人もいる。―――「そうか、この物件って、サブスクみたいなやつなんだ」
詳しくは、こんな解釈だ。
「この物件では、入居者が負担することになった原状回復の責任については、定額○万○千円を払えば、それで全部をカバーしてくれる……」
さらに、考えが飛躍してしまうケースもあるだろう。
「そうか、それならば、部屋を汚さないよう、傷付けないよう、毎日気を使って生活するのは損になる。どうせ○万○千円を取られるのなら、気楽にだらしなく暮らしてしまおう」
それは、繰り返すが誤解だ。
ハウスクリーニング特約は、「入居者が負うことになった原状回復の責任」に対し、これをカバーするものではない。
意味としてはその逆だ。
「本来、入居者が責任を負わなくていい、オーナーが負担するべき物件の損耗等の回復に充てられる」―――ものだ。
どういうことかというと、いまどき、入居者が退去したあとの物件については、汚れの度合いが多い、少ないにかかわらず、オーナーはほぼ一律に業者を呼び、ハウスクリーニングを依頼する。(あるいは管理会社がパッケージとしてそのように動く)
その際、オーナーとしては、「立つ鳥跡を濁さず」ではないが、部屋を出て行く入居者がその費用を負担してくれると非常にありがたい。(1住戸にかかる金額は少なくとも、抱える戸数分となるとオーナーの出費は大きいのだ)
そこで、設けられたのがハウスクリーニング特約だ。いまや多くの契約で見られ、かなり一般的になってきている。
しかしながら、こうしたかたちでのハウスクリーニングは、理屈としては次の入居者を確保するためのいわば「部屋の化粧直し」にあたるものだ。本質的にはオーナーによる投資となる。
そのため、これに要する費用を入居者に求めるのは、本来筋違いな行為だ。なので、前出「ガイドライン」も、こうした意味でのハウスクリーニング費用はオーナーが負担するべきものに分類している。
ともあれだ。そうした評価や議論はともかく、ハウスクリーニング特約について、入居者にとっての正しい解釈は、まとめるとこうなるわけだ。
「この特約は、入居者が負うことになった原状回復の責任について、これをカバーするためのものではない。入居者が負うべき原状回復の責任が存在するのならば、その費用は別途入居者が負担する」
―――にもかかわらず、これを「物件汚し放題のサブスク契約」のように思い込むのは大きな誤解であり、危険な判断となることが理解できるだろう。
なおかつ、そこまでいかなくとも「特約部分に書かれた金額のほかに入居者の負担はない」などと安心していると、あとで驚く結果になることがあるので注意したい。
とはいうものの、現実をいえば、こうした“ルーティーン”としてのハウスクリーニングの過程で、入居者が責任を負うべき原状回復部分も実際はカバーされているケースはそれなりに多いだろう。ある意味、それは穏便な流れといっていい。(オーナー側もこの特約の目的や効果をそれと理解していることが少なくない)
ただし、その場合、入居者は本来払わなくてよい費用を払い、払うべき費用は免れるという、やや面白い立場に立つことにはなる。
(ハウスクリーニング特約を成立させ、法的な争いとなった際もゆるがないようにするには一定の要件が求められる。詳細は下記リンク先の記事で)
(文/賃貸幸せラボラトリー)
【関連記事】
賃貸・水道パッキンの交換は入居者が負担するって、正しいの?
「退去します」の予告は撤回できない!? 賃貸・知られざる厳しい決まりごと
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室