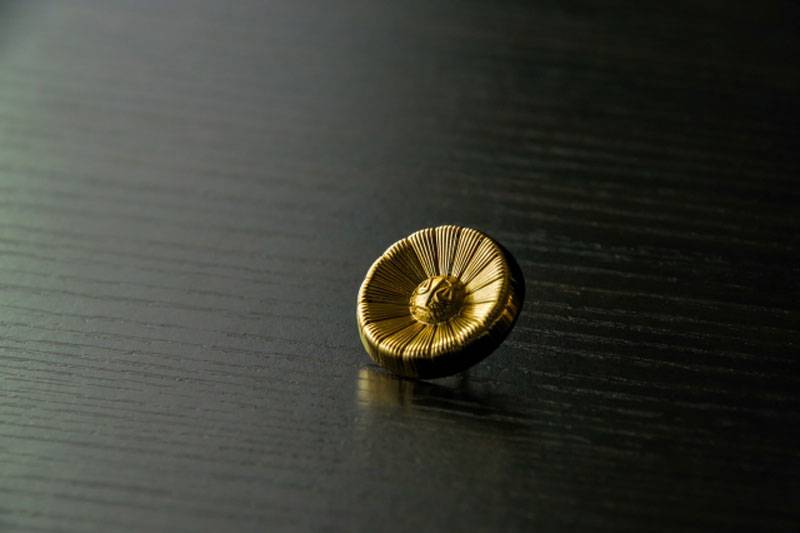賃貸・退去「3カ月前までに予告せよ」は早すぎる? 違法じゃないの?

2024/08/05

退去予告の通知期間を過ぎています
昨年秋まで、首都圏のある賃貸マンションに暮らしていた20代の男性会社員、Aさんの話だ。
「去年の9月1日のことです。地方への転勤を内示され、住んでいた部屋から引っ越すことになりました。赴任先での勤務開始はひと月後の10月1日です。1カ月前の内示です。そこで、その日のうちに早速、管理会社に電話したところ……」
こう言われたそうだ。
「残念ですが、ご希望の日にちでは解約していただけません」
「え!なぜですか?」
「今月30日をもって賃貸借契約を終了、解約。その数日前までには退去のご予定とのことですが、Aさんの住んでいらっしゃるお部屋の場合、解約予告ができる期間が解約日の3カ月前までとなっています。なので、申し訳ありません。今現在、期限を大幅に過ぎている状態です」
「そんな!ひと月前の転勤命令なんてよくあるタイミングですよ」
「もちろん『引っ越すな』ということではありません。ご安心ください。こういう方法が採れます。Aさんからは、本日申し入れをいただいた扱いとし、今から3カ月後までの家賃をお支払いいただきます。そうすれば、その間、お好きな日に解約・退去が可能になります。用紙を送りますので、今日の日付を入れてご返送ください」
つまり、こういうことだ。
あらかじめ約束された予告通知期間を守れなかったAさんは、いまから違約金を払わされるのだ。具体的には、Aさんがこの部屋を去って以降の2カ月ちょっと―――その間の家賃が、これに相当することになるだろう。
だがAさん、これに納得がいかず、
「3カ月前までに予告しろなんて、あまりに早すぎませんか? そんな契約になってましたっけ?」
「なっています。お手元の契約書をご覧ください」
探し出し、読んでみると、たしかに管理会社のスタッフが言うとおり、そこにはこんな約定が記されていたそうだ。
「第〇条 借主は、貸主に対して少なくとも3カ月前に文書にて解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる」
「2 前項の規定にかかわらず、借主は、解約申入れの日から3カ月分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む)を貸主に支払うことにより、解約申入れの日から起算して3カ月を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる」
「3カ月前までに」は、違法ではない
ガックリ来たAさん。「退去したあとの無駄な家賃を2カ月分以上も支払うのか」と、しばらく沈み込んでいたそうだ。
さらに、Aさんは、同じように賃貸で暮らしている会社の同僚数人に「契約書はどうなってる?」と、尋ねてみたという。
「答えは、皆ほぼ一緒でした。予告通知期間は『1カ月前まで』か、あるいは『30日前まで』です。そのくらいが普通のようです。『3カ月前まで』なんてせっかちな例はひとつもありませんでした。あのあと、僕は仕方なく泣き寝入りしましたが、あの契約内容は違法だったのではと、今も疑問に思っています」
―――さて、結論だ。
契約内容の違法性を疑っているというAさんだが、上記はおそらく違法ではない。かなりの高確率で「適法」と判断されるはずだ。
ちなみに、国土交通省はこれに問題が無い旨ハッキリと言い切っている。「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版・令和4年3月)」から抜粋してみよう。
(質問)
2年契約でアパートを借りていましたが、転勤となり1年で退去しようと思い、12月に当月一杯で退去すると連絡をしたら、退去の場合には3カ月前には告知する必要があり、即時解約の場合には家賃3カ月分の違約金が必要と言われました。転勤の辞令が出たのが1週間前であるため、退去予告はできない状況でしたが、支払う必要がありますか?
(答え)
契約の中途解約に当たるため事前告知が必要であり、直前での解約は事前告知債務の不履行に当たるため、違約金を支払う必要があります。
―――このとおりだ。ほぼAさんの事例と同じ内容となる。なので、たとえ昨年争っていたとしても、Aさんに勝ち目はなかっただろう。
ただし、この事例集の別のページを見ると、以下のような興味深いことも書かれている。
「予告期間について3カ月以外とする特約がある場合は、不当に長い期間でない限り、原則として特約に従うことになります」
「3カ月よりも短い特約に関しては有効と考えられますが、3カ月よりも長い場合、どの程度から不当といえるかは、この点について基準を明確にした判例もないため、個別具体的な検討が必要と考えられます」
つまり、こういうことだ。
3カ月という期間は、ここではどうやら特別な意味をもっているようなのだ。すなわち、これを境にして、その約定が「不当ではない」ものなのか、「不当とされる可能性が出てくる」のか、判断が分かれるらしい。
すると……、この気になる「3カ月」の出どころは何なのか?
賃貸住宅で暮らしている人のほとんどが知らないであろう、その答えを以下にひもといていこう。
「3カ月」は、民法が認めている線引き
答えは「民法」にある。まずは617条を見てみよう。
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
民法第617条 第1項
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 1年
二 建物の賃貸借 3箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 1日
―――見てのとおりだ。ここに3カ月(箇月)が出て来た。
この条文によれば、建物の賃貸借における解約の申し入れは、要は「3カ月前までにせよ」ということになっている。そのうえで、これに間に合わなかった場合、その時点から3カ月の間、契約期間が続くことを申し入れた側は納得しなければならない決まりだ。つまり、Aさんが体験したのとかなり似た立場ということだ。
とはいえ、お気付きだろうか。この規定は、括弧書きにもあるとおり「期間の定めのない」賃貸借契約について定めたものになる。
一方、一般的な建物賃貸借契約の場合、通常は期間が定められている。アパートや賃貸マンションといった居住用の物件だと、その多くは「2年」だろう。そこで、これに対応するのが次の条文となる。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
民法第618条
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
―――分かりにくいが、こういうことだ。
民法は、賃貸借契約において「期間」が定められている場合、当然ながら、まずはこれを重く見るのだ。すなわち、貸す側も借りる側も「お互いが合意して決めた『期間』をきちんと守りなさい」―――その原則がここでは示されている。
そのうえで、
「当事者の一方、あるいは双方が『期間内でも解約できる権利』を持つことをお互い合意していた場合」(=権利を留保していた場合)
その場合は、当該権利を持つ者の申し出によって、期間内での解約ができることになっている。
さらに、その際は、
「617条の期間に従う」(=前条の規定を準用する)
と、いうことで、
「建物の賃貸借については、解約申し入れの日から3カ月を経過することで、契約期間は終了する」(=3カ月前までに予告せよ)
―――これが結論となるわけだ。すなわち「3カ月」の出どころだ。
よって、さきほどの国交省の事例集が、3カ月の境をもって、
「これよりも短い期間は有効」
「これよりも長い場合、どの程度から不当といえるかは検討云々……」
と、判断を切り分けている理由は、以上に挙げた民法の規定にある。
つまり、アパートや賃貸マンションを貸すオーナーにとって、この3カ月というラインは、安心・安全のラインと言えるものなのだ。民法が認めている線引きであり、それゆえ、あとで「不当だ」と指摘されることはおそらく無いであろう、頼れる基準となるわけだ。
すると、こうも言えることになる。
入居者からの退去予告の通知期間を「1カ月前まで」あるいは「30日前まで」としていることが一般的な多くの建物賃貸借契約は、実は、入居者側にかなり寄り添っている。民法よりも“優しい”線引きで当事者が合意しているかたちとなるため、不当ともならない。
とはいえ、退去予告を受け、次の入居者募集に向けて動き出さなければならないオーナー側の事情を考えると、実のところ、1カ月では時間的にキツいケースも多いはずだ。本来ならば「45日前~2カ月前」くらいが一般的であってもおかしくはないだろう。
ただし、この点、国交省は多くの事業者がひな型とする「標準契約書」に「30日前」を盛り込むことで、事実上これを推奨している。もちろん、このことはオーナーではなく、入居者の保護を優先してのことに違いない。
ちょっと怖い契約?
ところで、その入居者だ。入居者は、上記民法の条文を読んで、以下の点に気付いておく必要がある。
民法第618条にはこのように書かれていた。
「当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する」
これは、裏を返せば、
「一方または双方が『期間内に解約をする権利を留保しなかった』場合は、前条の規定を準用しない」
と、言っていることになる。
つまり、その契約が、一般的な、
「〇年間の契約」(賃貸借の期間が定められている)
であって、
「契約の中に、期間内に解約できる旨の条項が定められていない」
そんな稀(まれ)なかたちになっていると、その契約は、
「契約期間満了まで解約ができない」
ちょっと怖い契約となる。
ましてや、そうした条項が存在しないだけでなく、「入居者は中途解約権を留保しない」旨がひっそり条文に盛り込まれ、念押しされていたりすると、それは本格的に怖い契約だ。
たとえば、2年の契約で、入居後1年で退去しても、入居者は残り1年分の家賃の支払いから逃れられないことになる。
とはいえ、実際にそんな契約が結ばれることはまず無いだろうし、現実に結ばれたとして、それが係争化した際は、司法は、入居者保護の視点に沿った判断を通常の場合、していくことになるだろう。たとえば、消費者契約法による消費者保護のための規定が適用されるなどだ。
だが、とりあえず上記は「怖い」仕組みだ。
弱者・高齢者を狙っての意図的なものなど、悪意が介在するケースも考えられるので、読者はこの機会にぜひ以上のことを覚えておくのがいいだろう。
借地借家法によるオーナーへの縛り
最後に、これも非常に大事なことだ。
さきほども示したとおり、民法に従えば、期間の定めがある建物賃貸借契約にあっては、期間内に解約をする権利を留保した当事者は、3カ月前までの予告をもって、期間内での解約が可能だ。つまり、ここでの対象には、借主=入居者も、貸主=オーナーも含まれる。
しかしながら、現実にはオーナーにこの規定は適用されない。なぜなら、オーナーは、民法に優先するかたちで、借地借家法による別の決まりに縛られることになるからだ。
ひとつは「正当事由」となる。クリアするのがなかなか難しい「正当事由の具備」がなければ、オーナーは入居者に対し、解約の申し入れができない。(借地借家法第28条)
さらには、正当事由が具備され、申し入れが成立するにしても、その賃貸借契約は、申入れの日から6カ月を経過しないと終了しない。(借地借家法第27条)
以上は、この記事で紹介した民法の内容に比べると、より多くのオーナー、あるいは入居者も、すでにご存知のことだろう。
(文/賃貸幸せラボラトリー)
【関連記事】
「退去します」の予告は撤回できない!? 賃貸・知られざる厳しい決まりごと
賃貸・家賃を「値上げします」と言われたら
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室