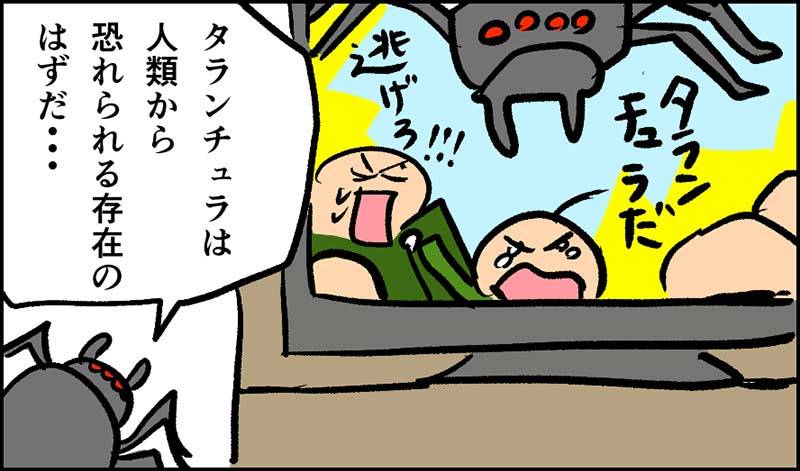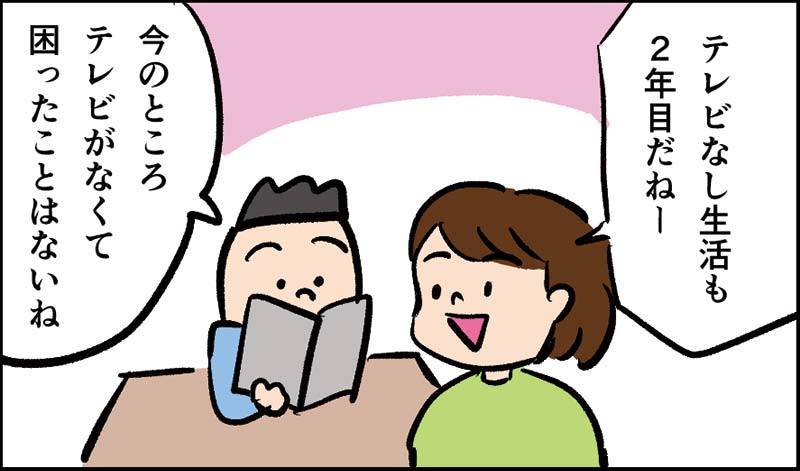コロナ禍によって変わる女と男の関係――コロナ離婚と少子化

2020/06/29

イメージ/©︎imtmphoto・123RF
40を超えて、子どもが欲しいという強い思いに突き動かされて
東京アラートが発動され、コロナ禍が収まらない6月5日、2019年の出生率が発表された。その内容は4年連続低下の1.36、出生数は過去最少の86万5234人になったという。コロナ禍の中ではDV、コロナ離婚など家族のかたちに少なからず影響を与えているようだ。
Nさんは、業界ではトップの規模を誇る企業で働いている。
男性ばかりの職場で、初めて、女性として管理職の座を勝ちとった女傑だが、大企業の肩書を振りかざすこともなくテキパキと仕事をこなし、人望も厚く任される仕事は多い。今の役職に就くまで夢中で頑張ってきたが、2年ほど前から急に孤独を感じ無性に家族が欲しくなった。パートナーと呼べる男性と同棲しているが、今までお互いに結婚など考えていなかった。適度な距離感が心地よく、好きな時に好きなことをする関係が楽だと思っていた。
Nさんは41歳の誕生日に、意を決して結婚の話を持ち出した。結婚して子どもをつくりたいと言うと、相手は結婚してもよいと答えはしたが、今のままの関係でもいいじゃないか、とも言った。彼は、遊び人で、束縛を嫌うタイプだったのでNさんとの結婚にそこまで乗り気ではないようだった。
Nさんは、子どもができれば彼も結婚に前向きになるのではと考えた。悩んだ末に、婦人科に相談することにした。年齢のこともある。自分の身体が子どもをつくれる状態なのか知りたくもあった。血液検査の結果をみて、医師はIさんに自然妊娠は非常に難しいと伝えた。年齢とホルモンの状態を見ると、一刻も早く不妊治療に踏み切るべきだと言った。
Nさんの焦りは加速し、彼氏に近いうちに籍を入れて一緒に不妊治療に取り組んで欲しいと詰め寄った。相手は、驚き、戸惑い、口論の末、急には決められないと言って、マンションを飛び出しその日は帰って来なかった。翌朝は帰宅したが、結婚の話も不妊治療の話もうやむやにされてしまった。
仕方なくNさんは、一人で不妊治療に取り組むことにした。「新しい相手を探す時間はもうない。彼には時間をかけて説明しよう。一生懸命努力している姿を見せればきっと分かってくれるはずだ……」とNさんは思った。
コロナ禍によって、隠していた本音があらわになって
不妊治療は、その性質上パートナーの協力は不可欠であるし、仕事をしながらの通院は男女ともに負担になる。特に女性には、身体的、精神的にキツイものだ。加えて未入籍の状態では書類の手配などで面倒事が増える。
Nさんの苦労は並大抵の物ではなかったが、それでも、忙しい仕事の合間を縫って通院し、渋る相手をどうにか説得して、Nさんは三度の体外授精を受けた。しかし三度とも妊娠には至らず、Nさんの焦りは自分と相手を徐々に追い詰める結果になった。二人の関係は悪化した。コロナウイルスが東京で猛威をふるいだした矢先、相手はそれを理由に田舎に帰ると言って、それきりNさんのマンションに戻ることはなかった。
その後、Nさんはしばらく茫然自失の状態であったが、友人たちに支えられなんとか元の生活を取り戻しつつある。この人しかいないと思い込んでいた相手が去ったことによって、結婚と妊娠の呪縛から解放されたようだ。
緊急事態宣言が解除されて、Nさんは久しぶりに友人と食事をする機会を得た。心配する友人にNさんは「今まで、私も彼も仕事と遊ぶことしか考えてなかったんだよね」と言った。
友人からは、「次の相手はさ、つらい時に寄り添ってくれる人にしなよね」となぐさめられると、Nさんは、「そうだね、そうするよ」と言って、少し寂しそうに笑った。
2019年の出生数は過去最低という発表があったが、不妊治療のために婦人科の門戸を叩く件数は年々増加傾向にあるという。晩婚や晩産化の影響によるところが大きい原因と言われている。しかし、その深層は世の中が豊かになったからではないだろうか。貧しい時は、生存のために団結し、協力して困難に立ち向かわなければならないが、余裕があれば煩わしい共同生活などわざわざしなくとも生きて行くことができる。
現代の日本では結婚は最重要事項でなくなって久しい。豊かになって、人生に選択肢が増えたのだ。喜ばしいことであるはずなのに、増えた選択肢が人を孤立させる。誠に皮肉なことである。植物に肥料を与えすぎると結実しないことがあるが、人間も同じで、余裕があるがゆえに次の世代に子孫を残すことを忘れてしまうのかもしれない。
この記事を書いた人
精神科医
1946年、新潟県生まれ。千葉大学医学部卒業。精神医療の現場に立ち会う医師の経験をもと雑誌などで執筆活動を行っている。著書に『素朴に生きる人が残る』(大和書房)、『医者がすすめる不養生』(新潮社)などがある。