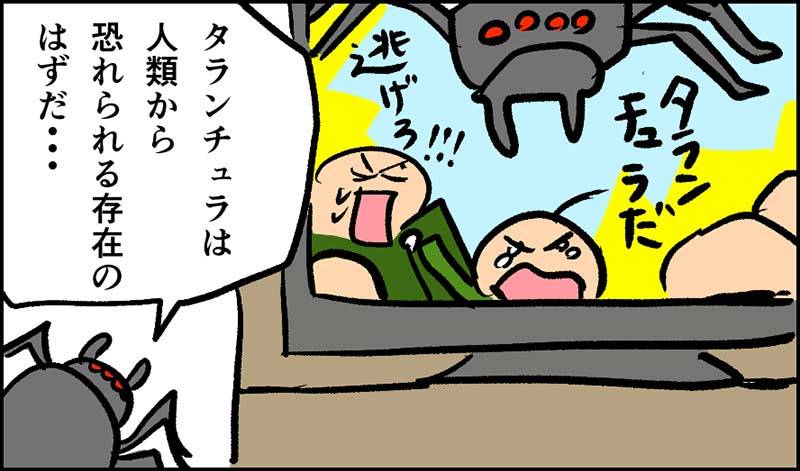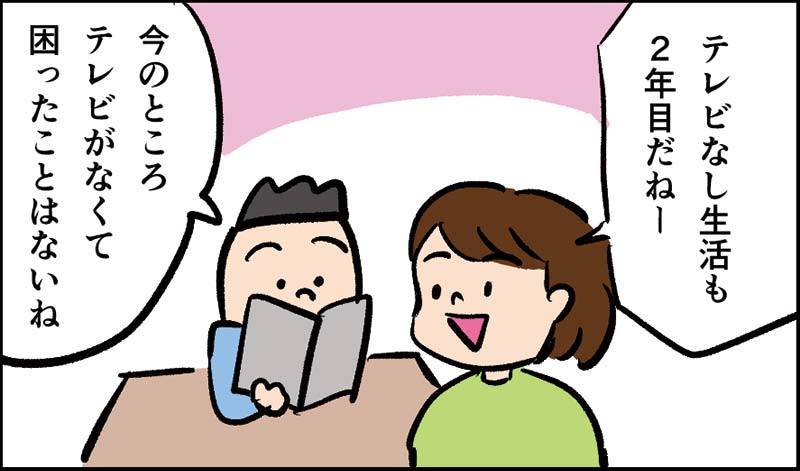まちと住まいの空間 第22回 1世紀ターム変貌する丸の内――高層化と美観論争

2020/04/07

武家地であった丸の内
東京都心部で超高層ビルが立地する場所を見ていくと、単独の超高層ビルはほぼ大名屋敷の跡地だといって間違いない。しかしながら、森ビルが試みた都市再開発の手法のように、台地の大名屋敷地と低地の下級武家地、あるいは町人地とを組み合わせるケースも見られるようになる。前回登場したアークヒルズ、六本木ヒルズがそれにあたる。それでも、種地は大名上屋敷で、アークヒルズが美濃大垣藩戸田家、六本木ヒルズが長門府中藩毛利家であった。
平成6(1994)年に、東京タワーの展望台から東京都心部の光景をパノラマで見た(写真1)。超高層ビルは、まだまばらに点在しているに過ぎなかった。超高層ビルが建つ規模として、1万㎡の土地が必要となる。その点、大名の上屋敷が整然と配置されていた丸の内は、超高層ビルを林立させる土地環境を備えていた。だが、その丸の内に100mを越える超高層ビルが出現する時期は遅く、2002年に竣工した丸ビルを待たねばならなかった。

写真1、東京タワーの展望台から見た東京都心部(1994年)
バブルの時代(1985〜1991年)には、大手建設会社がこぞって300mを越える超高層ビルの構想を東京で描いてみせた。三菱地所も丸の内において、300mを越える超高層ビルを約60棟建てる「マンハッタン計画」を1988年に発表している。この構想はバブル崩壊により、具体化することはなかった。
バブル崩壊後に訪れた日本の経済危機は、東京都心部の超高層ビル化による経済的な活性化に糸口を見つける他なく、丸の内も超高層化の時代を担うことになる。1986年に、皇居側から丸の内をパノラマで撮影した(写真2)。百尺のスカイラインを越えて建つ建物の数は東京海上ビルディング本館(以下「東京海上ビル」、99.7m、1974年竣工)などわずかであった。2019年に、30数年前に撮影した同じアングルで丸の内を撮影すると、凄まじい勢いで超高層ビル化された現状がそこにあった(写真3)。

写真2、丸の内のパノラマ(1986年)

写真3、丸の内のパノラマ(2019年)
丸の内に超高層ビルが建てられる前段階
丸の内におけるビルの超高層化は、1970年代前半の東京海上ビルの出現からである。地形の高低差がほとんどない丸の内は、それまで軒高百尺(約31m)のスカイラインが街の風景全体に統一感を持たせていた。1970年代には、東京海上ビルの他、1973年の三菱ビル、1976年の日本郵船ビルなど、高さ百尺(約31m)を越えるビルも建ちはじめていた。東京海上ビルは、当初127mの超高層ビルが建てられる予定だった。だが、皇居に近いこともあり、景観論争が巻き起こる。景観論争の末に、東京海上ビルの建物高さは100m以下に押さえられた経緯があった(写真4)。

写真4、東京海上ビルディング本館
美観論争が起きる以前、昭和23(1948)年に市街地建築物法施行規則の改正があり、丸の内地区は「当分の間、美観地区既定を適用しない」という適用除外を受けた。昭和25(1950)年の建築基準法制定では、運用条例を別途に定めなければ美観地区を活用できないという縛りも加わる。戦後の丸の内地区は、美観に関して広告物のみが禁止されているだけで、運用条例がなく、身動きが取れない地区指定となっていた。
美観地区指定の適用がなされていない状況下で、100mを超える建物高さの超高層ビルがどうして美観論争に展開したのか。東京海上火災株式会社は、大正7(1918)年に竣工した丸の内の旧本館ビル(設計:曽禰中條建築事務所)を取り壊した後、高さ127mの超高層ビル(設計:前川国男)の建築申請を昭和41(1966)年に出した。これは三井霞が関ビルが建つ2年前のことだった。しかし、東京都側は当時担当した建築主事が建築申請の許可を出さなかった。その対立が世論を巻き込む美観論争となる。皇居に面する丸の内は、スカイラインの保全と高層化に向かう開発が真っ向から衝突した。
では、美観論争が起きる以前の街並みはどうだったのか。昭和30年代なかば、丸の内の建物は戦前の美観地区の指定と建築基準法の高さ制限、さらに地震に対する自己規制が強く働き、「百尺(約31m)」の高さで揃うスカイラインの景観が人々の目を楽しませてきた。そのような時代に、丸の内にある昭和12(1937)年に竣工した国鉄本社社屋(現・ニッセイ・ライフプラザ丸の内・丸の内オアゾ)を建て替え、24階建ての超高層ビルとする構想が持ち上がった。柔構造を導入することで、地震大国・日本でも31mを遥かに越える建物を実現させる可能性が生まれた。国鉄(現JR)は、その後膨大な赤字を抱えていたこともあり、本社社屋をそのまま利用することで落ち着き、実現しなかった。
このことで、超高層ビル建設が具体的に可能となったことから、日本の超高層ビル建設はにわかにリアリティを持ちはじめた。同時に超高層ビル化に向けた法的整備も整っていく。昭和38(1963)年の建築基準法改正では、容積規制の範囲内なら、建築物の高さ31mを超えてもよい法的環境となった。周辺に広い公共空地を確保すれば、斜線制限などの規制を解除する「特定街区」の制度が活用できた。また、より利用勝手のよい「総合設計制度」が後に登場する。美観論争でもめた東京海上ビルの竣工に先立ち、これらの制度を運用して、丸の内周辺では地上17階の帝国ホテル新本館(61m、設計:高橋貞太郎、1983年竣工のタワーは129m)が昭和45(1970)年に、建物高さ約100mの三和銀行が1973年に姿を現した。丸の内のスカイラインが大きく変わりはじめる。
丸の内の超高層ビル建設の時代
平成12(2000)年以降、丸の内の建て替えを促進させた背景としては、現行の容積率(1000%)に文化的な貢献、近代建築の保存などをすることで、容積のボーナスを与えられたことがあげられる。さらに、東京駅の保存再生が具体化しつつある時、東京駅上の余っている容積の売買により、文化的貢献をしなくともより高いビルが建てられるようになった。
丸の内が本格的な超高層ビル群の都市景観に変貌する先駆けは、平成14(2002)年に竣工した丸の内ビルディング(以下「丸ビル」、179m)の建て替えであった。丸ビルの建て替えを皮切りに、その後新丸の内ビルディング(198m、2007年)、大手町のJAビル(280m、2008年)、東京中央郵便局の建物を一部保存したJPタワー(200m、2011年)と、空中権の売買を利用した超高層ビルが次々と建ち、丸の内の都市景観を大きく変貌させていく(写真5)。ただし、お濠端に面して新築した東京会館が入る丸の内二重橋ビルディング(以下「丸の内二重橋ビル」、高さ150m、2018年竣工)は、東京駅に近い側で160m以上の超高層ビルが高さを競うなかで、皇居を意識したのか、高さが抑えられた。

写真5、新丸の内ビルディング
重要文化財である明治生命館の保存とセットに、その背後の超高層ビル化が2004年に図られた。明治生命館を保存して建てられた丸の内マイプラザ(高さ147m)である。2009年には三菱一号館の復元とセットに超高層ビルの丸の内パークビルディング(高さ157m)が建つ。この2つのビルを比較すると、建物高さで10mの違いがある(写真6)。丸の内マイプラザ、丸の内二重橋ビルは建物高さが抑えられており、今後の丸の内における都市景観のあり方に大きく影響する可能性がある(写真7)。

写真6、明治安田生命館と背後の超高層ビル

写真7、お濠端の街並み
丸の内での興味深い試みは、再開発によって一挙に超高層ビルを建設し、都市空間を再構築していないことだ。2002年の丸ビル建て替えから20年近くが経過した。その間に、多くの超高層ビルが誕生したが、建物高さ百尺(約31m)のビルも多く見かける。丸の内は、一世紀のタームで都市空間の更新を考えていると聞く。三菱が主導する丸の内だからこその発想だが、都市景観を時間軸の中で描こうとする試みは興味深い。
建築の超高層化は、技術の進歩とともに高さを増している。7年後には東京駅前常盤橋プロジェクトB棟(390m 、2027年)が300メートルを遥かに超え、11代目の最高高さの新記録ホルダーとなる。東京駅前常盤橋プロジェクトB棟は400メートルに迫る高さに到達し、電波塔の東京タワー(333m 、1958年)を上回る。今から30年以上も前のバブルの時期に、大手建設会社が描いた300mを超える超高層ビルのスケッチが現実のものとなろうとしている。
この記事を書いた人
岡本哲志都市建築研究所 主宰
岡本哲志都市建築研究所 主宰。都市形成史家。1952年東京都生まれ。博士(工学)。2011年都市住宅学会賞著作賞受賞。法政大学教授、九段観光ビジネス専門学校校長を経て現職。日本各地の土地と水辺空間の調査研究を長年行ってきた。なかでも銀座、丸の内、日本橋など東京の都市形成史の調査研究を行っている。また、NHK『ブラタモリ』に出演、案内人を8回務めた。近著に『銀座を歩く 四百年の歴史体験』(講談社文庫/2017年)、『川と掘割“20の跡”を辿る江戸東京歴史散歩』(PHP新書/2017年)、『江戸→TOKYOなりたちの教科書1、2、3、4』(淡交社/2017年・2018年・2019年)、『地形から読みとく都市デザイン』(学芸出版社/2019年)がある。