新設住宅着工戸数80万戸割れ。リーマン・ショック直後並みの低い数字に
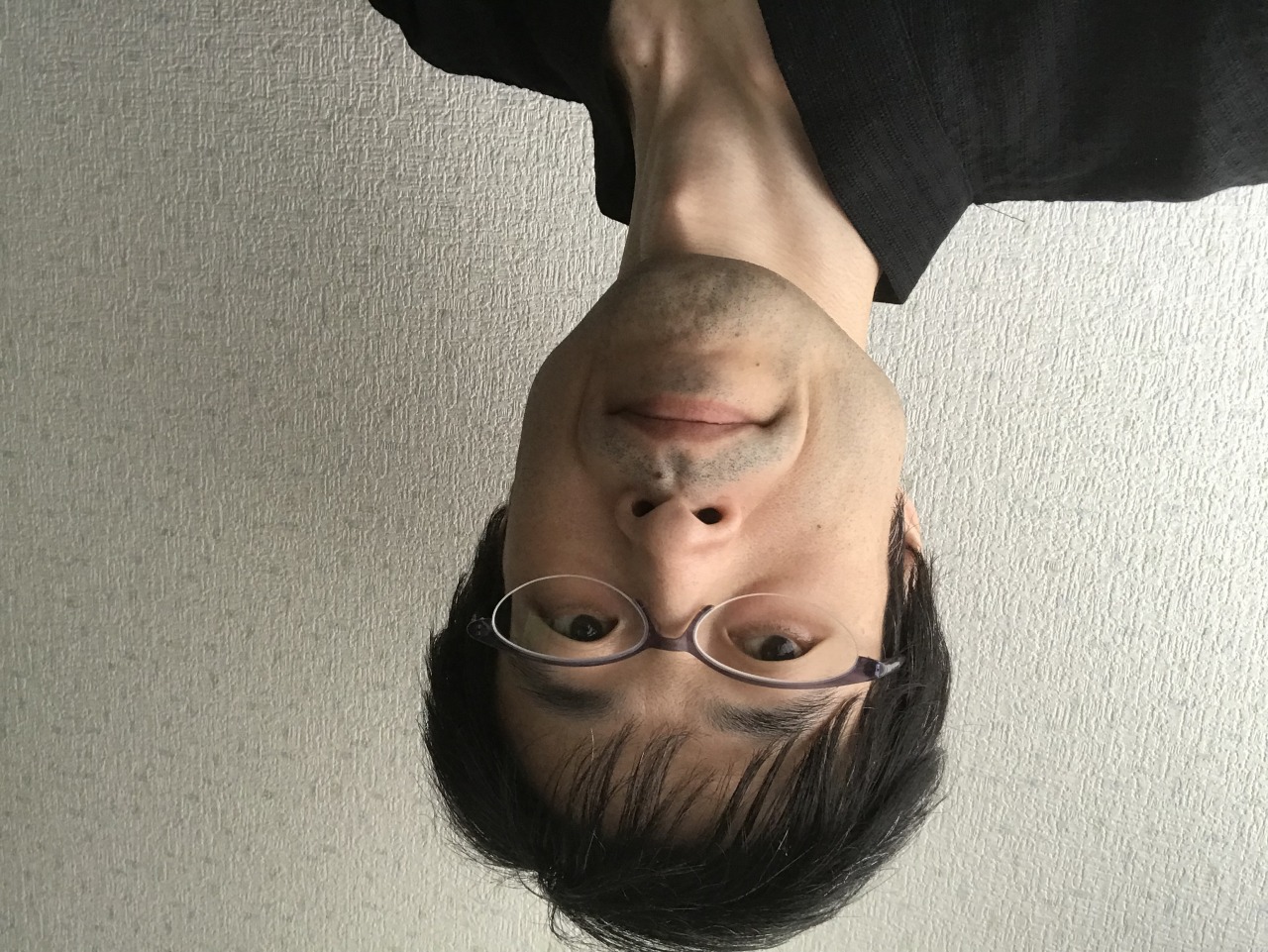
2025/02/13

「建売氷河期」も数字に反映
この1月末、国土交通省が「建築着工統計調査報告」の令和6年(2024)計分を公表している。内容をいくつかピックアップしていこう。
まずは、新設住宅着工戸数の総計だ。79万2098戸となった。前年比3.4%の減。2年連続の減少だ。
さらに、80万戸割れはリーマン・ショックの翌年09年以来のこと。利用関係別には以下のとおりとなっている。
| 種類 | 新設住宅着工戸数 | 前年比 | 備考 |
| 持ち家 | 21万8132戸 | 2.8%減 | 3年連続の減少 |
| 分譲一戸建て | 12万1191戸 | 11.7%減 | 2年連続の減少 |
| 分譲マンション | 10万2427戸 | 5.1%減 | 2年連続の減少 |
| 貸家 | 34万2044戸 | 0.5%減 | 2年連続の減少 |
見てのとおり、いずれも前年比は「減」。そのうち、分譲一戸建ての数字がやや突出したかたちとなっている。以下は、同数字のここ6年間の状況だ。
| 年 | 戸数 | 前年比 |
| 19年 | 147,522戸 | +3.6% |
| 20年 | 130,753戸 | -11.4% |
| 21年 | 141,094戸 | +7.9% |
| 22年 | 145,992戸 | +3.5% |
| 23年 | 137,286戸 | -6.0% |
| 24年 | 121,191戸 | -11.7% |
このとおり、20年と昨年がともに落ち込みの顕著な年となっている。なお、前者は「コロナ禍」の年だ。その翌年からの回復を経て、再び23年、昨年と、数字は大きく下がっている。
ちなみに、昨年は「建売氷河期」なる言葉が住宅業界内の一部に飛び交った年でもあった。上記は、そんな印象どおりの推移が示されたものといえるだろう。
なお、建売―――分譲一戸建て市場が冷え込んだ理由としては、直近の需要増(上記では21、22年の数字に表れている)からの反動、価格の上昇による低所得者世帯の顧客離れ等、いくつかの要因が指摘されているところだ。
消費税が直撃した過去と、ここ2年の重苦しい数字
冒頭にも触れたとおり、昨年における新設住宅着工戸数の総計「80万戸割れ」は、リーマン・ショックの影響が著しかった09年以来のこととなる。
以下に、08年以降の推移を掲げてみる。
| 年 | 戸数 | 前年比 | 備考 |
| 08年 | 1,093,519戸 | +3.1% | 9月にリーマン・ショック発生 |
| 09年 | 788,410戸 | -27.9% | リーマン・ショックの影響 |
| 10年 | 813,126戸 | +3.1% | |
| 11年 | 834,117戸 | +2.6% | |
| 12年 | 882,797戸 | +5.8% | |
| 13年 | 980,025戸 | +11.0% | 日銀による金融異次元緩和 |
| 14年 | 892,261戸 | -9.0% | 4月に消費税率引き上げ |
| 15年 | 909,299戸 | +1.9% | |
| 16年 | 967,237戸 | +6.4% | |
| 17年 | 964,641戸 | -0.3% | |
| 18年 | 942,370戸 | -2.3% | |
| 19年 | 905,123戸 | -4.0% | 10月に消費税率引き上げ |
| 20年 | 815,340戸 | -9.9% | 1月に国内で感染者確認・コロナ禍始まる |
| 21年 | 856,484戸 | +5.0% | この年後半から国内物価上昇 |
| 22年 | 859,529戸 | +0.4% | |
| 23年 | 819,623戸 | -4.6% | |
| 24年 | 792,098戸 | -3.4% | 実質賃金3年連続マイナス |
このとおり、リーマン・ショックの暴風が吹き荒れた09年における極端な数字を除いては、目立つ下落の年として14年と20年が挙げられる。それぞれ前年比9%以上となる大幅な「減」だ。
そのうえで、両者に共通するキーワードがある。それは「消費税」だ。
ちなみに、20年は繰り返すが「コロナ禍」の年だ。しかしながら、ここでの-9.9%という大きな減少幅の理由は、おそらくそれだけではない。いま思えば、前年に引き上げられた消費税率との合わせ技によるものだった可能性がどうも高そうだ。(つまりコロナが無くともかなりの数字が出ていた?)
なお、消費税率の引き上げは、時の政権の生死を分かつ「鬼門」とよくいわれる。だが、それ以上のものとして、わが国経済への負のインパクトはやはり大きいといえるのかもしれない。
一方、昨年の数字だ。一昨年から連続しているその下落幅は、上記、消費税増税の絡んだ年には及ばないが、大きいといえば大きい。
関連が思い浮かぶものとして、3年続いている実質賃金のマイナスをカッコ書きのとおり挙げておいた。
建築費高騰を表す「減」と「増」
24年における、全建築物の着工床面積は1億273万9千平方メートルとなっている。前年比7.6%の「減」だ。
一方、同じく建築物全体における工事費予定額は29兆2420億円で、こちらは前年比2.4%の「増」となっている。
つまり、面積は結構な割合で減ったが、工事費用は増えたということで、要は前年よりも平米当たりの単価が上がっている。建築費高騰が叫ばれる現状が、端的に示されたものといえるだろう。
なお、以上のことは、用途別に居住用、非居住用、いずれの建物にあっても変わらない。以下のとおりだ。
| 種類 | 着工床面積 | 前年比 | 工事費予定額 | 前年比 |
| 居住用建築物 | 6353万9千平方メートル | -6.2% | 16兆2210億円 | +0.9% |
| 非居住用建築物 | 3920万平方メートル | -9.8% | 13兆210億円 | +4.3% |
こうした建築費高騰の背景には、資材価格に加え、人件費、物流コスト等、さまざまな価格・費用の上昇や高止まりがある。すなわち、支える要因が多様な総合的結果といえるものなので、予期せぬ大きな経済的変動が起こらない限り、傾向はさらに続きそうだ。
15年後の新設着工は現在より3割近く減
有名シンクタンクのひとつ、野村総合研究所(NRI)は、昨年6月のリリースで「2040年度の新設住宅着工戸数は58万戸に減少」との予測を立てている。
前出、昨年(年度ではない)の数字に対しては約73%となり、要は3割近くの“激減”だ。もちろん、このことの基礎部分には、わが国の人口も激減していく現実がある。
一方、建物を生む「新築」に対し、最期を看取る「解体」に関しては、昨年5月公表の国交省の統計にこんな数字が挙がっている。(建設業許可業者の現況 令和6年3月末現在)
| 年 | 3月末現在の業者数 |
| 21年 | 60,926 |
| 22年 | 62,691 |
| 23年 | 65,138 |
| 24年 | 67,525 |
見てのとおり、こちらは縮小していく市場に対して、現在拡大傾向にあるとされる市場の姿を表すひとつのデータとなっている。
以上、国交省「建築着工統計調査報告」令和6年(2024)計分の内容は、下記リンク先にて確認いただける。
「国土交通省 建築着工統計調査報告 令和6年(2024)計」
(文/朝倉継道)
【関連記事】
地価LOOKレポート2024年第3四半期 全地区上昇が3期連続
去る人に理由を聞こう。賃貸・退去時アンケートのススメ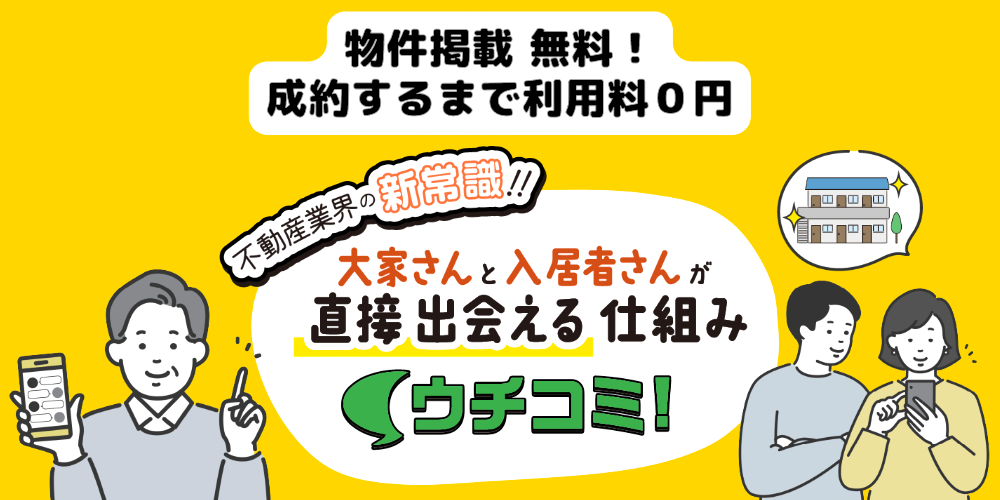
無料で使える空室対策♪ ウチコミ!無料会員登録はこちら
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。





















