牧野知弘の「どうなる!? おらが日本」#18 アフター・コロナで躓く オフィスビルマーケット
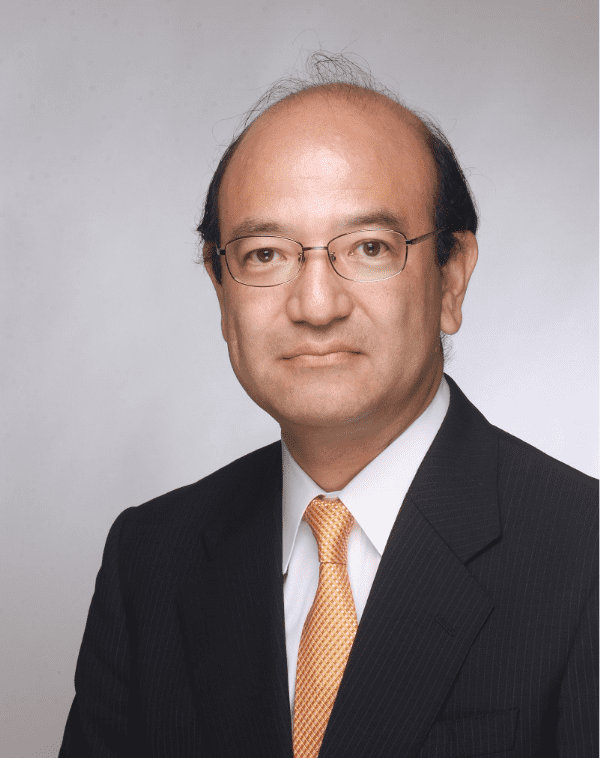
2020/10/16

イメージ/©︎paylessimages・123RF
コロナ禍がもたらすレヴォリューション
コロナ禍による不動産マーケットへの影響については、ホテルなどの宿泊産業や商業施設の惨状が報告された。だが、ホテルも商業施設も、新型コロナウイルスという感染症が収束すれば、回復までに時間を要しながらも持ち直していくものと考えられる。人が移動をする、食料品やモノを購入するという行動は、一部カタチを変えても残っていくものだからだ。したがってこれらの業界に属する会社は感染症克服までの我慢比べが生き残る唯一の戦術だ。
ところが一連のテレワークを通じて、多くの勤労者が通勤をせずとも、かなりの仕事ができることを知ってしまったオフィスのあり方については、今後大きなマインドシフトが生じてくる。日本人の働き方は、政府が唱えてきた働き方改革など及びもつかない、「働き方革命」をもたらした可能性が高いからだ。
オフィスビルマーケットは五輪が開催される予定の東京都区部のみならず、名古屋、大阪を加えた三大都市圏から地方四市(札幌、仙台、広島、福岡)のマーケットも2020年前半まで絶好調をキープしてきた。たとえばコロナ前の20年2月、各エリアの空室率は東京(都心5区)で1.49%。名古屋2.21%、大阪1.94%と極めて低い水準が保たれていた。この傾向は地方都市も全く同じで、同時期のデータを拾うと、札幌1.62%、福岡2.29%など軒並み2%台以下の水準にある。
オフィスの空室率は一般的には4%が貸手、借手の分水嶺と言われる。つまり4%を超えると賃貸借の条件交渉などでは俄然テナント側が優位に立てる、4%を切るとビルオーナー側が強気になる、そんな水準が4%なのだ。
この物差しでみると、日本の主要都市はどこもオフィスは貸手市場ということになり、テナントはほぼ身動きができない状況に陥る。つまりあるテナントが業容拡大などで、もっと広い大きなビルに借り換えようと思っても、マーケットには適当な物件がないという状況を物語っているのだ。
ドワンゴは在勤恒久化 富士通はオフィス半減
ところが今回のコロナ禍では、すでに業務の大半をテレワーク化して、余分となったオフィス床を減らしていこうという動きが一部で顕在化しはじめている。富士通は23年度までに賃借オフィスの面積を半減させると発表した。ドワンゴは在宅勤務を恒久化するという衝撃的な発表を行った。そのいっぽうで、こうした素早い動きをしているのは、東京の渋谷などにオフィスを構えている新興系のIT企業の動きであって、オフィスマーケットそのものに深刻な影響を及ぼすものではないとの見方もある。

7月6日、2023年までにオフィスの規模を半減すると発表した富士通/©︎tktktk・123RF
さらに一部のデベロッパーからは、コロナ禍が過ぎ去れば、オフィスにはコロナ前と同様に社員が出勤するようになる。それどころか企業は、従業員の感染リスクを極小化するために社員同士のソーシャルディスタンスを保たなければならないので、社員間の机を2メートル以上離すことが必要になる。だからオフィス床を増床するだろうとの楽観的な観測まで出ている。
だが現実、多くの企業では、社内の部署ごとにテレワークができる部署、できない部署に分け、社員の勤務体制をシフト勤務にしていくのが、これからの大きな流れになっている。そして肝心なのはこうした動きがコロナ禍における特別な態勢ではなく、ポスト・コロナ時代においての「通常の勤務体制になる」ということだ。これからは社員の人数分の机や椅子を用意せずにすむことから、オフィス床を極限まで小さくすることができることになる。オフィス賃貸料は企業にとって、人件費に次ぐ重たい固定費である。コロナ禍で業績を落とす企業が多い中で、デベロッパーの思惑通りにオフィス床を唯々諾々と増床するような余裕のあるテナントは少数だろう。ということは、今後オフィスをスリム化する動きは顕著になってくるものと思われる。
人々の働き方の形態そのものが今回のコロナ禍を契機に大きく変わる可能性があるというのが、ポスト・コロナにおける重要な視点なのだ。そうした意味では「結局もとに戻る」という意見は、コロナ禍は一過性の感染症にすぎず、働き方そのものには大きな変化は生まれないという前提に立っていることになる。しかし、そう言っている多くの人たちは実は古くから存在する大企業の役員たちに多いようだ。世の中の変化に鈍感なのは古くて組織の大きな企業の特徴でもある。

コロナ禍により、政府が唱えてきた働き方改革など及びもつかない、「働き方革命」がもたされた/©︎ponsulak・123RF
都心5区 1カ月で2万4000坪の空室
オフィスビルマーケットは、実体経済の好不調に約半年遅れて影響を受けるといわれている。通常の賃貸借契約は、解約する場合には6カ月前に予告をしなければならないので、実際に解約となって空室にカウントされるのは6カ月先になるからだ。また大規模ビルに入居するテナントの多くは定期借家契約で3年から5年の比較的長期の契約を結んでいるところが多い。こうした状況から考えると、オフィスマーケット悪化の予兆が表れてくるのは今年冬以降からになりそうだ。
だがすでに兆候は表れだしている。20年8月の三鬼商事のオフィスマーケットデータによれば、東京都心5区の空室率は3.07%に跳ね上がってしまったのだ。この数値は対前月比で0.3%の上昇だ。三鬼商事のデータベースでは0.1%はおおむね8000坪相当だ。したがってわずか1カ月で2万4000坪相当の空室がエリア内で発生したことになる。これは新宿にある55階建ての超高層ビル新宿三井ビルのオフィステナントがすべていなくなってしまったことに匹敵する。たかが0.3%ではなくこの上昇傾向の速さは大いに気になるところだ。
日本総研の予測では企業従業員の1割がテレワークになった場合、東京都心5区の空室率は15%近くに急上昇し、平均賃料も約2割下落するとしている。これはやや極端な予想にも見えるが、少なくとも分水嶺の4%はそう遠くない時期に突破してもおかしくないと思ったほうがよさそうだ。
気を付けたいのは、やはり人々のマインドがコロナ前とコロナ後では大きくチェンジしたことにある。これまでのいわば常識であった働き方が実は違うのだ、違ってもよいのだ。通勤なんてしなくても仕事はできたんだ、という気付きをオフィスで働くほぼ全員が「共有化」できたところにある。また学生に対するリクルーティングでもこれまでは「渋谷のオフィスで働く」というのは大いなる宣伝効果があったのだが、渋谷のような「密」な場所に毎日通勤することのリスクを避ける気持ちが強くなれば、そもそも渋谷にオフィスを構えることの意味が失われることになるのだ。
ポスト・コロナ 都心の在り方が変わる
ポスト・コロナ時代において、オフィスはその役割をずいぶん変質させていくのではないか。これまでは全員がひとところに集まって仕事するということが社員たちの意欲を促し、労働生産性を高めるものと考えられてきた。ところが実際にはオフィス床というものが、必ずしも働く場として必要なものではないと分かった瞬間、オフィスの存在意義を問い直されたのがこのコロナ禍だ。オフィスはただ単に時折、社内外の人と会って互いの存在を確認しあうだけの場になっていくことになりそうだ。
これからの多くの企業は一部のヘッドクォーターのみを残して、組織は限りなくバーチャル化していくものと思われる。このようになると、現在都心部で大量に供給されているオフィス床は、無用の長物と化していくことが容易に想像される。あらかじめ各社員の役割が明確に決まっているような事業であれば、オフィスという存在なくしても、事業は十分回っていくからだ。
一方、いくらネット上でつながっているからといって、全員がオンライン上だけですべての事業を遂行していけるとも思えない。そうした意味で、一部の職種ではオフィス床が必要であることに異論はない。
ただ、ポスト・コロナは、都心部の在り方を確実に変えていくことだけは間違いがなさそうだ。多くのオフィスは郊外などのコワーキング施設や企業が独自に展開するサテライトオフィスになっていくだろう。そうしたオフィスは何も高層ビルである必要もない。高層ビルがステータスであった時代はすでに過ぎ去っているのだ。郊外の自然豊かなオフィスで働くのが普通の働き方になってくるだろう。

ポスト・コロナでは都心の在り方そのものが変わる可能性がある/©︎tobusora・123RF
単純な事業企画の方程式は成り立たない
ポスト・コロナ時代は多くのオフィスで集中から分散へと流れが変わってくる。賃料についてもこれまでは丸の内や大手町ならば坪5万円、六本木なら4万円など、ビルオーナーは、立地さえ確保すれば賃料は自動的に決定されるものと考えてきた。だからそうした土地をまず押さえることがビル業の第一歩だった。
三菱地所が丸の内や大手町を、三井不動産が日本橋を、森ビルが六本木を手放さないのは、その地を押さえていることにオフィスとしての価値があったからだ。
しかし、これからはオフィス立地についてそれほど単純な方程式は成り立たなくなってくる。都心部の良い立地に土地を押さえれば、まずはオフィスにして坪あたり賃料5万円とって事業は成立、あとは容積率の割り増し分でホテルや美術館を組み込んで、はい出来上がりといった単純な事業企画では勝負が難しくなってくるのだ。
ポスト・コロナはオフィス大変革時代の幕開けなのである。

『不動産激変——コロナが変えた日本社会』牧野知弘 著・祥伝社新書 刊 定価880円+税
新型コロナ騒動の収束後、不動産の世界は激変し、まったく違う姿になっている。社会が変われば不動産も変わる。その構図を明らかにし、業界の明日を大胆に予測する!
この記事を書いた人
株式会社オフィス・牧野、オラガ総研株式会社 代表取締役
1983年東京大学経済学部卒業。第一勧業銀行(現みずほ銀行)、ボストンコンサルティンググループを経て1989年三井不動産入社。数多くの不動産買収、開発、証券化業務を手がけたのち、三井不動産ホテルマネジメントに出向し経営企画、新規開発業務に従事する。2006年日本コマーシャル投資法人執行役員に就任しJ-REIT市場に上場。2009年オフィス・牧野設立、2015年オラガ総研設立、代表取締役に就任。著書に『なぜ、町の不動産屋はつぶれないのか』『空き家問題 ――1000万戸の衝撃』『インバウンドの衝撃』『民泊ビジネス』(いずれも祥伝社新書)、『実家の「空き家問題」をズバリ解決する本』(PHP研究所)、『2040年全ビジネスモデル消滅』(文春新書)、『マイホーム価値革命』(NHK出版新書)『街間格差』(中公新書ラクレ)等がある。テレビ、新聞等メディアに多数出演。
























