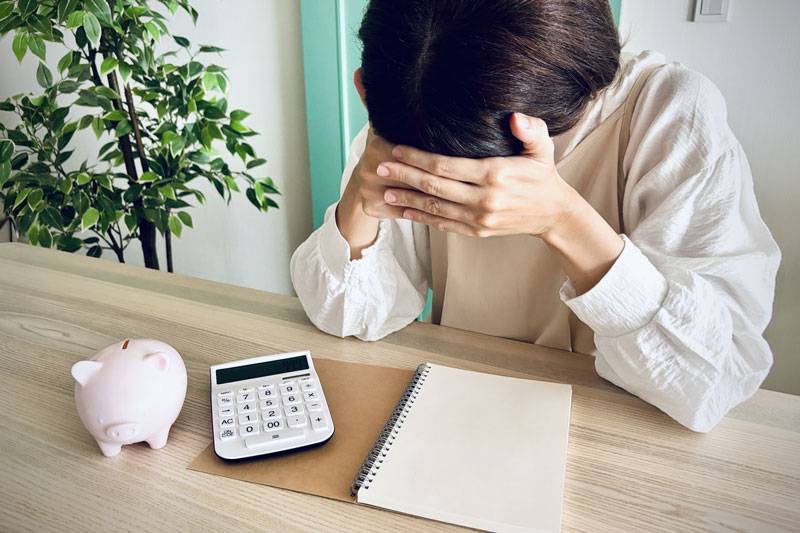非弁行為と賃貸住宅管理会社 業界が抱く不安とは?

2025/11/15
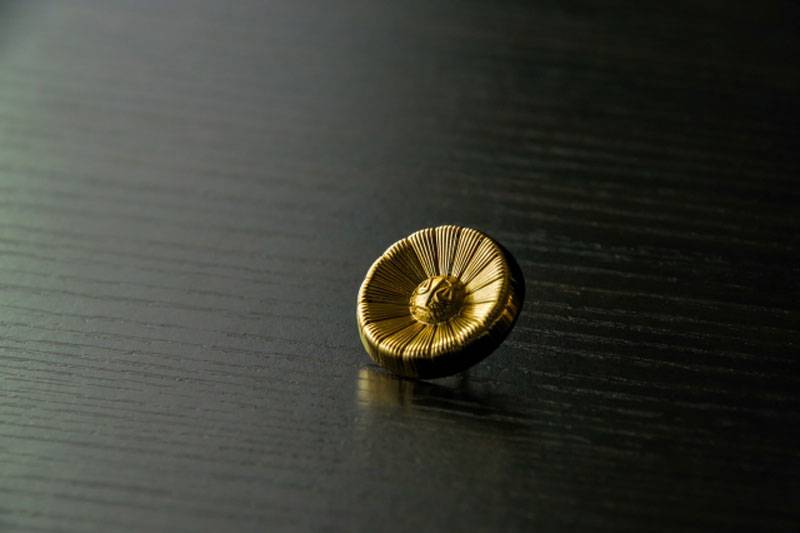
退職代行サービス会社に「非弁行為」の疑い
先月半ば過ぎのこと。「非弁行為」という、一般にはあまり知られない言葉がニュースに採り上げられ、広く報道された。
10月22日、警視庁保安課が、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスおよび関係先に対し、100人体制と報じられたものものしい陣容で家宅捜索に入った。
容疑は弁護士法違反となる。同社の行っていた事業の中に「非弁行為」さらには「非弁提携」と呼ばれる実態があったとの疑いが持たれている。
このうち、非弁行為とは、法律上、弁護士でない者がやってはいけない行為を指す。
非弁提携とは、非弁行為をしている者から、弁護士が事件―――法律事件とそれに関わる法律事務―――の紹介を受けることなどを指す。
そこで、これらをあてはめると、以下2つの点で、モームリおよび関係先に対し、違反の疑いがかけられていることが推測される。
(1)モームリ(株式会社アルバトロス)自身が、非弁行為をしていた疑い
勤めている会社からの退職を希望する客、すなわち依頼者に関わる法律事務を弁護士にあっせんし、取り次ぐことで、報酬(紹介料)を得ていたのではないか。たとえば、未払いとなっている残業代の請求交渉など。
(2)関係先である弁護士事務所(2カ所と報道されている)が、非弁提携を行っていた疑い
モームリ側から上記の紹介を受け、これに対し報酬を支払っていたのではないか。
ちなみに、上記報酬の支払いについては、モームリ側が実態のない労働組合をつくり、そこへの賛助金名目で行われていたとの証言も出ている。事実とすれば、これは当然ながら非弁行為を隠す目的のものと見られることになるだろう。
昨今、話題の退職代行サービスの業態にするどいメスが入ったともいえるこの一件、同業他社、企業の人事担当など、今後の展開に注目している人は多いはずだ。
非弁行為と賃貸住宅管理会社
ところで、以上の非弁行為・非弁提携だが、このうち非弁行為について、これを規定するのは弁護士法第72条となる。こう書かれている。
「(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
見てのとおり、条文後半に「これらの周旋をすることを業とすることができない」とある。今回、モームリが実行を疑われている行為は、報じられているとおりならば、この部分に該当する。
すなわち、法律事件に関わる法律事務を弁護士にあっせん(周旋)し、その見返りとして紹介料(報酬)を受け取ることを反復継続して行っていた(業としていた)―――との疑いだ。なお、周旋を受けた弁護士は、弁護士法第27条などの違反となる。
一方、これ以前のこととして、上記72条は、弁護士でない者が法律事件に関わる法律事務を自ら行うこと自体をそもそも禁止している。条文前半のとおりだ。
そこで、モームリはこれを避けるために、弁護士と提携したものと思われる。
なぜなら、勤務先からの退職を希望する依頼者の意志を会社側へ伝えるだけであれば、弁護士法違反とはならないはずだが、そこにはどうしても交渉ごと、すなわち法律事件に関わる法律事務が絡んできやすい。
そのため、モームリとしては、その部分を外部の弁護士に任せるかたちをとってはいたものの、その際に自社の収益が生じる仕組みをそこに置いてしまった。
これが、結局のところ避けたかったはずの弁護士法違反となり、警察による大規模な捜索を招いた様子がうかがえる。
そのうえで、一般的には、非弁行為の例として挙げられるのはどちらかというとあとに述べた方だ(条文前半の方)。たとえば、
「弁護士でない者が、頼まれるたびに、報酬と引き換えに借金の取り立てを行っている」
―――いわゆる取り立て屋だ。非弁行為の典型的な一例となる。
すると、こんなケースはどうだろう。
「賃貸住宅の管理会社が、オーナー(大家)から頼まれ、家賃を長く滞納している入居者と会い、滞納家賃や今後の家賃の支払い、契約の継続等について交渉する」
実は、この行為にあっては、非弁行為と見られる可能性が少なからずある。
「いやいや、管理会社の業務としてこれは普通のことではないか」
オーナーの多くはそう思うかもしれないが、これを先ほどの弁護士法第72条に照らすと、問題点があきらかに浮かび上がってくる。
- 弁護士ではない「管理会社」が
- 家賃の滞納という「法律事件」にかかわって
- 交渉等「法律事務」を行うことを
- 管理料等、すなわち報酬を受けての反復継続される「業」として
―――行っていることになるからだ。
では、次はどうだろう。
「オーナーから依頼を受けた管理会社が、入居者に会い、物件からの立ち退き交渉を行う」
答えは同じだ。こちらも非弁行為となる可能性がある。
次はどうか。
「家賃を値上げしたいオーナーの依頼を受け、管理会社が、その納得を得るため入居者と交渉、協議する」
実は、賃貸住宅管理会社が行っている業務のうち、仮に法的な争いとなれば、管理会社が非弁行為を疑われ、弁護士法違反に問われる可能性があるものは結構多いといわれている。
ほかにも、退去時の原状回復の際のトラブルにかかわる仲裁等々、たしかにそういわれてみれば―――と、いったかたちになるわけだ。
ちなみに、そこでの法的な判断としては、当該オーナーから管理会社に渡っている、主には管理料、あるいはその他の金銭につき、これがどういった業務の対価と認められるかが、大きなポイントになると想像される。
ゆえに、管理契約の具体的内容も重要な論点となるだろう。
加えて、実際にどんな交渉が管理会社と入居者との間で行われたか、あるいは普段行われているのか、その実態など。
非弁行為が認定されるか否かについては、これら個別の実情に照らして、一律ならざるかたちで判断されることになると思われる。
よって、仮に、管理会社の上記行為やこれらに類する行為に対し、そのたびごとの成功報酬が支払われているような場合、管理会社が厳しい立場に置かれる可能性はかなり高いといえそうだ。
そろそろ区分けが必要?
以上、退職代行サービス「モームリ」運営会社などへの家宅捜索のニュースを入り口に、普段、業界内でもあまり話題にのぼらない件を採り上げてみた。
もっとも、あまり話題とならないのは、もっぱら賃貸管理―――不動産業界側においてのことだろう。弁護士側は多分そうでもない。
「賃貸管理の仕事は弁護士法の観点からグレーだ」「これまで大きな議論にならずに来ただけのこと」
これらは時折、聞かれる声となっている。
ともあれ、いえることは、賃貸住宅オーナーは知らずに管理会社に対し、非弁行為が疑われる仕事を頼んでしまい、それが実際に違法性を認められる可能性が「実はある」ということだ。パートナーをあやうい立場に追い込む結果となりかねない。
現状、そういったことが大きく問題化した例はあまり聞かないが、理屈は述べたとおりだ。知識のひとつとして、おさえておくのがよいだろう。
加えて、そろそろ整理も必要かもしれない。賃貸住宅管理業は、ご存じのとおり近年国の登録業務となった。業態がいわば公的に確立した。
そのうえで、今後、同業界と弁護士の方々との間で、非弁行為の範囲にかかわる実態に即したかたちでの折り合いがつけば、それは多くにとって幸いといえるだろう。
もっとも、これはおそらく難しい課題のはずだ。(自動車保険会社が行うことを許されている示談代行のようにはスムースに切り分けられないのではないか―――理由は割愛)
それでも、進展がいくらかでもあれば、よく勉強している管理会社ほど自らの仕事に不安を感じてしまう現状をあらためていけることになるはずだ。
(文/賃貸幸せラボラトリー)
【関連記事】
賃借物の一部使用不能による賃料の減額などにかかる裁判例の動向
大麻密売グループと仲介会社スタッフが管理会社を騙した! 罰則が強化されている大麻事犯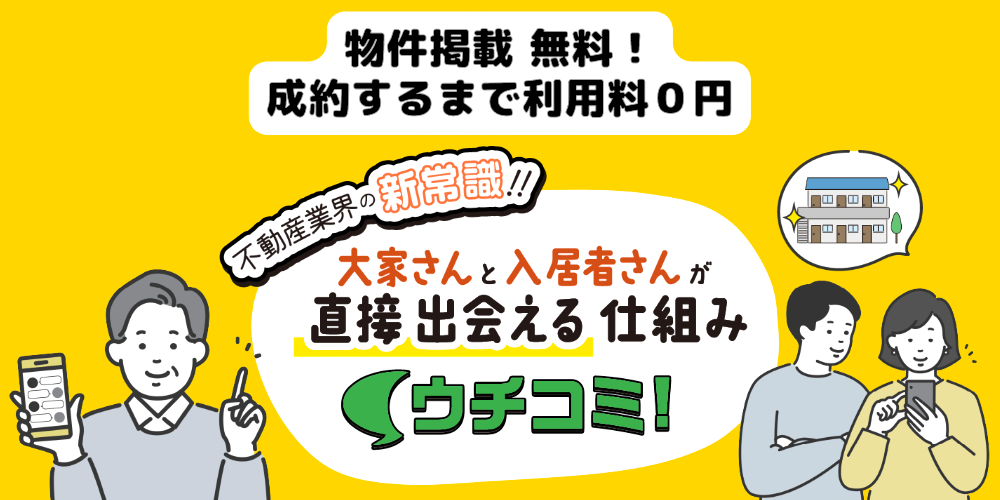
無料で使える空室対策♪ ウチコミ!無料会員登録はこちら
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室