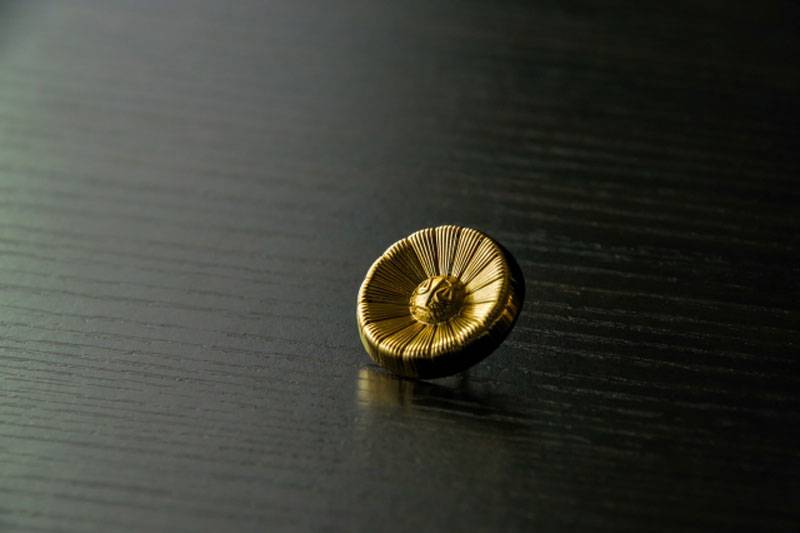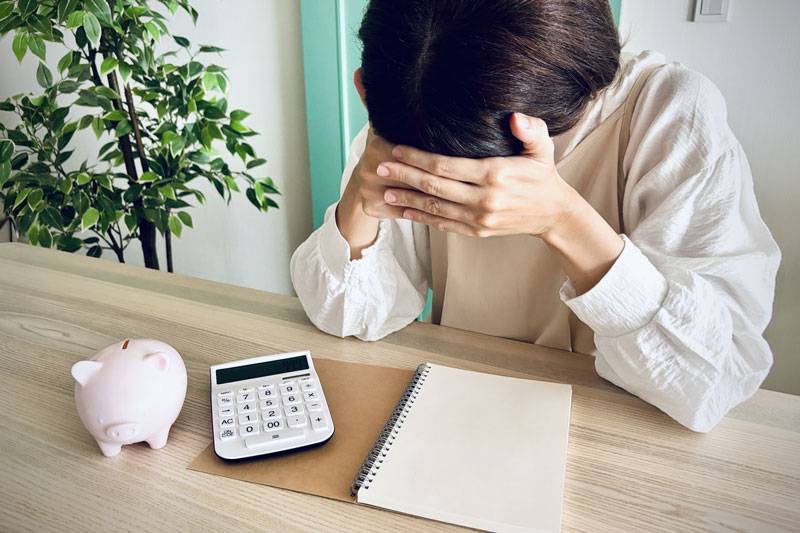賃借物の一部使用不能による賃料の減額などにかかる裁判例の動向

2025/10/18

地震や豪雨、台風など自然災害が猛威を振るう昨今、こうした天災によって賃貸建物の一部が滅失・損壊してしまった場合に、当該賃貸物件を取り巻く当事者間の関係が如何に規律されているのか、という点について、十分な知識を持っている方は必ずしも多くないのではないでしょうか。
今回は、賃借物の一部が、滅失などによって使用不能になった場合の賃料の減額について規定した民法(以下法令名略)611条1項について、令和2年4月1日より施行された同条項とその改正趣旨を概説するとともに、賃借物の一部使用不能による賃料の減額などに係る裁判例の動向について紹介します。
改正611条1項について
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第611条
1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
平成29年改正前の旧611条1項は、賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人はその滅失した部分の割合に応じて賃料の減額を請求することができると規定していました。
しかし、賃貸借は、継続的給付をその目的とする性質から、賃貸人が賃借人に使用収益させる義務を履行するのに応じて、その対価として、賃借人の賃料支払義務が時々刻々と発生するものであり、賃貸借の目的物を使用収益することができない状態になった場合は、その期間は賃貸人の使用収益させる債務の履行がされていないのであるから、その対価である賃料債権も発生していないと考えられます。
そのため、賃借物の一部滅失の場合に限らず、より広く使用収益をすることができない場合一般について(一部滅失以外の事由によって同様の状態が生じている場合として、例えば、2階建ての建物を賃借している場合に、災害によって1階部分が浸水して使用収益できなくなっている場合などが挙げられます。)、賃借人による賃料減額の請求の有無にかかわらず、当該一部分の賃料が当然に減額されることとされました。
「賃借物の一部が…使用および収益をすることができなくなった場合」とは
では、「賃借物の一部が…使用および収益をすることができなくなった」場合として、賃料の減額が認められるのは、具体的にどのような場合なのでしょうか。
裁判例は、賃借物が一部滅失はしていないものの、使用収益ができなくなった場合に、賃貸借契約の目的を達成することができないほどに使用収益ができなくなっているか否かについて判断しています。
具体的には、天井や壁からの雨漏り(裁判例①・名古屋地判昭和62年1月30日)、トイレからの漏水とそれに伴う部屋全体へのカビの発生・増殖(裁判例②・東京地判平成17年8月30日)、窓の破損によるすきま風と騒音の侵入(裁判例③・東京地判平成18年9月29日)、換気扇の不具合や便器の取付け部からの汚水の漏れ(裁判例④・東京地判平成23年12月15日)などの事例において、いずれも建物の一部が使用収益できない状態にあったことを認め、賃料の減額を認めています。
一方で、エアコンの不具合や備品の軽微な不具合(裁判例⑤・東京地判平成15年6月6日)、照明器具や換気扇の故障(裁判例⑥・東京地判平成15年7月28日)の事例では、修繕費用が軽微であること、居住の不便さを与えたことは否定できないが、使用収益が一部不能であったとまではいえないことなどを理由に、賃料の減額を否定しています。
賃料減額の割合
では仮に、建物の一部の使用不能が認められ、賃料減額が認められる場合、その減額金額はどのように定められるのでしょうか。
減額される賃料額について判断した裁判例をみると、雨漏りによって使用不能となった面積分の按分を考慮して減額幅を決めた事例(裁判例①)や、使用不能状態を生じさせている要因が「本件建物の使用収益に及ぼす障害の程度」を考慮要素とした事例(裁判例③、裁判例④)、「カビによる被害などは、賃借人においてもっと防止に努力すれば、より軽減された可能性のあること」「被告A(賃借人)には本件カビの発生を知ったときから、これに対する防除の措置をとることが可能であり、またこれを期待し得たこと」、「本件カビの拡散には被告Aの対応の不備も与っていると思われること」といった被害防止可能性をも考慮に入れた事例(東京地判平成6年8月22日、裁判例②)など、賃料金額決定の一要因を示す裁判例も存在するところではあります。しかし、多くの裁判例においては事案ごとの個別の判断が行われており、前述の一部滅失の程度に関するものと同様、裁判例の蓄積による客観的で明確な基準は示されているとはいえないのが現状です。
そのため賃貸人は、紛争予防の観点から、賃借人から、修繕を要する箇所を発見した旨の通知を受けた場合には、速やかに現場確認をし、一部使用不能の程度が通常の居住をすることができない状態であるか、当該状態の発生につき賃借人に帰責事由がないかを確認の上、適正な減額割合や減額期間、減額の方法(賃料設定は変えずに一定の期間一部免除とするのか、賃料設定そのものの変更とするのか、など)などを賃借人と協議し、決定するのが望ましいといえます。なお、賃料減額の協議・決定に当たっては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が公表している、「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」が参考になります。本ガイドラインには法的拘束力があるわけではありませんが、発生した不具合ごとに目安となる賃料の減額割合が示されており、協議におけるベースラインを設定することが可能です。
賃借人による賃料の一部/全部の支払拒絶に対する解除の可否
最後に、賃借人が、賃料減額を主張して、賃料の支払いを拒絶ないし一部の支払いにとどまるような場合に、賃貸人としては賃料不払いを理由に当該賃貸借契約を解除することができるか否かについて、裁判例の動向を概観します。
⑴ 信頼関係の破壊
賃貸借契約は、売買契約のような一度きりの契約とは異なり、当事者間の信頼関係を前提とした継続的な契約です。そのため、仮に賃借人に債務不履行があったとしても、それが当事者間の信頼関係を破壊しないと認めるに足る特段の事情が存在する場合、賃貸人による契約の解除は認められないという判例法理が存在します。これを、信頼関係破壊の法理などと呼びます。
⑵ 裁判例の検討
賃借人が賃料減額を主張して賃料の支払いを拒絶ないし一部の支払いにとどまっているような場合に、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められるか否かという点について、裁判例は、この信頼関係の破壊が認められるか否かについて判断しています。
裁判例は賃貸人の契約解除の意思表示の効力を否定したもの(裁判例③、裁判例④)と、その効力を肯定したもの(裁判例⑤)とに分かれていますが、当事者間の信頼関係が破壊されたか否かを判断するにあたっては、そもそも賃借人が主張する賃料減額が認められるか否か、賃料不払いの要因となっている貸主の修繕義務不履行の態様(例えば、賃借人が入居当初から不具合を主張し、賃貸人に何度も修繕を要求したにもかかわらず、長期間修繕がされなかった、というような事情は信頼関係不破壊を基礎づけうる事情と評価されています)や賃借人の賃料不払いにある程度の根拠が認められるか否かといった点を考慮しています。
まとめ
以上のように、建物の一部使用不能による賃料の減額については、裁判例による一義的に明確な基準が存在していないのが現状です。そのため、たとえ話し合いによる解決が優先されるとしても、紛争を予防するため、あるいは均衡のとれた解決策を確立し、当事者間の円満な関係性を維持するため、専門的な知見をもつ専門家に相談することが肝要であるといえます。
以上
【関連記事】
無断での多人数居住に関するトラブル
退去時のハウスクリーニング特約の有効性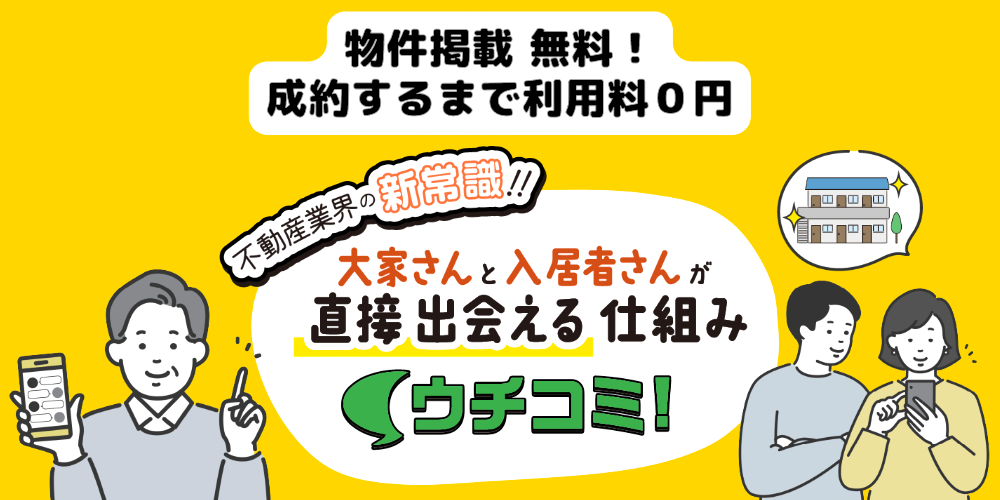
無料で使える空室対策♪ ウチコミ!無料会員登録はこちら
この記事を書いた人
弁護士
弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。