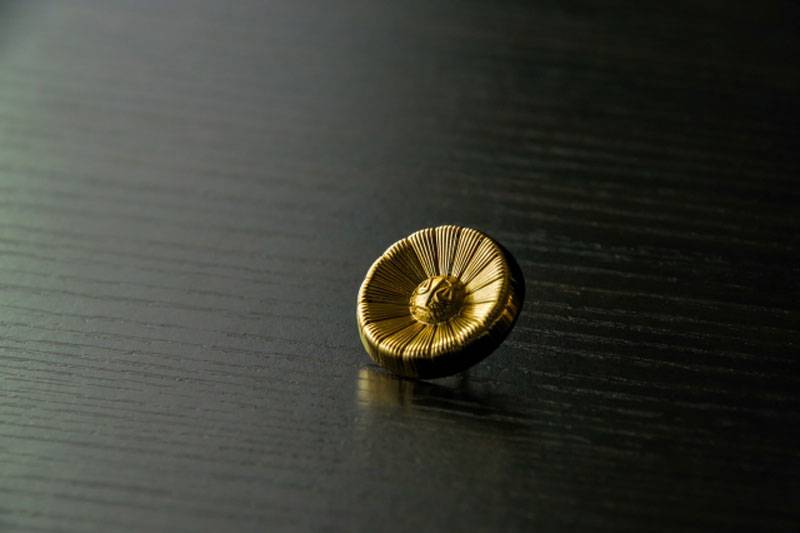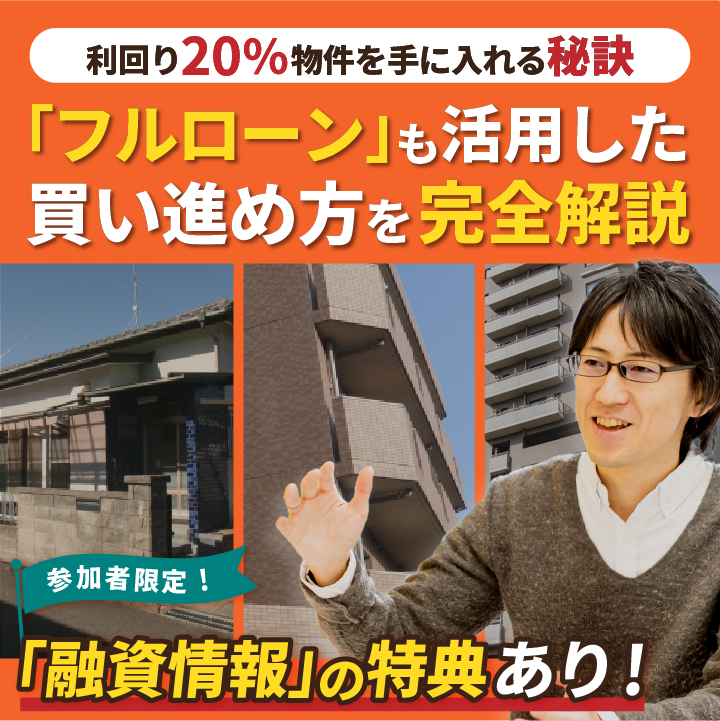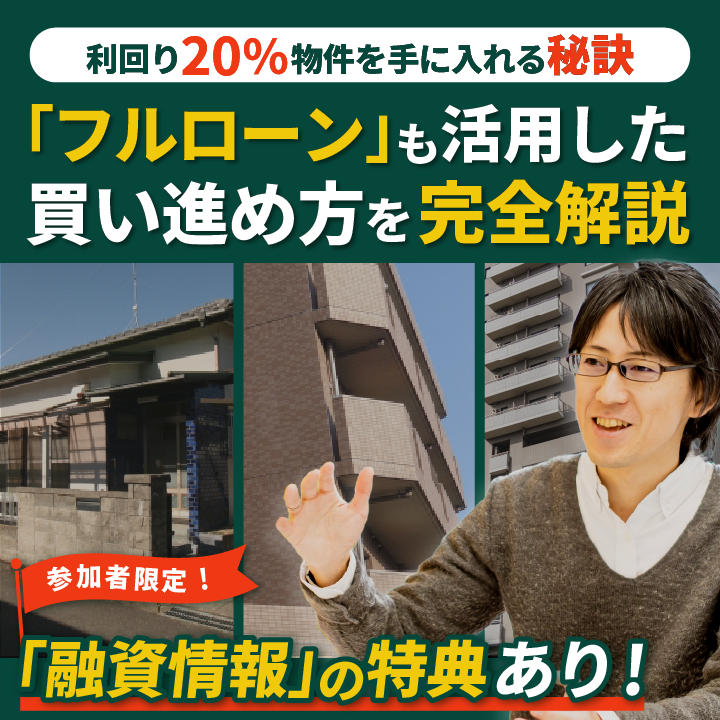家賃爆上げ―――理不尽で強引なやり方に慌てないために

2025/08/27
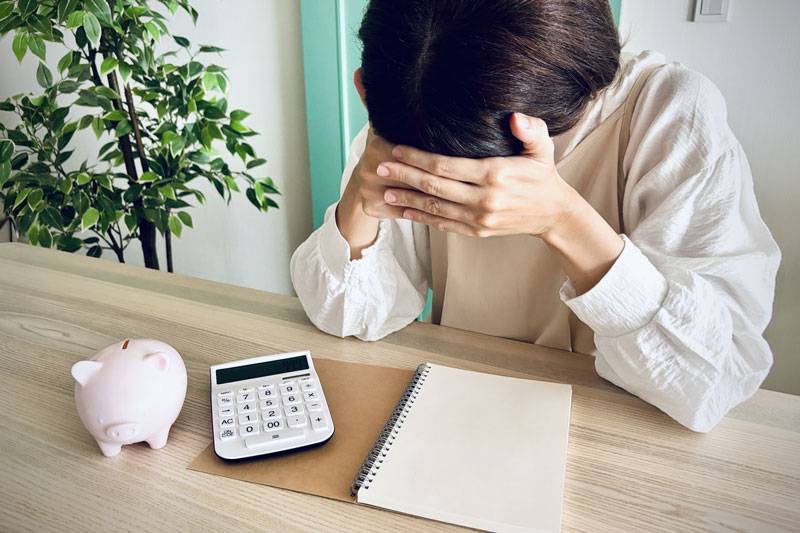
突然、飛び込んだ家賃「爆上げ」の通知
今年の前半、不動産関連のあるニュースが国会まで巻き込んで世間を賑わした。東京・板橋区で起きた「家賃爆上げマンション」に関わる一件だ。
年明け間もない1月半ば過ぎのこと。7階建ての賃貸マンションに暮らす入居者のもとに、書面1枚からなる通知が舞い込んだ。なんと、家賃を月額7万円前後から、一気に19万円へ―――2.5倍以上に値上げするという。
発信元はこの物件のオーナーだ。だが、以前とはその名前が違っている。実は、この直前、マンションはある中国系の会社の手に渡っていた。一連の詳しい取材内容をネット上に公開している「集英社オンライン」によると、以前の所有者は地元の金融機関の子会社だった。しかしながら、同社は昨年の11月に物件を売却。転売を経て、件(くだん)の会社のものになったと記されている。
なお、結論からいうと、オーナーはこの物件のおそらくは全戸、もしくは可能なかぎりの住戸を使って民泊を始めようとしていたらしい。そのために、近隣相場の2倍程度に及ぶ法外な家賃への値上げを住人に突き付け、追い出そうとしていたものと見られている。
加えて、その民泊も、自治体への届出無しに行おうとしていたようだ。年間宿泊日数の制限を無視しての違法な民泊であれば、賃貸物件として普通に部屋を貸すよりも、さらに儲けを見込めるからだ。
しかし、結局のところ、この違法民泊は開始後ほどなく住人から通報され、阻止された。だが、その仕返しなのか、今度はエレベーターが突如おかしな理由で使用停止とされてしまう。
すると、こうした住人の苦悩を知ったマスメディアが、現地に乗り込み、状況を取材、報道し始めた。ネット上も当然賑わい、ついにはこの騒動は国会でも採り上げられるに至っている。
そこで、やっとオーナー側も慌てたようだ。長期間に渡り不具合によって動かせなくなった筈のエレベーターの運行を再開。それとともに、家賃値上げを撤回する旨を書面で住人に通知―――と、いうのが、この件に関する6月中旬までの動きとなっている。
家賃値上げの通告に対する基本の心構え
さて、以上、板橋区「家賃爆上げマンション」にかかわっての一件だが、こうした理不尽な家賃値上げの通告があった際、あるいは、理不尽なレベルでなくともそうした請求があった場合、入居者として、慌てることなく判断・行動ができるよう、われわれが知っておきたい大事なことがある。簡単にまとめていこう。
なお、以下は、賃貸物件の貸し借りにおいて一般的な「普通借家」契約を前提とした話になる。
文中、オーナーとは「大家」「家主」「貸主」―――すなわち賃貸住宅の賃貸人を指す。対する賃借人は「入居者」と表記する。
1.法律による条件を満たさないと、オーナーはそもそも家賃値上げを言い出せない
法律とは何か?「借地借家法」だ。
「入居者に味方し過ぎ」と、嘆く声も聞かれるこの決まりによって、わが国では賃貸住宅の入居者は強力に保護されている。
借地借家法の家賃値上げに関する規定(第32条)に従えば、オーナーが入居者に対して家賃の値上げを申し入れるには、以下3つの条件のうち、少なくともいずれかが満たされなければならない。
- オーナーが支払う、土地や建物に対する租税等の負担が増加している
- 土地や建物の価格の上昇や、経済事情の変動が生じている
- 近隣の同様の物件の家賃に比べて、その物件の家賃が不相当に安い状態となっている
なお、見てのとおり、これら3つの条件それぞれは、ひとつが成立していれば他も成立している可能性が高いものとなる。
ともあれ、以上をクリアしていなければ、オーナーには賃料増額請求権が発生しない。「家賃を値上げさせてくれ」と、そもそも言い出せないのだ。
よって、逆をいえば、「家賃を上げさせてほしい」と入居者にお願いするには、オーナーはそのための準備をしっかりと整えておかなければならない。
当該請求が、上記の条件を踏まえてのものであること。また、それに照らした上で、増額の幅が客観的にも妥当なものであること。
以上につき、数字等の裏付けも示しながら、明確に説明できることが必須となる。
2.値上げの理由に納得できなければ、入居者は従う必要はない
家賃値上げの申し入れをされた入居者が、オーナーの示すその理由や金額に納得できないとする。
あるいは、オーナーが理由を説明しなかったり、説明が不十分で信頼に足るものでなかったりしたとする。
そうした場合、入居者はオーナーの請求に合意する必要はない。なおかつ、オーナーの示す値上げ後の家賃を支払う必要もない。
すると、どうすればよいのか?
借地借家法は、入居者は、「(自らが)相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる」と、している。
入居者が相当と認める額というのは、要は、いま払っている家賃の金額であると解釈していい。
つまりは、従前と同額の家賃だ。これをきちんと払い続ければ、入居者には何ら落ち度が生じないことになる。(特殊な事例を除く)
一方、それに対し、オーナー側が納得いかず、決着をつけたいのならば、オーナーは裁判所に調停を頼まねばならないことになる。それでダメなら次に裁判だ。
結果、オーナーの言い分の全部が、あるいはある程度が認められたとしよう。すると、従前よりも高い家賃が、おそらくは日にちをさかのぼるかたちで決まることになる。
その場合、入居者は「不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払う」ことになっている。家賃に利息を上乗せされるわけだ。ここはちょっと痛い。
だが、そもそもの話として、オーナーの賃料増額請求が先ほど掲げた条件を備えていないものであるならば、裁判所がオーナーの言い分を認めることはない。
よって、まさにそのケースに当たる板橋区の例―――値上げの幅は法外なもので、満足な理由説明もなかった―――では、住人からの相談を受けた法律のプロ、不動産のプロは、誰もが「オーナーは勝てない」と、アドバイスしていたはずだ。
3.入居者がやってはいけないことと、供託の話
ところで、以上のような争いが生じた際に、入居者が決してやってはいけないことがある。よく覚えておこう。
それは、オーナーの請求に納得がいかないからといって、家賃の支払い自体をやめてしまうことだ。
これは、現在有効に結ばれている契約に違反する行為そのものになる。すなわち、債務不履行だ。
契約解除および、物件からの退去をオーナーから迫られることにつながるなど、自らを不利な立場に追い込むまずいやり方なので、これは絶対にやってはならない。
一方、その逆だ。
争いが続く中、オーナーが家賃の受け取りを拒否したら、入居者はどうすればよいだろうか。
「値上げした額の家賃でなければ受け取らない」―――との意志をオーナーが示してきた場合の対処だ。
答えはこうなる。
まず、入居者は、この場合も従前の額の家賃の支払いを怠ってはならない。「オーナーが受け取らないから支払いはやめました」ではまずいのだ。
そこで、供託をする。
供託所(法務局、地方法務局、またはこれらの支局)に家賃を納め、預けておく。
これをしていれば、入居者は、債務不履行せずにちゃんと家賃を払い続けていることになる。オーナーは「滞納された」と言えなくなるわけだ。
これぞ賃貸のメリット(?)―――斜め上に立つ考え方
以上、1、2、3について、覚えてもらえただろうか。
逆にいえば、家賃の値上げというのは、オーナーにとっては非常にハードルの高い、しんどい作業ともなるわけだ。
そのうえで近年、不動産の値上がりが、他の物価上昇などとともにいよいよ鮮明になって来た。
そのことで、経済環境に見合う程度の賃料増額を請求できる状況が、オーナーにとっては「長年待ち続け、やっと訪れた」と、いったところが現状だろう。
それでも、願いが少しでも行き過ぎれば、やはりそれは通らない。それが、現に布かれているところの日本の法律であり、それに沿っての司法あるいは社会の判断だ。
なお、オーナーからの家賃値上げ請求への対応については、さらに詳しい内容を下記記事に記してある。
―――「賃貸・家賃を『値上げします』と言われたら」
こうした知識と心構えがあれば、突然のことに慌てず済むだけでなく、オーナーとの交渉にも落ち着いて臨めることになる。
最後に。もうひとつ付け加えよう。
この考え方には賛否があるだろう。また、そのようには動けない事情を抱えた人ももちろん大勢いるはずだ。
だが、ここではあえて以下も示しておきたい。
考え方とは、こうだ。
今回の板橋の件のように、借りている物件のオーナーが面倒な組織や人に替わったり、あるいは、物件内外の環境が悪化したり、などなど―――。
そんな場合は、早々に見切りをつけてそこから去ってしまう。嫌なことに関わる時間を極力無くす。
交渉する場合でも、いわゆる立ち退き交渉のみにシンプルに注力する。
これも、賃貸に住んでいるからこそのメリットを活かした、妥当な対応といえるものだ。
なぜなら、考えてみよう。
一戸建てや分譲マンションといった持ち家に住んでいる場合、ましてや、そのためのローンを抱えた状態といった場合、こうした身軽な行動は通常叶わない。
「憂鬱な環境の中、5年、10数年、我慢してそこに暮らしている」―――といった、たびたびニュースになるような悲劇は、賃貸ではなかなか起こり得ない、持ち家だからこそのものといえるはずだ。
それでも、
「迷惑住人が隣の部屋に引っ越して来た。そのせいでこっちがアパートを出る羽目になった」
そんなケースでは、多くの人は、自分が損をさせられた、泣き寝入りさせられたと思い、悔しい気持ちになるだろう。
だが、反面、これは持ち家にはない賃貸ならではのメリットが存分に発揮されたシーンでもある。
自然災害による被害に対し、保険が役立ったときのように、賃貸が持つリスクヘッジ機能がここで効果を生んだと、前向きに考えるのも十分可能なことだ。
ちなみに、自然災害といえば、家が洪水で浸水したり、地震で壊れたりしても、それは自分の財産ではないというのも、賃貸住宅が持つ大きなメリットにほかならない。
(文/賃貸幸せラボラトリー)
【関連記事】
家賃上昇の波高く、大学新入生市場は息切れ? 2025年前半・家賃の「いま」
賃貸・家賃を「値上げします」と言われたら
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室