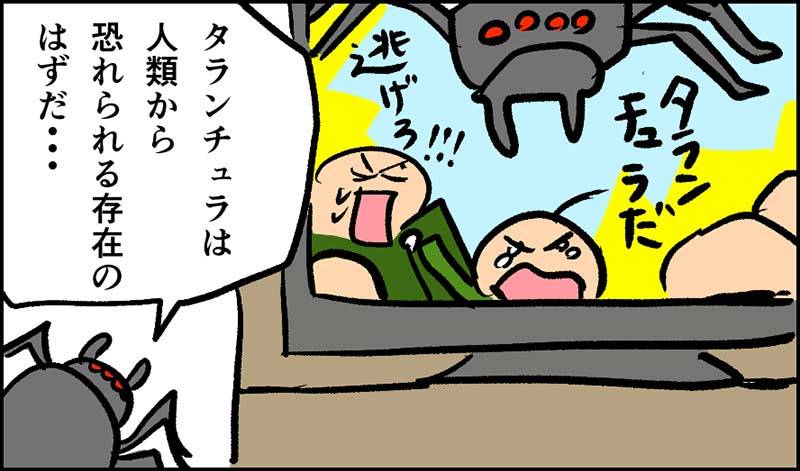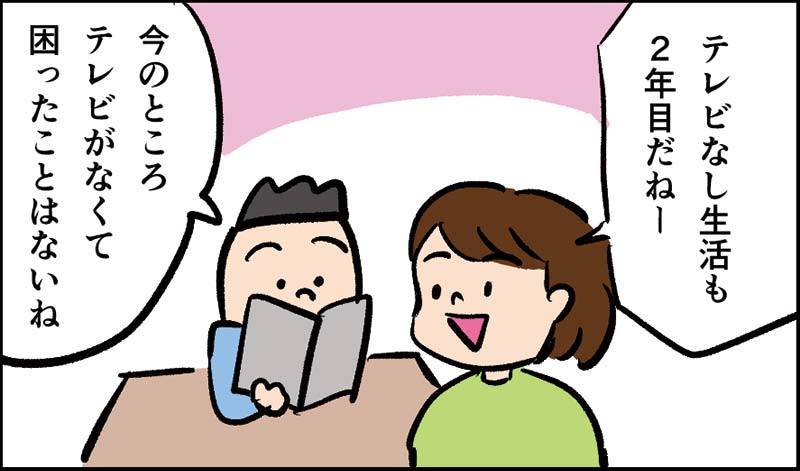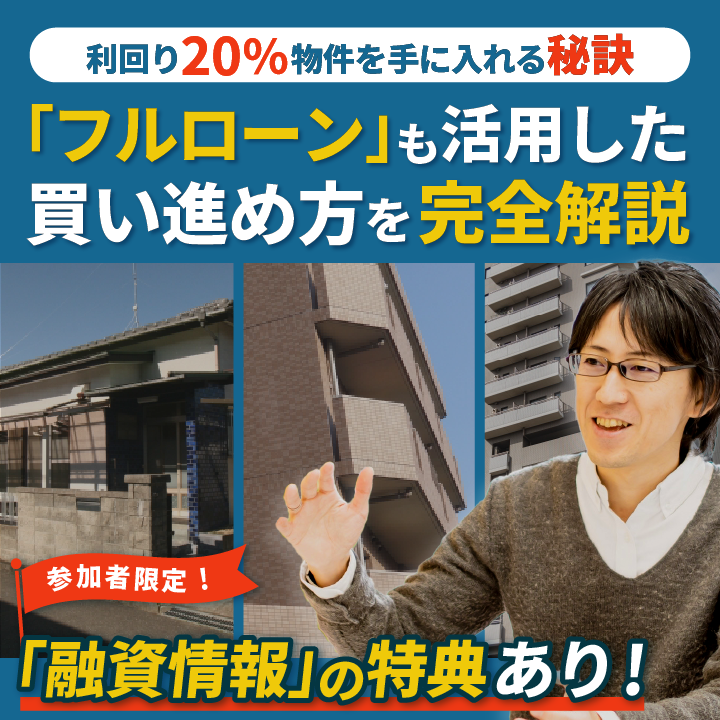平均寿命と健康寿命との不安な差。2024年「簡易生命表」を読み解く
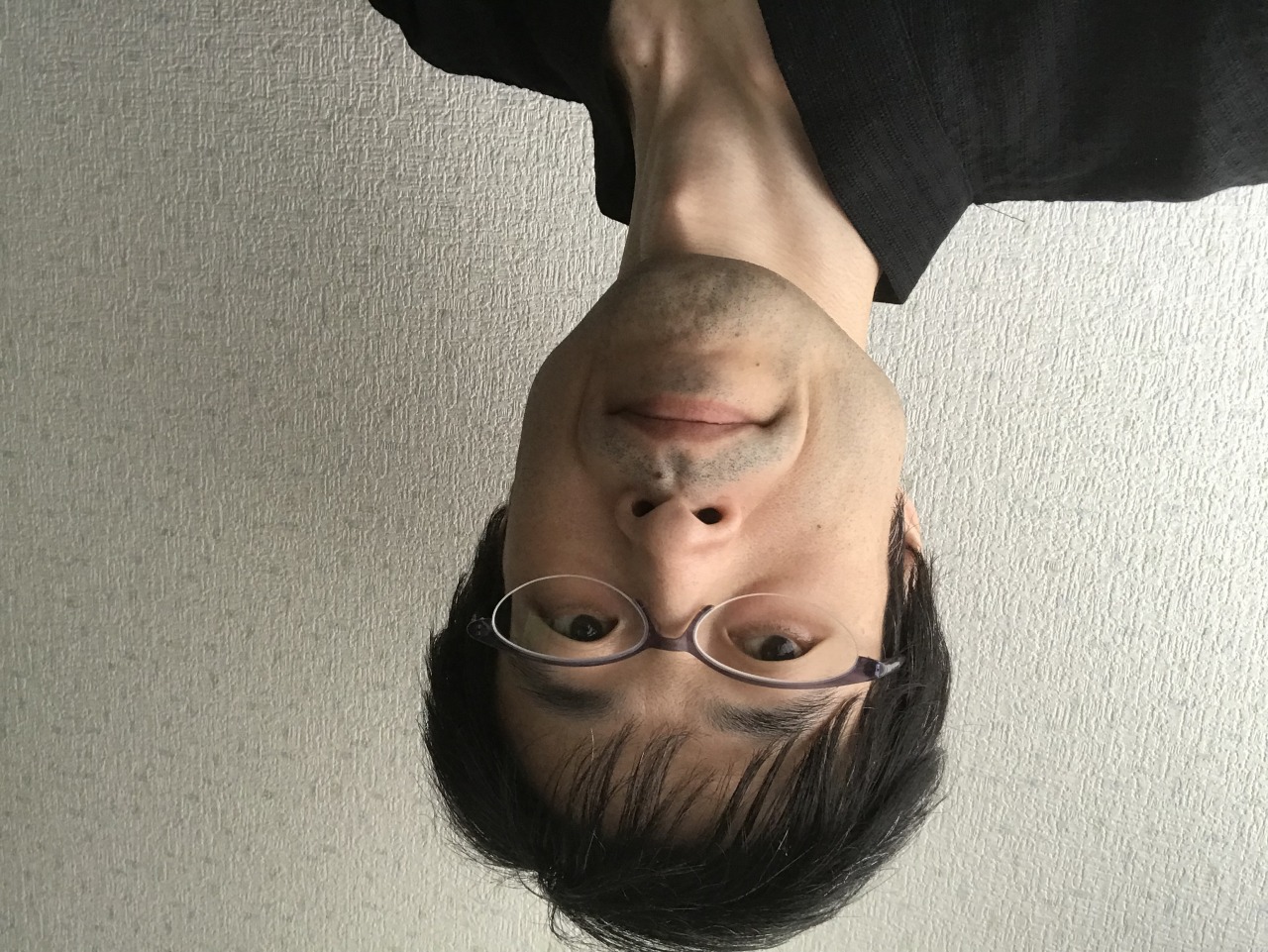
2025/08/05

日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳
この7月下旬、厚生労働省が令和6年(2024)分の「簡易生命表」を取りまとめ、公表している。いくつか目につくところを挙げていきたい。
まずは、日本人の最新の平均寿命だ。標題のとおりとなる。なお、前年と比較すると、男性は横ばい。女性は0.01年下回った。
各国の状況も併せ、ランキングのかたちで見てみよう。
| 男性 | 1位 スウェーデン | 82.29歳 |
| 2位 スイス | 82.2歳 | |
| 3位 ノルウェー | 81.59歳 | |
| 4位 イタリア | 81.436歳 | |
| 5位 スペイン | 81.11歳 | |
| 6位 日本 | 81.09歳 | |
| 7位 オーストラリア | 81.07歳 | |
| 8位 キプロス | 81.0歳 | |
| 9位 アイスランド | 80.9歳 | |
| 10位 イスラエル | 80.79歳 | |
| 女性 | 1位 日本 | 87.13歳 |
| 2位 韓国 | 86.4歳 | |
| 3位 スペイン | 86.34歳 | |
| 4位 スイス | 85.8歳 | |
| 5位 フランス | 85.6歳 | |
| 6位 イタリア | 85.495歳 | |
| 7位 スウェーデン | 85.35歳 | |
| 8位 シンガポール | 85.2歳 | |
| 9位 オーストラリア | 85.11歳 | |
| 10位 キプロス | 85.0歳 |
なお、厚労省によると、「平均寿命の諸外国との比較は、国により作成基礎期間や作成方法が異なるため」―――厳密には困難とのこと。同省手元の資料からは、以上が導かれるということのようだ。
平均寿命とは大きな差が―――「死亡年齢最頻値」
ところで、上記の平均寿命とは「0歳における平均余命」を指す言葉だ。そのため、新生児や乳幼児等、幼くして亡くなる人のわずかな年齢も母数には加わることになる。それらが数字を押し下げる。
よって、われわれがざっと周囲を見渡したうえで「このくらいの年齢で亡くなる人が多い」と、感じる辺りからは、若干印象がずれがちだ。
そこで、イメージにもっとも近い数字を挙げるとすれば、「死亡年齢最頻値」が、多分それに当たる。文字どおり、亡くなる人の数が現状もっとも多い年齢のことだ。今回の簡易生命表においては以下のとおりとなっている。
| 性別 | 死亡年齢最頻値 | 平均寿命との差 |
| 男性 | 88歳 | +6.91歳 |
| 女性 | 92歳 | +4.87歳 |
見てのとおり、平均寿命との差がやや開いている。現実として、多くの人が同寿命をさらに超えて生き続けるということだ。
よって、いわゆるライフプラン―――特にマネープランを考える際の基準としては、平均寿命ではなく、これら最頻値を意識しておくのが無難といえるだろう。
長生きとは何歳以上をいうのか?――「寿命中位数」
日本人が平均的にどのくらいまで生きるかにあっては、さらに「寿命中位数」というデータもある。
出生者のうち「半数が生存している」ことが、現状、期待される年齢として算出されるものだ。これを超えて生きている場合、その人は長生き(長く生きている半数の側の人)と見られてよいことになるだろう。
| 性別 | 寿命中位数 | 平均寿命との差 |
| 男性 | 83.89歳 | +2.8歳 |
| 女性 | 90.04歳 | +2.91歳 |
このとおり、女性の寿命中位数は90歳を超えている。
すなわち、女性は80代で亡くなると、「まだ若いのに(同い年の半分以上がまだ生きているのに)」と、かたちとしては惜しまれるべきこととなる。
高齢者でいる時間―――男性は約20年、女性は約25年
次に、平均余命を見てみたい。2つの年齢をピックアップする。
| 65歳の平均余命 | 男性 | 19.47年 |
| 女性 | 24.38年 | |
| 75歳の平均余命 | 男性 | 12.08年 |
| 女性 | 15.75年 |
このうち65歳は「前期高齢者」となる年齢だ。75歳で「後期高齢者」となる。
しかしながら、数字は見てのとおり。65歳時にあっての平均余命は、男性にして20年近く、女性は25年近くにも及んでいる。これらの期間を老後、あるいは余生などと呼ぶにはいかにも長すぎる。
われわれの周りにある65歳以上を一律に高齢者と定義した上でのさまざまな制度設計には、そろそろ(かなり以前から?)無理が生じているといえるだろう。
最大の課題―――「健康寿命」
さて、そこで課題となるのが「健康寿命」だ。
亡くなるまでの寿命ではなく、高齢化にともなう健康上の問題によって、日常生活に制限が生じるまでの期間を指してこのように呼ぶ。
以下は、昨年12月に厚労省「第4回 健康日本21(第三次)推進専門委員会」で示された、健康寿命の「令和4年値」だ。
| 性別 | 健康寿命 | 平均寿命との差 | 死亡年齢最頻値との差 | 寿命中位数との差 |
| 男性 | 72.57歳 | -8.52年 | -15.43年 | -11.32年 |
| 女性 | 75.45歳 | -11.68年 | -16.55年 | -14.59年 |
このとおり、健康寿命と平均寿命の差は大きく、死亡年齢最頻値や寿命中位数との差はさらに大きい。
すなわち、われわれ日本人が老いて死を待つまでの間、「健康ではない」状態でいる時間は、平均してかなり長いということになる。
もちろん、その間に生じる「日常生活での制限」がどの程度かにもよるが、ともあれ、上記に挙がる数字は、見る人ほとんどにとって、不安なものでしかないだろう。
このことは、われわれの実に切実な課題となる。
人生の終わりを出来るかぎり健やかに生きたい―――そのためにはどういう努力をすべきか。あるいは、何を避けるべきなのか?
われわれ個々人においての重い課題であるとともに、高齢者医療・福祉等に費やされる膨大なコストという面に関わっては、当然ながら、これらは国レベルでの重要課題というほかない。
紹介した資料は下記でご覧いただける。
「厚生労働省 令和6年(2024)簡易生命表の概況」
「同 第4回 健康日本21(第三次)推進専門委員会 資料」
(文/朝倉継道)
【関連記事】
孤独死によって起こる「悲劇」の防止。国民レベルの課題とすべき?
認知症600万人時代をわれわれはどう戦うか?
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。