2025年「地価公示」3つの話題―――「バブル」「地方4市」「消費者物価」
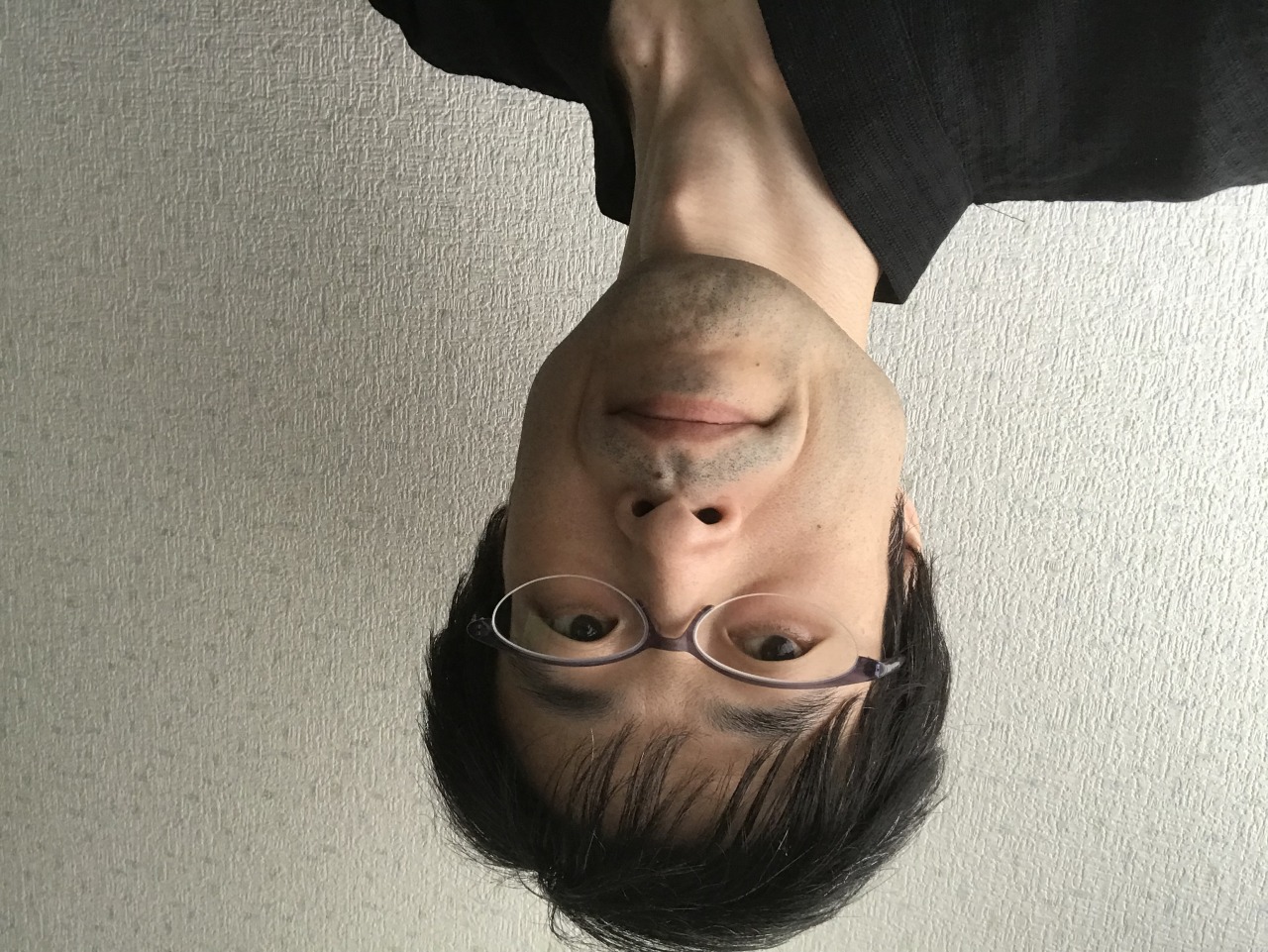
2025/04/03

前回を上回る「バブル期以来」の伸び率
3月18日に、国土交通省が「令和7年(2025)地価公示」の内容を公表している。いわゆる公示地価の発表となる。
- 「全国・全用途の平均が前年比2.7%の上昇」
- 「上昇は4年連続」
- 「バブル崩壊後の92年以降、最高だった昨年の2.3%をさらに上回る数字」
―――など、各報道が示すとおりだ。
以下、この記事では、少し変わった視点からの3つの話題を挙げていく。
バブル直前と似た数字
バブル崩壊以降、わが国の地価は上昇に転じたかと思えばリーマン・ショックの波に呑まれ、さらにはコロナ禍にも翻弄されと、2度にわたって大きな経済的変動により頭を押さえつけられたかたちとなっている。
下記、そのあらましを掲げてみよう。
バブル期以降の地価公示『全国・全用途』の平均における上昇率の推移
| 年 | 率 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| バブル景気の時代 | 1985年 | 2.4% | バブル景気の発端とされるプラザ合意の年 |
| 1986年 | 2.6% | バブル景気の始まりとされる年 | |
| 1987年 | 7.7% | ||
| 1988年 | 21.7% | ||
| 1989年 | 8.3% | ||
| 1990年 | 16.6% | ||
| 1991年 | 11.3% | バブル崩壊の本格的な始まりとされる年 | |
| バブル崩壊後の地価低迷時代 | 1992年 | ▲4.6% | バブル崩壊が地価に波及 |
| 1993年 | ▲8.4% | ||
| 1994年 | ▲5.6% | ||
| 1995年 | ▲3.0% | ||
| 1996年 | ▲4.0% | ||
| 1997年 | ▲2.9% | ||
| 1998年 | ▲2.4% | ||
| 1999年 | ▲4.6% | ||
| 2000年 | ▲4.9% | ||
| 2001年 | ▲4.9% | ||
| 2002年 | ▲5.9% | ||
| 2003年 | ▲6.4% | ||
| 2004年 | ▲6.2% | ||
| リーマン・ショック前のミニバブル期 | 2005年 | ▲5.0% | |
| 2006年 | ▲2.8% | ||
| 2007年 | 0.4% | ||
| 2008年 | 1.7% | リーマン・ショック発生 | |
| リーマン・ショック後の地価低迷時代 | 2009年 | ▲3.5% | リーマン・ショックの地価への影響始まる |
| 2010年 | ▲4.6% | ||
| 2011年 | ▲3.0% | ||
| 2012年 | ▲2.6% | ||
| 2013年 | ▲1.8% | アベノミクスの実質的スタート | |
| 2014年 | ▲0.6% | ||
| 2015年 | ▲0.3% | ||
| コロナ禍前の地価回復時代 | 2016年 | 0.1% | |
| 2017年 | 0.4% | ||
| 2018年 | 0.7% | 訪日外国人客数3千万人を初めて突破 | |
| 2019年 | 1.2% | ||
| 2020年 | 1.4% | 日本においてのコロナ禍発生 | |
| コロナ禍の影響~回復~現在 | 2021年 | ▲0.5% | コロナ禍が地価に影響 |
| 2022年 | 0.6% | ||
| 2023年 | 1.6% | ||
| 2024年 | 2.3% | 92年以来最高の上昇率。かつ33年ぶりの2%超えとなる | |
| 2025年 | 2.7% | 今回 | |
以上、日本の地価は今後も上がっていくのか。それとも「ショック」や「禍」がまた何か生じて熱は冷やされるのか。まさに、神のみぞ知るといったところだろう。
ところで、やや下世話な、居酒屋談義的指摘となるが、今回の地価公示における全国・全用途の平均プラス2.7%という数字は、バブル景気始まりの年とされる86年の数字(プラス2.6%)に奇妙に近い。
昨年もそうだ。24年のプラス2.3%は、バブル景気の発端といわれる「プラザ合意」があった85年の同2.4%とやはり似ている。
そう思えば、プラザ合意と同じアメリカ絡みの変動としては、昨年、自国ファーストを何よりの信条とする第2次トランプ政権の発足が決まった。
これにより、プラザ合意の時と同様、その後の世界経済は心理的にひどく揺れ動いている。
ちなみに、わが国では、プラザ合意によるそうした心の揺れが、円高不況への国を挙げての怖れを生んだ。それが当時の政策に色濃く反映され、バブルを生む重要な一因となっている。
そういうわけで、何やら数字を見ていて変な気分にもなってくる今回の地価公示だが、以上は駄弁だ。繰り返すが、居酒屋談義以外の何ものでもない。
もっとも、件のトランプ政権にあっては、ご存じのとおりアメリカにおける製造業の復活をテーマに日々ハッスルしている。
よって、為替レートを自国有利に調整するため(ドル安へ)、次なるプラザ合意を画策するようなシナリオも、ひょっとすると今後用意されたりするのかもしれない。もちろん、その念頭には最大の貿易赤字相手国である中国がある。
とはいえ、人民元に対してのドルの切り下げは、中国の名目GDP(ドル換算)を肥大化させる行為ともなる。併せて、購買力の増加を通して中国経済の力を実態以上に世界に対しシグナライズさせることにもなり、それが、ともすれば中国による経済的覇権を伸張させかねない可能性があるため、アメリカにとってはかなり悩ましい選択となる。
なお、関係ないが、余談を重ねると、トランプ氏はプラザ合意の少しあとより一時期、舞台となったプラザホテルのオーナーになっている。
地方四市の明暗
今回の地価公示におけるトピックのひとつが、地方4市(札幌、仙台、広島、福岡)平均における数字の落ち着きだろう。
地方4市・全用途および用途別の平均上昇率
| 用途 | 本年 | 前年 | 前々年 |
|---|---|---|---|
| 全用途 | 5.8% | 7.7% | 8.5% |
| 住宅地 | 4.9% | 7.0% | 8.6% |
| 商業地 | 7.4% | 9.2% | 8.1% |
いずれも高い数字ながら、前年よりは少なからず下がっている。まさに「落ち着き」を見せつつあるのが見てとれる。
ちなみに、地方4市を除いた地方圏の数字はこうなっている。
地方圏(その他)
| 用途 | 本年 | 前年 | 前々年 |
|---|---|---|---|
| 全用途 | 0.8% | 0.7% | 0.4% |
| 住宅地 | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 商業地 | 0.9% | 0.6% | 0.1% |
こちらは、地方4市とは対照的にわずかずつながら上昇率は拡大傾向となっている。
よって、コロナ禍の際も上昇が止まなかった(コロナの影響が濃かった21年でも全用途でプラス2.9%だった)地方4市における地価の沸騰は、現在、次第に冷めつつあるようにも思える。
が、中身をよく見ると、実は4市で違いが生じている。挙げていこう。
| 用途 | 本年 | 前年 | 前々年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 全用途 | 4.0% | 9.1% | 13.2% | 住宅地、商業地ともに上昇率は今回大幅に縮小。 |
| 住宅地 | 2.9% | 8.4% | 15.0% | ||
| 商業地 | 6.0% | 10.3% | 9.7% | ||
| 仙台市 | 全用途 | 7.0% | 7.3% | 6.1% | 住宅地は縮小したが上昇率自体は高い。なおかつ商業地は拡大。 |
| 住宅地 | 6.3% | 7.0% | 5.9% | ||
| 商業地 | 8.3% | 7.8% | 6.1% | ||
| 広島市 | 全用途 | 3.0% | 2.6% | 2.2% | 住宅地、商業地ともに数字は小さいものの3年連続で拡大。 |
| 住宅地 | 2.4% | 2.0% | 1.7% | ||
| 商業地 | 4.6% | 4.2% | 3.7% | ||
| 福岡市 | 全用途 | 9.9% | 10.7% | 9.0% | 住宅地、商業地ともに上昇率は縮小したが、数字は未だ大きい。 |
| 住宅地 | 9.0% | 9.6% | 8.0% | ||
| 商業地 | 11.3% | 12.6% | 10.6% | ||
このとおり、特に目立つのが、札幌市と他の3市との間におけるコントラストだろう。札幌においては、街への投資の勢いが他に比べてより急速に鈍化しつつある様子がいまのところ窺える。
ちなみに、札幌に関してのニュースといえば、つい先ごろ、北海道新幹線の札幌延伸が目標よりも大幅に遅れる見通しが明らかとなった(30年度末から38年度末へ)。また、現地からは、住宅需要の勢いがにわかに弱まってきたとの声も聞こえて来る。
これら諸々の状況によっては、地方4市の明暗は、札幌を焦点に今後よりはっきりと分かれてくる可能性もある。
地価公示も2.7 消費者物価も2.7
今回の地価公示を採り上げた各メディアの記事中、日本経済新聞電子版にこんな記述があった(3月18日)。抜粋したい。
「バブル期の地価は上昇率が10%を超え、最大2~3%台で推移していた消費者物価の伸び率とは大きな開きがあった。現在は地価も物価も伸びはほぼ同じ水準で、資産インフレの色が濃かったバブル期とは様相が異なる」
実際に数字を並べてみよう。
先ほども掲げた、地価公示「全国・全用途」の平均上昇率と、消費者物価指数「全国平均・総合指数」の上昇率だ。
| 年 | 地価公示 | 消費者物価(前年平均) |
|---|---|---|
| 2021年 | ▲0.5% | 0.0% |
| 2022年 | 0.6% | ▲0.2% |
| 2023年 | 1.6% | 2.5% |
| 2024年 | 2.3% | 3.2% |
| 2025年 | 2.7% | 2.7% |
このとおり、記事内容については概ね納得がいくものとなっている。なるほど、直近の数字に至っては、双方2.7%でピタリと一致だ。
現在のわが国の地価上昇に関しては、一部リゾートエリアなど、やや過熱気味の箇所がいくつか見られないわけでもない。しかしながら、都市部を中心とした多くにあっては、上昇はあっても、オーバーヒートしているといえるような状況はほとんど見当たらないといっていいだろう。
よって、国内のもの、海外からのもの含め、いまのところは投機的な思惑ではなく、実需を踏まえた堅実な投資がこれらを生んでいることに、ほぼ間違いはない。
以上、今回の地価公示については、各資料を下記にてご確認いただける。
(文/朝倉継道)
【関連記事】
中国が5割を超えて最多。外国人による「重要土地」等の取得
地価LOOKレポート2024年第4四半期 ジェントルな地価上昇が継続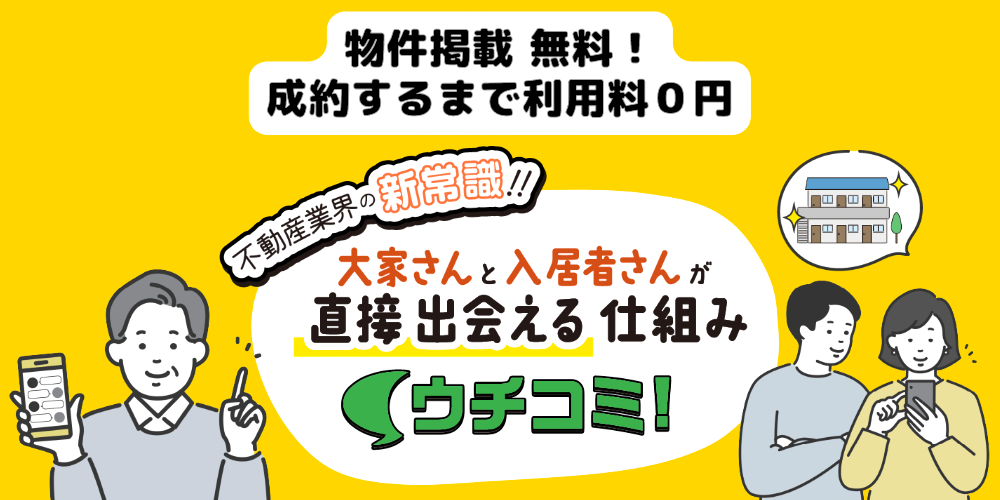
無料で使える空室対策♪ ウチコミ!無料会員登録はこちら
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。






















