牧野知弘の「どうなる!? おらが日本]#2 2018年日本の不動産はこうなる
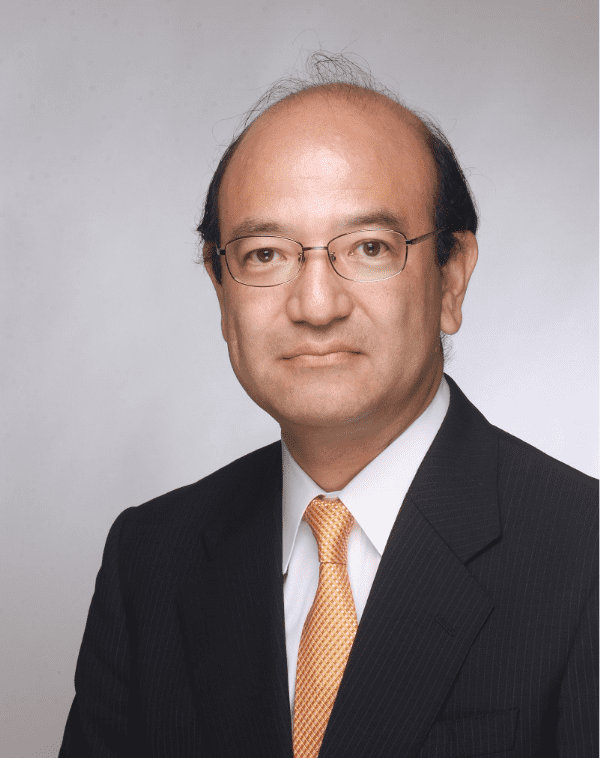
2018/02/20

イメージ/123RF
首都圏マンションの平均価格は7.6%も上昇
2017年の不動産マーケットは実に好調だった。
地価は上昇が顕著になってきた。銀座の山野楽器前の公示地価は㎡あたりで5000万円を超え、平成バブル期の水準になった。地価の上昇は東京、大阪、名古屋の三大都市圏から地方四市といわれる札幌、仙台、広島、福岡といった都市にも波及していった。
地価の上昇を背景に売買マーケットも好調だった。都市未来総合研究所によれば、2017年度上期の不動産取引額は1兆8213億円と前年度同期比で18.5%もの伸びを示した。
都心では数多くのクレーンが所狭しと立ち並び、超高層オフィスビルの建設ラッシュが続く。「都心居住」の掛け声のもと都心部のマンションの値段は急上昇。2017年首都圏(1都3県)で供給されたマンションの平均価格は5908万円と前年比7.6%も値上がりし、もはや庶民にはマンションは買えないレベルとまで揶揄されるようになった。
都心部でオフィスと覇を競うように建設ラッシュとなっているのが、ホテルだ。インバウンド(訪日外国人)の需要増を当て込んだホテル業界には、他業態からの新規参入も陸続して大変な活況となっている。
さて、こうした流れを受けて2018年の日本の不動産はどうなるのだろうか。業界内では「まだまだ好調は続く」という見方と「そろそろ宴は終了」という見方が交錯している。それぞれの見方を検証しながら2018年の不動産マーケットを占ってみよう。
まず2018年日本の不動産をポジティブに予測してみよう。ポイントは以下の5つだ。
1.国家が支える官製不動産マーケット
2.セミプロ投資家の急増
3.ブランドマンション、ブランドビル時代の到来
4.猛威を振るうインバウンドマネー
5.新しい不動産メニューの勃興
2018年、いよいよ日本の不動産投資マーケットに「巨大な買手」がやってくる。その名は年金積立管理運用独立行政法人(GPIF)、運用資金総額156兆円の「化け物投資家」である。GPIFは厚生労働省の所轄法人であり、厚生年金と国民年金の運用を司っている。2014年10月第二次安倍政権において、GPIFは運用構成が変更され、これまでの国内債券を中心とした運用から一定のリスク資産にも投資できるように改定された。具体的には国内債券35%、国内株式25%、外国債券15%、外国株式25%が新しい運用割合となったのだ。一見するとGPIFが不動産投資を行うのは不可能なように見えるが、実はカラクリがある。
同改正では、運用体制の整備に伴って、オルタナティブ資産に対する投資をリスクリターン体制に応じて資産全体の5%まで認められるようになったのだ。オルタナティブ資産とは①インフラストラクチャ―、②プライベートエクイティ(未上場株式など)、③不動産という定義になっている。これらの対象に簡単にいえば、上記の債券や株式という「カタチ」を通じてであれば投資が可能となったのだ。
2017年12月19日GPIFは不動産投資の運用機関として三菱UFJ信託銀行を選定した。同行が組成する不動産投資ファンドを通じて国内不動産への投資を本格的に実行する体制が整ったことになる。136兆円の5%といったら6.8兆円。すべてが不動産投資に回るわけではないが、発足して16年になる国内REITマーケットの資産規模が約15兆円であるからそのインパクトは絶大である。
国はすでにREITに対してもマーケットでは日銀を通じて一定額を買い支えているが、不動産マーケットに公的資金を注入することで不動産マーケットを支える構図が出来上がることとなる。
働き方改革で個人不動産投資家の台頭も
働き方改革でどうやら「副業」も幅広く認められる方向である。不動産投資は今やネットを利用すれば、個人でも多くの情報を居ながらにして得ることができる。2018年は残業がなくなった自由時間を利用して「小金」を不動産に振り向ける個人が急増し、「セミプロ」と呼ばれるような個人不動産投資家が台頭してくる可能性もある。
いっぽうで法人でも個人でも良くも悪くも「格差」社会の到来と言われている。富める者はますます富み栄え、貧する者との格差は拡大する、そんな中でオフィスビルやマンションでは究極の「ブランド化」の時代を迎えるだろう。
今後2020年までに都心部を中心に建設が予定されている多くのオフィスビルは都心5区に立地し、しかもワンフロアの面積が数百坪から1000坪を超えるような巨大航空母艦のような建物だ。当然賃料も高く、入居できるテナントは大企業オンリーとなる。都心居住が進む中、都心部のタワマンに住めるのはもちろん一定の高額所得層のみとなる。大企業も個人富裕層も無類の「ブランド好き」だ。ブランドビル、ブランドマンションが「とんでもない価格」で取引する年となってくることだろう。
インバウンドは2018年ついに3000万人の大台を超えるはずだ。人数ばかりが注目されるが、実は彼らが持つマネーは日本で猛威を振るっている。インバウンドマネーはすでに北海道のニセコや長野の軽井沢などでは、日本人には信じられないような価格で取引が行われ、外国人だけの独自の不動産マーケットを形成しつつある。インバウンドマネーは東京、大阪のマンションやアパート、そして地方都市へと拡散している。2018年も不動産マーケットはインバウンドマネーの恩恵に大いにあずかることになるだろう。
インバウンド対象ビジネスとしては、2018年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行される。ようやくルール化される民泊はこれまでの違法民泊を駆逐する一方で、大量の新規供給を促すこととなる。空き家の活用、空室に悩むアパートオーナーにも民泊活用は朗報だ。
このように考えてくると2018年日本の不動産マーケットは「おおむね好調を維持できる」と考えることができるのだ。
「金利」と「有事」を甘くみてはいけない
世界情勢は目まぐるしく変動する。日本も例外ではない
一見すると死角がないかのように映る日本の不動産、実はかなり脆弱なシャシーなのに猛烈なスピードで突っ走るポンコツ車なのだとする見方もある。
こうした見方はおおむね以下5点に集約される。
1.「金利」と「有事」で逆回転となる不動産マーケット
2.需要なきオフィスビルマーケットでのテナント争奪戦の始まり
3.投資家不在で消えるマンションマーケット
4.民泊ビジネスの限界
5.逃げる外国人、立ちすくむ日本人不動産投資家
日銀によるマイナス金利政策の継続によって、資金を借りて投資を行う不動産投資にとってはこれほどの快晴状態はなかなかない。しかし、こうした低金利政策はすでに異常ともいえる長期間に及んでいる。
日本は安全だと多くの日本人は漫然と思っているが、戦争が終わってからわずか70年強。日本や世界の歴史を紐解くならば、むしろ平和が長く続くことのほうが歴史的には稀なのである。
「金利」と「有事」を甘く見ないほうが良い。2018年はこのどちらの要素も問題が勃発する可能性が高いからだ。いうまでもなくアメリカは度重なる利上げをすでに発表している。その影響が日本にとって円高に出るか円安に振れるかは専門家の間でも意見が分かれるが、日本の金利がこれ以上に下がる可能性は少ないといってよい。
金利の上昇は借入金に頼る不動産投資の世界には確実に効く効果的なパンチとなる。
北朝鮮のみならず世界中のどこでテロや戦争が起こってもおかしくない時代、日本だけが惰眠を貪れるはずはない。安全な国、日本というキャッチフレーズなどミサイル一本の着弾で粉々になるのだ。
「金利」や「有事」などの外部環境が不変であっても、日本の不動産が2018年も安泰である保証はどこにもない。
現在都心5区を中心に航空母艦のような巨大ビルの建設ラッシュだが、低金利の金融環境でじゃぶじゃぶお金を借りられるのならば、誰でも巨大なオフィスビルを「こしらえる」ことはできる。アクセルさえ踏めばどんなに脆弱なシャシーの車でも一応スピードは上がるのだ。だが、問題はそこに誰が入るかだ。
大企業でなければ高い賃料を負担してこの巨大ビルに入居することはできない。ところが日本の大企業の多くは実は国内ではなく海外で稼いでいる。日本に多くのオフィスを借りる必要のある企業は少なくなっているのが実態だ。
現在建設中のビルのほとんどは既存ビルの建替えだという。今のオフィスビルマーケットの好況は建替えのために既存ビルから追い出された企業がやむなく現在空いているビルに入居して、空室率が低くなっているにすぎない。2018年後半以降続く航空母艦ビルの竣工は、テナント需要が伸びない日本では、再び多くの空室をマーケットに生み出すことになりかねないのだ。
2019年10月の消費税率アップ前の駆け込み需要を期待するマンション販売についても楽観できない。建設費がうなぎ上りの中、マンション販売各社は郊外マンションに注力しているが、全体価格に占める建物代の割合が80%程度を占めるマンションで、土地代が安い郊外に戦線を拡大しても、全体の価格は建設費に引っ張られて高くなってしまい、郊外のマンションを買わざるを得ない一般庶民には「お高い買い物」となってしまう。ましてやこれだけ都心居住が進む中で郊外部のマンション需要は窄まるばかりだということだ。
都心部のマンションも「都心居住」の浸透と言いながら実はその多くの需要はインバウンドマネーと富裕層だ。「金利」と「有事」に敏感な彼らがいなくなるとき、マンションマーケットが大きな影響を受ける可能性も考えなければならないだろう。
民泊新法の施行もよい側面ばかりではない。インバウンドが激増する中、新しい宿泊形態としての民泊の定着を望む声がある一方で、既存のホテル旅館業界からの猛烈な反発で、この新法は民泊を「促進」するどころか厳しく「規制」する法律になってしまったことはあまり知られていない。営業日数を極端に短くする動きなどはすでに京都などインバウンドの多い自治体でも公然と唱えられ始めている。
東京五輪が近づくにつれて、これまでニッポンを買ってきた外国人投資家はそろそろ「売り」の季節に入る。外国人は日本人とちがって別に日本に「想い」があって不動産を買っているわけではない。海外のいろいろな場所に投資を行い、ポートフォリオを組んでいる外国人投資家にとって、日本が「売り」と感じれば不動産はさっさと売って、他の有望な地域に買い替えるだけだ。逆に日本の投資家は逃げ場がない。逃げる外国人の背中を眺め立ち尽くすだけだ。
さて、全く異なる見方が並列する2018年不動産だがあわてる必要はない。不動産は読んで字のごとく動かすことができない財産だ。きちんと磨きをかけて中長期を見据えた確実な運用を続けることがいつの時代でも鉄則だ。くれぐれも投資マネーなどの移り気な空気に乗せられて行動しないように心したいものだ。
この記事を書いた人
株式会社オフィス・牧野、オラガ総研株式会社 代表取締役
1983年東京大学経済学部卒業。第一勧業銀行(現みずほ銀行)、ボストンコンサルティンググループを経て1989年三井不動産入社。数多くの不動産買収、開発、証券化業務を手がけたのち、三井不動産ホテルマネジメントに出向し経営企画、新規開発業務に従事する。2006年日本コマーシャル投資法人執行役員に就任しJ-REIT市場に上場。2009年オフィス・牧野設立、2015年オラガ総研設立、代表取締役に就任。著書に『なぜ、町の不動産屋はつぶれないのか』『空き家問題 ――1000万戸の衝撃』『インバウンドの衝撃』『民泊ビジネス』(いずれも祥伝社新書)、『実家の「空き家問題」をズバリ解決する本』(PHP研究所)、『2040年全ビジネスモデル消滅』(文春新書)、『マイホーム価値革命』(NHK出版新書)『街間格差』(中公新書ラクレ)等がある。テレビ、新聞等メディアに多数出演。






















