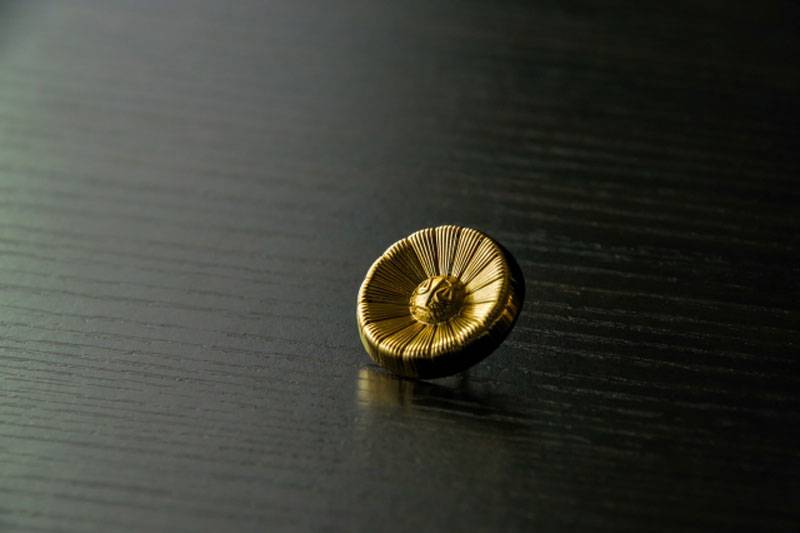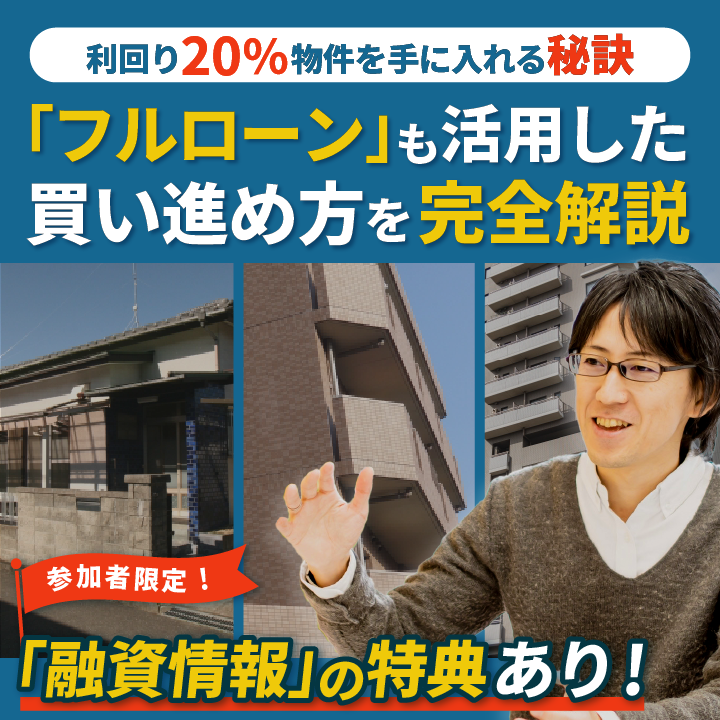株価の一番底を確認の3つの指標――5月の推奨株22銘柄

2020/05/13

©︎blueone・123RF
史上最速の株価暴落に最速リカバリーを期待
新型コロナウイルスが欧米で爆発的に感染拡大し、日本は初の緊急事態宣言をし、先の見えない状態が続いている。
株式市場は戦後最悪の不況を織り込む動きを見せ、リーマン・ショック以上のスピードで下落をし、焼け野原状態となった。その過程で、一番底を確認する指標が幾つか点滅した。
1つ目は、市場の変動予測を示すVIX(恐怖)指数が82.6(3月16日)と08年秋のリーマン・ショック時の80.8(11月20日)の水準まで急騰し、投資家心理はピークに達している。
2つ目は、解散価値であるPBR(純資産倍率)が0.82倍(3月16日)とリーマン・ショック時のボトムである0.81倍(09年3月9日)に次ぐ水準まで急低下した。
3つ目は、ショック安による株価の下落幅が▼7737円と、リーマン・ショック時の▼7606円を上回った。
これらから判断すると、コロナショックでの株価はリーマン・ショック級の極限まで売りたたき一番底を形成している。
リーマン・ショックとの共通点は、①どこまで広がるか分からない恐怖感、②世界的な経済への打撃と終息が見えないことにあり、相違点は、①金融システムの問題はない、②バブルの発生ではない、③アルゴリズム(コンピューター売買)が下げ幅を増幅、④同時多発テロや東日本震災などの突発事故(構造的な問題ではない)であり、終息にかかる時間が違うこと。
その対策として、各国の中央銀行は緊急の金利引き下げや資産購入という大規模な流動性の供給の発表により株価は反転を開始し、NYダウやナスダック指数は下落幅の半値戻しの水準を達成した。日本でもかつてない規模の経済対策(GDPの約2割規模の108兆円)を発表し、ようやく4月末に東京市場は半値戻しを達成した。
流動性の供給や当局による需要創造(財政出動)は必要だが、一番の特効薬は治療薬・ワクチンの開発で、治療薬やワクチンの治験の結果が待ち望まれる。
過去最大の下落幅・下落率のブラックマンデーの株価の回復は6カ月、リーマン・ショックは回復に5年を要した。「明けない夜はない(シェークスピア)」、「悪いニュースは投資家のベストフレンド(バフェット)」という言葉どおり、今回は史上最速の株価暴落だけに史上の最速のリカバリーを期待。
注目業種・注目22銘柄
「相場に亀裂が入ると、物色の流れが」という経験則がある。今回のコロナ禍を機にデジタル新時代が一気に広がり、テレワーク、オンライン学習、オンライン診療などの普及が加速していくとみられる。
今回はグローバル・サプライチェーンの寸断という「供給ショック」に、世界の動きを止めたことによる「需要ショック」が加わっただけに、正常な状態に戻るには時間がかかり、生産回復や消費回復は緩やかなものになりそうで、当面の企業業績は厳しいものになる。しかし、これを契機に新たな需要が生まれる期待も。
富士フィルム(4901)傘下の富山化学が開発した新型コロナ治療薬の「アビガン」、その原料を製造する広栄化学(4367)、同社はレムデシビルにも原料を提供、新型コロナに効くリウマチ薬「アクテムラ」を製造する中外製薬(4519)。
ワクチンでは、独自の技術でワクチンを開発するアンジェス(4563)、製造を受け持つタカラバイオ(4974)。
国立感染研究所とワクチンを共同開発するアイロムG(2372)、検査薬では、臨床試験大手の栄研化学(4549)、短時間での検査薬を開発したクラボウ(3106)、次亜塩素酸水製品を扱うOSGコーポレーション(6757)。


テレワークの情報インフラ整備のサーバーワークス(4434)、ウェーブ会議のブイキューブ(3681)。
厚生省の新型コロナウイルス感染症対策本部向けビックデータ分析やアルゴリズム開発のために人材派遣をするALBERT(3906)。
オンライン治療のメドレー(4480)、オプティム(3964)、医療ポータルサイトのエムスリー(2413)、医療用画像の管理のテクマトリックス(3762)。
オンライン学習・教育のベネッセ(9783)、ジャストシステム(4686)、クラウド型教育支援システムの朝日ネット(3834)、弁護士向け営業支援サイトの弁護士ドットコム(6027)などに注目。

新型コロナ不況で業績の下方修正銘柄が目立つ中、次世代MPU用パッケージの増産効果で想定以上の増益の見通しを発表したイビデン(4062)、レーザーテック(6920)、ホロン(7748)、ローツェ(6323)が注目。

二極化するREIT――注目の投資信託
不動産投資信託(REIT)市場で二極化が鮮明となっている。3月に乱高下した東京REIT指数は新年度に入り膠着しているものの、個別に見ると物流系の上昇が際立つ一方で商業系やオフィス系は軟調だ。
世界的な金融緩和による低金利環境で、相対的に高い利回りを狙う資金が流入しやすいのだが、投資家はコロナ禍の長期化に備えて銘柄選別を強めている。
物流不動産に関するサービス全般を事業領域とするシーアールイー(3458)が運用する物流施設特化型REIT(不動産投資信託)は、テナントに応える良質な物流関連施設「ロジスクエア」に重点を置いたポートフォリオを展開しており、中期的な資産運用、明確な外部成長戦略を特徴としている。
REITについては、新型コロナウイルスの感染拡大によって、オフィスやホテルREITへの警戒が根強く、ただ物流施設の重要性は増しており、投資家の関心も高まっている。
幅広いJリート銘柄に投資するETFは、大半が東証REITに連動するため、市場全体の価格回復の恩恵を受けやすく、投資単位も同指数の10倍と少額で投資が可能。ETFで投資するなら一定額を定期的に継続投資する方法が有効だ。
※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。
この記事を書いた人
コンサルタント、ラジオパーソナリティ
1971年慶應大学法学部卒、同年山一証券入社。1985年新本証券国際部入社、パリ駐在員事務所長を経て企業部にて新規公開企業の実務に携わる。 1998年退職後、コンサルタントとして独立。著書に『株をやさしく教えてくれる本(あさ出版)などがある。フジサンケイビジネスアイ株式初級講座、ラジオ日経の「株式宅配便」のパーソナリティを務める。