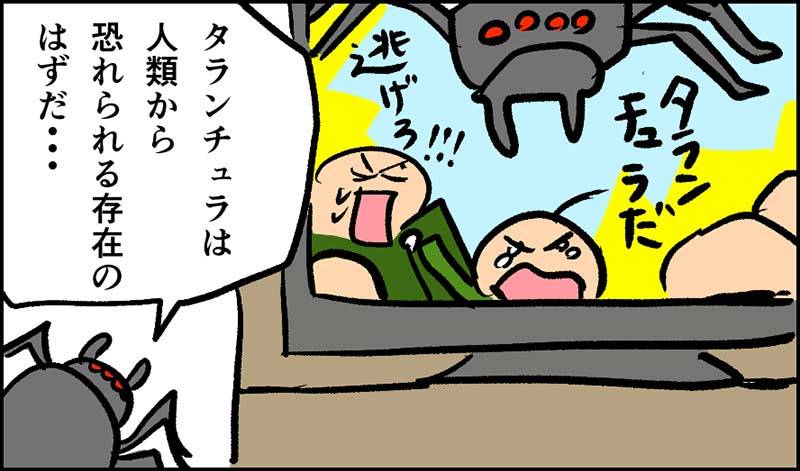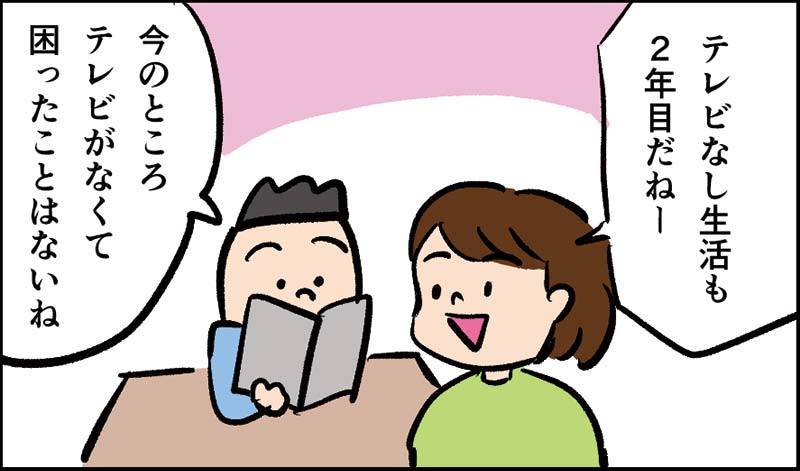東京でも見られる「彼岸」の「あの世」と此岸の「この世」

2019/09/20

イメージ/123RF
お彼岸は、日本人の霊魂観や死生観を考えるうえで、ひじょうにたいせつなお祭りだ。ご存じのとおり、彼岸には春の彼岸と秋の彼岸がある。それぞれ春分の日と秋分の日を中日として、その前後の三日間ずつをくわえた一週間が彼岸になる。
この期間に、寺では彼岸会という法会を開き、信者は寺に詣でて、本堂でお坊さんの話を聞いたり墓参りをしたりする。もっとも最近では、墓参りはしても、本堂の中に入ることは少なくなっている。ましてやお坊さんの話を聞く機会は激減している。
お彼岸の最大の特徴は、日本にしかない宗教行事だということだ。インドにもチベットにも中国にも韓国にもない。
また、お彼岸になれば寺に詣でて墓参りをするのだから、仏教の行事と思われがちだ。しかし、じつは仏教に由来していない。そもそも彼岸という言葉は「悟りの世界」を意味し、「俗世」を意味する此岸と対置された仏教用語なのだが、仏教の本場だったインドには、日本のお彼岸にあたる宗教行事は存在しなかった。
だから、「彼岸」はもともと「日願」だったのではないか、という説もある。
つまり、日本古来の太陽信仰に由来していたというのである。たしかに、春分の日と秋分の日は、太陽が真東からのぼり真西に沈む特別な日なので、太陽に対する信仰となんらかのかかわりがあったのかもしれない。
かつては春分と秋分の日に、太陽に向かって終日にわたり祈願する「日の伴(ひのとも)」と呼ばれる行事があった。人々は太陽のめぐる方向に沿って、東から南へ、南から西へと、その方向に位置する寺や神社に参拝していたのである。
さらにいえば、春のお彼岸は農作業の開始時期に、秋のお彼岸は農作物の収穫時期に、それぞれかかわっている。この意味からすると、春のお彼岸は太陽と祖霊に今年の豊作を祈願し、秋のお彼岸は太陽と祖霊に今年の豊作を感謝する祭と解釈することもできる。こう考える、春と秋のお彼岸に墓参りをする理由もわかってくる。
いろいろな史料から判断すると、お彼岸は平安時代の初期には催されていたらしい。ただし、国分寺の僧侶たちに『金剛般若経』を読ませると書かれているだけなので、具体的にどんな行事だったか、わからない。
平安時代の中期になると、お彼岸の性格や目的がわかってくる。この時期は、西方極楽浄土への往生をひたすら願う浄土信仰が大流行しはじめたときで、「日願」が「彼岸」に変容した可能性もある。浄土信仰の修行法のなかには、「日想観」といって、沈む夕日をみつめて、はるか西方のかなたにあるという極楽浄土を瞑想する方法もあるから、太陽信仰が浄土信仰へ移行する下地はあったのだろう。
ちなみに、浄土には生きたままでは行けないことになっている。いいかえると、死んでからでないと行けない。そこでいつしか「彼岸」は「あの世」、此岸は「この世」という理解が生まれ、今ではむしろこの方が一般化している。
とても興味深いのは極楽浄土の様相だ。それを詳しく説く『観無量寿経』によると、極楽浄土は完璧な人工環境で、自然はまったくない。地面はラピスラズリで敷きつめられ、縦横に黄金をはじめ、さまざまな貴金属や宝石で区画線が引かれている。もし転んだら、さぞ痛いだろう。樹木はたくさんあるが、全部が七宝でできている。綺麗な水をたたえた大きな池があちこちに配置されていて、涼しい風がつねに吹きわたっている。
極めつきは、区画ごとに、天まで届くように聳え立つ巨大な高層建築である。その数は、一区画で五〇〇億もあるから、全体ではいったいどれくらいあるのか、想像もできない。
そんなこんなで、現代の東京、とりわけ臨海部あたりを昔の人が見たら、「ここは浄土か!」と思い込んでしまうかもしれない。
この記事を書いた人
宗教学者
1953年、神奈川県生まれ。筑波大学大学院博士課程修了。専門は宗教学(日本・チベット密教)。特に修行における心身変容や図像表現を研究。主著に『お坊さんのための「仏教入門」』『あなたの知らない「仏教」入門』『現代日本語訳 法華経』『現代日本語訳 日蓮の立正安国論』『再興! 日本仏教』『カラーリング・マンダラ』『現代日本語訳空海の秘蔵宝鑰』(いずれも春秋社)、『密教』(講談社)、『マンダラとは何か』(NHK出版)など多数。