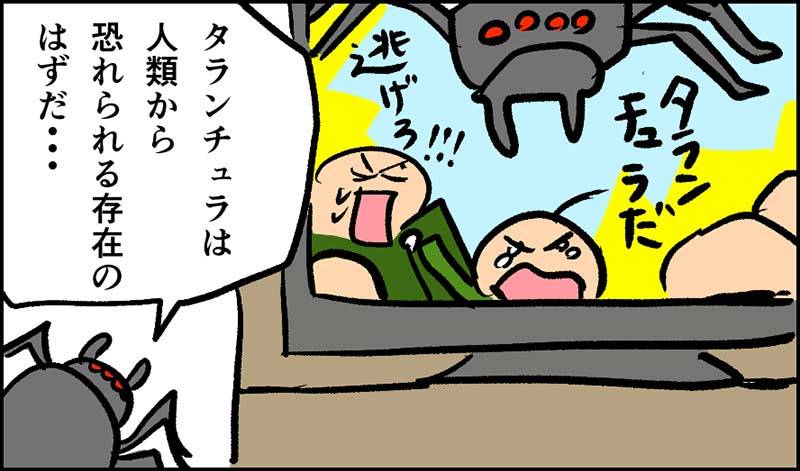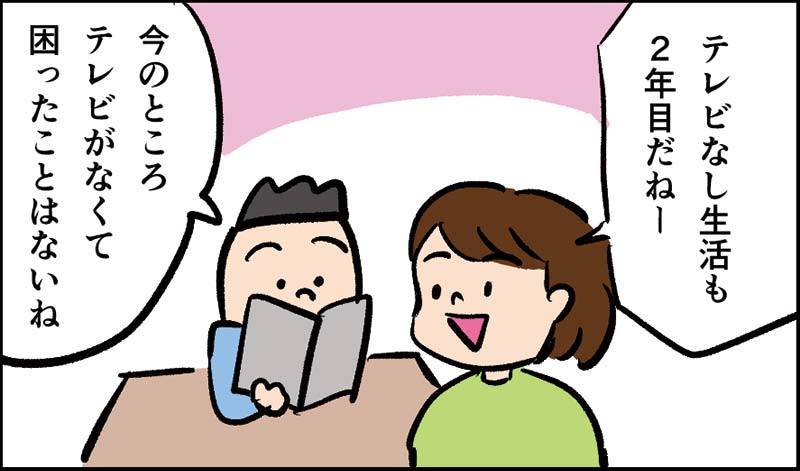介護と相続の現場から

2018/10/16

唯一の財産が不動産だということも多々いらっしゃると思うが、介護のために、とんでもない相続になってしまうこともある。そんな2つの実例を紹介したい。
私が理事長を務める(社)介護相続コンシェルジュ協会は、介護や相続に関する相談だけでなく、暮らしに関わる悩みや疑問を弁護士や税理士、金融FPなどがチームを組んで相談に乗っている。
そんな中で多いのが不動産の相談だ。介護をきっかけとする不動産の相談は、①親が自立型の介護施設に入居するために売却したい、②親の住居を子どもに生前贈与したい、③元気なうちに子どもの近くに引っ越したいというパターンが多い。
親が健康なら、マネーシミュレーションをして、生前贈与にかかる税金、特定の子どもに不動産を生前贈与した場合の、特別受益に関連する法的整備などのアドバイスをする。たとえば、売却するケースであれば、そのお金を介護費用にあてるかどうかなど、法律、税務、金融のトータルで答えを見出していくことになる。
言うまでもないが、不動産の売却は、“法律上の契約”行為だ。当事者間で「売ります」という意思と「買いたい」という意思が合致してはじめて成立する。あくまでもスムーズに売買手続きが完了するのは、不動産所有者に判断能力がある場合だ。
今や超高齢化が進む日本の問題ともいえる認知症と所有者が判断された場合はどうか。私たちに持ち込まれた相談実例を紹介したい。
介護施設に入居するために、不動産売却を希望されているとの相談が、娘さんから寄せられた。娘さんのヒアリングでは親御さんは「認知症のペーパー検査でも高い得点を出しているので、判断能力は、十分にあります」とのことだった。
そこで、社団のコンシェルジュメンバーである弁護士に一次面談をしてもらった。すると、 「“まだら認知症状態”で、判断能力が十分あるとは言い切れない状態だったが、それでも『自宅を売却したい』というAさんの意思確認はできた」というものだった。
しかしながら、“まだら認知”であることは否めなめず、弁護士と私は親御さん1人で意思を表明し、契約を締結するには問題があると判断した。もちろん、判断能力を判定するのは、医師の役割。そこで私たちは、医師の判断を仰ぐことを娘さんにアドバイスをした。
こうした場合、親族の方の中には、「何とかなるんじゃないですか?」という方もいらっしゃる。その気持ちはわかるし、できるものならしてあげたいとは思うが、これは完全な法律違反にあたる。
そんな話を娘さんにすると「わかりました。では、任意後見制度を利用して、任意後見人に私がなろうと思います」と言ってきた。しかし、実はこれもまた不可能といわざるを得ないのである。
任意後見契約とは、委任者(この場合親御さん)が、受任者である娘さんになり、委任契約になる。
なぜこのケースでは不可能なのか。
任意後見契約は、委任者が書面で「誰々に後見人になってもらいます」と書けば終わりというような類いのものではなく、公正証書で締結することが法律で制定されている。公証人役場の公証人というと、単なる事務の人と思う人もいるようだが、30年以上の実務経験を有する法曹界からの任命であったり、長年、法務に携わった学識経験者などが務めている“法律のスペシャリスト”なのだ。この人たちに「何とかごまかしてもらえませんか? 頼みます」となどいっても、通用するはずもない。
こうした場合に覚えておきたいのが、“法定後見制度”だ。
家庭裁判所に本人や配偶者、4親等内の親族、区市町村長等が申し立て(申請)を行い、家庭裁判所の審理を経て、家庭裁判所が援助者を選び、判断の能力が不十分な方を保護する制度だ。
申し立てを行う家庭裁判所は、住民票の住所ではなく、本人が実際に住んでいる住所を管轄する家庭裁判所だ。このことは勘違いされる方も多いので覚えておきたい。
家庭裁判所の審判後は、本人の能力により、3種類に分かれての保護となる(表参照)。
■後見人3つの分類
とはいえ、相談現場では、これですべてが終了ではない。親族間の感情の問題があるからだ。
たとえば、先のケースでは、娘さん以外にもう一人子どもがいた。そのため親御さんにもしものことがあった場合、法定相続分は2人の子どもが2分の1ずつの相続になる。
単純に「半分ずつ分ければいいのでは?」と思うかもしれない。だが、現実は大きく事情が変わる。実際の介護をしているのは相談に来られた娘さんで、もう一人の子どもとは絶縁状態で、所在も不明な状態だった。それでも親御さんにもしもの場合があれば、法律上は2分の1ずつになるのだ。
親族間の感情による相続争いの実例は山ほどあるが、こうしたケースでは、当然、遺言書の作成は必須だ。しかし、それには判断能力が問われることは言うまでもない。
また、相続のトラブルが起きやすいのが親族関係が複雑な家庭のケースである。相談事例の中には再婚して前の配偶者との間に生まれた連れ子や養子がいるケースも少なくない。
実際にあった相談事例をご紹介しよう。
このケースは後妻であった母親が亡くなり、唯一残されたのが不動産だけだった。子どもの2人きょうだいの仲はよかった。そのため相続でお互いに争うつもりなど本人たちも考えていなかった。
当初ふたりは残された不動産物件を2分の1ずつ相続するつもりだった。
ところが、この2人はすでに他界している父親の養子と前妻との間に生まれた子どもで、父親が他界したあと、2人はその後妻である母親とは養子縁組をしていなかった。そのため後である母親には「子どもがいない」ものとされ、法律上の相続権はこの後妻母親の兄弟姉妹となってしまったのだ。
このように養子や連れ子と長年一緒に暮らし、仲が良かったとしても、法律は法律。このケースでは後妻とその兄弟姉妹とはほぼ交流はなくなった彼女を最後まで親身に看取ったのは、血のつながらない2人だった。その後妻である母親が遺言書を残さなかったために、2人は自分の父親の財産を一切相続することができなかったのである。
相続や介護は奥が深い。一方、高齢者に限らず、一般の方は法律には疎い。自分で勉強されている方もいらっしゃるが、やはり餅屋は餅屋。弁護士の見解とは違うことも多い。もしあなたの両親が「終活はきちんとやっている」と言っても、その言葉通りに受け取らないほうがいい。事実、この後妻さんのケースでも、生前から「終活はきちんとやっているから安心して」と話していたが、法律上の遺言書はなく、あったのは“メモ”だけだった。
不動産は大きなお金が動くだけに、家族関係が複雑な家庭ほど慎重にと願う。遺恨をうまないためにも、早めに弁護士・税理士・金融綜合FPに総合的にアドバイスを受けることが必要だと考える。
この記事を書いた人
一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会理事長
アルバイトニュース・テレビぴあで編集者として勤務。出産を機に専業主婦に。10年間のブランクを経て、大手生保会社の営業職に転身し、その後、業界紙の記者を経て、2007年に保険ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。認知症の両親の遠距離介護を自ら体験し、介護とその後の相続は一体で考えるべきと、13年に一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会(R)を設立。新聞・雑誌での執筆やテレビのコメンテーター、また財団理事長として、講演、相談などで幅広く活躍している。 介護相続コンシェルジュ協会/http://www.ksc-egao.or.jp/