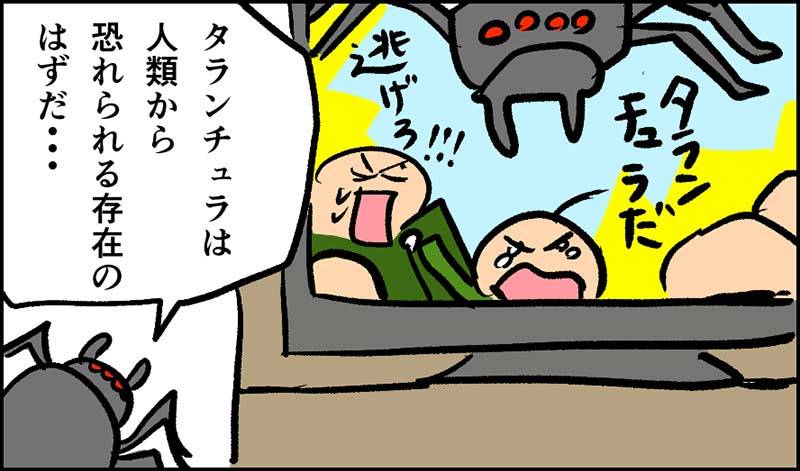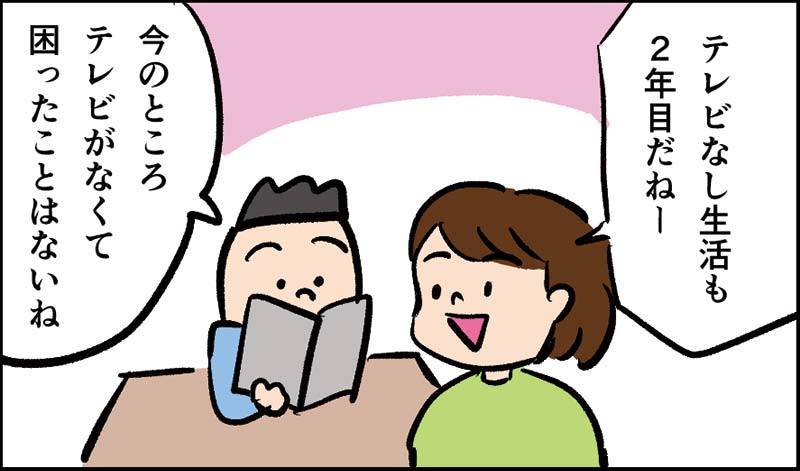孤独死によって起こる「悲劇」の防止。国民レベルの課題とすべき?

2025/07/23

昨年、そして今年も。まだ若い俳優の孤独死
昨年12月、女性俳優の中山美穂さんが自宅で孤独死したニュースに衝撃を受けた人も多かっただろう。年齢はまだ若く54歳。入浴中、不慮の事故に遭ったことによる溺死と見られている。
発見は早かった。そのため、遺体の損壊など、孤独死でしばしば起こる“厳しい”状況は避けられたかたちとなっている。ご冥福を心よりお祈りしたい。
さらに、この7月3日には、東京都内にある、やはり女性俳優の遠野なぎこさん宅から身元不明の遺体が発見された。死後、時間を経ていたため、腐敗が進んでいたとの報道もされていた。その後、2週間経った17日に、親族より発表があった。遺体はやはり遠野さん本人だった。死因はこちらも何らかの事故とされている。
遠野さんは中山さんよりもさらに若く、まだ45歳だった。俳優・芸能人として円熟の時期をこれから迎えるはずの年齢だった。中山さんに重ねて、ご冥福をお祈りしたい。
「孤独死するのは高齢者が殆ど」のイメージは、ほぼ間違い
一人暮らしの人が自宅で孤独死。早期に発見されたり、されなかったり―――。これらは、主に高齢者の身に起こるものとのイメージが強い。
そのため、中山さんや、遠野さんのような世代での事例は、一般的には稀なことのように感じている人も多いだろう。
しかし、実はそうではない。
一般社団法人 日本少額短期保険協会の公表による、9回目となる「孤独死現状レポート(2024年12月)」を見ると、孤独死における世代別の割合は、以下のとおりとなっている。
「賃貸住宅居室内で死亡した事実が死後判明に至った一人暮らしの人」
(データ収集対象期間:2015年4月~24年3月)
| ~29歳 | 3.2% | 現役世代計 47.5% |
| 30~39歳 | 4.8% | |
| 40~49歳 | 9.4% | |
| 50~59歳 | 17.6% | |
| 60~64歳 | 12.5% | |
| 65~69歳 | 16.1% | |
| 70~79歳 | 26.6% | |
| 80歳~ | 9.8% | |
このとおり、64歳までのいわゆる現役世代が47.5%と、約半数を占めている。もう少し若く、59歳までのところにラインを引いても35.0%だ。3人に1人を超えている。
なお、重ねて言うが、上記はアパートや賃貸マンションなど、賃貸住宅に限っての数字となる。だが、それだけに、
「賃貸オーナー(大家)が孤独死を恐れて高齢者に部屋を貸したがらない」
―――こうした一般的傾向が、やや的外れとなっている点も指摘されるものとなる。
孤独死による社会的ロスを避けたい
孤独死は、通常、その発見が遅れれば遅れるほど、周りへの影響が増していく。
主には、遺体の腐敗・損壊が進むことで、部屋・建物・設備等、より広範囲に汚損等が拡大する。それにともない、原状回復費用も嵩んでいく。
以下、先ほどと同じ、日本少額短期保険協会によるデータだ。
| 項目 | 平均費用 | 最大額 |
| 残置物処理費用 | 295,172円 | 1,913,210円 |
| 原状回復費用 | 474,170円 | 4,546,840円 |
残置物の処理と原状回復、両方を合わせ、平均では70万円超、最大では600万円を超える損害も(当データからは)予想されるものとなっている。
加えて、孤独死による遺体の腐敗・損壊等が起こったアパートや賃貸マンションから、他の住人が多数退去してしまうというのもよくあることだ。オーナーにとっては、家賃収入への重大なダメージとなる。
さらには、その後の入居者募集において、いわゆる「告知」を行わざるをえなくなることで、賃貸経営への影響が長期間、継続することも少なくない。
場合によっては、オーナーのみならず、亡くなった方の遺族にもさまざまな負担がのしかかることがある。
なお、孤独死の発生による周りの住人の退去は、いま述べたように専らオーナーの損害として語られることが多いが、実際はそれにとどまらない。転居を判断する住人の方も、当然ながら、予期せぬ出費や手間などに苦慮させられることとなりやすい。
よって、社会にもたらされる大きなロス、ダメージとして、孤独死の発見の遅れは、極力誰もがこれを避けたいものとなる。
孤独死「未然対策」システムの提案
「孤独死現状レポート」には、日本少額短期保険協会による傾聴すべき提案も盛り込まれている。
簡単に紹介しよう。
ここでは、国が取り組むべき施策として、スマートフォンアプリを利用しての「一人暮らしを家族が見守る」システムの構築が提言されている。
見守りの対象となる人の歩行状況、さらには、1日の間におけるスマートフォンの操作開始時刻と終了時刻が、見守る家族の側に提供される。
これを国の管理のもと、運用する。
公のシステムとすることで、個人のプライバシーを守り、悪用を抑える。併せて、無料化および普及の最大化を実現するというものだ。
よいたたき台になっている。
IoT化された家電や住宅設備との連携など、さらなる可能性も含め、ぜひ担当省庁レベルでの議論の俎上にのせてもらいたい。
単独世帯の著しい増加
孤独死の基本的な要因となる一人暮らしの増加は、もはや現状避けがたいものとなっている。
一人暮らし―――単独世帯の数の推移を国の資料に覗いてみよう。厚生労働省「2024年 国民生活基礎調査」の結果となる。(本年7月4日公表)
| 年 | 世帯数 | 全世帯に対する割合 |
| 1986年 | 682万6千世帯 | 18.2% |
| (中略) | ||
| 2001年 | 1101万7千世帯 | 24.1% |
| (中略) | ||
| 2022年 | 1785万2千世帯 | 32.9% |
| 2023年 | 1849万5千世帯 | 34.0% |
| 2024年 | 1899万5千世帯 | 34.6% |
このとおり、昭和の終わり近くとなる86年の数字に対し、昨年はその2.78倍となっている。21世紀最初の年である01年に比べても1.72倍だ。
加えて、国立社会保障・人口問題研究所による昨年公表の推計では(24年4月)、単独世帯の数は今から11年後の36 年にピークに達するとされている(2,453万世帯)。
なお、単独世帯が著しく増えた理由としては、いわゆる未婚化・非婚化、核家族化のほか、一人暮らしの自由を求める価値観の広がり等、いくつかを挙げることができる。そのうえで、こうした条件は、おそらく今後もしばらくは単独世帯増加の強力な基盤となり続ける。
と、同時に、孤独死の数も増えていくと思われるが、そこで生じる事後のリスクに関しては、対処はかなりの程度可能なはずだ。キーワードは第一に「早期発見」となる。
人の死は容易に予測しえないものだ。だが、それが起きた際に周りが早期発見するについては、それほど難しい課題ではないだろう。工夫のしかた、やり方が、さまざまにあるものと思われる。
日本少額短期保険協会のレポートは下記でご覧いただける。
「一般社団法人 日本少額短期保険協会 第9回 孤独死現状レポート」
(文/賃貸幸せラボラトリー)
【関連記事】
孤独死への手厚い補償と手数料収入 これからの火災保険はオーナー自身が選択するべき
思わず寒気が…! エレベーターで起きる事故のことを知っておこう
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室